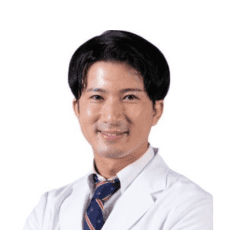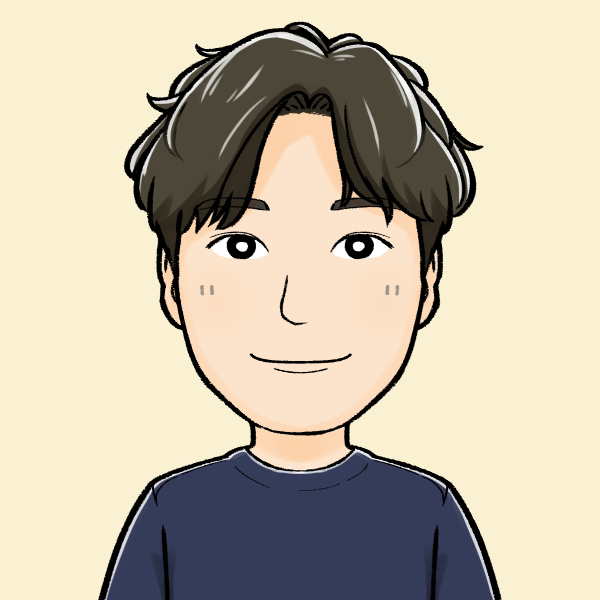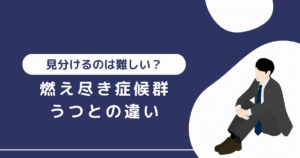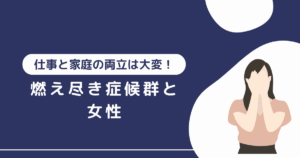勉強中に周りとのやる気の差を感じることはありませんか?それはもしかしたら燃え尽き症候群かもしれません。
燃え尽き症候群は「勉強の頑張りすぎ」であらわれることがあります。
定期テストや受験勉強中に、気づいたらやる気が出ないという人も多いのではないでしょうか。また勉強がなかなか進まず、テストが近づくにつれて不安になっていくこともありますよね。
そこでこの記事では、勉強で燃え尽き症候群になるのを防ぐ方法やなりやすいタイミングを解説します。やる気が出なくても焦らず、自分のペースで勉強が進められる手助けになれば幸いです。
燃え尽き症候群で悩むお子さんがいる親御さんは、こちらもご覧ください。

燃え尽き症候群と勉強の関係【なりやすいタイミング】

燃え尽き症候群はひとつのことに集中して、モチベーションが高いときになる可能性があります。
「勉強を頑張ること」も燃え尽き症候群を引き起こす原因のひとつです。
熱心に勉強に取り組んだ結果、あるとき急に「勉強したくない」「教科書を開きたくない」とやる気を失ってしまうのです。
とくに学生時代は、定期テストや受験など勉強に関するイベントが多くあります。勉強に関して燃え尽き症候群になりやすいタイミングは以下の通りです。
模試や定期テスト後
定期テストのあとに「なんだか動けない」と疲れてしまい、動けなくなった経験がある人はいませんか?
定期テストのあとは以下のような気持ちを感じることがあります。
「勉強から開放されて嬉しい気持ち」
「目標がなくなって何かを失ったような気持ち」
勉強に熱心に取り組んでいた人ほど「嬉しい気持ち」よりも「喪失感」が強くなり、燃え尽きてしまうため動けなくなってしまうのです。
定期テストは学校にいればほとんどの人が経験するイベントです。「いい点数をとるため」「親に怒られないため」と理由はいろいろありますが、頑張って取り組む人が多い傾向にあります。
勉強を頑張りすぎた結果、燃え尽き症候群になってしまうことも多いです。
大学共通テスト後・二次試験前
燃え尽きるタイミングとして「大学共通テストの後」も挙げられます。
ほとんどの場合、大学受験では「大学共通テスト+二次試験」がセットになっており、二次試験まで長いスパンで頑張り続ける必要があります。
「大学共通テスト」はひとつの大きなイベントであり、定期テストや模試よりもプレッシャーがかかりやすいです。テストを受け終わった瞬間に、緊張の糸が切れてしまい勉強できなくなってしまうのです。
「なんとか勉強を再開しても、気づいたら二次試験まで日にちがない」
このようなことも考えられます。大学共通テストのあとの「燃え尽き症候群」にも注意しましょう。
高校・大学受験後
高校や大学受験のあとは、受験勉強の反動でやる気がでないケースがあります。
勉強を頑張っている学生の多くは「高校受験や大学受験で良い結果を残すこと」を勉強の最終的な目標としています。そのため、多くの時間をかけて高い熱量で勉強に取り組みます。
受験が終わり、最終的な目標が達成されると、急にやるべきことが分からなくなり、燃え尽きてしまうことがあるのです。
- 高校受験・大学受験が終わる
- 休み期間中に何もやる気が起きない
- 高校や大学入学後もやる気のない状態が続く
新生活が始まってもやる気が出ない状態が続くと、せっかく入った高校や大学に行く意味が見つからずに退学してしまう場合もあります。
「燃え尽き症候群かどうか分からない、チェックしたい」という人はこちらもご覧ください。

勉強で燃え尽き症候群になるのを防ぐ3つの方法

勉強中にいくつかのポイントを意識すれば、燃え尽きずに勉強に集中できるでしょう。
意識するポイントは以下の3つです。
それぞれ解説します。
勉強と休憩のメリハリをつける
「勉強する時間」と「休憩する時間」をしっかりと分けましょう。
勉強と休憩のメリハリをつけると、脳がリフレッシュしやすくなり勉強の効率が高まりやすいです。
時間のメリハリをつける方法として「ポモドーロテクニック」があります。
- 25分間集中して勉強する
- 5分間休憩する
- 1,2を数set行う
- 30分程度休む
- 1~4を繰り返す
※時間やset数は自由に変更してよい
時間を決めて勉強し、決まった時間になったら必ず休憩しましょう。休憩時間が終わったら再度時間を決めて勉強を開始します。この繰り返しです。
休憩時間は「散歩」や「音楽を聴く」など勉強に関係ないことをするとリフレッシュできます。
勉強と休憩でメリハリをつけることで、勉強効率も高まっていくでしょう。
量ではなく時間で目標を設定する
勉強の目標を設定する際は、量ではなく時間を指標にしてみましょう。
× 数学のテキストを30ページ進める
○ 数学に1時間取り組む
量で目標を決めると、達成できなかったときに以下のような行動をとることがあります。
- その日のうちに出来なかった分を、追加で勉強しようとする
→睡眠時間を削る - 後回しにして次の日にやる量が増える
→次の日も出来ず、繰り返す
「睡眠時間を削る」や「勉強の予定が崩れる」など悪影響を及ぼしやすいです。
時間で目標を設定すると「1時間勉強できた」と目標を達成しやすいです。成功体験が増えることで、勉強へのモチベーションも保ちやすくなります。
時間の目標を達成できるようになってきたら、
- 「1時間で5ページ進める」
- 「30分で英単語20個覚える」
このように、量と時間を組み合わせた目標を設定してみるのも良いでしょう。
ひとりではなく誰かと一緒に勉強する
勉強している時間を誰かと共有するようにしましょう。
1人で勉強をしている時間は孤独なため「私は何でこんなに勉強しているのだろう」と不安に感じることがあります。
誰かと一緒に勉強するメリットは以下の通りです。
- ひとりじゃないと思って頑張れる
- 休憩中にリフレッシュできる
- 困ったことがあったら相談できる
一緒に勉強することで「相手が頑張っているから私も頑張る」といったように、やる気を維持しやすいです。
勉強で悩んでいるときは相談も出来るため、頑張りすぎで燃え尽きる可能性も低くなるでしょう。
勉強で燃え尽き症候群になったときの対処法

勉強を頑張りすぎて燃え尽きてしまった場合は、しっかり休んでみてください。休むときは勉強から完全に離れてみるのが良いでしょう。
- 「少しでも勉強しなきゃ」
- 「周りと差がつくのが怖い」
このように思うかもしれませんが、中途半端に勉強に手をつけるのは逆効果です。
再び勉強に意欲的に取り組めるようになる早い方法は「出来るだけ早く燃え尽き症候群を治す」「良くなってから勉強に少しずつ取り組む」ことです。
燃え尽き症候群の症状は適切に対処すれば良くなる傾向にあります。
より早く燃え尽き症候群を良くしたい場合は、専門家にカウンセリングを受けるのも良いでしょう。自分にあった最適な回復方法や勉強での注意点を教えてくれます。
燃え尽き症候群から回復する方法を詳しく知りたい人はこちらもご覧ください。

まとめ
この記事では燃え尽き症候群と勉強の関係や、未然に防ぐ方法について解説しました。
勉強は学生にとって避けて通れないため、頑張る人も多いです。
頑張り過ぎた結果、燃え尽きてしまい満足に勉強出来ず、定期テストや大学共通テストで思うような結果を出せないこともあります。
勉強や休憩にメリハリをつけたり、誰かと一緒に勉強したりすると勉強へのモチベーションを保ちやすいです。
それでも燃え尽き症候群になった場合は、しっかり休んで回復するのを待ちましょう。
おおかみこころのクリニックでは、ひとりひとりの状態を丁寧にカウンセリングしています。ぜひ一度お気軽にご相談くださいね。