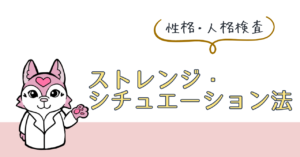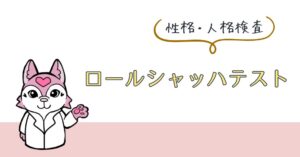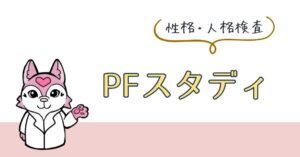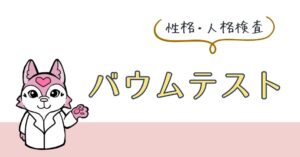TAT(主題統覚検査)とはどんな性格検査|方法や解釈について解説

この記事は検査の内容を含むため、
結果に影響を与える可能性があります。
検査を受ける本人でない場合のみ、お進みください。
TAT(主題統覚検査)とは、ある場面が描かれたカードに対して物語をつくる投影法による性格検査です。想像した物語の内容から、被験者の深層心理を調べていきます。
その他の心理検査については、以下の記事をご覧ください。
TAT(主題統覚検査)の概要
TAT(Thematic Apperception Test)とは、1943年にマレーとモーガンを中心としたハーバード心理学クリニックのスタッフが作成した性格検査です。別名「主題統覚検査」とも呼ばれます。
ある場面が描かれた20枚のカードを提示され、被験者はそれぞれのカードに対して想像して物語を作る検査方法です。[1]
性格検査のうちの投影法に分類され、ロールシャッハテストと並んで二大投影法と位置づけられますが、実際の臨床場面ではあまり使用されません。[2][3]
投影法にはTATのほかにも「PFスタディ」「バウムテスト」「SCT(文章完成法)」などがあります。[1]

「投影法ってどんな方法だろう?」と思ったら
下記の記事をご覧ください。
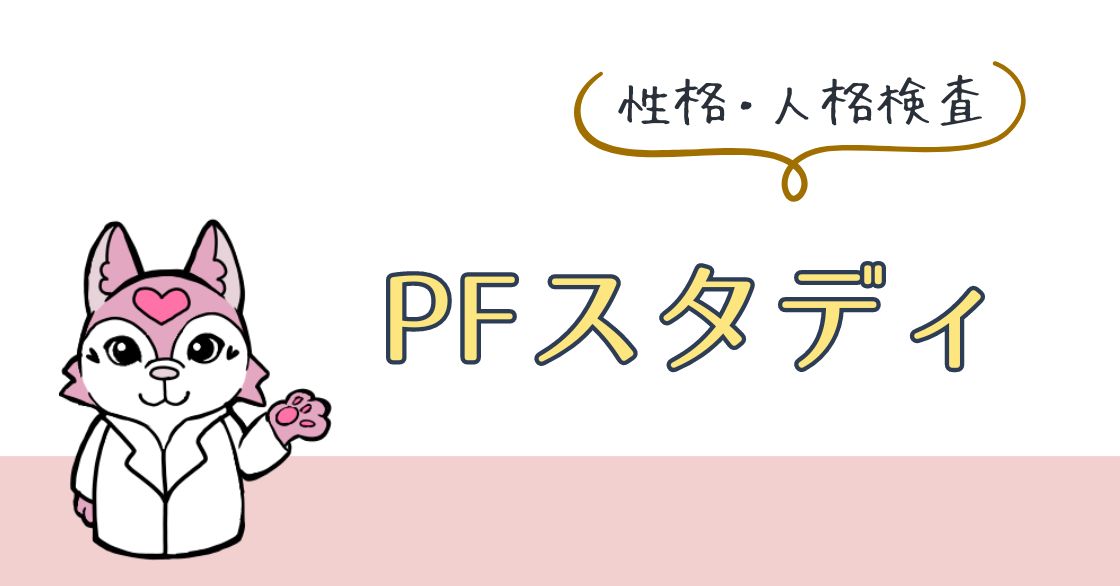
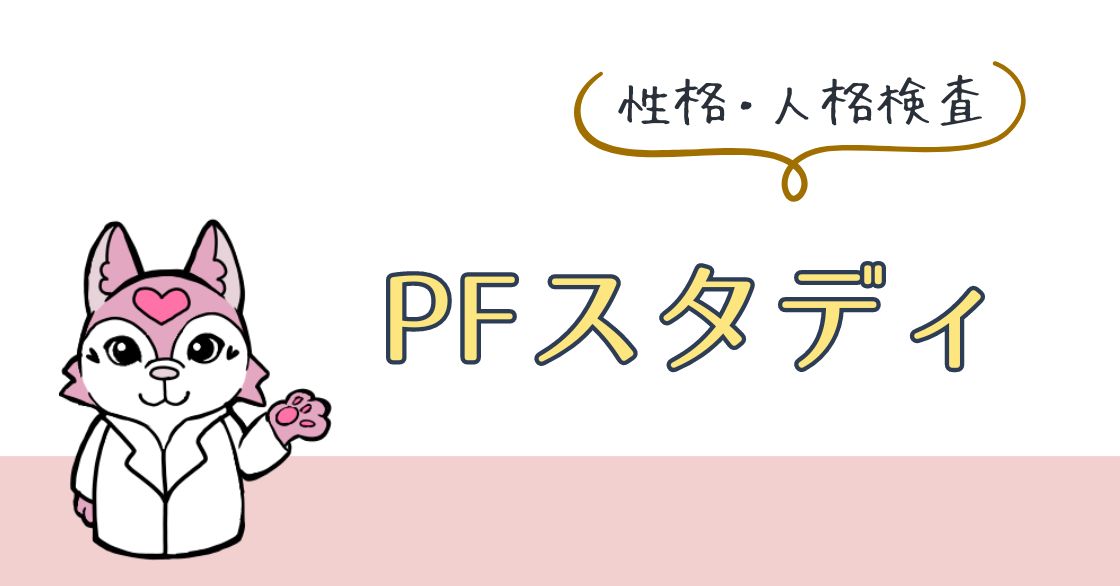
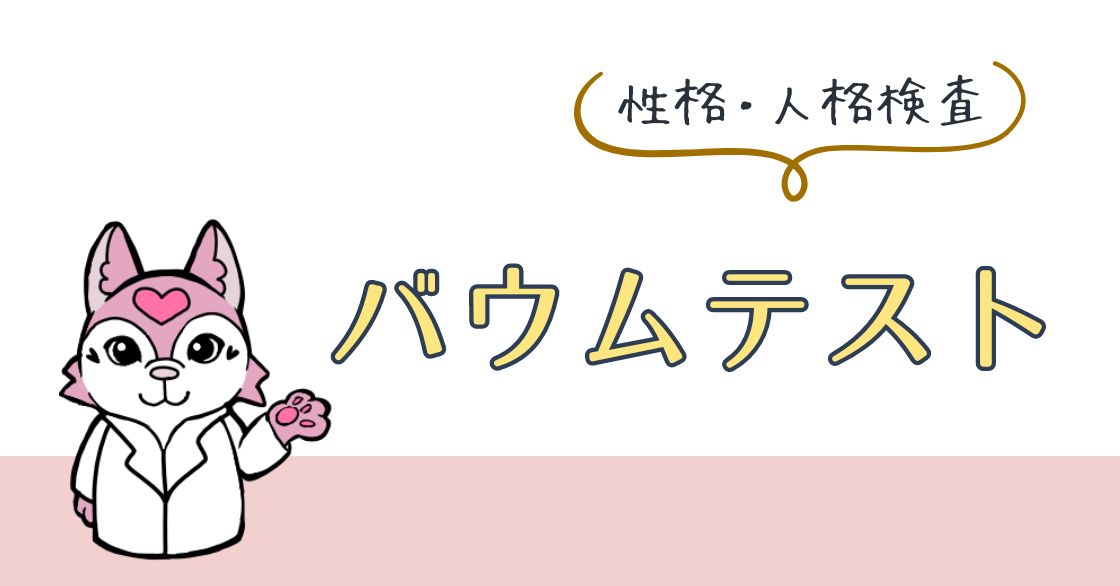
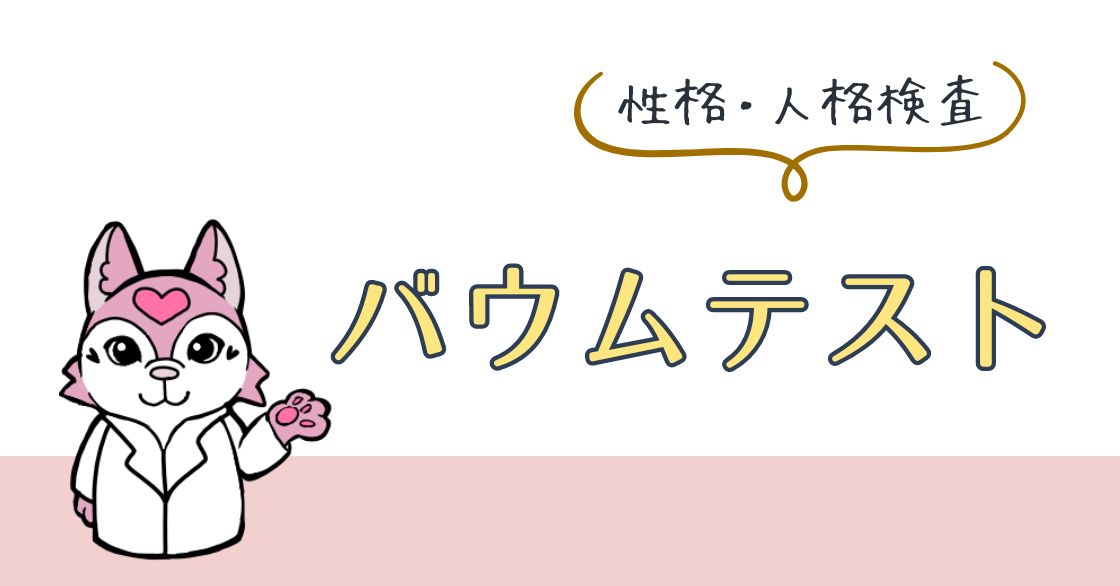
TATの目的
TATを作成したマレーは、臨床領域でTATを使用する目的に、以下の4つを挙げています。[4]
- 抑えられた性質と葛藤を明らかにし、それに抵抗する状態を捉えること
- 治療的な働きかけができること
- 治療効果の判定手段として用いること
- 精神身体的疾患を探すために使うこと
TATでは、被験者のパーソナリティを分析できます。それだけでなく、心理療法における治療を促進させることも可能です。
TATを含む投影法の目的は、被験者の深層心理を把握することです。そのため、課題の意図が分かりづらい、または抽象的という特徴があります。[1]



自分でも気づいていないことに気づけるかもしれませんね!
TATのやり方
被験者は20枚のカードを見て、提示されたそれぞれのカードに対して物語を作ります。
ただし実際には、20枚のカードが使われることはほとんどありません。多くの臨床現場では、使用するカードの種類や枚数を被験者に合わせて、選定して使用されるのです。[3]
被験者が話したことを記録しなければならないので、検査中の会話を録音することも。[2]
見せられたカードに対して回答するものに、同じく投影法である「PFスタディ」があります。カードに描かれた場面の吹き出しを埋めるのがPFスタディであるのに対して、描かれた場面から想像して物語を作るのがTATです。



カードを見て感じたままの物語を作りましょう!
TATの結果の解釈
TATの結果の分析・解釈に統一されたものは、まだありません。ただ、2021年に兵庫教育大学の遊間義一氏と東條真希氏は、TATのマニュアルを開発しました。
他人と同じように絵を見ているかの「反応領域」、他人と同じように感じて物語を作っているのかの「着眼点」の視点から、被験者の深層心理を調べます。[5]
物語の分析は、反応領域の「認知」「省略」「歪曲」の有無を見ます。
- 認知:カードを見て、気づいたこと
- 省略:気づいてないこと
- 歪曲:カードを見て、誤った認識をすること
たとえば、少年とバイオリンが描かれたカードを見て「バイオリンの練習をして……」と始まると、「少年」という言葉はなくても、少年に気づいている「認知」とみなされるのです。バイオリンをトランペットと認識した場合は「歪曲」と判断されます。
また「考え込んでいるうちに夕方になって、部屋の中も暗くなってきた……」のように回答したら、被検者は抑うつ感情や悲観的な気分を持つと考えられます。[5]
齋藤(1994)の研究において、精神分裂病(現在の統合失調症)患者におこなわれたTATの回答には、カードが変わっても同じような主題が繰り返されたり、複数枚のカードにわたって物語を続けたりすることが見られました。特に繰り返される主題は、被験者にとって意味のあるもの、無意識のコンプレックスに関連するものと考えられます。
さらに齋藤は、精神分裂病患者に提示されたカードのうち家族に関する物語がまったく出てこないこともある、と指摘しました。その場合、家族との結びつきが破綻しており、自分の世界に閉じこもっていると分析されます。[6]
TATの注意点
TATは、実施に手間や時間がかかってしまうため、統一の分析・解釈の方法がいまだ確立されていません。そのため、臨床現場ではTATよりも、ロールシャッハテストの方がよく使用されるのです。[6]
クリニックで使用するときは、時間の制限があることも懸念点となります。ロールシャッハテストやウェクスラー式知能検査などの検査時間は、全体で2時間ほどです。
しかし、TATの検査時間は2時間を超えることが多く「診察枠の取りづらさ」「被検者の体力」などの問題を考えなければなりません。[2]TATをやってみたいという人がいても、実際に検査を受けるのは難しいでしょう。



どうしてもTATをしたいならば、主治医の先生に相談してみるといいでしょう!
まとめ
TATは提示されたカードから想像して物語をつくり、自分の深層心理を理解できる性格検査です。実施方法に手間や時間がかかったり、解釈が統一されていなかったりする点から、臨床場面ではあまり使用されていません。
おおかみこころのクリニックでは、ロールシャッハテストやPFスタディなど他の投影法による心理検査を実施しています。検査をご希望の方は、以下のお問い合わせページからお願いいたします。
【参考文献】
[1]面白いほどよくわかる!臨床心理学,下山 晴彦,西東社
https://amzn.asia/d/bonNkMY
[2]初学者の TAT(主題統覚検査)の学び方、実施前の構えについての一論考
https://senshu-u.repo.nii.ac.jp/record/12545/files/3061_0316_04.pdf
[3]TAT(主題統覚検査)についての一考察
https://fuksi-kagk-u.repo.nii.ac.jp/record/149/files/KD200606.pdf
[4]TATの心理療法的意義に対する試案
https://www.sgu.ac.jp/faculty/f-psy/dep-cli_psy/j09tjo00000f89nw-att/14_p001.pdf
[5]TAT検査(標準比較法)の教材開発
https://web.hyogo-u.ac.jp/yuma/bunsekikaishaku.pdf
[6]臨床場面におけるTAT解釈の手がかり(その1)
https://www.i-repository.net/contents/outemon/ir/301/301941208.pdf