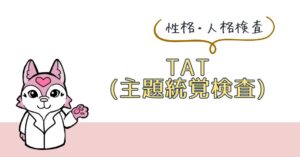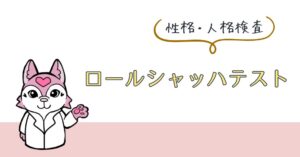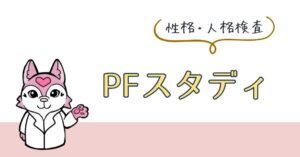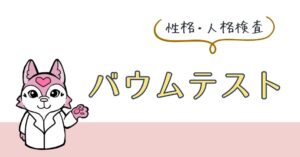ストレンジ・シチュエーション法で分かること|活用法や注意点とは
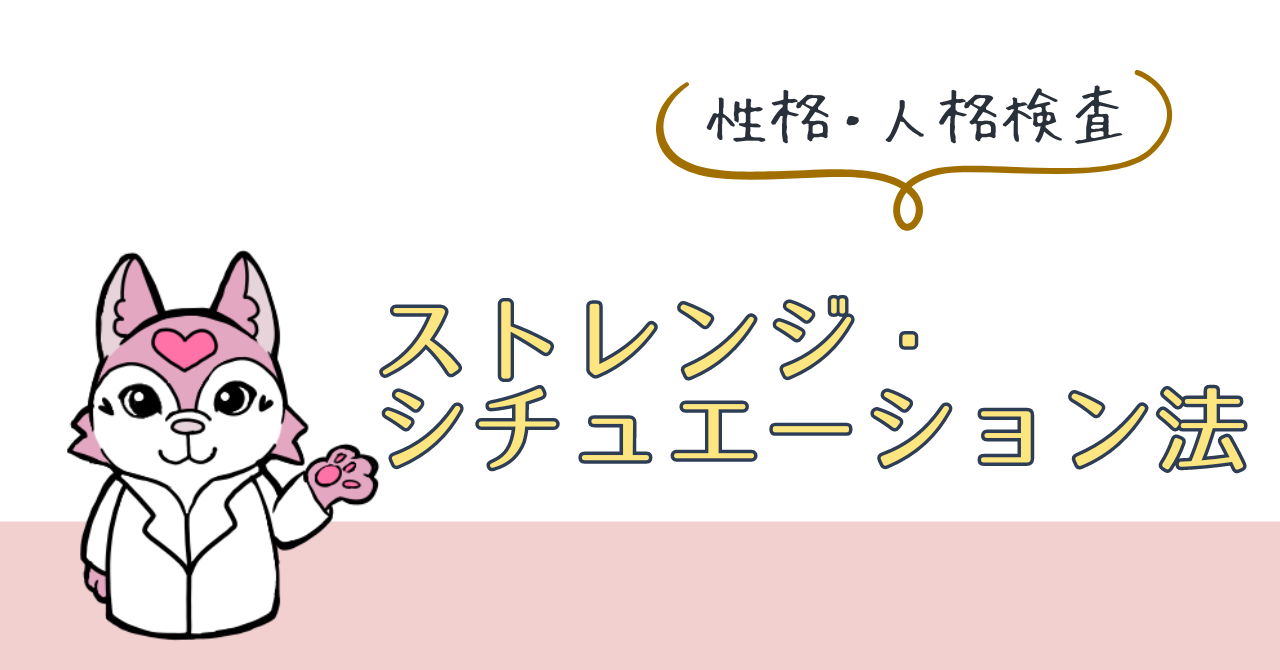
この記事は検査の内容を含むため、
結果に影響を与える可能性があります。
検査を受ける本人でない場合のみ、お進みください。
ストレンジ・シチュエーション法とは
ストレンジ・シチュエーション法とは、人見知りの強い12〜24か月の乳幼児を対象として「愛着の型」を評価する観察方法です。
乳幼児にとってストレスとなる状態(養育者と一時的に離れる、見知らぬ場所で見知らぬ人と対面するなど)にどのように反応するかを観察します。[1]
愛着とは、おもに母親を「安心、安全な場所」として捉える状態で、以下のような訴えに繰り返し応えることで育まれます。
- 生命を維持する訴え(例:ご飯やおっぱいがほしい)
- 安全を求める訴え(例:不安を軽減してほしい)
健全な愛着は「誰にでも」「一時的な」状態で築かれるものではありません。
「特定の人(多くの場合は母親)」と「安定して」維持されていることが大切です。[2]

子どもの愛着の型を知ることで、子どもとの関わり方を見直すきっかけになります!
ストレンジ・シチュエーション法の実施手順
ストレンジ・シチュエーション法は以下の8ステップで構成されます。(表1)[2]
| ステップ | 手順 | 時間 |
| ① | 案内人が母親と子どもを観察部屋に案内し、退室する | 30秒 |
| ② | 母親と子どもがおもちゃで遊ぶ | 3分 |
| ③ | 見知らぬ人(ストレンジャー)が観察室に入る | 3分 |
| ④ | 母親のみ観察室から退室し、見知らぬ人と子どもだけが残る | 3分 |
| ⑤ | 母親が観察室に戻り、見知らぬ人が退室する | 3分 |
| ⑥ | 母親も観察室から退室し、子どもひとりきりになる | 3分 |
| ⑦ | 見知らぬ人が入室し、子どもを慰める | 3分 |
| ⑧ | 母親が入室し、見知らぬ人は退室する | 3分 |
ストレンジ・シチュエーション法の観察では、子どもの様子や反応に「一貫性があるかどうか」がもっとも重視されます。
ストレンジ・シチュエーション法の分類と親の特徴
ストレンジ・シチュエーション法では、子どもの「愛着の型」を以下の4つに分類します。
それぞれ解説します。[2][3]



子どものことを客観的にしるきっかけと思って愛着の型を見てみましょう。
A:回避型
回避型の子どもとその親の特徴として以下が挙げられます。(表2)
| 子どもの特徴 | 親の特徴 |
| ・母親と分離しても混乱しない ・母親との再開時に接触しない ・母親の入室を無視し距離を置く | ・子どもの働きかけを受け止めない ・子どもが泣いたり接触を求めたりすると離れる |
回避型の子どもは、愛着を求めるサインを出しても報われない経験をしています。
そのため子どもは愛着のサインを最小限に留め、親と一定の距離を取るようになるのです。
B:安定型
安定型の子どもとその親の特徴として以下が挙げられます。(表3)
| 子どもの特徴 | 親の特徴 |
| ・母親との分離時に混乱する ・再開時は母親に近づき落ち着く | ・子どもの変化や欲求を敏感に捉える ・子どもに過剰な働きかけをしない ・子どもとの遊びや身体接触を楽しむ |
安定型の子どもの親は、子どもの訴えや感情の変化を捉え適切な関わりをしています。
そのため子どもは親の反応を予測しやすく「自分が困っているときは親が助けてくれる」という強い信頼感を抱けるのです。
C:アンビバレント型
アンビバレント型の子どもとその親の特徴として以下が挙げられます。(表4)
| 子どもの特徴 | 親の特徴 |
| ・分離時に激しく混乱する ・再開時に母親へ怒りや抵抗をぶつける | ・子どもの欲求に気づくのが苦手である ・子どもの欲求に「応えるとき」と「応えないとき」がある ・応え方に一貫性がない(優しく応える or 怒りながら応えるなど) |
アンビバレント型の子どもの親は、欲求への応え方に一貫性がなく子どもはどのように愛着を求めればよいか分からなくなります。
親への安心感や信頼感が乏しくなるため、怒りを示したり激しく愛着を求めたりすることで養育者の関心を引きとめるのです。
D:無秩序・無方向型
無秩序・無方向型の子どもとその親の特徴として以下が挙げられます。(表5)
| 子どもの特徴 | 親の特徴 |
| ・母親に怯えるような素振りを見せる ・母親よりも見知らぬ人に近づく ・見知らぬ人に怯えたときは母親から離れ壁にすり寄る | ・突然立ちすくんだり声色を変えたりする ・子どもの欲求に急に無反応になる ・虐待や不適切な養育をしている |
無秩序・無方向型の子どもの親は、抑うつ傾向やトラウマ体験から精神的に不安定な部分があるとされています。
親が子どもに恐怖を与える存在となるため、子どもは親を頼らずひとりでやり過ごすようになるのです。
虐待を受けている子どものうち約80%が無秩序・無方向型に分類されるという報告もあるため、このタイプの親子は注意深く観察する必要があります。
ストレンジ・シチュエーション法の活用方法
ストレンジ・シチュエーション法の活用方法として、以下の2点が挙げられます。
それぞれ解説します。
子どもへの関わり方を見直す
回避型、アンビバレント型、無秩序・無方向型に分類された場合は、子どもへの関わり方を見直す機会と捉えましょう。
適切な対応をすることで、子どもの愛着が安定型に移行することが分かっています。[2]
以下の観点から自分の行動を振り返ってみましょう。
- 子どもの行動や感情を読み取れているか
- 自分の都合で子どもへの対応を変えていないか
- 自分の精神状態は安定しているか
子どもの欲求に応えるためには、親自身の心身の安定が重要です。
必要に応じて医療や福祉のサポートを受け、子どもの欲求への感受性を高めたり気持ちの余裕を作ったりして関わりを見直しましょう。
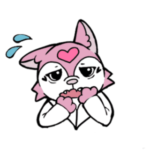
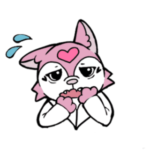
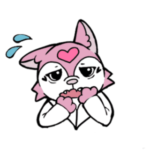
親だって人間なので、安定したかかわりって意外と難しいですよね💦
家族の関係性を見直す
ストレンジ・シチュエーション法は、家族の関係性を見直すきっかけになります。
どれほど安定した関わりをしていても、夫婦喧嘩が絶えない環境では安定した愛着を保てません。
夫婦喧嘩は子どもを持続的に不安な状態にさせ、発達の問題を引き起こすことが分かっているからです。
子どもの健やかな発達には、きょうだいや祖父母を含めて温かく調和的な雰囲気があることが大切です。
子どもの愛着に問題が見られた場合は、家族関係に改善できる部分がないか考えてみましょう。[3]
ストレンジ・シチュエーション法の注意点
ストレンジ・シチュエーション法の注意点として以下の2点が挙げられます。
それぞれ解説します。
親の愛情不足が原因ではない
愛着の不安定さは「親の愛情不足が原因」とは言い切れません。
愛情深く子育てをしていても、以下のような原因から適切に対応できない場合があるからです。
- 感情や行動を読み取るスキルが低い
- 親自身が心身の障害を抱えている
- 子どもに育てにくい特性がある
親自身や子どもの特性により適切な子育てができない場合は、医療や福祉のサービスを利用するのがよいでしょう。
「愛情不足かもしれない」と考えすぎ、自分を責めないようにしてください。[3]
子どもに育てにくい特性を感じたら、下記のような発達検査もあるので参考にされてください。
すべてが親の責任ではない
子どもに愛着の不安定さがみられても、すべてが親の責任ではありません。
愛着には以下の要因が関連するからです。
- 遺伝率:14%
- 共有環境(養育者や家庭の環境):32%
- 非共有環境(家庭以外の環境):53%
子どもの愛着には、保育園をはじめとした家庭以外の環境も大きく影響するため、すべての責任を親が背負い込まないよう注意しましょう。[3]



1つの結果だけで「愛情不足」や「親の責任」と判断するのはよくありません。
まとめ
ストレンジ・シチュエーション法とは、子どもの「愛着の型」を明らかにする観察法です。
愛着の型は以下の4つに分類されます。
愛着に不安定な部分が見られた場合は、子どもとの関わりや家族関係を見直す機会と捉えましょう。
必要に応じて医療や福祉のサポートを利用し、ひとりで抱え込まないことが大切です。
愛着には、親自身の心身の安定や家庭外での体験も影響します。
「愛情が足りていないのかも」「育て方が悪いのかも」と責任を感じすぎないように注意してください。
参考文献
[1]乳児院入所児の愛着の形成・修復を担う 直接処遇職員への支援の必要性 Ⅲ先行研究の動向と結果 1.愛着と援助者支援に関する研究の動向
[2]アタッチメント
http://jachn.umin.jp/pdf/chiikikangoindex/No19_attachment.pdf
[3]個別的要素の観点から見るアタッチメント理論の現在
https://www.psy.bun.kyoto-u.ac.jp/COE21/report/H15/9D-0.pdf