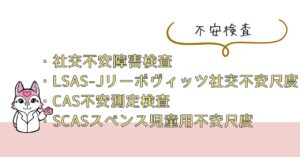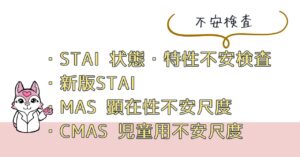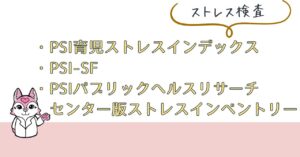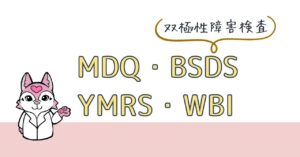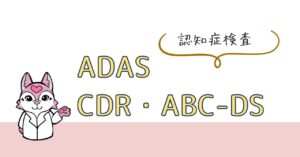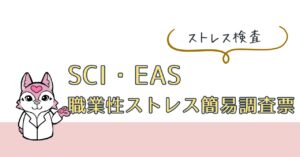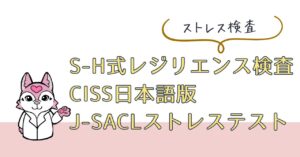統合失調症の心理検査(SCSQ・BPRS・PANSS・BACS・UPSA-B)

この記事は検査の内容を含むため、
結果に影響を与える可能性があります。
検査を受ける本人でない場合のみ、お進みください。
統合失調症の心理検査とは
統合失調症の心理検査は、患者さんの症状や認知機能を評価するための検査です。
面接や質問紙を通じて、幻覚や妄想などの症状の程度、記憶力や注意力などの認知機能を詳しく調べていきます。たとえば、簡単な質問に答えたり、ロールプレイをする課題に取り組んだりするのです。
心理検査の結果は、医師が治療方針を立てる際の判断材料となり、より効果的な治療につながります。また、定期的に検査を行うと治療の効果や症状の変化を客観的に確認できるようになるのです。薬物療法やカウンセリングなどの効果を評価できると、必要に応じて治療内容を見直せます。
また、検査結果を通じて患者さんやご家族が病状をより深く理解できるようになります。治療に対する理解や協力が深まり、よりよい治療環境を整えられるのです。
統合失調症の心理検査一覧
統合失調症の心理検査には、症状や認知機能を評価できるものが5つあります。
患者さんの状態を把握するのに役立つ心理検査です。

それぞれの心理検査を見ていきましょう
心の状態推論質問紙(SCSQ)
心の状態推論質問紙は、他人の気持ちや意図を理解する能力を調べるための検査です。[1]
日常生活で起こりうる、人との関わりで困った場面や悩みやすい状況を質問されます。その場面で相手がどのように感じているか、また相手は何を考えているのかを想像して答えるのです。たとえば「この状況で相手がどのように感じていると思いますか?」や「この人はなぜそのような行動を取ったと思いますか?」などの質問があります。
検査は、次の5つの項目から構成されています。
- 言語記憶
- 文脈からの推論
- 心の理論
- メタ認知
- 敵意バイアス
最終的な合計点は、言語記憶・文脈からの推論・心の理論・メタ認知を合計したもので、最高得点は40点です。[2]検査結果は、患者さんの対人関係の改善や社会生活への適応をサポートするための重要な情報となります。
簡易精神症状評価尺度(BPRS)
簡易精神症状評価尺度は、統合失調症の症状を短時間で評価できる検査です。
医療現場で広く使用されており、患者さんの精神症状を効率的に確認できます。とくに、症状の変化を定期的に把握したいときに役立つのです。
医師や看護師が患者さんに質問をして、患者さんの発言をもとに点数を付けていきます。BPRSの評価項目には、次の18項目があります。[3]
- 心気症
- 不安
- 情動的引きこもり
- 概念の統合障害
- 罪責感
- 緊張
- 衒奇症と不自然な姿勢
- 誇大性
- 抑うつ気分
- 敵意
- 猜疑心
- 幻覚による行動
- 運動減退
- 非協調性
- 不自然な思考内容
- 情動の平板化
- 興奮
- 失見当識
それぞれの項目で、1点(症状なし)~7点(重度)の7段階で採点されます。点数が高いほど、症状が重いと判定されるのです。[3]検査結果は数値化されるため、治療の効果を客観的に評価できます。
陽性・陰性症状評価尺度(PANSS)
陽性・陰性症状評価尺度は、統合失調症の主要な症状を詳しく評価する検査です。
検査者は患者さんの症状を観察し、インタビューを通じて情報を集め状態を評価します。
項目は陽性症状、陰性症状、総合精神病理尺度のグループに分けられ、合計30項目を評価します。それぞれの項目は以下の通りです。[4]
【陽性症状】
- 妄想
- 概念の統合障害
- 幻覚
- 興奮
- 誇大性
- 疑念/被害念慮
- 敵意
【陰性症状】
- 情動の平板化
- 情動的引きこもり
- 疎通性の障害
- 受動性/意欲低下による社会的引きこもり
- 抽象的思考の困難
- 会話の自発性と流暢さの欠如
- 常同的思考
【総合精神病理尺度】
- 心気症
- 不安
- 罪責感
- 緊張
- 衒奇症と不自然な姿勢
- 抑うつ
- 運動減退
- 非協調性
- 不自然な思考内容
- 失見当識
- 注意の障害
- 判断力と病識の欠如
- 意志の障害
- 衝動性の調節障害
- 没入性
- 自主的な社会回避
それぞれ1(症状なし)~7(最重度)までの7段階で評価され、検査結果は治療方針の決定や、薬物療法の効果確認に活用されます。[4]
統合失調症認知機能簡易評価尺度(BACS)
統合失調症認知機能簡易評価尺度は、思考や記憶などの認知機能を評価する検査です。
BACSでは、記憶力や注意力、問題解決能力などを総合的に評価します。
短時間で効率的に実施できるよう工夫されており、患者さんの負担を少なくできるのです。
6つの項目を約30~40分で実施し、認知機能の領域を評価します。[5]
- 言語性記憶と学習
- ワーキングメモリ
- 運動機能
- 言語流暢性
- 注意と情報処理速度
- 遂行機能
それぞれの項目の得点を計算したら、各得点と合計点を分析し認知機能の状態を評価します。
約30分で多様な認知機能を評価できるため、臨床現場での実用性が高いでしょう。検査結果は、認知機能のリハビリテーションの計画立案や、治療効果の確認に役立てられます。
UCSD日常生活技能簡易評価尺度(UPSA-B)
UCSD日常生活技能簡易評価尺度は、日常生活での実践的な能力を評価する検査です。
買い物や公共交通機関の利用など、実生活で必要となる具体的なスキルを確認します。患者さんの生活の質を向上させるため、サポートにつながる情報を得られるのです。
検査はロールプレイ形式で行われ、実際の生活シナリオに基づいて患者さんの行動を観察します。たとえば、買い物の予算決めや電話での会話などが行われます。
UPSA-Bを構成する項目は、次の2つです。[6]
- 金銭管理技能
- コミュニケーション技能
それぞれの課題は50点満点で評価され、合計点は100点です。検査結果は、リハビリテーションの計画立案や、自立支援のための具体的な目標設定に活用されます。
統合失調症の心理検査における注意点
統合失調症の心理検査を受ける際は、2つの注意点があります。
- 検査内容を事前に調べない
- 質問項目には正直に答える
検査の内容を事前に調べたり準備したりすることは避けてください。事前に準備をすると、正確に評価できない可能性があるためです。
また、質問には必ず正直に答えることが大切です。自分をよく見せようとして実際と異なる回答をすると、適切に評価できなくなってしまいます。その結果、最適な治療方針を立てることが難しくなる可能性があるのです。



事前に何の検査か知ることで正確な結果が出なくなってしまいます💦
まとめ
統合失調症の心理検査は、患者さんの症状や認知機能を評価し、効果的な治療につなげるためのツールです。
心理検査には、症状の評価を行うBPRSやPANSS、認知機能を測定するBACSなど、さまざまな種類があります。それぞれの特徴を表にまとめました。
| 検査名 | 調べる内容 | 特徴 | 検査方法 |
| 心の状態推論質問紙(SCSQ) | 他人の気持ちや意図を理解する能力 | 社会的な場面での理解力を測定 | 日常生活の葛藤場面について質問に答える |
| 簡易精神症状評価尺度(BPRS) | 精神的な症状の全体的な重さ | 短時間で幅広い症状を評価 | 18項目の症状を7段階で評価する |
| 陽性・陰性症状評価尺度(PANSS) | 統合失調症の症状の程度 | 詳しく症状を評価 | 30項目の症状を7段階で評価する |
| 統合失調症認知機能簡易評価尺度(BACS) | 思考や記憶などの認知機能 | 統合失調症に特化した認知機能を測定 | 6つの分野で課題をこなす |
| UCSD日常生活技能簡易評価尺度(UPSA-B) | 日常生活でのスキル | 実際の生活能力を簡単に測定 | 日常生活の場面を想定した課題をこなす |
これらの検査を組み合わせることで、患者さんの状態を多角的に把握できるのです。
心理検査を受ける際は、事前に内容を調べたり準備したりせず、質問には正直に答えましょう。定期的な検査により、治療の効果を確認し治療方針を見直せます。
統合失調症の診断を確定させるために、心理検査を有効活用してください。
【参考文献】
[1]統合失調症の社会認知機能を経頭蓋直流刺激で改善 ~精神疾患を対象とした特定臨床研究~|国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター National Center of Neurology and Psychiatry
https://www.ncnp.go.jp/topics/2022/20220726p.html
[2]PCN Volume 68,Number9の紹介
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1170020166.pdf
[3]BPRS 日本語版・評価マニュアル(Ver.1.1)
https://www.ych.pref.yamanashi.jp/kitabyo/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/BPRS.pdf
[4]統合失調症について|名城大学薬学部
https://www-yaku.meijo-u.ac.jp/Research/Laboratory/chem_pharm/09jugyou/091016%20SCZ%20summary.pdf
[5]統合失調症の認知機能障害と機能的アウトカム
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbp/20/2/20_2_83/_pdf/-char/en
[6]UCSD日常生活技能簡易評価尺度(UCSD Performance-based Skills Assessment-Brief,UPSA-B)日本語版の開発,住吉チカ,西山志満子,水上祐子,住吉太幹
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/77/0/77_3AM-044/_pdf/-char/ja