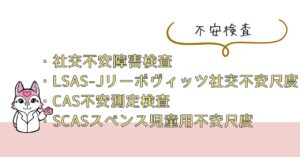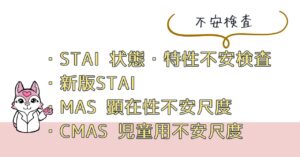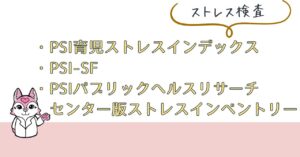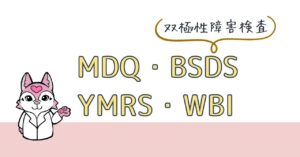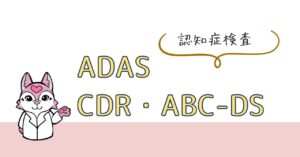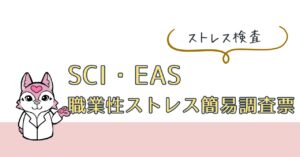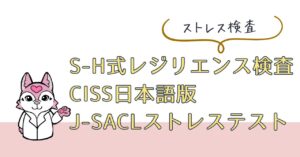解離性障害の心理検査(DIS-Q・DES・CDS・SDQ-20)
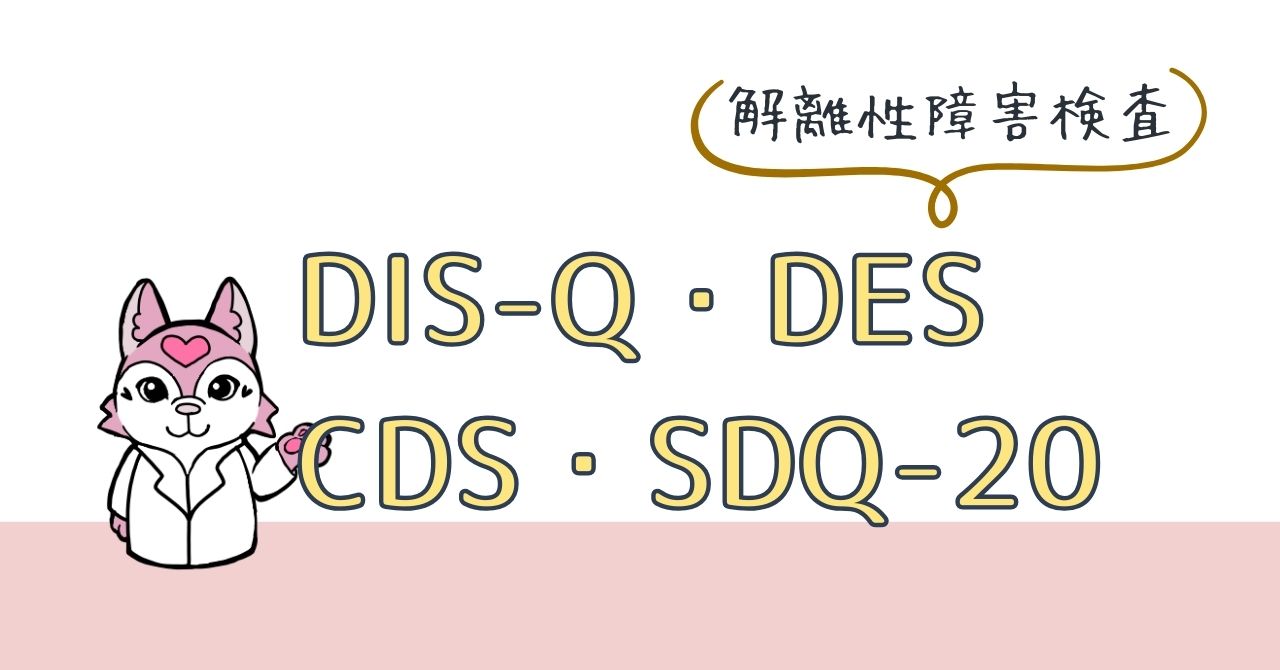
この記事は検査の内容を含むため、
結果に影響を与える可能性があります。
検査を受ける本人でない場合のみ、お進みください。
解離性障害の心理検査における目的
解離性障害の心理検査には、次の3つの目的があります。
- 治療計画を立てる
- 診断の精度を上げる
- 症状や行動のパターンを客観視できる
まず、治療計画を立てる際の参考情報になります。心理検査の結果から症状の種類を把握でき、一人ひとりに適切な治療方法を選べるようになるのです。
次に、診断の精度を高める材料となります。心理検査を行うことでより正確な診断ができ、適切な治療につなげられるのです。
また、患者さん自身も症状や行動のパターンを客観的に確認できます。心理検査によって数値化された結果をもとに、症状の変化を追跡できるようにもなります。
これらの目的を達成することで、より効果的な治療につなげられるのです。

検査をすることで自分の症状に気づくきっかけにもなります
解離性障害の心理検査一覧
解離性障害の心理検査は、次の4種類です。
それぞれについて見ていきましょう。
解離症状質問票(DIS-Q)
DIS-Qは、日常生活における解離症状の有無を確認する心理検査です。
63個の質問に、1(全くなし)~5(非常にあてはまる)の5段階で回答していきます。[1]
質問項目は記憶の途切れや離人感、現実感の喪失といった症状に関するものがあります。たとえば「自分の行動をロボットのように感じる」「自分の体が自分のものではないように感じる」などの内容です。
質問項目は、次の4つから構成されています。
- 健忘
- 没頭
- 同一性混乱・分裂
- コントロール喪失
DIS-Qの得点が高くなるほど、解離症状の程度が高いと判定されます。
解離性体験尺度(DES)
DESは、解離性障害の症状を詳しく評価する心理検査です。
この検査では、28項目の質問に答えていきます。たとえば「運転している時に、どうやって目的地まで来たのか覚えていない」「自分の身体が自分のものではないように感じる」といった日常的な体験について尋ねられます。
それぞれの質問に対して0〜100%の11段階でどのくらい解離した体験があるかを回答すると、解離症状の程度を数値化できるのです。[2]
DESは簡単な心理検査なので、診察の待ち時間に患者さんが回答できます。検査結果は点数が高いほど、解離性障害の疑いがあると判定されます。[3]
解離症状を見つける検査方法として有効なのです。



簡易的に取り組めるため使用しやすいですね!
ケンブリッジ離人尺度(CDS)
ケンブリッジ離人尺度は、離人症状に焦点を当てた心理検査です。
29個の質問があり、離人感や現実感の喪失について詳しく評価します。たとえば「周りの世界が不自然に見える」「鏡で見る自分の姿が他人のように感じる」といった項目について、過去半年間に起きた頻度を回答するのです。
頻度は0(全くない)~4(いつもある)の5段階で回答します。頻度で0以外の回答をした項目では、持続時間を1(数秒間)~6(1週間以上)の6段階で答えます。[4]
CDSでは、離人症状の程度を客観的に把握できます。合計点が高くなるほど、症状が強いと判定されるのです。
身体表現性解離質問票(SDQ-20)
身体表現性解離質問票は、身体症状として現れる解離症状を評価する心理検査です。
20個の質問に答えていき「体の一部が麻痺したように感じる」「声が出なくなる」などの身体的な症状について尋ねます。
症状の頻度を0(全く当てはまらない)~4(非常に当てはまる)の5段階で評価し、解離症状の程度を明らかにできます。[5]
点数は20~100点の範囲でつけられ、それぞれの項目の点数を合計して求めます。40点以上になると解離性障害を発症している可能性があると判定されるのです。[6]
解離性障害の心理検査における注意点
解離性障害の心理検査を受ける際には、2つの注意点があります。
- 事前に質問紙の内容を調べない
- 家族が心理検査を受けることも検討する
まず、事前に質問紙の内容を調べないようにしましょう。質問の内容を知っていると、無意識のうちに「こう答えるべきだ」という思い込みが生まれてしまいます。できるだけありのままの状態で検査にのぞんでください。
また、家族が心理検査を受けることも検討しましょう。解離性障害を発症している方は、自身の状態に気づいていない可能性があります。そのため、普段の様子をよく知っている家族が検査を受けることで、より正確な状況把握ができるのです。
まとめ
解離性障害の心理検査は、治療計画の立案や診断の精度向上などに役立ちます。検査には、解離症状質問票や解離性障害評価尺度などの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
検査を受ける際は事前に質問内容を調べず、必要に応じて家族による受検も検討することが大切です。これらの注意点を守ることで、より正確な検査結果を得られます。
心理検査は、解離性障害の治療において重要な役割を果たします。検査結果をもとに、医師と相談しながら治療を進めていきましょう。
【参考文献】
[1]心的外傷との関連からみた精神分裂病患者の解離症状
https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/00044707/00044707.pdf
[2]DES-Ⅱ尺度で測定した日常解離性体験の体験頻度及びその体験評価について p52
https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/2228903/p051.pdf
[3]解離性障害をいかに臨床的に扱うか
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1170060399.pdf
[4]現実世界からの逃走ー離人症状の分類と回避傾向の関連について
https://www.jstage.jst.go.jp/article/personality/15/3/15_3_362/_pdf
[5]身体表現型解離尺度の検討ー被虐待経験との関連からー
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/72/0/72_2AM020/_pdf
[6]Somatoform Dissociation Questionnaire
https://emdrtherapyvolusia.com/wp-content/uploads/2016/12/SDQ-20.pdf