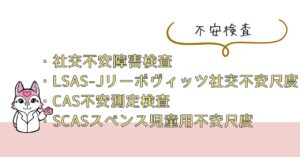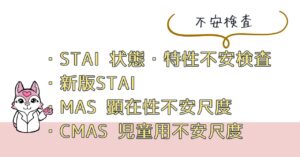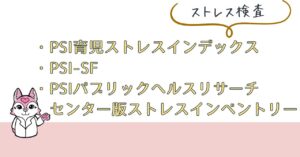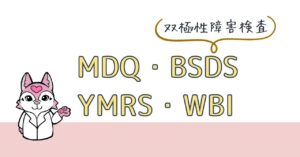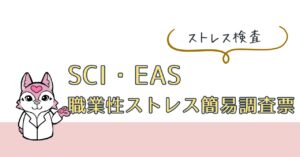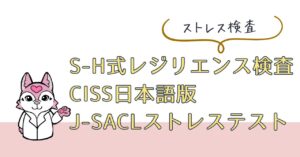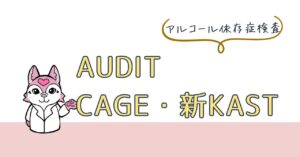認知症の心理検査(ADAS・CDR・ABC-DS)
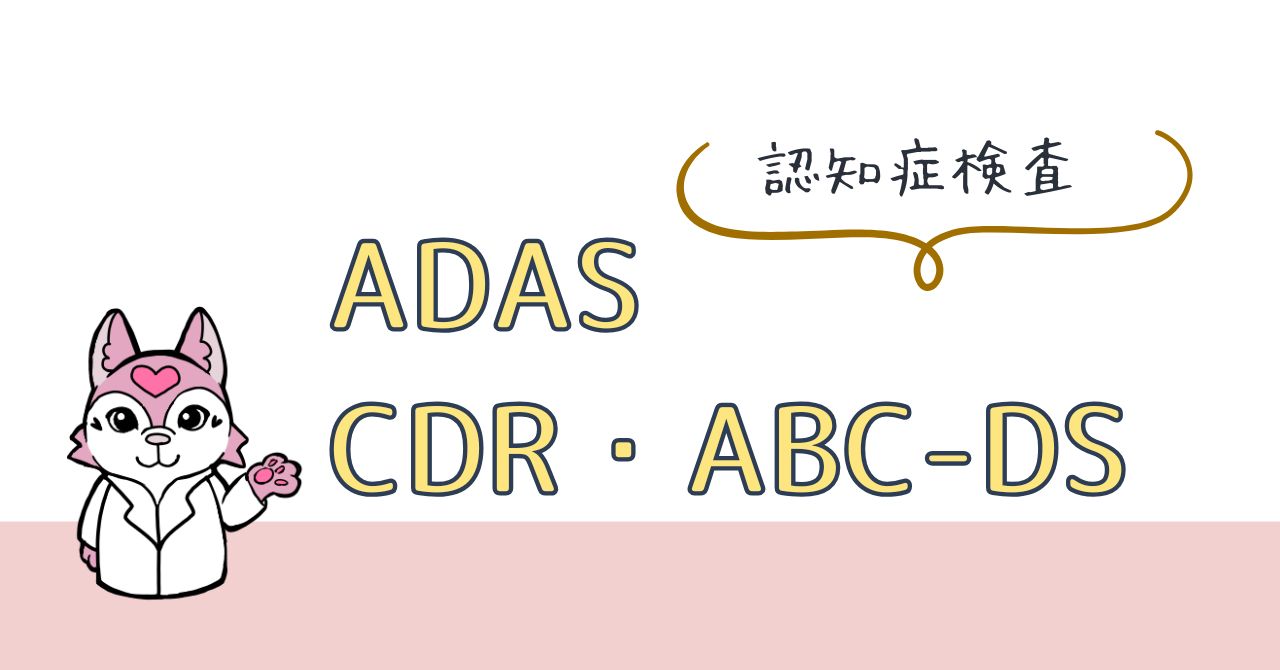
この記事は検査の内容を含むため、
結果に影響を与える可能性があります。
検査を受ける本人でない場合のみ、お進みください。
認知症の検査
認知症の心理検査には、スクリーニング(認知症の疑いがあるかを見つける検査)や認知症重症度を判断するための検査など、多くの検査があります。
同じ検査を3か月後、1年後などにくり返し実施することで、認知症の進行や症状の改善を評価できるのです。
この記事では、以下の認知症心理検査を紹介します。
他の認知症心理検査は下記の記事をご覧ください。
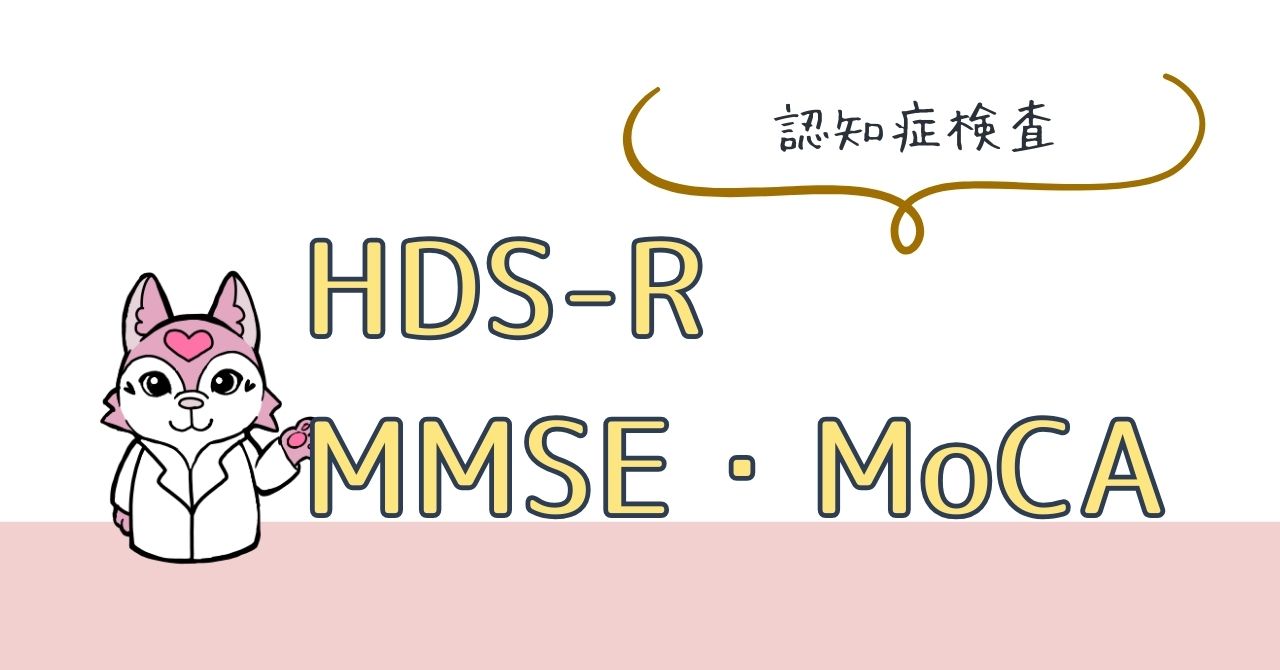

アルツハイマー病評価尺度(ADAS)
ADASは、アルツハイマー型認知症の認知機能を評価する心理検査です。[1]
検査時間は約40分前後で、認知症で低下しやすい項目で構成されており診断や抗認知症薬の治験などで国際的に活用されています。
以下の2点が特徴的な検査です。[2]
- くり返し検査が可能
- 学習効果が生じやすい記憶課題
ADASは、認知機能下位尺度(ADAS-cog)11項目と非認知機能下位尺度(ADAS-non cog)10項目の2つの下位尺度から構成されています。
検査内容
認知機能下位尺度(ADAS-cog)独自で使用されることが多いため、ADAS-cogについて見ていきましょう。[3]
ADAS-cogは記憶・言語・行為の3領域の評価に重点をおき、11項目で構成されています。[]
- 単語再生
- 口頭言語能力
- 言葉の聴覚的理解
- 喚語困難
- 口頭命令に従う
- 手指および物品呼称
- 構成行為
- 観念運動
- 見当識
- 単語再認
- テスト教示の再生能力
結果
点数による評価は以下のとおりです。[3]
23.1 ± 7.7点:極軽度
22.9 ± 8.9 点:軽度
38.6 ± 9.8 点:中等度
54.8 ± 7.6 点:高度
ADAS-cogは、全問正解で0点、全問不正解で70点の検査です。HDS-RやMMSEとは採点が異なり、高得点になるほど認知機能障害の可能性が高くなります。
実際の検査用紙は、こちらの厚生労働科学研究成果データベースにあります。
Clinical Dementia Rating(CDR)
CDRは、認知症の重症度を評価する観察式の心理検査で世界中で広く使われています。[3]
観察式のため、患者さん本人だけではなく、患者さんの日常生活をよく知っている人からの情報も必要です。
6項目を5段階で総合的に評価し、認知症の重症度を判断します。

日常をよく知っているご家族からの情報は、
本人をよく知るために大切です。
検査内容
CDRの質問項目は以下のとおりです。[3]
- 記憶
- 見当識
- 判断力と問題解決
- 地域の活動
- 家族状況および趣味
- 身の回りの世話
結果
各項目を下記の5段階で評価します。[3]
0点:健康
0.5点:認知症の疑い、軽度認知障害(MCI)
1点:軽度認知症
2点:中等度認知症
3点:高度認知症
5 段階でそれぞれの項目を評価し、 項目の評価点を総合的に判断するのです。
実際の検査用紙は、こちらの厚生労働科学研究成果データベースにあります。
ABC認知症スケール(ABC-DS)
ABC認知症スケールは、認知症の重症度評価を目的として作成された、ADL・BPSD(認知症の行動・心理状態)・認知機能を同時に評価できる検査です。[4]
評価者は特別な資格は必要なく、誰でも検査ができます。
約10分という短時間で、13項目を9段階で評価する行動観察スケールです。[5]
ABC認知症スケールに関しては、医療イノベーション推進センターのこちらで詳しくご覧ください。
認知症の心理検査における注意点
認知症の心理検査をする際には、患者さんが安心して取り組めるように以下のことに注意しましょう。[6][3]
それぞれ詳しく解説します。
検査導入時の対応
認知症の心理検査を患者さんの本来の姿で行うために、リラックスできる環境を整えることが大切です。
心理検査をするときは「何をするのかな?」「この結果で自分はどうなってしまうのかな?」という不安を抱いたまま検査をすると、緊張や不安で本来の自分を出せずに検査が終了するケースも珍しくありません。
他にも、検査者が「この検査は決まっている検査だから!」と高圧的な態度をとると、患者さんの緊張や不安はさらに高まります。
まずは信頼関係を築きコミュニケーションを取りながら、安心して検査を受けられる環境を整えることから始めましょう。
検査目的を伝える
今から行う検査はどのような目的があるのか、何のために行うのかをハッキリと患者さんに伝えましょう。
以下の目的を伝えることで、検査への協力をお願いしやすくなります。
- 診断の手助けになる
- 今後の治療に役立つ
- 今の症状の具合を知ることができる
何が目的か分からない状況で検査を行うと、不安は募るばかりです。安心して検査に取り組んでもらうためにも、検査目的を明確に伝えることが大切です。
検査後のアフターケア
検査終了時に「あまりできなかった…」と嫌な気持ちで終わると、自信を失ってしまうことがあります。そのため、検査後のアフターケアが大切です。
「はい、終了です」で終わるのではなく「疲れましたか?今日はゆっくり休んでくださいね」「ご協力ありがとうございます」などのねぎらいの言葉をかけることも効果的です。
まとめ
この記事では認知症の心理検査として、ADAS、CDR、ABC-DSについて解説しました。
心理検査によりなにが苦手なのかや重症度を判断することで、日常生活で困っていることへのサポートを考えることができます。
また、定期的にくり返し検査を行うことで、治療効果や症状の進行具合を適切に把握することも可能です。
認知症の心理検査を行う場合は、患者さんが安心して取り組めるように、今回紹介した注意点を参考にしてください。
【参考文献】
[1]物忘れ外来における神経心理検査について|関 美 雪
https://www.ohashi.med.toho-u.ac.jp/iryokan/vk7ie40000000l26-att/rhlvl80000001e8x.pdf
[2]健常者と軽度認知障害/認知症の 2 群に分類するのに有効な心理検査|杉下 守弘、逸見 功https://www.jstage.jst.go.jp/article/ninchishinkeikagaku/15/2/15_103_1/_pdf/-char/ja
[3]神経心理学的検査|河月 稔
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jamt/66/J-STAGE-2/66_17J2-3/_pdf/-char/ja
[4]ABC 認知症スケールの妥当性について|阿南 君佳、下田 航
https://www2.am.nagasaki-u.ac.jp/ot/homepage/pdf/a7.pdf
[5]認知機能の評価法と認知症の診断|一般社団法人 日本老年医学会
https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/tool/tool_02
[6]改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)の理解と活用|加藤伸司
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjcgp/4/0/4_47/_pdf/-char/ja