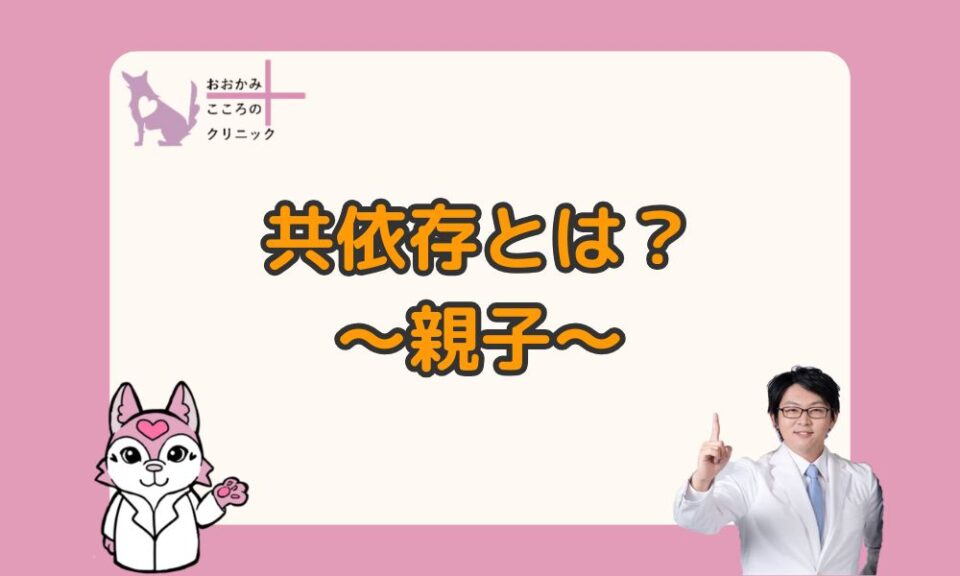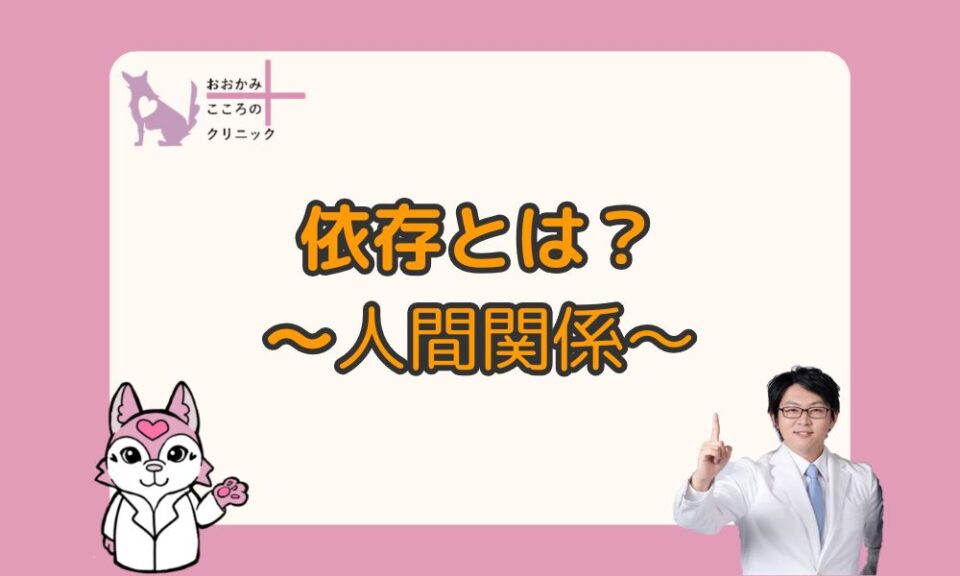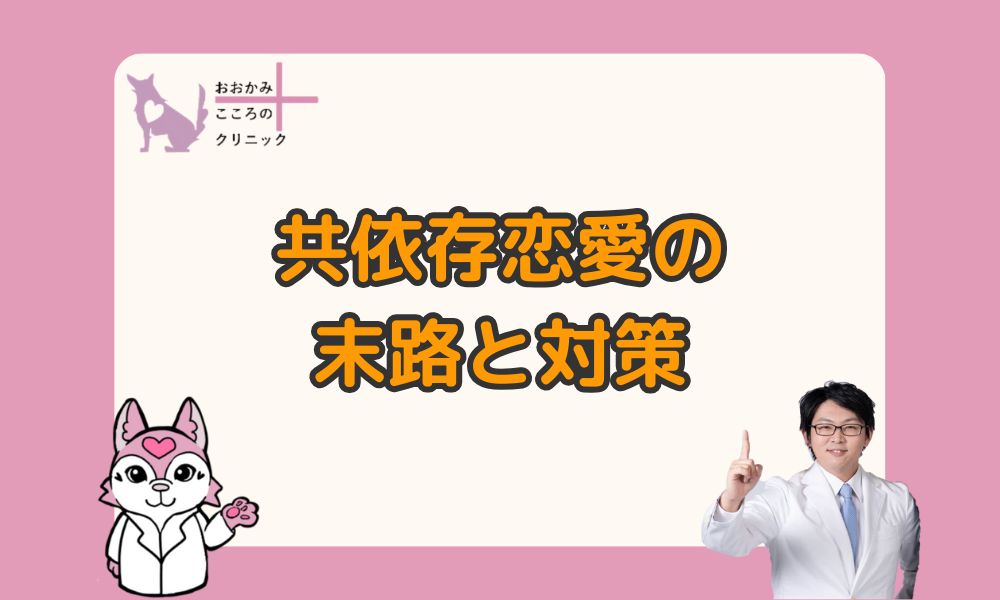「相手に合わせすぎて疲れてしまう」
「嫌われたくなくて言いたいことが言えない」
そのような行動に、こころが疲れていませんか。
それは、共依存的な行動パターンによって生まれている負担かもしれません。
共依存とは、特定の人との関係に依存して離れられない状態を指します。[1]
共依存の行動パターンや背景を知り、無意識のクセに気づけば、自分をすり減らす関係性から少し距離をとり、安心できるつながりを築くことが可能です。
この記事では、共依存的な行動パターンの特徴や背景、抜け出すためのヒントなどについてお伝えします。
この記事を通して、共依存に悩むあなたのモヤモヤが少しでも軽くなれば幸いです。
共依存者の行動パターンチェックリスト
共依存的な傾向がある人の行動パターンとして、以下7つが挙げられます。[2]
▢ ひとりでやっていけるという自信が持てない
▢ 自分を犠牲にしてまで相手の世話を焼いてしまう
▢ 相手の行動や感情・考え方をコントロールしてしまう
▢ 自分に自信がなく、相手に見捨てられるのが怖くて本音を言えない
▢ 自己評価が低く、相手の期待に応えることでようやく自分の価値を感じられる
▢ 他者との境界線があいまいで、相手の問題や感情を自分の責任のように感じる
▢ 自分の感情や欲求がわからず、自分自身を大切にできない(自己確立ができていない)
当てはまる項目が多いほど、共依存の傾向が強いと考えられます。
ただ、共依存は「性格」ではなく「状態」です。
たとえば、パートナーと一緒にいるときは「相手の機嫌を優先して自分の気持ちを言えない」といった共依存的な行動が出やすくても、友人といるときは本音で話ができ自然体で過ごせる場合があります。
このように、共依存的な行動は、誰とどんな関係にいるかによって変わることがあるのです。
一部分だけを見て「わたしは共依存者なんだ」と決めつける必要はありません。
共依存の傾向はあなたの一部にすぎないため、あなた自身をまるごと否定する必要はないのです。

よいところも悪いところも含めてあなた自身です。
一部だけをみて、決めつけないようにしてくださいね♪
共依存者の行動パターンの背景にある特徴
共依存的な行動の背景にあるのは、育った家庭環境や過去の人間関係です。
とくに以下のような生育歴が共通していると考えられています。 [3]
- 親に必要以上に突き放された
- 虐待やネグレクトを受けていた
- 親が過保護で自分の意見を持てなかった
- 摂食障害やパーソナリティ障害・依存症などを抱えた家族と暮らしていた
- 自分の気持ちや願いに家族や周囲の反応がなく「わかってもらえた」「認められた」と感じることが少なかった
このような環境で育つと、相手に尽くすことで「自分はここにいていい」という安心感を得るようになり、相手に依存する傾向が強まるのです。
親子関係における共依存について知りたいときは、こちらの記事を合わせてご覧ください。
共依存者の行動パターンにより感じやすいこころの負担
共依存的な行動パターンで感じやすいこころの負担を、以下の視点にわけて解説します。
ひとつずつ見ていきましょう。
自分自身が感じやすいこころの負担
共依存的な行動は、本人にとっても心身の負担となります。
他人を優先しすぎると自分の気持ちや疲れに気づきにくくなり、ストレスや孤独感を得やすくなるのです。
例として、以下のような状況が挙げられます。
- ストレスや疲労感が長く続きやすい
- 孤独感や自己否定感を抱えやすくなる
- 一時的に安心感を得てもすぐに不安になってしまう
誰かとつながるためにムリをすると、知らず知らずのうちにこころがすり減ってしまうのです。

ちょっと立ち止まってムリをしていないか考えてみましょう!
相手との関係で感じやすいこころの負担
共依存的な行動により、気づかないうちに相手との距離感や関係のバランスが崩れてしまうことがあります。
例として挙げられるのは、以下のような状況です。
- 上下関係ができて対等な関係が築けなくなる
- 相手に執着しすぎてつらくても離れられなくなる
- 相手の気持ちや考えをコントロールしてしまう(またはコントロールされてしまう)
こうした関係性は、気づかないうちに苦しさや不安定さを深め、相手との関係を負担に感じやすくなります。
人間関係全体で感じやすいこころの負担
共依存的な行動が続くと、特定の相手だけでなく他の人との関係でも負担を感じやすくなります。
無意識のうちに「自分を必要としてくれる人」を求めてしまい、多くの人とかかわる機会を逃しやすくなるためです。
結果として、以下のような傾向が見られます。
- 不安や孤独を抱えた人と深くかかわりやすくなる
- どの人間関係においても「役に立たなければ」とムリをしがちになる
- 安定したつながりが築きにくく自分をすり減らす関係を繰り返してしまう
このように、人間関係全体においてもムリをする苦しい関係を築きやすくなってしまうのです。
人間関係における依存について知りたい方は、こちらの記事を合わせてご覧ください。
共依存者の行動パターンから抜け出す方法
共依存的な行動パターンから抜け出す方法として、以下3つが挙げられます。
ひとつずつ見ていきましょう。
共依存のサインに気づく
共依存的な行動から抜け出すためには、まず共依存のサインに気づきましょう。
共依存は無意識に身についた「こころのプログラム」のようなもので、自分では気づきにくいのが特徴です。[3]
以下のような思いを感じたときは「相手との関係が共依存になっているかも」と立ち止まりましょう。
- 相手がいないと不安になる
- 相手の機嫌に左右されて気疲れする
- 相手の問題を自分の責任のように感じる
共依存的な行動から抜け出すためには、小さな違和感に気づくことが大切です。
そのサインを無視せずにあなたのこころに耳を傾けてみてください。
関係を見直す勇気を持つ
共依存的な関係から抜け出すために、まず関係を見直す勇気を持ちましょう。
共依存の関係は情や罪悪感が生まれやすく、苦しさを感じていても簡単に離れられるものではありません。
相手とこころの距離を保つのが難しいときは、以下のような方法で物理的な距離を取りましょう。
- スマホの電源を一時的にオフにする
- 会う頻度を減らす(例:毎日→数日に1回 )
- ひとりになる時間を意識的につくる(カフェ・図書館など)
関係を断つことは、決して相手を否定することではありません。
自分のこころと向き合う時間をつくることが、お互いにとって健全な距離感を保つことにつながります。
共依存恋愛について詳しく知りたいときは、こちらの記事を参考にしてください。
相手以外とのつながりをつくる
共依存的な関係から少しずつ距離をとるためには「相手以外ともつながること」が有効です。
特定の相手だけに気持ちが向きすぎると、自分自身の気持ちや考えが見えにくくなってしまいます。
以下のような方法で、他者とのつながりを増やしてみましょう。
- カフェや公園で、店員さんや他の利用者にあいさつをしてみる
- SNSで趣味のアカウントをフォローして気が向いたらコメントする
- 職場以外のコミュニティ(ボランティアやサークル、オンラインコミュニティなど)に参加する
誰かと深くかかわる必要はありません。
「外の空気をちょっと入れてみよう」くらいの気軽なつながりを探しましょう。
まとめ
共依存は、誰にでも起こりうるこころのクセのひとつです。
相手を思って行動していても、気づかないうちに自分をすり減らし、関係そのものが苦しみの原因になることがあります。
少しずつ相手との距離や、自分の気持ちを見つめ直す時間を作りましょう。
共依存的な行動パターンに繰り返し悩んでしまうときは、育った環境や深い自己否定感が関係していることがあります。
つらさが続くときは、ひとりで抱え込まず、信頼できる第三者に相談することも大切です。
おおかみこころのクリニックでは、あなたが自分らしく人とかかわれるようサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考資料】
[1]こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/over/864
[2]大学生の共依存傾向と自己愛傾向との関連について
(Microsoft Word – 08-0701\201@\220\302\226\330\217\272\215G\201@\215\317.doc)
[3]柿澤 暁|共依存症問題についての考察 2.2 共依存症の概念と定義
https://mu.repo.nii.ac.jp/record/1257/files/humanstudies9_05.pdf
- この記事の執筆者
- とだ ゆず
精神科看護師としての経験を活かし、メンタルヘルスを中心とした記事を執筆。こころと身体のつながりを大切にしながら、そっと寄り添う文章を心がけています。
保有資格:看護師、保健師、上級心理カウンセラー、漢方養生指導士