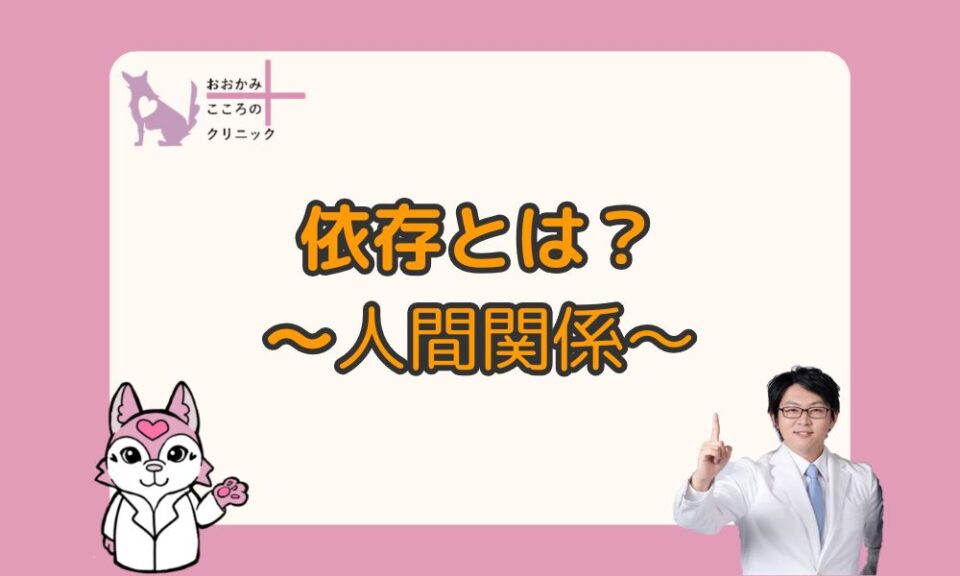依存症と聞くと、アルコールや薬物のような深刻なものを思い浮かべるかもしれません。
ただ、依存症は特別な人だけがなるものではなく、誰にでも起こりうる「脳のはたらき」に関する病気です。
買い物やスマホ、恋愛や人間関係など、身近なものが知らず知らずのうちに依存の対象になるケースもあります。
この記事では、依存症の種類や「依存症かも?」と思ったときの心理、依存症になるまでの3段階などについて解説します。
「これって依存症かも?」と不安になったときに、自分のこころを見つめ直すきっかけになれば幸いです。
依存症一覧
依存症は、大きく分けて以下の3つのタイプに分類され、いずれも自分の意思ではやめられない状態です。[1]
ただ、これらはきっちりと分けられるものではなく、実際には複数のタイプにまたがるケースも多く見られます。
それぞれ詳しく見てみましょう。
ものへの依存
ものへの依存とは、ある物質を摂取することで脳が感じる「気持ちよさ」や「安心感」を繰り返し求めてしまう状態です。
具体例として、以下が挙げられます。
- アルコール
- ニコチン(タバコ)
- カフェインやスイーツなどの食べ物
- 医療用の薬(精神安定剤や睡眠薬など)
- 薬物(大麻や覚醒剤、危険ドラッグなど)
とくにアルコールやカフェイン、食べ物のように日常生活の中にあるものは、依存していても自分では気づきにくいことがあります。
行為への依存
行為への依存とは、ある行動の始まりから終わりまでの過程に強く惹かれ、気づかないうちにやめられなくなる状態です。
具体例として、以下のような行為が挙げられます。
- 万引き
- ギャンブル
- カルト集団への執着
- ダイエットや過度な運動
- 性的行為(痴漢・盗撮など)
- 買い物(浪費や衝動買いなど)
- 自傷行為(例:リストカット)
- 過剰な仕事(ワーカホリック)
- ゲームやスマホ・ネットの長時間使用
このタイプは行動によって得られるスリルや達成感、気分の高まりなどが脳に快感として記憶され、繰り返すほど強化されていきます。
日常のストレスや孤独感、不安から気をそらす手段として使われることも多く「やめたいのにやめられない」と悩みやすいのが特徴です。
特定の行為をやめたいと思いながらもやめられないときは、ストレスや孤独が隠れているかもしれません。

やめたいと思ってもやめられない…
依存症で苦しんでいる人は多くいます💦
人間関係への依存
特定の相手に気持ちが偏りすぎたり「その人がいないと不安」「拒まれるのが怖い」と感じたりすると、人間関係そのものが依存の対象になります。
人間関係への依存には、以下のような形があります。
- 共依存(相手を支えることで自分の価値を感じる関係)
- 恋愛依存(仕事やお金よりも恋愛を優先してしまう)
- 性的依存(セックスや盗撮など性的関係に強く執着する)
- 家族関係の依存(DVや虐待、ひきこもりなど)
「大切な人だから」「好きだから」と思っていた関係が、いつのまにか自分を苦しめているなら、それは依存のサインかもしれません。
人間関係の依存について詳しく知りたいときは、以下の記事をあわせてご覧ください。
依存症かも?と思ったときの心理
「もしかして依存症かも?」と思っても、自分の状態を否定したりまだ大丈夫と軽く考えてたりするのは自然な反応です。
例として、以下のような考え方が挙げられます。[2]
- 相談するほどじゃない
- もっと深刻な人がいるから
- 自分の勝手だからほっといて
- そんなだらしない人間じゃない
- 依存症なんて特別な人がなるもの
- コントロールできているから大丈夫
このような考えにとらわれながら「つい繰り返してしまう」「やめたいのにやめられない」という状態が続くときは、依存症のサインかもしれません。
少しでも気になることがあれば、自分を責めずに信頼できる場所に頼ることが大切です。
すぐに相談先を知りたいときは、こちらを先にお読みください。

ひとりで悩まずに相談にきてくださいね
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
依存症になるまでの3段階
依存症になるまでには以下の3段階があります。[1]
それぞれ解説します。
1.趣味や気分転換の段階
日常生活を豊かにする健全な趣味や、気分転換として楽しめる段階です。
対象となる行動や物ごとを自分の意思で調整でき、生活や人間関係に悪影響を与えることはありません。
例として、以下のような状態が挙げられます。
- 仕事のご褒美に買い物をする
- 同僚と仕事帰りにお酒を飲む
- 疲れた日に甘いものを食べてホッとする
このように生活のバランスを保ちながら楽しめている場合は、依存ではなく健全な趣味や気分転換の範囲です。
2.依存症予備軍の段階
依存に近づいているサインがあっても自覚がないケースが多く、早めの気づきが重要な段階です。
本人の努力によってコントロールは可能ですが、日常生活への悪影響が少しずつ出始める場合があります。
例として挙げられるのは、以下のような状態です。
- ゲームのことばかり考えて仕事中に気が散る
- お酒を飲まないと決めたのについ誘惑に分けてしまう
- 夜更かしして動画を見続け寝坊して遅刻しそうになる
この段階は「少しハマりすぎたかな」程度の感覚でとらえやすく、依存の可能性を見逃しやすいのが特徴です。
やめたほうがいいとは思いつつも続けてしまう場合は、すでに依存の手前にあるかもしれません。
###3.依存症の段階
この段階は自分の意思ではやめられない状態で、日常生活に深刻な影響が出ることが多くなります。
やめたいと思っていても、時間やお金、人間関係を犠牲にしてまで続けてしまう状態です。
例として、以下のような状態が挙げられます。
- お酒を飲みすぎて家族との関係が悪化している
- スマホゲームに没頭し仕事や家事が手につかない
- もう買わないと決めたのにまたネットで衝動買いしてしまう
依存症の段階は本人の意思や努力だけでの回復は難しく、医療機関や専門家の支援が必要です。
依存症はこころが弱い人がなる病気ではない
依存症はこころが弱い人がなる病気ではありません。
依存症は脳の「快感」や「安心」を感じる仕組みが強く働くことで欲求が高まり、自分ではコントロールが難しくなる病気です。
性別や年齢、社会的な立場などにかかわらず、誰にでも起こるとされています。[2]
依存症の背景には以下のようなこころの痛みや、生きづらさが隠れているケースがあります。
- 孤独感
- ストレス
- 過去のつらい体験
多くの場合、苦しさや不安をまぎらわせるために始めた行動が、やがて自分を追い詰めるものになってしまいます。
依存症になった本人や周囲を責めず、支えが必要な状態として向き合っていくことが大切です。
依存症の相談先
「もしかして依存かも…」と感じたときは、ひとりで抱え込まず以下のような相談先を利用しましょう。
- 依存症専門の医療機関
- 依存症に特化した診療を専門医が行う病院やクリニックです。
精神科や心療内科でも依存症は診れますが、依存症は専門外なところもあります。
受診前に「依存症の相談ができるか」を確認しておくと安心です。
- 精神保健福祉センター・保健所
- 各自治体に設置されており、依存症についての相談や情報提供を行っています。
無料で利用でき、必要に応じて医療機関や支援機関につないでもらうことも可能です。
- 自助グループ
- 同じ悩みを抱える人が対等な立場で集まり、支え合うグループです。
アルコールやギャンブル、恋愛など、テーマごとにさまざまなグループがあります。
医師の診断がなくても参加できるため、気軽に話を聞いたり自分の気持ちを整理したりする場として活用できます。
まとめ
依存症は「ものへの依存」「行為への依存」「人間関係への依存」の3つに分けられ、自分でも気づかないうちにエスカレートします。
依存症はこころの弱さや性格の問題ではなく、脳の働きにかかわる病気です。
背景には孤独感やストレス、過去のつらい経験などが関係しているケースもあり、苦しさから逃れるために始めたことが依存になるケースが少なくありません。
「依存症なのか、自分ではよくわからない」「話を聞いてほしいだけでもいいのかな…」という不安を感じているときは、おおかみこころのクリニックにご相談ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考資料】
[1]榎本稔 よくわかる依存症 主婦の友社
[2]厚生労働省|依存症啓発リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001297557.pdf
- この記事の執筆者
- とだ ゆず
精神科看護師としての経験を活かし、メンタルヘルスを中心とした記事を執筆。こころと身体のつながりを大切にしながら、そっと寄り添う文章を心がけています。
保有資格:看護師、保健師、上級心理カウンセラー、漢方養生指導士