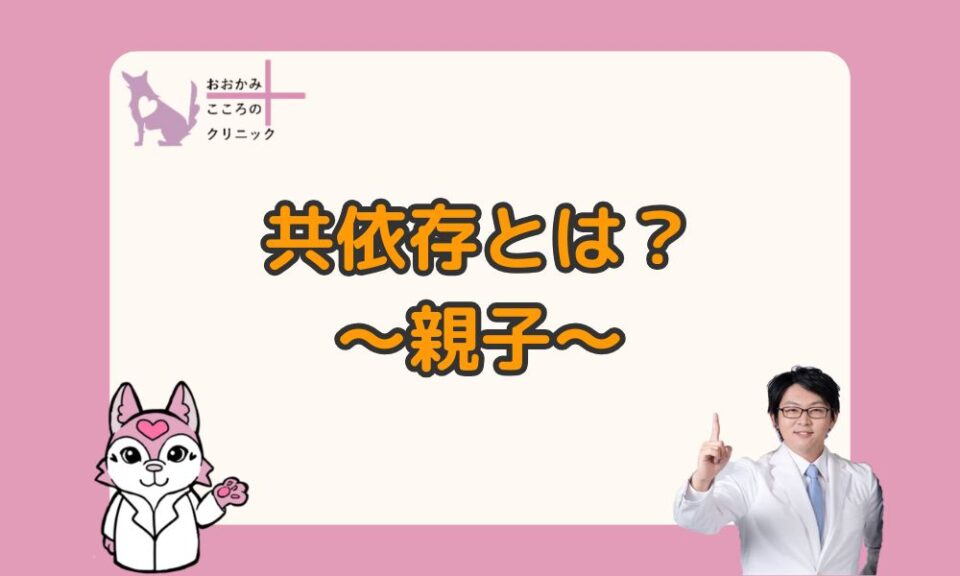「親のことは大切だけど、自分の人生も大事にしたい」
「このままの親子関係が続いたら、将来どうなるのだろう…」
親を大切に思う気持ちと、あなたの人生を歩みたい気持ちとの間で板挟みになり、息苦しさを感じていませんか。
あなたが感じている親への罪悪感は、決してあなただけのせいではありません。
周りからは「仲良し親子」といわれる関係が、実はあなたの恋愛や仕事、そして将来の選択肢を縛る「共依存」の可能性があります。
この記事では、共依存関係にある親子が迎える末路と罪悪感の正体、あなたらしい人生を送るための3つの方法を解説します。親を尊重しつつ、あなた自身も大切にできる親子関係を築くヒントになれば幸いです。
共依存の親子関係がもたらす末路
共依存関係は、一見すると「仲の良い親子」に見えますが、あなたの人生の可能性を気づかないうちに狭めてしまうかもしれません。
共依存関係を続けた先にある末路として、以下の3つのパターンが挙げられます。
共依存があなたの人生に与える影響についてみていきましょう。
共依存の親子関係については下記の記事で詳しく解説しています。チェックリストもありますので、あわせてご覧ください。
夢や仕事を諦めてしまう
「親が心配するから」「どうせ反対されるから」という気持ちから、自分の夢や興味のある仕事に挑戦したい気持ちをおさえてしまいます。
共依存の関係では、親の価値観が自分のものであるように感じ、挑戦を無意識に避けてしまいがちです。
また、母親からの「こうあるべき」という期待がプレッシャーになっている母娘関係では、娘の「アイデンティティ形成」がうまくいかない可能性があるとされています。[1]
アイデンティティとは、「自分がほかの誰とも違う存在である」という感覚で、自分らしさを大切にするために必要なものです。母親からのプレッシャーが強いが、自分が本当にやりたいことがわからなくなるといえます。
「親をがっかりさせたくない」という思いと、自分のやりたいことがわからない状態から新たな一歩を踏み出しにくくなるのです。
親以外の人間関係が築きにくい
友人や恋人などの親以外との大切な人間関係を築きにくくなります。
たとえば、友人との約束よりも親との予定を優先したり親があなたの友だち関係に口を出したりすることで、孤立してしまうかもしれません。
また、密着した親子関係は、いざというときに社会的なサポートが受けにくい側面もあります。[2]
親が高齢になり介護が必要になったとき、相談できる相手がおらず、ひとりで抱え込んで共倒れになってしまう可能性があるのです。

親も友人も大切にしたいですね💦
恋愛や結婚のチャンスを逃してしまう
「わたしが恋人と過ごしている間、親はひとりになってしまう」という罪悪感から、恋愛や結婚のチャンスを逃してしまうかもしれません。
自分自身の幸せを優先することに「親不孝だ」と感じてしまい、新しい一歩が踏み出せなくなるのです。
また、親密なパートナーができたとしても、無意識にこれまでの親子関係に似た相手を選んでしまう可能性があります。
たとえば、自分の意見が強い親のもとで育った場合に、同じような恋人を選んでしまうというケースです。相手を優先してしまう関係が繰り返され、結局うまくいかなくなるおそれがあります。
「親がかわいそう…」と感じる罪悪感の正体とは
共依存から抜け出そうとするとき、多くの人が直面するのが「親を見捨てるようで申し訳ない」という強い罪悪感です。
罪悪感は、あなたの優しさの証でもありますが、その正体を理解することで、自分を責めることなく親子関係を見直す助けになるでしょう。
「親がかわいそう…」と感じる罪悪感の正体は、以下の3つです。
親に対する罪悪感の裏にあるこころの動きについて解説します。
「よい子」でないと見捨てられる恐怖
「親をがっかりさせたくない」「期待に応えなければ」という思いから、つい「よい子」を演じてしまうことはありませんか。
共依存の関係では、親を喜ばせることで自分の価値を感じる状態に陥りがちです。
その背景には「自分の気持ちを優先したら、わたしは愛されないかもしれない」といった不安があるのかもしれません。
そのため、自分の気持ちを犠牲にしてでも、親の期待に応えようと尽くしてしまうのです。
「わたしが幸せにしないと」という思い込み
「親の幸せまで自分が背負うべきだ」と無意識に思い込むことが罪悪感につながります。
親の幸せを願う強い責任感が、あなたの人生を優先しようとするときに罪悪感となり重くのしかかります。
ただ、親とあなたの人生は、それぞれ独立したかけがえのないものです。
あなたが親を大切に思う気持ちはとても尊いですが、親の幸せのすべてをコントロールできません。
まずは「親の人生は親のもの、自分の人生は自分のもの」と、切り分けて考えることが大切です。

大切に思うことはよいことですが…親は親で幸せになってもらいましょう!
親の悲しみを自分のことのように感じてしまう
共依存関係の親子は、こころの境界線があいまいになりがちです。そのため、親の機嫌や感情をまるで自分のことのように敏感に感じてしまいます。
あなたが自立しようと距離を取ったとき、もし親が「わたしを見捨てるの?」といった態度を示せば、親の悲しみが伝わり罪悪感を抱いてしまうでしょう。
しかし、親の感情にまで、あなたが責任を感じる必要はありません。
「親を大切にする」と「自分を犠牲にする」のは、決してイコールではないと理解することが大切です。
共依存の親子関係を断ち切るための3つの方法
「このままではいけない」と感じても、具体的にどう行動すればよいのか分からなくなりがちです。
共依存の親子関係を断ち切るためには、次の3つの方法でできることから始めてみましょう。
3つの方法について、それぞれ解説します。
あなたの「したい」を大切にする練習
これまでは「親がどう思うか」を基準に考えていたかもしれません。
これからは、小さなことでも「自分がどうしたいか」と、あなた自身を主語にして考える練習をしてみましょう。
たとえば「気になる人と映画に行きたいな」「この分野の勉強を始めてみたいな」など、内側から湧き出る気持ちをキャッチすることから始めてみてください。
親との間に「こころの境界線」を引く
家を出ることが難しくても、あなたのこころのなかで親との境界線を引く習慣をつけることが大切です。
たとえば「これは親の問題」「これは自分の問題」と線を引く習慣をつけていくことを意識しましょう。
もし、あなたの「〇〇がしたい」といったことに対して親が不機嫌になったとします。
その不機嫌さの背景には「新しいことをして、わたしのところを離れてしまうのでは」という悲しさがあるのかもしれません。
悲しさと向き合って処理していくのは親自身が取り組むべき問題で、あなたが責任を負う必要はありません。
こころの境界線を意識することで、親の感情に振り回されすぎず、あなたの思いを大切にできるようになるでしょう。
ひとりで抱え込まず、信頼できる人に話してみる
共依存からの脱却は、ひとりで成し遂げるには難しい道のりです。
なぜなら、長年かけて築かれた関係性だからです。
自分を責めたりひとりで抱え込んだりせず、誰かの力を借りることが大切になります。
具体的には、以下のような方法で人間関係を広げたり専門家に相談したりしましょう。
- 家族以外の人間関係を広げる:
趣味のサークルや習い事など、親とは関係のないコミュニティに身を置くことで、新しい価値観に触れて視野を広げられます。 - 自助グループへの参加:
自助グループとは、同じような悩みを抱える人たちが集まって経験を共有する集まりです。親との距離の取り方や工夫の参考になると同時に「悩んでいるのは自分だけじゃない」という安心感につながります。 - カウンセリングや心理療法:
専門家のサポートを受けることで、共依存関係の原因を深く理解し、あなたに合った解決策を見つけるサポートが得られます。
あなたが抱える親子関係での悩みは、決しておかしなものではありません。
信頼できる誰かに話してみることから始めてみてください。
まとめ
親に対する罪悪感は、親子の距離が少し近くなりすぎることで、親の悲しみをあなたの傷つきとして体験することで生じます。
ただ、あなたのせいではなく、長年の親子関係の中で無意識のうちにそうなってしまっただけです。
親を大切に思うことと、あなた自身を犠牲にすることは違います。
あなたが「したい」という気持ちを大切にし、親との間に適度な境界線を引くことは、親不孝ではありません。
あなたらしい人生を歩むのは、長い目で見ると親の自立も促すことにつながります。
まずは、あなたの小さな「したい」ことから始めてください。
もし、ひとりで抱えきれないほどの苦しさを感じていたら、決してひとりで悩まずに身近な人に相談してみましょう。
おおかみこころのクリニックでは、親子関係や将来の不安などの悩みについての相談もできます。お気軽にお問い合わせください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]赤木真弓「母娘関係が娘のアイデンティティ形成と精神的健康に与える影響:母娘関係尺度の作成を通して」発達心理学研究 29:114–124,2018
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjdp/29/3/29_114/_pdf
[2]Azeem Ali, Mehwish Ashraf, Tayiba Rasheed, & Rashid Hameed. (2025). The Relationship between Family Dynamics, Social Support and Substance Abuse on the development of Codependency in Young Adults. Social Science Review Archives, 3(1), 332–349.
https://policyjournalofms.com/index.php/6/article/view/314
- この記事の執筆者
- 片桐 はじめ
公認心理師、臨床心理士として精神科病院・クリニックで精神疾患を抱える方のカウンセリングや心理検査に従事。臨床経験をもとに、身近な例からわかりやすく説明する文章を心がけています。