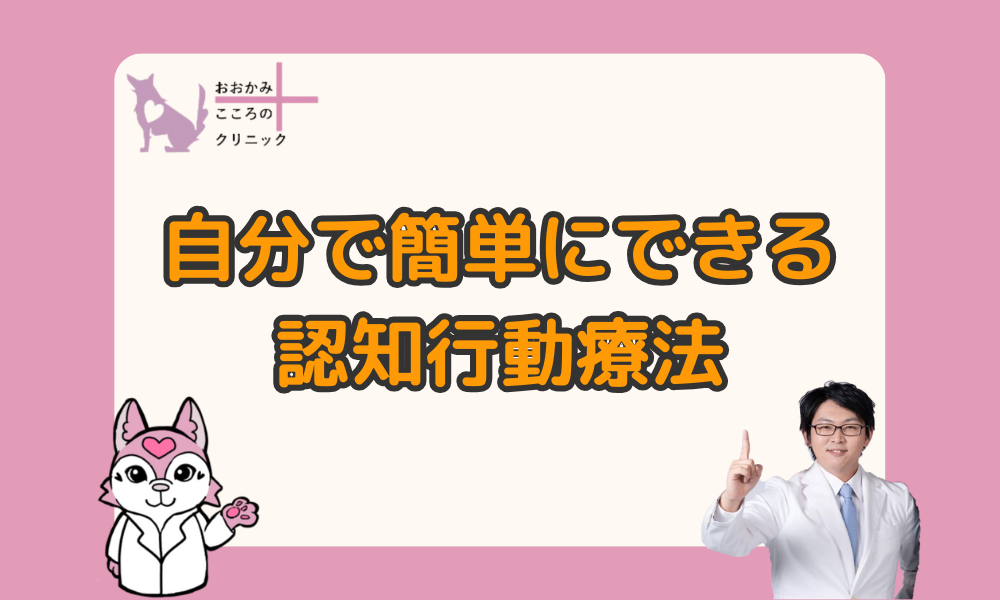認知行動療法を勧められたけれど「わたしに合っているのか」と不安に感じていませんか。
あるいは、現在治療を受けているものの思うように進まず「わたしには向いていないのかもしれない」と、つらい思いをしているかもしれません。
治療法に対して不安を感じたり、効果が実感できずに焦ってしまったりするのは、ごく自然なことです。
この記事では、認知行動療法に向かない人の特徴を3つ紹介します。
今のあなたにとって認知行動療法が最適なのかを考えるヒントや、合わないと感じたときの選択肢も解説します。
あなたが安心できる治療法を見つけるための参考にしてください。
認知行動療法とは
認知行動療法(CBT)とは、あるできごとに対する考え方(認知)や行動に働きかけることで、つらい気分をやわらげる心理療法です。[1][2]
わたしたちは、なにかつらいできごとがあったとき、その「できごと」自体が気分を落ち込ませる原因だと考えがちです。
一方で、認知行動療法ではできごとを「どのように捉えたか」という、あなたの考え方が気分に関係していると考えます。
たとえば、職場でミスをして上司に注意されたとき「自分はダメな人間だ」と考えると気分はひどく落ち込むでしょう。一方で「次は気をつければいい」と考えることができれば、落ち込みは少し軽くなるかもしれません。
このように、ストレスにより狭くなった視野を広げ、考え方のバランスをととのえていくのが認知行動療法です。
ムリにポジティブな考え方をするのではなく、考え方の選択肢を増やすことを目的としています。
認知行動療法に向かない人の3つの特徴
認知行動療法はこころや身体の状態によっては、かえって負担になってしまうことがあります。
とくに、以下の3つの特徴にあてはまるときは、まだ認知行動療法を始めるタイミングではないのかもしれません。
3つの特徴について詳しく解説します。
自分と向き合うのがつらい
認知行動療法では、あなたの考え方や行動パターンを振り返ることが中心となります。
ただし、過去のつらい記憶(トラウマ)や、思い出したくない体験が強く残っていると、自分自身と向き合うことが苦痛になることがあります。
そのため、自分と向き合うのがつらく、治療を進めるのが難しいかもしれません。
また、現在進行形でDVやハラスメントといった問題を抱えているときは、治療に取り組むこころの余裕がもてないでしょう。
そのようなときは、まずは安全な環境を確保するような、環境調整が優先されます。
今は治療に前向きになれない
認知行動療法は、治療者とあなたが一緒になって、悩みや問題の原因と対策を考えていく共同作業です。
カウンセリングで話し合うだけでなく、日常生活の中で課題(ホームワーク)に取り組むこともあるでしょう。
たとえば、日々の気分や行動を記録したり、考え方のクセを見つけるワークシートに取り組んだり主体的な参加が求められます。
もし「誰かになんとかしてほしい」という気持ちが強かったり、変化に対して不安があったりするときは、思うような効果が得られないかもしれません。
治療へのこころの準備がととのえてからの方が、認知行動療法がスムーズに進むでしょう。
こころや身体の元気が足りない
精神症状が強く、集中力や思考力が低下している状態では、治療がうまく進まないことがあります。認知行動療法では、自分の考え方のクセに気づき、他の考え方を探していく作業に集中力が必要なためです。
たとえば、以下のような状態のときは、休養が優先されるでしょう。
- 考えがまとまらない
- 集中して本や雑誌を読むことが難しい
- ホームワークに取り組む気力がわかない
心身が回復していない状態でムリに治療を進めようとすると「うまくできない」と自分自身を責めてしまい、症状が悪化する可能性もあります。
まずは休養や薬物療法で、こころと身体の状態を安定させることを優先しましょう。

ゆっくり休憩してエネルギーをためて始めたらよいのです!
【状況別】認知行動療法以外の選択肢
もし認知行動療法が合わないと感じても、不安になる必要はありません。
あなたの悩みや状況に合わせた、他の選択肢があります。
ここでは、以下の3つの状況別に認知行動療法以外の治療法を紹介します。
状況に応じた治療方法をそれぞれ解説します。
休養を優先したいとき
「こころや身体の元気が足りない」と感じるときは、まずエネルギーを回復させることが大切です。ストレスとなっている環境から離れて休む時間を作りましょう。
また、抗うつ薬や抗不安薬などを用いた薬物療法でつらい症状をやわらげ、こころの状態を安定させるのも有効な方法です。
薬物療法で十分な改善がみられないときには、脳の特定の部分に磁気刺激を与えることでバランスをととのえるrTMS療法という治療法もあります。
rTMS療法については下記の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。
対人関係の悩みから解決したいとき
治療に前向きになれない原因が対人関係の悩みによるものなら、対人関係療法が有効かもしれません。
対人関係の悩みは考え方を切り替えるだけでは解決しないことがあるからです。
対人関係療法とは、うつ病の治療法として開発され、現在の対人関係の問題と症状を結びつけて解決を目指す心理療法です。
以下の4つの領域に焦点を当て、コミュニケーションのパターンを見直します。[3]
- 大切な人との別れ
- 身近な人とのすれ違い
- 役割の変化
- 対人関係の孤立
対人関係療法では、こうした人との関係でのできごとと、現在のつらい気分とを結びつけ問題解決のサポートをしていきます。
過去の傷つき体験を解決したいとき
「自分と向き合うのがつらい」原因が過去のトラウマによるものだと感じるなら、トラウマに特化した心理療法がよいでしょう。
トラウマ特化の心理療法として代表的なのは、以下の2つです。
- 持続エクスポージャー療法(PE):
PTSD(心的外傷後ストレス障害)への効果が実証されている治療法です。つらい記憶やそれに伴う感情にあえて向き合い、トラウマが日常生活にあたえる支障を減らします。[4] - EMDR:
つらい記憶を思い浮かべながら治療者の指の動きを目で追うことで、脳の情報処理を促し、トラウマ記憶の苦痛をやわらげます。[5]
トラウマ体験によるつらさがやわらげば、考え方や行動にも自然と変化が生じるでしょう。
認知行動療法に関するよくある疑問
認知行動療法を受けるときに抱えがちな以下の3つの疑問について、現役の公認心理師がQ&A形式でお答えします。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
Q1.認知行動療法を自分でやることは可能ですか?
A.セルフケア用の書籍やアプリを使って、ご自身で取り組むことも可能です。
とくに、コラム法(思考記録法)と呼ばれるワークシートを使って、日々のできごとや考え、感情を記録すると、自分の考え方のクセに気づくための練習になります。
ただし、症状が重いときや、ひとりで進める中で混乱したり気分が落ち込んだりするときは、ムリせず専門家に相談してください。
Q2.発達障害(ASD・ADHD)の人にも向いていますか?
A.発達障害の特性に応じた認知行動療法は、有効とされています。
認知行動療法は、発達障害の特性から生じる二次的な問題や、日常生活でのストレスに対して役立ちます。具体的な内容は以下のとおりです。
- ASD(自閉スペクトラム症)
- 自分の考え方のクセと特性がどのように関係しているかを理解し、ストレスにうまく対処する方法を学びます。たとえば「予測が苦手(特性)だから、想定外のできごとがあると焦る(感情)」というようにできごとと感情、考えのつながりを理解します。[6]
- ADHD(注意欠如・多動症)
- 計画立てや時間管理、整理整頓などの困りごとに対して認知行動療法が有効です。多くは、薬物療法と並行して行われます。[7]
Q3.認知行動療法が合わないとき、医師やカウンセラーにどう伝えればよいですか?
A.「合わない」と感じることを、正直に伝えて大丈夫です。勇気を出して伝えることで、治療方針を見直すきっかけになります。
感情的に「効かない」と伝えるのではなく、次のように客観的な事実や具体的な困りごとを伝えてみましょう。
「考え方のクセを意識してみたんですが、なんだか自分でもどこが変わったのかよく分からなくて…。もし他に合いそうな治療法があれば教えていただけますか?」
「最近、考えがうまくまとまらなくて…。今のわたしには、この方法が合っているのでしょうか?」
「教えてもらったワークを試してみたのですが、気分が落ち込んで続けるのがしんどく感じます…」
ポイントは、あなたの正直な気持ちや困っている状況を具体的に話すことです。
「治療をよりよくしていくために、一緒に考えていきたい」という姿勢で相談できるとよいでしょう。
まとめ
「認知行動療法が自分には合わないのかもしれない」と感じるのは、あなたが治療に真剣に向き合っているからこそ感じる大切なサインです。
認知行動療法に対する違和感の背景には、エネルギー不足や過去の体験など、さまざまな理由が考えられます。
治療法はひとつではありません。大事なのは、違和感を無視せず、あなたに合ったほかの選択肢を探すことです。
ただ、どの方法が最適か、ひとりで決めるのは難しいものです。
おおかみこころのクリニックでは、あなたの現在の状態やお悩みを丁寧に聞いた上で、あなたに合った治療法を一緒に考えていきます。
オンライン診療もおこなっておりますので、全国どこからでもお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【参考文献】
[1]うつ病の認知療法・認知行動療法(患者さんのための資料)│厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/04.pdf
[2]認知行動療法:用語解説│こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-1666
[3]近藤真前(2018)「一般外来におけるうつ病に対する対人関係療法」精神神経学雑誌120巻5号
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1200050408.pdf
[4]石丸径一郎・金吉晴(2009)「PTSDに対する持続エクスポージャー法」精神保健研究55:89-94,2009
https://www.ncnp.go.jp/mental-health/docs/nimh55_89-94.pdf
[5]EMDRとは│日本EMDR学会
[6]思春期・成人期の高機能自閉スペクトラム症者を対象とした認知行動療法│認知行動療法推進協会
https://cbtnet-npo.com/pdf/202012-1.pdf
[7]中島美鈴(2024)「大人の注意欠如多動症の認知行動療法」総合病院精神医学36(3),200-210,2024-07-15
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjghp/36/3/36_200/_pdf/-char/ja
- この記事の執筆者
- 片桐 はじめ
公認心理師、臨床心理士として精神科病院・クリニックで精神疾患を抱える方のカウンセリングや心理検査に従事。臨床経験をもとに、身近な例からわかりやすく説明する文章を心がけています。