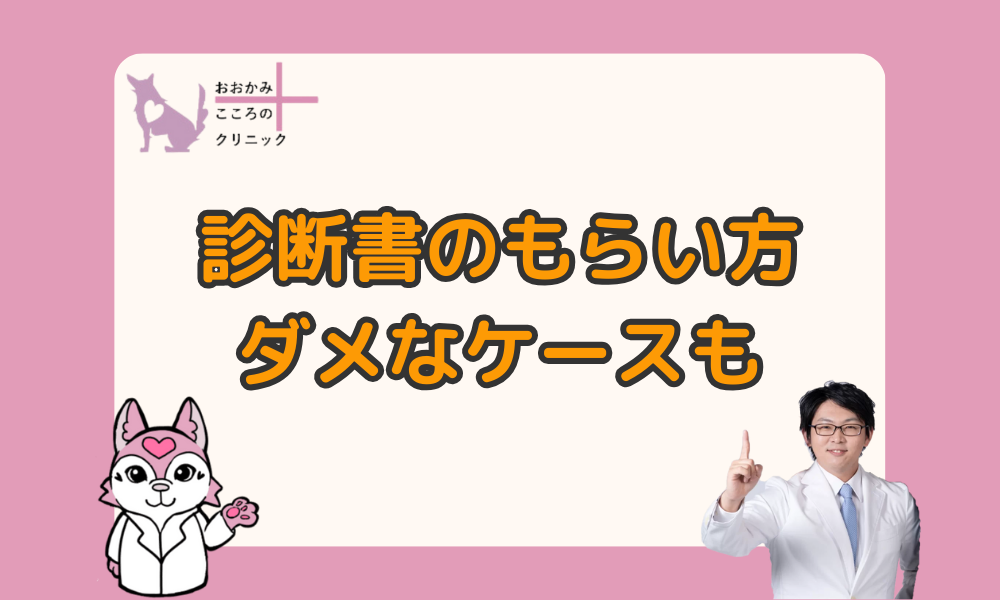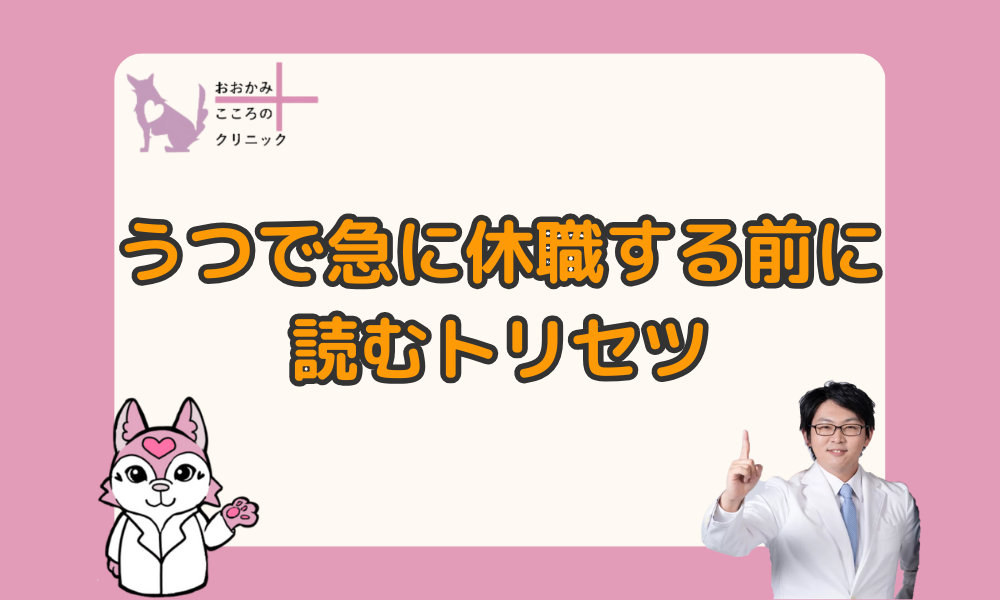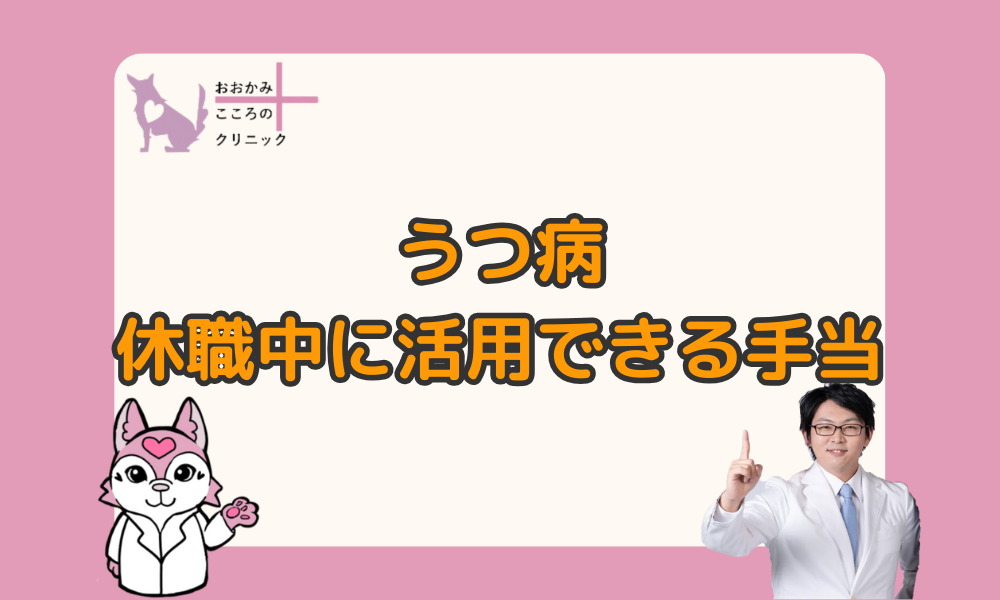「うつ病の診断書が欲しいけど、どうやってもらうのかわからない」
「診断書をもらうには病院の先生に何て伝えればいいのか知りたい」
「診断書で本当に休めるの?」
このような悩みはありませんか。診断書は医師が「必要」と判断しないともらえません。
診察ではどのような症状があって、日常生活で何にこまっているのかなど伝える必要があります。うまく伝えられないと的確な判断がされず、うつ病と診断されない可能性もあるでしょう。
そこで、この記事ではうつ病の診断書のもらい方について解説します。診断書をもらう際の注意点も解説するのでぜひ最後までご覧ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
うつ病の診断書のもらい方

うつ病の診断書は以下のステップで取得します。
順番に解説します。
精神科や心療内科を受診する
診断書は医師の診察をもとに書かれるため、まずは医療機関を受診しましょう。
診察時は、緊張してうまく話せないこともあります。事前にWebサイトで医師のプロフィールや病院の雰囲気を見て確認しておくことで少し不安がやわらぐでしょう。
あなたが「ここの病院よさそうだな。行ってみようかな」と思える病院を選ぶことも大切です。
担当医に症状を伝える
診察では、以下のようなことを担当の医師に伝えましょう。
- 診断書がほしい理由
- 心身におこっている症状
- 日常生活でこまっていること
医師は、診察時の話の内容や様子で病状を判断するため、ありのままのあなた自身のことを伝てください。
とはいえ、いつも通りに話すことが難しこともあります。そんなときは「どのような症状があるのか」「日常生活でで困っていること」などを事前にメモを書いておくと、伝えやすくなります。
書いてきたメモを読みながら伝えたり、話すのも緊張したりするときは先生にそのままメモを渡してみるのもよいでしょう。

先生は優しいので安心して話して大丈夫ですよ!
会計時に診断書をもらう
診断書が必要と判断されたら、お会計時に処方せんと一緒にもらえることもあります。
ただし、即日発行できるかは病院によって異なります。
診断書は医師の記入に時間がかかるため、当日すぐには発行されず数日〜1週間ほど後に受け取りになるケースも多くあるのです。
もし、診断書がもらえたら、学校や会社に提出するため汚さないように管理しましょう。
おおかみこころのクリニックでは、診断書の即日発行が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
うつ病の診断書はもらえないケースがある
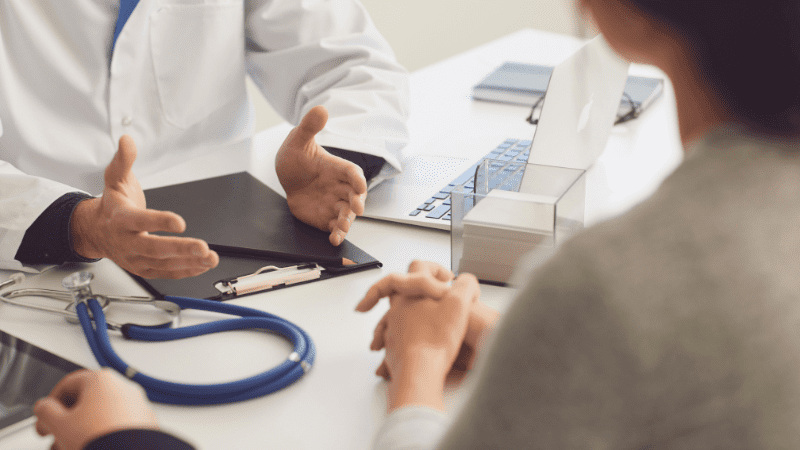
診断書は必ずもらえるわけではありません。症状によってもらえない場合があります。
うつ病の診断書をもらえるケース
うつ病の診断書がもらえるケースは以下の通りです。
- うつ病の症状がある
- 休職で症状の改善が見込まれる
以下の症状が2週間以上続くときは、うつ病の可能性があります。[1]
診断基準
以下の症状が2週間以上続く場合、うつ病を疑います。
1.自分の言葉か、まわりから観察されるほとんど毎日の抑うつ気分
2.ほとんど毎日の喜びの著しい減退
3.著しい体重の減少、あるいは体重増加、ほとんど毎日の食欲の減退または増加
4.ほとんど毎日の不眠または過眠
5.ほとんど毎日の精神運動性の焦燥または制止(他者によって観察可能)
6.ほとんど毎日の易疲労性、または気力の減退
7.ほとんど毎日の無価値観、または過剰であるか不適切な罪責感
8.思考力や集中力の減退、または決断困難がほとんど毎日
9.死についての反復思考、反復的な自殺念慮、または自殺企図
※診断基準を参考に、医師が診察で「うつ病」と判断した場合に診断されます。
うつ病の診断書がもらえないケース
うつ病の診断書がもらえないケースは以下の通りです。[2]
- うつ病以外の診断名がつく
- 症状がないのに診断書が欲しい
- 雇用者や家族など第三者が請求した
うつ病の症状が部分的にあっても、診断基準に該当しなければ適応障害のような別の診断名で診断書をもらうことがあります。
また、症状がない場合は、診断書が不正に利用される可能性があるため、診断書を発行することはできません。
ほかにも、本人でなく第三者が診断書の発行を請求してきても、守秘義務にふれるため診断書は発行されません。
診断書取得にかかる費用

診断書はおおよそ3,000円〜5,000円です。健康保険適応外で全額自己負担のため、医療機関により価格が異なるります。

事前に電話などで確認しておくと安心でしょう。
初診日でも診断書はもらえる

診断書は、本人が希望し医師が診断書が必要と判断すると、初診日にもらえることもあります。
一方で、こころの病はすぐに診断が難しいことも多いため、初診日に必ず発行されるとは限りません。とくに、うつ病は数回通院して診断されるケースもあります。
たとえば、最初は自律神経失調症や適応障害と診断されて、通院していくなかでうつ病に切り替わることもあります。
おおかみこころのクリニックも、診察で医師が診断書の発行が必要と判断したら、即日発行も行っております。まずは、お気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
うつ病で休職するときにやること

うつ病で休職するときのやることは以下の3つです。
順番に解説します。
うつ病で急に休職することになり、今後どのように過ごしていいか不安なときは、下記の記事も参考にされてください。
病院を受診して診断書をもらう
精神科や心療内科を受診し、診断書を発行してもらいます。
症状によっては必ず診断書を発行してもらえるわけではありません。逆にうつの症状にあてはまらなくても、医師が「休職が必要」と判断した場合には別の病名で診断書を発行されることもあります。
必要書類を職場に提出
診断書と休職届など職場に必要な書類を提出します。必要な書類は職場によって異なるため、事前に就業規則などで確認をしましょう。
書類の提出先は、会社によって異なるため直属の上司か人事部に確認してください。
また、休職すると現場の人数が減るため、理解を示さない職場も少なくありません。
休職の手続き中は気まずい思いをすることもありますが、ムリをして働き続けると体調が悪化する可能性もあります。
「今は休職してゆっくりする時間が必要と医師が言っているんだ」と気持ちを割り切って、手続きをすすめましょう。
就業規則で休職制度について確認
確認する内容は下記のとおりです。[3]
- 休職中の給料
- 会社と休職期間中の連絡方法
- 休職期間中に症状が改善しなかった場合の対応
休職中に給料が発生するかは、会社や加入している健康保険によって異なります。詳しくは、就業規則や健康保険組合に確認しましょう。
また、休職期間中の連絡方法を決めておくと安心です。
たとえば、人事部なのか直属の上司なのかは会社によって異なります。ほかにも、どのくらいの頻度で連絡するのかも合わせて確認してください。
以下の記事では、うつ病で休職中に活用できる手当を紹介しています。あわせご覧ください。
まとめ
うつ病の診断書はうつ病と診断され、医師が診断書が必要と判断すると発行されます。
1度の診察だけでは判断が難しいときは、何回か通院しないともらえないこともあるでしょう。
また医師の診察により、適応障害のような別病名の診断書が発行される可能性があります。
休職するときは、休職期間中の収入や会社との連絡方法を確認しましょう。傷病手当金の申請方法や会社との連絡窓口を確認しておくことで安心して休めます。
心身ともにつらい時期ですが、健康を第一に考えて生活しましょう。
おおかみこころのクリニックは、あなたのストレスが少しでも軽くなるように一緒に今後の方針を考えていきます。土日診療も行っていますので、お気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
参考文献
[1]こころの病気について知る うつ病|厚生労働省 こころもメンテしよう
https://www.mhlw.go.jp/mobile/m/kokoro/kokoro/youth/mobile/stress/know01.xhtml
[2]診断書の発行の義務と勤務医の過重労働|日本医師会
https://www.med.or.jp/nichinews/n201220p.html
[3]第3回社員がメンタルヘルス不調で休業することになったら|厚生労働省 こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/mental-health-qa/mh-qa003/
[4]改定 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き|厚生労働省 中央労働災害防止協会
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-1.pdf
- この記事の編集者
- 和田直人
作業療法士。薬機法管理者。障害者入所施設や就労支援施設を経験。現在は放課後等デイサービスで勤務しながら、フリーライターとして活動。医療・健康分野を中心に執筆中。