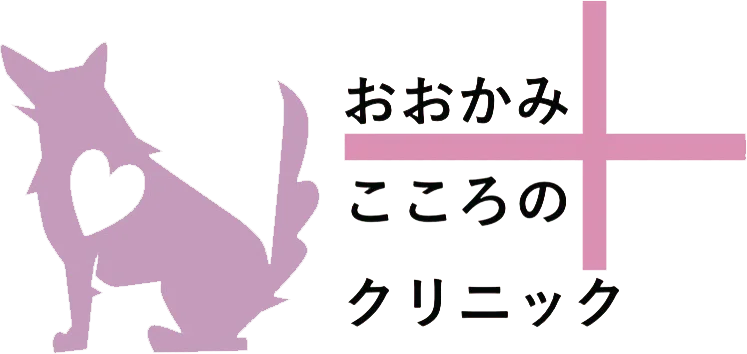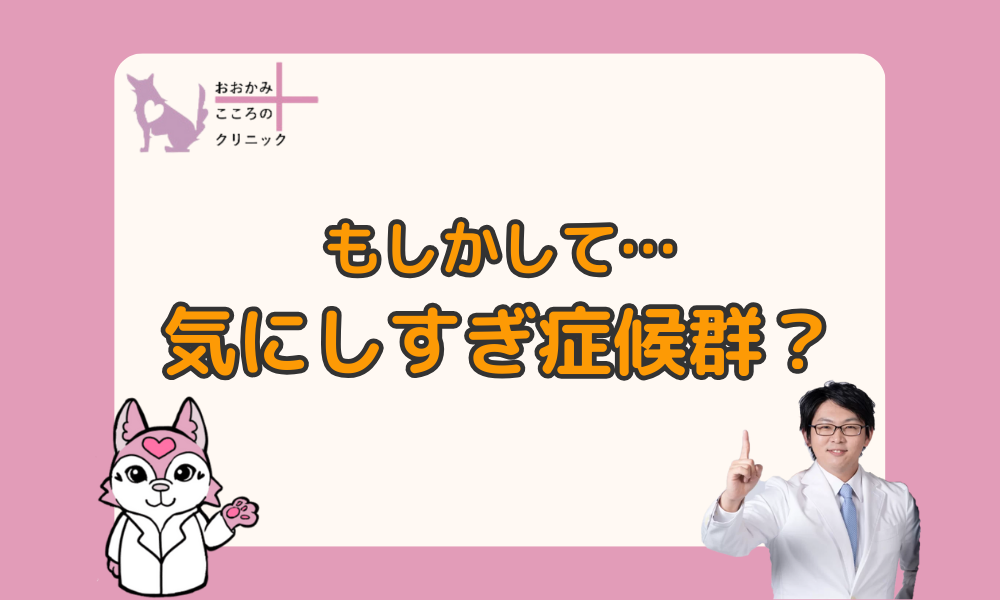「心配性だなぁ」と言われたことはありませんか?
もしかしたら「気にし過ぎ症候群」かもしれません。
「気にし過ぎ症候群」は病気ではなく、思考パターンのひとつです。これまでの失敗体験や、周りの言動に影響される性格などが関係しています。
とはいえ、周りの人から指摘されてしまうと「自分は変なのかな」と心配になりますよね。心配ごとが増えると心が疲れてしまいます。
気にし過ぎへの対処法はいくつもあります。余計な不安を手放して、毎日を穏やかに過ごしましょう。
「気にし過ぎ症候群」をチェックするポイント
日常生活で、「これって私だけかな」と思う瞬間はありませんか?
もし、以下のような状況に心当たりがあるなら、それは「気にし過ぎ症候群」のサインかもしれません。
詳しく見ていきましょう。
うまくいっているのにいつも心配の種を探している
成功しているにもかかわらず、「何か問題が起こるかも……」と不安の材料を探していませんか?
順調な状況を素直に信じられず、起きてもいないことを心配するのは「気にし過ぎ症候群」によくみられる特徴です。
うまくいっているときほど、悪いことが起こったらと思うのは自然なことです。
人は失敗を恐れる生き物。順調であればあるほど、リスクを予測して備えようとすることもあります。

用心するのも大切ですが、心配しすぎて疲れちゃいます💦
小さな問題なのに深刻に考えてしまう
取るに足らないささいなことが、妙に気にかかって思い悩むことはないでしょうか。
「隣に住む人が顔を見て挨拶してくれなかった」「同僚が強くデスクの引き出しを閉めた」など、他人のしたことが気になるかもしれません。自分が悪いのかも……と深く考えてしまうこともあるでしょう。
ですが、当人は深く考えずに行動していることもあります。あまり思いつめず、受け流すのがおすすめです。
ぐるぐるとマイナス思考が止まらなくなってしまうときは、下記の記事をご覧ください。
周りにどう思われているかいつも気になる
人は自分がどう見られているかを気にするものです。でもその思いが強過ぎると、日常生活に支障をきたす可能性があります。
「嫌われたくない」という気持ちは誰にでもあります。ですが、あまり気にし過ぎると、心が疲れてしんどいと感じるでしょう。
自分が思うよりも、人は他人を意識していないものです。
周りの目ではなく、今の自分が心地よく過ごしているかどうかを意識してみてください。
何度も同じことを確認してしまう
家を出る際に鍵をかけたか何度も確認するなど、同じ行動を繰り返すことはありませんか?
一度きちんと確認しているにも関わらず「もしできていなかったら」と、心配になることもありますよね。
こうした人は、職場でもしっかり確認をしてくれるのでミスは少ないです。
ですが、心配性も度が過ぎると、周りの人を不安にさせてしまうかもしれません。ダブルチェックをして、他の人と一緒に確認するとよいでしょう。
いつも最悪の事態を想定して行動する
「もしこうなったらどうしよう」と、常に最悪のシナリオが頭に浮かぶ人もいます。
たしかに、リスクに備えるのは素晴らしいことです。ですが、考え過ぎはストレスがたまります。
ちょっと難しく感じるかもしれませんが「そのときはそのとき!」と開き直るのも手です。
最悪の事態を考えるのは、トラブルに対して冷静に対処したいという気持ちがあるから。
パニックになりたくないとも考えるでしょう。
あなたが想像する最悪の事態とは、まったく違う問題が起こるかもしれません。何も起きない可能性も考えられます。
「どのような状況でも、そのときになったら柔軟に対応しよう」と決めてみましょう。気持ちが楽になりますよ。

ときには「なるようになる!」「起きたときに考えよう!」と思うことも大切です。
電話やメールに対して「悪い知らせでは」と感じる
スマホやメールの着信音を聞くたびに「何か悪い知らせかも」と感じるのも「気にし過ぎ症候群」の特徴です。
こうした人は、過去にネガティブな連絡を受けて傷ついた経験をした傾向にあります。
たとえば苦手な上司に電話で叱られた記憶が残っていると、着信音が聞こえただけで嫌な気持ちになるでしょう。
上司の名前がスマホの画面に出ていると、それだけで「叱られるのかも」と気持ちが暗くなります。
過去の経験に影響されるのは当然のことです。ですが、とらわれ過ぎるとつらくなってしまいます。日常生活に支障をきたすかもしれません。
もしも電話やメールに対応するのが怖いと感じたら、カウンセラーなどに症状を打ち明けてみましょう。対処法を見つけるきっかけになります。
おおかみこころのクリニックでは、あなたの日常生活の中での困りごとの相談もお受けしています。お気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
気にし過ぎるのは病気?症状をチェックしてみよう
気にし過ぎるのは個性といえますが、精神疾患などが影響しているケースもあります。
心配や不安が症状としてあらわれるものとして、以下の4つがあげられます。
- うつ病
- 気分変調症
- 不安症
- 更年期障害
それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 原因 | 症状 | 改善法 | |
| うつ病 | ・環境性格の傾向遺伝的要因 | ・憂うつ感 ・意欲の低下 | ・休養薬物療法 ・カウンセリング |
| 気分変調症 | ・環境性格の傾向遺伝的要因 | ・不眠・仮眠 ・集中力の低下 ・憂うつ感の持続 | ・休養薬物療法 ・カウンセリング |
| 不安症 | ・遺伝的な要因 ・生活環境 ・心身の状態 | ・不安感 ・息切れ ・集中力の低下 ・心拍数の上昇 | ・薬物療法 ・認知行動療法 ・カフェイン摂取量の低減 |
| 更年期障害 | ・閉経加齢女性ホルモンの減少 | ・イライラ感 ・情緒不安定 ・ほてり・のぼせ ・めまい・動悸 | ・生活習慣の改善 ・心理療法 ・薬物療法 |
「気にし過ぎ」を改善するための対処法
気にし過ぎるのは、周りの人から「めんどくさい」と思われる可能性があります。
円滑な人間関係を築くためにも、少しずつ対処していきましょう。
1つずつ見ていきましょう。
心配ごとをひとつずつ書き出して整理する
心の中にある不安や心配ごとを紙に書き出してみましょう。

簡単に、箇条書きで大丈夫ですよ!
- 電話が怖い
- ○○の業務がうまく進むか心配
- 同僚に嫌われたくない
このように、頭の中にある不安を書き出して目に見えるようにします。
自分が何を気にしているのかを把握しやすくなりますよ。
「起こっていない未来」よりも「今」に意識を向ける
気にし過ぎ症候群の人は、現在よりも先を心配する傾向があります。
先読みして行動するのは素晴らしいことですが、今を大事にするのも大切なことです。
起こってもないことを想像して、不安にとらわれていては疲弊してしまいます。
まずは、「今ここ」を意識して、自分が「今」どうすれば気持ちよく過ごせるかを意識してみましょう。
考えるより先に行動してみる
心配ごとが増えるのは、それだけ時間があまっていると考えられます。
日々仕事や家事、趣味などに忙しくしていると、悩む時間すらないものです。
もしも新しいことを始めるとなれば、失敗する可能性などは考えず、まず行動してみるのをおすすめします。
意識的に、不安を抱える時間と心のゆとりを埋めるのです。
行動すれば、必ず状況は変化します。そのときどきに対応する柔軟性を持つよう、心掛けてみてください。
自分だけで抱え込まず周りの人に相談する
自分の頭だけで考えていると、視野が狭くなってしまいます。
あなたが信頼できる家族や友人に相談し、意見を聞いてみてください。別の人の視点からものごとをとらえられるようになります。
ひとりで心配事を抱え込んでいても、なかなか解決しません。
自分とは異なる価値基準を持つ人に相談すれば、思わぬ解決策が見つかることがあります。

自分では思いつかなかった返事がもらえるかもですよ♪
成功している自分をイメージする
自分が成功しているイメージをしっかり固めるのも大切です。
「いつも不安なのに、成功している自分なんか思い浮かばない」と思うかもしれません。
ですが、イメージトレーニングは自分への自信にもつながります。
いきいきと行動している自分を思い浮かべていると、次第に言動がポジティブに変わっていきます。
- 電話で明るく対応している自分
- 家族と笑顔で会話を楽しむ自分
- 同僚と協力して働いている自分
このように、小さな成功でいいのです。
前向きな自分の姿を意識してみてください。
マインドフルネスを実践する
マインドフルネスとは、瞑想を通して脳と身体を休めるための方法です。
背筋を伸ばしてどっしりと座り、腹式呼吸を繰り返します。
- 背筋を伸ばした状態で床、または椅子に座る
- 視線は斜め45度にする
- 腕は自然にたらし、手のひらを上に向ける
- ゆっくり腹式呼吸をする
リラックスした姿勢で、深い呼吸を意識するだけでも気持ちがスッキリしますよ。
夢中になれることを見つける
ふとしたときに不安になるのは、時間が余っているからかもしれません。
趣味や習いごとなど、自分が夢中になれることを見つけましょう。
「楽しい」「面白い」など、ポジティブな感情で心を満たしてあげるのです。
心配事から一時的に離れ、ポジティブなエネルギーを得ることができます。何か新しいことを始めることで、自己成長の機会にもなり、自信をつけることができます。
まとめ
「気にし過ぎ症候群」は病気ではありません。
更年期障害などの影響を受けていることもありますが、多くはネガティブな状況を避けたい気持ちが強いためです。
まず、どんな悩みがあるのかを整理して、ひとつずつ対処していきましょう。
- 未来よりも今に集中する
- 悩む時間を行動にあてる
- ポジティブな自分をイメージする
など、治し方はたくさんあります。
もしも日常生活に支障が出るくらい不安感が強いなら、カウンセラーに相談してみましょう。
大切なのは、あなたがひとりで悩みを抱え込まないことです。
思いを聞いてもらい、心にある不安の種を少しずつ取り除いていきましょう。
24時間予約受付中
参考文献
1)【厚生労働省 「更年期症状・障害に関する意識調査」について】
https://www.mhlw.go.jp/content/000969136.pdf#page=12
2)【公益社団法人 日本産科婦人科学会 更年期障害】
https://www.jsog.or.jp/citizen/5717/
3)【うつ病と持続性抑うつ障害に対する援助の必要性に関する 認識の差異】
https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/education/course/psychology/paper/22/094.pdf
4)【こころの耳 気分変調症】
https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-1537/
5)【e-ヘルスネット 不安症/不安障害】
6)【こころの耳 不安症(不安障害)】
https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-1679/
7)【こころの情報サイト 不安症】
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=BLA9JV0KhiWPIMzX
8)【MSDマニュアル 不安症の概要】
9)【MSDマニュアル 抑うつ障害群】