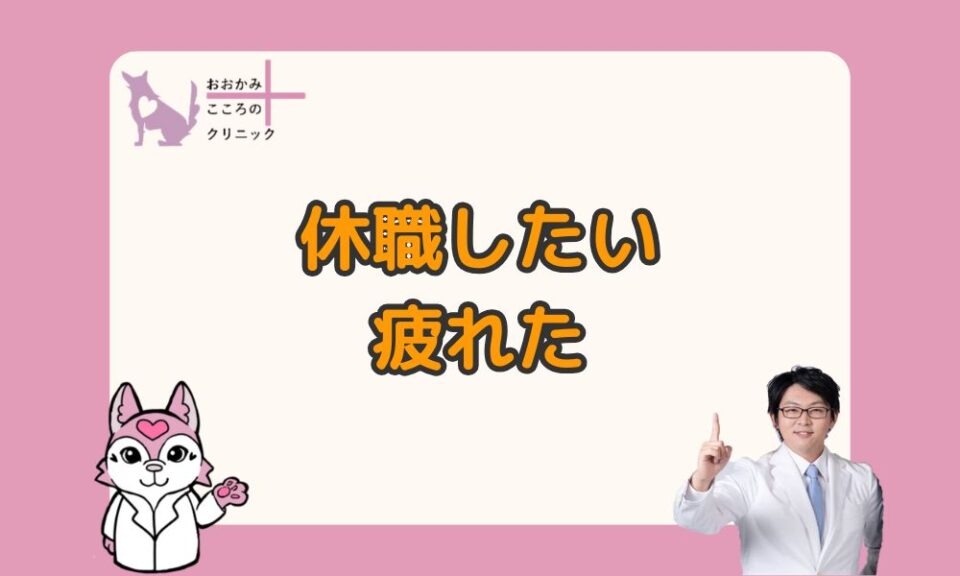仕事への意欲が湧かず「休職したい疲れた」と感じた経験はありませんか。
責任感が強い人ほど「自分が休むわけにはいかない」と追い詰めてしまいます。
休職したいと思うほどの疲れは、心身からくる限界のサインです。疲れを放置せずに適切に対処できれば、再び仕事に集中して取り組めるようになるでしょう。
この記事では、仕事に疲れたから休職したいは甘えなのか、休職を考えるべきサインを解説します。心身の健康を取り戻し、前向きな一歩を踏み出すヒントを見つけていただければ幸いです。
仕事に疲れたから休職したいは甘えなのか
「仕事に疲れたから休職したい」と考えることは、決して甘えではありません。
責任感が強い人ほど「自分が休んだらまわりに迷惑がかかる」とムリを重ねてしまうのです。しかし、心身の不調を無視して働き続けると、うつ病や適応障害などの精神疾患につながります。[1]
うつ病を発症すると、回復までに長い時間がかかったり退職せざるを得ない可能性があります。休職は心身の健康を回復させ、再び意欲的に仕事に取り組むために有効な選択肢のひとつです。
休息が必要だと感じても、罪悪感を覚える必要はありません。あなたの健康を最優先に考えていきましょう。

こころのSOSです!
休職したい疲れたと思う原因
「休職したい疲れた」と感じる背景には、次の3つの原因があります。
- 労働条件
- 仕事のストレス
- 職場の人間関係
長時間労働や休日出勤といった労働条件は、心身を疲弊させる要因のひとつです。
肉体的な疲れだけでなく精神的な余裕も失われ、仕事への意欲を低下させるでしょう。
また、仕事の内容自体がストレス源になるケースもあります。
たとえば、達成困難なノルマや目標、能力や適性に合わない業務などです。
さらに、職場の人間関係も要因となります。
2011年に行われたメンタルヘルス対策実態調査結果によると、こころの健康問題の原因のうち職場の人間関係は47%という結果でした。[2]
あてはまる原因があるときに「休職したい疲れた」という状態につながるのです。
休職したい疲れたと感じたときの過ごし方
「休職したい疲れた」と感じたときの過ごし方には、次の3つがあります。
意識的に休息を取り、心身を労わる時間を持ちましょう。あなたに合う方法を見つけ、少しずつ試してみてください。
睡眠を6時間以上とる
「休職したい疲れた」と感じたときは、睡眠を6時間以上とりましょう。[3]
心身の回復には、質の高い睡眠が必要です。「休職したい疲れた」と感じるほどの状態であれば、睡眠不足が続いている可能性も考えられます。
睡眠時間を確保するためには、就寝前の習慣を見直すことも有効です。寝る前にスマホやパソコンを使用すると、ブルーライトの影響で寝つきが悪くなるため控えましょう。また、軽いストレッチやぬるめのお風呂でリラックスすることも、質のよい睡眠につながります。
十分な睡眠時間を確保し、質の高い眠りを意識することで心身を回復させましょう。
紙に気持ちを書き出す
「休職したい疲れた」と感じたときは、気持ちを紙に書き出し整理してみるのもひとつの方法です。
頭の中で悩みや不安を考えているだけでは、気持ちの整理がつきません。
手を動かして文字にすると漠然としていた感情がわかり、客観的に捉えられるようになります。[4]
何を書けばよいかわからないときは、今の気持ちをそのまま書き出してみましょう。
「疲れた」「休みたい」など、どんな言葉でも大丈夫です。
誰かに見せるものではないので、きれいに書く必要はありません。
また「仕事でつらいと感じる瞬間」といったテーマを設定し、あなたの考えや感情を深掘りしましょう。書き出すうちに何にストレスを感じ、何を求めているのかが明確になります。
書いた内容を後で見返せば、思考パターンや感情の変化に気づけるようになります。
SNSから離れる時間を作る
「休職したい疲れた」と感じているときには、SNSから離れる時間を作ることが有効です。
他人の投稿を見て自分と比較したりネガティブな情報に触れ続けたりすると、劣等感や不安感が増す可能性があります。
SNSから流れてくる情報に振り回されると、こころが休まらない状態になるのです。
たとえば、次のようなルールを決めて実践してみましょう。
- 通勤中は本を読む
- 寝る前1時間はスマホを見ない
- 休日はSNSの通知をオフにする
SNSから距離を置くと他人の動向を気にする時間が減り、自分自身と向き合う時間が増えます。情報過多から解放されると、こころが穏やかになるのを感じられるでしょう。
下記の記事では休職中の過ごし方を紹介しているので、あわせてご覧ください。
休職を考えるべきサイン
休職を考えるべきサインには、次の2つの側面があります。
休職を検討するタイミングを見極めるために、あなたの心身に現れる変化に注意しましょう。
それぞれについて解説します。
身体面
精神的なストレスや過労がたまると、さまざまな身体的な不調があらわれます。[5]
- 頭痛
- 動悸
- 発汗
- 倦怠感
- 疲労感
- しびれ
- めまい
- 肩こり
- 耳鳴り
- 食欲の低下
身体的なサインは、ムリを続けていることへの警告です。
放置すると症状が悪化したり、他の病気を引き起こしたりする可能性があります。
複数の症状にあてはまる、あるいはひとつの症状でも長く続くときは、早めに精神科や心療内科を受診しましょう。

ムリしないで、専門家に相談しましょう
精神面
身体的なサインと同時に、次のような精神面の変化にも目を向けましょう。[5]
- 緊張が高まる
- 自分を否定する
- 記憶力が下がる
- 周囲の人が気になる
- マイナス思考になる
- 考えがまとまらない
- 気分の浮き沈みがある
- 思考が偏る(白黒思考)
「休職したい疲れた」という気持ちが強くなると、こころが落ち着かなくなります。
精神的なサインは、こころが限界に近づいていることを示しています。
放置すると精神疾患につながる恐れがあるため、早めの対処が大切です。
ひとりで抱え込まず、信頼できる人や病院に相談しましょう。
休職を伝えるときのポイント
「休職したい疲れた」という気持ちが強く心身の不調が続くときに、休職は有効な手段です。
大切なのは、正直さと誠意をもってあなたの状態を伝える姿勢です。
ごまかしたり曖昧な伝え方をしたりするのではなく、現在の状況と休職の必要性を説明することが、周囲の理解を得ることにもつながります。
伝えるときは、感情的にならず落ち着いて話すことを心がけましょう。
休職は決してネガティブなものではなく、回復して再び会社に貢献するための前向きなステップであるという点を理解してもらうのです。
下記の記事では休職するときの正しい伝え方を解説しているので、あわせてご覧ください。
まとめ
仕事に対して「休職したい疲れた」と感じることは、誰にでも起こりうるこころの状態です。そのように感じる気持ちは、心身が休息を必要としているサインであり、甘えではありません。
ムリを続けて心身の不調が悪化してしまう前に、立ち止まってあなたの状態を見つめ直しましょう。
休職したいと感じたら、十分な睡眠をとったり紙に気持ちを書き出したりするなど、意識的に心身を休ませる時間をつくってください。
休職は心身の健康を取り戻し、再び前向きに歩み出すための大切な期間です。
あなたの健康を最優先に考え、必要な休息をとることを検討しましょう。
おおかみこころのクリニックでは、オンライン診療を行っています。診断書の発行もできますので「休職したい疲れた」と感じたら、お気軽に相談に来てください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]うつ病|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=9D2BdBaF8nGgVLbL
[2]メンタルヘルス対策実態調査結果について|大阪労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/library/osaka-roudoukyoku/H23/press/2011_11/231104-kenko.pdf
[3]健康づくりのための睡眠ガイド 2023
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
[4]今の気持ちを書いてみる|こころもメンテしよう ~若者を支えるメンタルヘルスサイト~
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/self/self_02.html
[5]うつ病等で休職に至る警告サインの明確化,佐藤大輔,安保寛明 p46
https://www.jstage.jst.go.jp/article/japmhn/29/1/29_19-035/_pdf/-char/ja