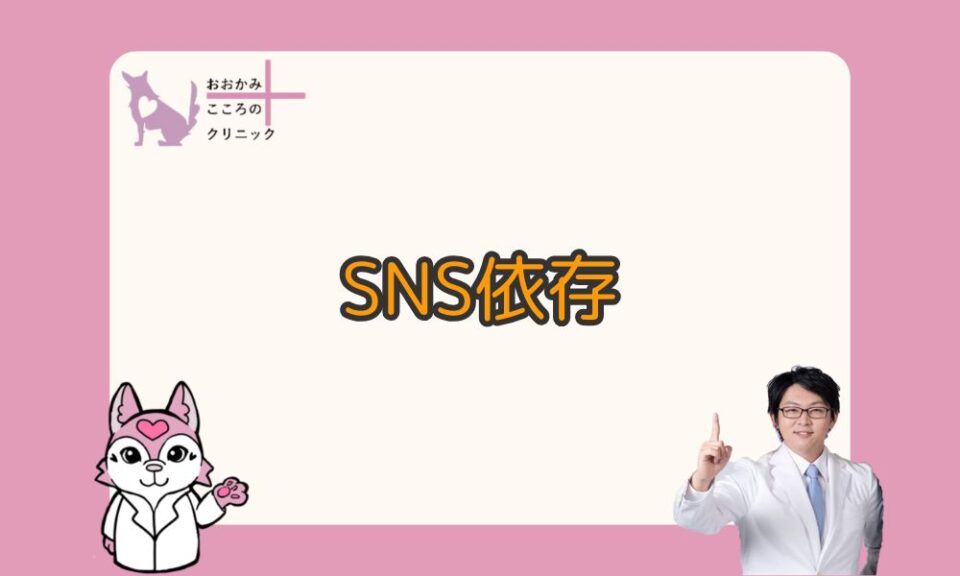「他人の評価に振り回されてしんどい…」
「もっと穏やかに生きたいけれど、どうしたらいいのだろう…」
SNSの「いいね」の数に一喜一憂したり、顔色をうかがって意見をいえなかったりするなど、承認欲求を気にして悩んでいませんか。
承認欲求は人間の成長に必要な欲求ですが、強すぎると自分を見失い、こころが消耗してしまうことも少なくありません。
承認欲求の正体を知り適切に距離を取る方法がわかることで、他人の評価に左右されない自分らしさを取り戻せるでしょう。
本記事では、承認欲求が強くなる原因やうまく付き合うためのポイントを紹介します。
承認欲求を気にせず自分らしく生きていくヒントになりますと幸いです。
承認欲求とは
「誰かから認められたい」「私を価値のある存在として受け入れてほしい」と願う気持ちを承認欲求といいます。
人にとって、ごく自然で基本的な欲求のひとつです。
承認欲求には、おもに次の2つがあります。[1]
・賞賛獲得欲求:
「すごいね」「さすがだね」とほめられたり、特別な存在として認められたりしたいという欲求
・拒否回避欲求:
「嫌われたくない」「仲間外れにされたくない」と、他人からの否定や拒否を避けたいという欲求
承認欲求は、「認められたい」という積極的な欲求から「嫌われたくない」といった受け身な欲求を含みます。
誰かに認められたいという気持ちは、私たちが社会の中で人とかかわり成長するための大切な原動力です。
承認欲求そのものは悪いものではないため、ムリになくす必要はありません。
問題なのは、承認欲求にとらわれて自分が思うように行動できない状態といえるでしょう。
SNSを活用して承認欲求を満たすこともあります。SNS依存症については下記の記事をご覧ください。
承認欲求が強くなる原因
承認欲求が苦しくなるほど強くなるのはなぜなのでしょうか。
おもな3つの原因について解説します。
承認欲求を満たす方法については、下記の記事でご覧ください。
自己肯定感の低さ
自己肯定感とは、ありのままの自分を肯定的に受け止める感覚です。
自己肯定感が低いと、自分で自分の価値を信じられず、人から認められることでこころの空白をうめようとしてしまいがちです。
ただし、人から与えられる承認はいつも期待どおりに得られるとは限りません。
承認が得られないとさらに自己肯定感が下がり、より一層強い承認を求めてしまうという悪循環になることがあります。
他人と比較しがち
自分を客観的に評価するために、他人と比較するのは自然なことです。
ただし、「他人よりも優れている」「負けている」と比較しすぎると、承認欲求を得たい気持ちが強くなりがちです。
とくに最近では、SNSを通じて他人との比較が生じやすくなっています。
「いいね」やコメント、フォロワー数といった形で比較されやすいのです。
ある研究では、承認欲求が強いほどスマホやSNSの接触頻度が高い傾向が示されています。[2]
他人から承認を得ることで生じる快感や、比較することで生まれる不安から、承認欲求が強くなってしまうのです。

比べすぎると疲れちゃいますよ💦
ありのままの自分を認められた経験の少なさ
子ども時代にありのままの自分を認められた経験が少ないと、大人になっても承認を強く求めてしまうことがあります。
たとえば、親から否定された体験が多いと「よい子でなければ愛されない」と無意識のうちに学んでしまうことがあります。
あるいは、「テストで100点をとれたらほめてあげる」といった条件付きの愛情が多いと、「何かを達成しないと自分には価値がない」と認識しがちです。
大人になってからも、常に他人の期待に応えようと頑張りすぎてしまうと承認欲求の強さにつながります。
承認欲求とうまく付き合うための3ステップ
承認欲求に振り回されないためには、ムリになくそうとするのではなく「うまく付き合っていくこと」が大切です。
承認欲求と付き合う方法として、具体的な3つのステップを紹介します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①ありのままの自分を受け入れる
承認欲求が強くて苦しいときは、完璧主義な考えが背景にあるかもしれません。
たとえば、「理想の自分でいないといけない」「失敗してはダメだ」などの自分に厳しい考え方です。
まずは、よいところも悪いところも含めた「あるがままの自分」を受け入れてみましょう。
例として仕事で失敗したとき、具体的には以下のように自分に優しい言葉をかける習慣をつけてください。
- 「誰にでも間違いはあるものだ」
- 「疲れていたのかもしれない」
- 「今日はやる気が出ないな、そんな日もある」
あなた自身に対して思いやりの気持ちを持つことは、心理療法でも活用される「セルフコンパッション」の考え方です。
セルフコンパッションとは、他人に思いやりをもって接するように、自分にも優しく大切に思うことを指します。
困難な状況や失敗に直面したときに、自分に優しく接することで感情的な回復力を高め、自己批判を和らげる効果があります。[3][4]
「失敗する自分もあるがままの自分なんだ」と認識することで、承認欲求に頼らなくてもこころを健やかに保てるようになるでしょう。

今のあなたのままで素敵なところを探しましょう
②自分にとって何が大切かを明確にする
他人の評価に頼ってしまうのは、あなたにとって大切な価値観がはっきりしていないのかもしれません。
大切な価値観とは、「人としてこうありたい」という人生の方向性をあらわすものです。
次のような視点で、何が大切か考えてみましょう。
- 自分の人生で本当に大切にしたいことは?
- 誰にもほめられなくても続けていきたいことは?
- これから先どのような人間関係を築いていきたい?
あなた自身が本当は何を大切にしたいかが明確になると、他人の評価を気にした行動が減ります。
たとえば「努力している自分を大切にしたい」とわかれば、勉強も「ほめられたい」ためではなく「自分の成長のため」と目的が変化します。
あなたが大切にしたい価値観を探すことで、他人の評価を気にせずに自分らしい目標が見つかるでしょう。
③どうしても悩むときは承認欲求から距離を取る
自分を受け入れたり価値観を大切にしたりしようと、どうしても悩むときは、承認欲求から距離を取ってみましょう。
あなたの感情や思考から距離を取る方法として、マインドフルネス瞑想が有効とされています。[5]
マインドフルネス瞑想とは、呼吸や音、身体の感覚などに注意を向けて、こころを「今」に集中させることです。
代表的なマインドフルネス瞑想の方法としては、以下のとおりです。[6]
- ボディスキャン:左足のつま先から頭に向かって注意を移動させながら、身体の感覚を観察する
- 静坐瞑想:自然な姿勢で座り、呼吸・からだ全体・音・考え・感情に注意を向けて観察する
- 歩行瞑想:歩きながら足の動きに注意を向けて感覚を観察する
マインドフルネス瞑想では、自然と浮かんでくる感覚や考えに注意を向けつつ、ムリに消さない姿勢を大切にします。
たとえば、呼吸に注意を向けていると「昨日、上司に言ったあの言葉で嫌われていないかな…」と心配事が浮かぶこともあるでしょう。マインドフルネス瞑想では「こんなことを考えたらダメだ」と自分を責めず「今、仕事の心配事が浮かんだな」と気づいてそのままにしておきます。
承認欲求にとらわれていることに気づいたとき、それを否定せずに少し距離を取る方法として、日常生活で活用できる方法です。
承認欲求に振り回されない人間関係のポイント
承認欲求とうまく付き合うには、人間関係の見直しも大切です。
「承認欲求を気にしすぎないようにしよう」と思っても、いざ人とかかわると自分の意見をうまくいえないこともあるでしょう。
自分の意見を効果的に伝える方法として「アサーティブコミュニケーション」があります。
アサーティブコミュニケーションとは、相手の気持ちを尊重しつつ自分の意見も伝える方法です。
あなたが感じている気持ちが相手に理解されやすくなり、自尊心が高まります。[7][8]
具体的には、「わたし」を主語にして自分の気持ちを伝えましょう。。[9]
たとえば、誰かにお願いするときは、次のように伝えると相手に配慮しつつあなたの思いを伝えられます。
△「これをやってもらえませんか?」
○ 「これをやってくれると、わたしはとても助かります」
承認欲求が強いと「嫌われたくない」という心配から、言いたいことを我慢してしまいがちです。
アサーティブコミュニケーションを意識すると、相手に配慮しつつ伝えられるので、あなたの思いを表現しやすくなるでしょう。
承認欲求が強い人との上手な付き合い方のコツを下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
まとめ
他人の評価が気になりつらいと感じるのは、あなたが真面目に生きようとしている証拠です。
それだけ周りの人たちと真剣に向き合おうとしているからかもしれません。
まずは、自分のこころと向き合おうとしているあなた自身を認めてあげましょう。そのあとで、本当にあなたが大切にしたいと思える価値観を見つけ、それに沿って行動することを意識してみてください。
もし、ひとりではどうすればよいかわからないときは、専門家に相談するのも一つの方法です。
おおかみこころのクリニックでは、心理師によるカウンセリングを通して気持ちやお悩みの整理をサポートしていますので、いつでもご相談ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]承認欲求についての心理学的考察│京都女子大学 現代社会研究科論集
http://repo.kyoto-wu.ac.jp/dspace/bitstream/11173/2640/1/0140_012_002.pdf
[2]承認欲求とソーシャルメディア使用傾向の関連性│情報教育
]https://www.jstage.jst.go.jp/article/rrie/1/0/1_18/_pdf/-char/ja
[3]マインドフル・セルフ・コンパッション (MSC)とは何か: 展望と課題│心理学評論刊行会
https://www.jstage.jst.go.jp/article/sjpr/64/3/64_388/_pdf/-char/ja
[4]Self-Compassion: Theory, Method, Research, and Intervention|Annual Review of Psychology https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-psych-032420-031047
[5]マインドフルネスにみる情動制御と 心理的治療の研究の新しい方向性│感情心理学研究
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsre/16/2/16_2_167/_pdf
[6]マインドフルネスのアプローチ│心身医学
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/61/6/61_61.6_522/_pdf
[7]健常者を対象にしたアサーション・トレーニングの効果に関する文献レビュー│順天堂大学医療看護学部 医療看護研究
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhcn/9/1/9_12/_pdf
[8]大学新入生に対するアサーション・トレーニングの効果│教育心理学研究
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjep/67/4/67_317/_pdf
[9]ストレスをためないコミュニケーション│筑波大学学生相談室
https://soudan.sec.tsukuba.ac.jp/content/uploads/sites/5/2020/07/f006dea0128b1afc87c4863fb7e6ab06.pdf
- この記事の執筆者
- 片桐 はじめ
公認心理師、臨床心理士として精神科病院・クリニックで精神疾患を抱える方のカウンセリングや心理検査に従事。臨床経験をもとに、身近な例からわかりやすく説明する文章を心がけています。