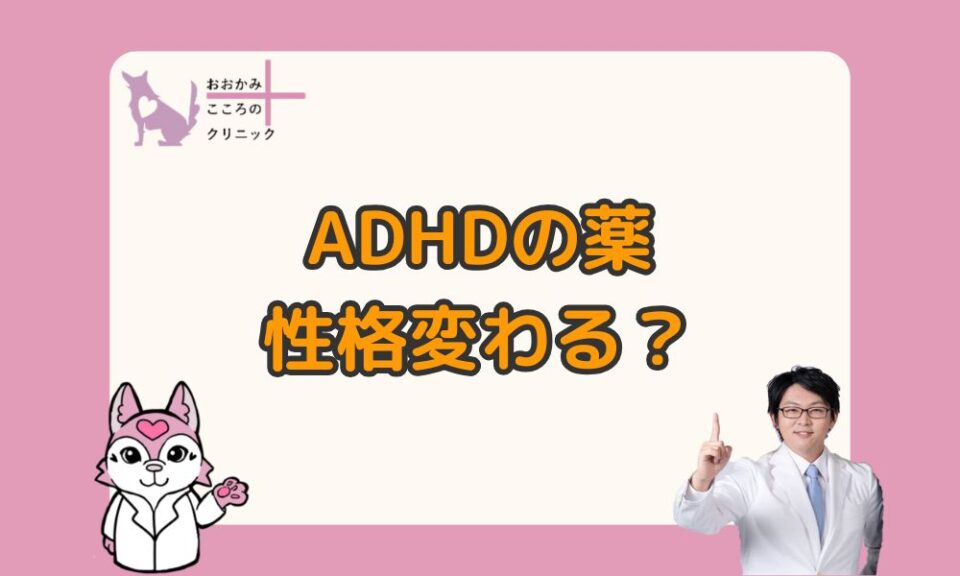「ADHDの薬って、本当によくないのかな…」
「副作用や依存性があるって聞くけど、飲んでも大丈夫?」
このように薬を飲むことに迷いや不安を抱いていませんか。
薬の特徴や副作用について正しく知ることで、不安がやわらぎ、あなたに合った治療を前向きに考えられるはずです。
この記事では「ADHDの薬はよくない」と言われる理由や、薬の特徴や副作用、いつまで薬を飲み続けるのかについて紹介します。
あなたが安心して治療を受けられるヒントになりますと幸いです。
この記事の内容
ADHDの薬が「よくない」と言われる理由
ADHDの薬が「よくない」と言われる理由は以下の3つです。
- ネットの情報
- 依存性の心配
- 副作用がつらい
2024年8月に、あるADHDの薬からごく微量の発がん性物質が検出されたとニュースになりました。[1]
その薬の発がんリスクは、120㎎を70年間飲み続けた場合、約13万9千人に1人ががんになる可能性がある程度です。[1]
現在は回収されていますが、こうしたニュースが「ADHDの薬はよくない」と言われる理由のひとつです。
また、SNSやネットでADHDの薬について調べると、以下のような言葉を目にします。
- 性格 変わる
- 副作用 つらい
- やめられない
薬を飲み始めようとしているときに、副作用や依存症についての情報を目にすると不安になるのもムリはありません。
ADHDの治療に限らず、治療に大切なのは「薬を飲むかどうか」よりも、あなたが「安心して治療を受けられるかどうか」です。
ADHDの薬の副作用や依存性については、この記事の後半で解説します。
すぐに知りたいときはこちらからご覧ください。

今から飲もうとしている薬について悪く書いてあると気になりますよね💦
ADHDのおもな治療薬の種類や特徴
ADHDの薬は、ADHDの症状があってもより暮らしやすくサポートする役割で用いられます。[2]
よく使われている代表的な薬は以下の3つです。
- コンサータ
- ストラテラ
- インチュニブ
薬の作用には個人差がありますが、コンサータは朝に1回服用すると比較的早い時間に作用があらわれ、12時間程度の持続が報告されている薬です。[3][4][5]
たとえば、仕事や学校など日中の集中力を高めたいときは、朝に飲めば昼間の活動時間に合わせて使いやすいとされています。
ただし、食欲が落ちたり夜眠れなくなったりする副作用が出ることもあるため、医師と相談しながら慎重に使うことが大切です。[4]
ストラテラは、コンサータとはちがい4~6週間で少しずつ作用があらわれる薬といわれています。[6][7]
また、薬への依存が少ないことや、1日2回の服用で1日中、症状に作用することも報告されています。[7]
インチュニブは、衝動性や不注意に効果が期待できるとされている薬です。[8]
インチュニブの副作用で、眠気や身体のだるさが生じることがあるため、運転や機械の操作をする際には注意してください。[8]
どの薬が合うかは、今あなたが生活で困っていることや身体の反応によって変わります。
あなたの生活に合っているかどうかを考え、医師と相談しながら薬の調整をしていきましょう。
ADHDの薬で性格が変わると言われることがあります。その理由については以下の記事で詳しく解説しています。
あわせてご覧ください。
ADHDの薬でみられるおもな副作用
ADHDの薬は、集中しづらい・落ち着かないといった症状をやわらげるために使われますが、身体に合うかどうかは個人差があります。
たとえば、ADHDの薬の副作用には次のような身体の変化が報告されています。[3][6][8]
- 食欲がなくなる
- 夜眠れなくなる
- だるさを感じる
また、一部の薬では、長期に服用していると依存性のリスクもあるため「ずっと飲み続けて大丈夫なのかな」と思ったときは医師に相談しましょう。[3]
副作用や不安があるときに、ひとりで悩み続けると服薬がイヤになったり通院が億劫になったりします。
ムリなく治療を続けるためには、あなたに合っているかどうか確かめながら調整していくことが大切です。
コンサータが効かないと感じる理由については、下記の記事をご覧ください。
ADHDの薬はやめられずに一生飲み続けるのか
ADHDの薬を飲む期間は、人によって異なります。
症状や生活状況に応じて調整されるため「ずっと飲まなければいけない」と決まっているわけではありません。
ADHDの治療薬は、集中力の向上や衝動性のコントロールをサポートするもので、症状が落ち着いてきたら減薬や休薬を考えます。
たとえば、以下のようなときは、薬を飲み続けるか検討するでしょう。[9]
- 薬の副作用が気になってきた
- 仕事や家庭での支障が減ってきた
- ストレスの少ない環境に変わった
また、一部の薬では依存性があらわれる可能性があります。[3]
「薬をもっと飲みたい」と思ったり副作用がつらかったりするときは、自己判断で飲む量の変更や服薬を中止せずに必ず主治医に相談してください。

気になることは主治医の先生に相談しましょう!
ADHDの薬を使わない治療法
ADHDの薬は、ADHDの症状によって生じる生活のしにくさへアプローチします。
薬だけに頼らず日常生活の工夫も大切です。
たとえば、以下のような対策が挙げられます。
「薬を使わない=治療をしない」ということではありません。
薬以外の方法も組み合わせることで、自分のペースで安心して過ごせるようになる人も多くいます。
「薬以外にもできることがある」と知るためにも、それぞれ詳しく見ていきましょう。
生活環境をととのえる
生活環境の見直しにより、ADHDの症状による日常生活の困りごとをやわらげることができます。
たとえば、仕事や家事で忘れ物が多かったり集中力が続かなかったりするときは、以下のような対策が有効です。
- 「やること」を紙に書き出す
- スケジュール管理アプリを使う
- 机や部屋をスッキリととのえる
このように工夫をすることで、タスクの抜けや遅れを防げるでしょう。
また、睡眠不足や疲れがたまっていると、注意力や集中力が落ちやすくなるとも言われています。[10]
毎日同じ時間に寝起きしたり休憩を意識的に取ったりなど、基本的な生活リズムを安定させることも大切です。
認知行動療法を受ける
認知行動療法とは、行動や思考の「クセ」に気づき、うまく対応するためのスキルを身につける心理療法のひとつです。
薬物療法とあわせて認知行動療法を行うと効果的だと報告されています。[11]
ADHDの認知行動療法では、以下のようなことへアプローチします。[11]
- 時間管理の工夫を身につける
- 感情のコントロール方法を学ぶ
- 注意力を持続させる時間を伸ばす
たとえば、あなた自身の思考や行動のパターンに気づくことで、やるべきことを先延ばしにしない工夫や感情のコントロールの仕方を身につけやすくなるのです。
焦らず取り組むことで、あなたらしく過ごせる毎日へ近づいていけるでしょう。
周囲の理解やサポートを得る
ADHDの症状によって生活がうまくいかないとき、「自分の努力が足りないんだ」と感じることもあります。
ただし、困ったときは信頼できる人や主治医に相談することも、大切な治療のひとつです。
たとえば、以下のようなことが挙げられます。[2]
- 家族やパートナーにADHDの特性を理解してもらう
- 職場でスケジュール共有や確認の仕組みをつくってもらう
- 医師や専門の相談機関に相談しあなたに合った対応を一緒に考えてもらう
薬だけでなく、あなたらしく過ごすための工夫や支援を取り入れることで、ADHDの症状とうまく付き合えるようになります。
ひとりで抱えこまず、ムリなく生活を送ることが大切です。
まとめ|安心して治療することが大切
ADHDの治療薬は、集中力や衝動性をやわらげ、日常生活を過ごしやすくするために用いられます。
ただ、副作用や依存性への不安から「飲み続けていいのかな」と迷う方も少なくありません。
大切なのは、あなた自身が納得できる治療方法を見つけることです。
薬だけに頼らず、生活環境の見直しやカウンセリング、周囲のサポートのような方法を組み合わせることで、よりあなたらしく穏やかに過ごせるようになるでしょう。
治療の不安をひとりで抱え込むとこころが疲れてしまいます。
医師や信頼できる人と相談しながら、あなたにとって安心できる治療を見つけてください。
おおかみこころのクリニックは「こんなこと相談してもいいのかな」というような不安も、安心してお話しいただけます。まずは、お気軽にお問い合わせください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]N-ニトロソアトモキセチンが検出されたアトモキセチン塩酸塩製剤の使用による健康影響評価の結果等について|厚生労働省医薬局医薬安全対策課 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
https://www.jshp.or.jp/content/2024/0902-7.pdf
[2]ADHD(注意欠如・多動症)|NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease07.html
[3]コンサータ 患者向医薬品ガイド|ヤンセンファーマ株式会社
https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ph/GUI/800155_1179009G1022_1_00G.pdf
[4]注意欠如多動症(ADD,ADHD)|MSDマニュアルプロフェッショナル版
[5]コンサータ錠 18mg,同 27mgCTD 第2部 CTD の概要 2.5 臨床に関する概括評価P15|ヤンセン ファーマ株式会社
https://www.pmda.go.jp/drugs/2007/P200700052/800155000_21900AMX01770000_G100_2.pdfutm_source=chatgpt.com
[6]ストラテラカプセル 患者向医薬品ガイド|日本イーライリリー株式会社https://www.info.pmda.go.jp/downfiles/ph/GUI/530471_1179050M1023_1_01G.pdf
[7]Q69:注意欠如・多動症(ADHD)にはどの様な治療法がありますか?|一般社団法人 日本小児神経学会
[8]インチュニブを飲んでいるみなさまへP2|武田薬品工業株式会社
https://www.pmda.go.jp/RMP/www/400256/0f3ed6df-8f2d-4a98-a111-9949c5be193e/400256_1179057G1021_07_001RMPm.pdf
[9]児童青年期患者における抗 ADHD薬の使用とその留意点p3|根來 秀樹
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jscap/57/1/57_164/_pdf/-char/ja
[10]健康づくりのための睡眠ガイド 2023(案)p36|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
[11]大人の注意欠如多動症の認知行動療法P7|中島 美鈴
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjghp/36/3/36_200/_pdf/-char/ja
- この記事の執筆者
- 柚木ハル
作業療法士として精神科で17年の臨床経験を積み、現在は訪問リハビリに従事。経験を生かしメンタルヘルスを中心に、やさしく寄り添う文章を心がけて執筆しています。