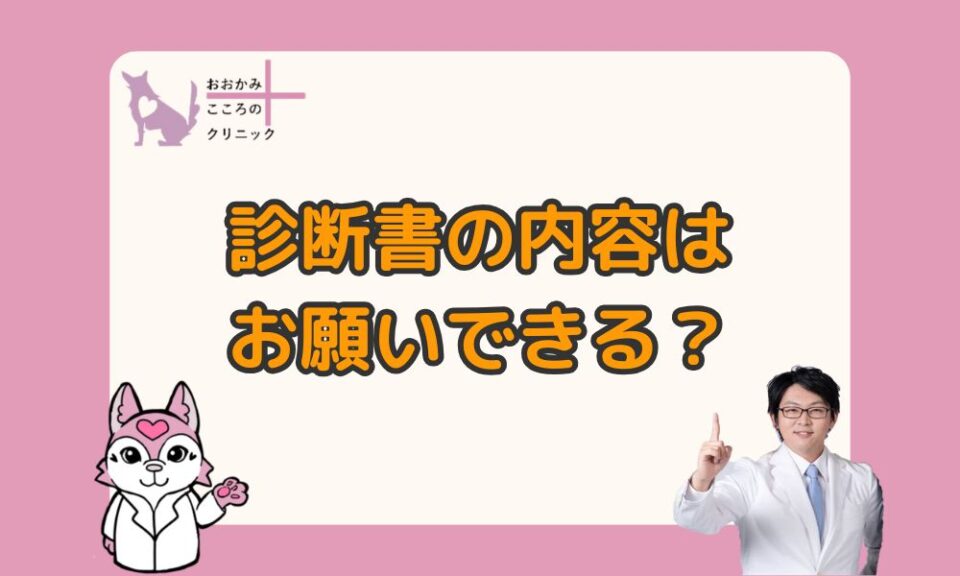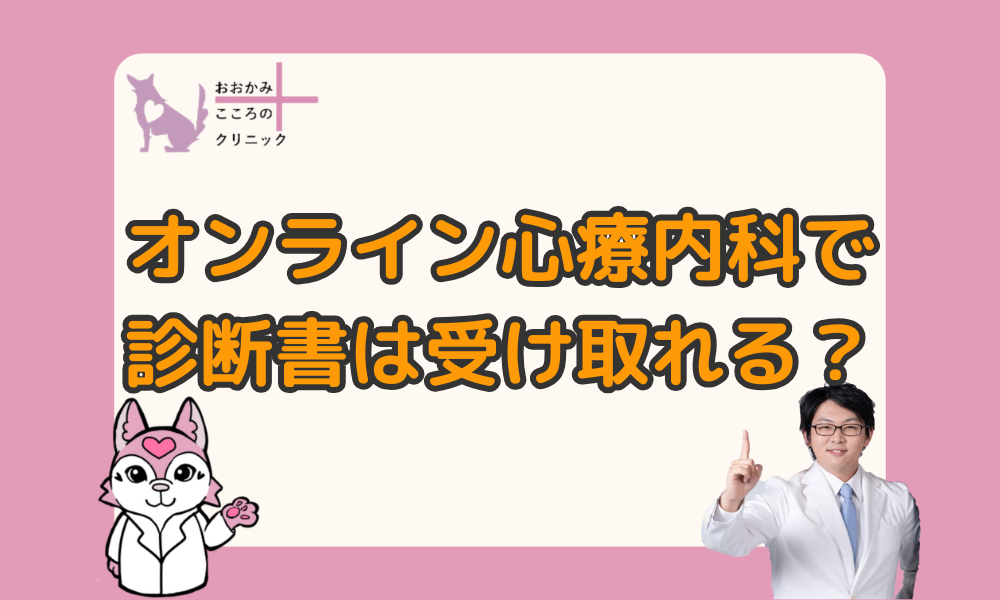「診断書に『休職が必要』と書いてほしいけどどう伝えればよいか…」
「会社に納得してもらえるような内容で診断書をお願いできるのかな?」
体調不良による休職を考えたとき、医師にどう伝えれば診断書の内容をお願いできるか悩んでしまいませんか。
診断書の内容をお願いするポイントを押さえておけば、休職の手続きや業務内容の調整をスムーズに進められます。
この記事では、診断書の内容はお願いできるのか、医師にお願いするときの伝え方を例文とともに解説します。
「どう伝えればよいかわからない」と悩む前に、適切な準備をして医師に相談する際に活用していただければ幸いです。
診断書の内容はお願いできる
患者さんは、診断書に記載してほしい内容を医師にお願いできます。
たとえば、休職や業務上の調整を求める際に、その旨を診断書に書いてほしいと伝えるケースが考えられるでしょう。
ただし、伝えられた内容がすべて記載されるわけではありません。医師は医学的な判断に基づき、事実に基づいた内容を診断書に記載します。
そのため、事実と異なる内容や医師の判断から外れる内容を記載するようお願いしても、受け入れられる可能性は低いでしょう。
診断書の内容をお願いするときは、あくまで「希望を伝える」という姿勢が大切です。
最終的な記載内容は医師の判断に委ねられることを念頭に置いて、相談しましょう。

思いを伝えるのは大切です
診断書に記載される内容
診断書は、会社や保険組合があなたの健康状態を把握するための書類です。
記載される項目はおおむね決まっており、一般的には下記の内容が含まれます。[1]
- 病名:医師が診察に基づいて判断した病名
- 本人情報:氏名や生年月日などの基本的な情報
- 療養方法に関する所見:入院や自宅療養の必要性など
- 初診日:病気やけケガで初めて医師の診察を受けた日付
- 療養にかかる期間:回復までに要すると考えられる期間の目安
- 医師や病院の情報:診断書を作成した医師の氏名や病院の名称・所在地
会社や保険組合は診断書に書かれた内容をもとに、休職の可否や業務上の調整、手当金の支給などを判断します。
診断書の内容を医師にお願いする際は、基本項目を踏まえたうえであなたの状況を伝えてください。
【例文あり】診断書の内容をお願いするときの伝え方
診断書を依頼する際は、まず病院を受診し医師の診察を受けましょう。
診断書が必要な理由を伝え医師が診断書の発行を承諾したら、後日クリニックの窓口や郵送などで受け取るのが一般的な流れです。
ですが、いざ医師を前にすると緊張してうまく話せるか不安に思うこともあるでしょう。
医師は多くの患者さんから、診断書の作成の相談を受けています。そのため、うまく話せなかったとしても、意図を汲み取ってくれるはずです。
ここからは、診断書の内容をお願いするときの伝え方を3つのケースから解説します。
医師とのやり取りをスムーズに進めるために準備していきましょう。
休職
休職を希望するときは、会社から診断書の提出を求められます。
診断書は従業員が療養に専念し、会社が休職の手続きを進めるための書類となります。
体調不良が続き仕事に支障が出ているときは、まず医師に相談し休職の必要性について判断を仰ぎましょう。
その後、診断書の作成を依頼する流れになります。
医師に状況を正しく理解してもらうために、現在の症状が仕事にどう影響しているかを具体的に伝えることが大切です。
【例文】
最近、不眠や気分の落ち込みなどの症状が続いており、仕事に集中するのが難しい状態です。通勤中の電車で気分が悪くなることもあります。
会社と相談し、一度休職して治療に専念したいと考えています。会社からは休職の手続きのために診断書を提出するよう言われました。
『(病名)のため、〇か月程度の休養が必要』といった内容で、診断書を作成していただくことは可能でしょうか。
医師に相談することで、休職に向けた手続きを進められるようになります。
傷病手当金
傷病手当金は病気やケガのために会社を休み、給与が支払われない期間の生活を保障するための制度です。
傷病手当金を受け取るためには、全国健康保険協会(協会けんぽ)が用意する「傷病手当金支給申請書」を提出しなくてはなりません。[2]
申請書には、本人が記入する欄のほかに、事業主と医師がそれぞれ記入する欄があります。
申請書では療養を担当した医師が「労務不能と認めた期間」を証明するため、医師の記入がないと傷病手当金は支給されません。
具体的には、次のようにお願いをしましょう。
【例文】
休職期間中の生活のために、傷病手当金の申請をしたいと考えています。
『傷病手当金支給申請書』なのですが、先生に証明を記入していただく欄があります。
お手数をおかけしますが、〇月〇日から本日までの期間について、労務不能であった旨の証明をお願いできますでしょうか。
専用の書類はあらかじめ保険組合から取り寄せておき、診察時に持参すると依頼がスムーズに進みます。
業務内容の調整
休職期間を経て職場に復帰する際に、業務内容の調整をお願いするために診断書が役立ちます。
医師から業務を減らす必要がある旨を診断書に記載してもらうと、会社に対して配慮を求めやすくなるのです。
口頭で「体調が万全ではない」と伝えるだけでは、どの程度の配慮が必要なのかが会社に伝わりにくいものです。
診断書があれば上司や人事担当者も状況を理解しやすく、残業の制限や異動など具体的な調整を検討できます。
次のように医師に伝えて、診断書の活用を検討しましょう。
【例文】
来月から職場に復帰したいと考えております。
ただ、まだ疲れやすさや不眠などの症状が残っており、以前と全く同じように働くことには少し不安があります。
もし可能でしたら、会社に業務内容の調整をお願いするために、『(病名)の治療継続のため、当面の間、残業や休日出勤を制限することが望ましい』といった内容で、診断書を作成していただくことはできませんか。
会社に業務内容を相談するためにも、まずは医師に相談してみましょう。
診断書はすぐ書いてもらえるのか
診断書が手元に届くまでの期間は、病院やクリニックによって異なります。
一般的には、依頼してから受け取るまでに数日から1か月ほどかかります。
診断書は公的な証明力を持つ書類のため、医師がカルテの内容を慎重に確認し、正確に記載する必要があるからです。
しかし、中には診断書の即日発行に対応している病院もあります。
おおかみこころのクリニックも、状況に応じて診断書の即日発行が可能です。
「急いで診断書を提出する必要がある」といった状況にも対応できますので、お急ぎのときはご相談ください。
あなたの状況に合わせて、発行にかかる期間を事前に病院へ確認し、余裕をもって依頼しましょう。
オンラインで心療内科を受診した際も、診断書の発行は可能です。詳しく知りたい人は下記の記事もあわせてご覧ください。
まとめ
診断書の内容は、記載してほしい点を医師に希望として伝えることは可能です。
ただし、医師は医学的な根拠に基づいて事実を記載するため、最終的な文面は医師の判断に委ねられます。
診断書を依頼する際は、休職や傷病手当金の申請など目的を明確にしておきましょう。なぜ診断書が必要で、どのような配慮を求めているのかを具体的に伝えると、医師も状況を把握しやすくなります。
また、診断書の発行には数日から1か月かかることもあります。提出期限を確認してから、早めに病院に相談しましょう。
おおかみこころのクリニックでは、診断書の即日発行が可能です。24時間来院の予約を受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]<診断書の作成上の注意点>|神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/115435/n02_shindansho_rei.pdf
[2]傷病手当金支給申請書の記入の注意点|全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kanagawa/cat080/hei/201910syoute.pdf