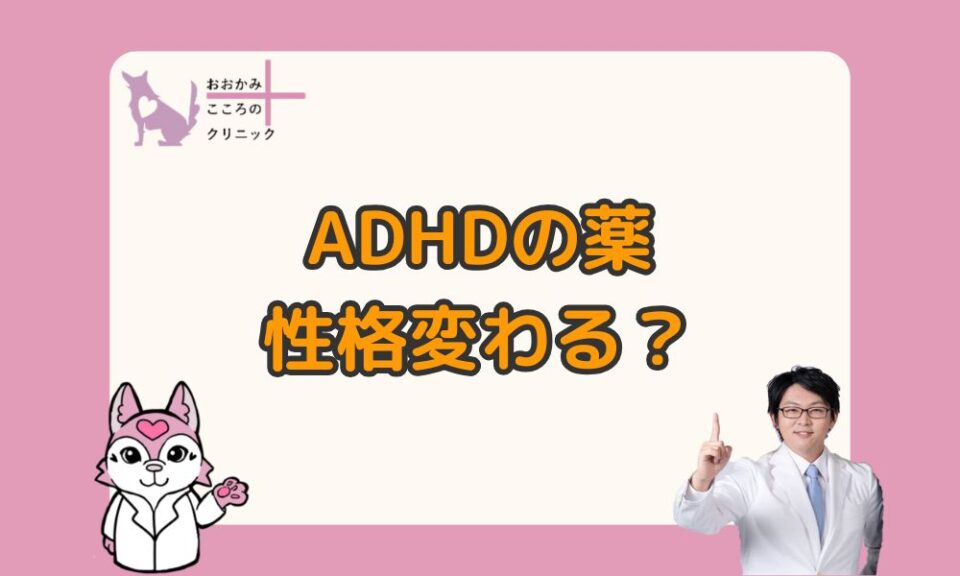「ADHDの薬をもらうにはどうすればよい?」
「病院に行かないと薬を処方してもらえないのかな?」
仕事や日常生活での困難が続き、ADHDの治療の選択肢として薬を考えたことはありませんか。
ADHDの症状は薬でやわらげられます。しかし、どこで薬を処方してもらえるのか分からない人も多いのではないでしょうか。
ADHDの薬は医師の診断のもとで処方されるため「薬が欲しい」と言ってすぐにもらえるわけではありません。
病院で診察を受けるという手順を踏むことが必要です。
この記事では、ADHDの薬を処方してもらう流れを解説します。受診への不安が少しでも軽くなり、悩みを解決する一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
ADHDの薬をもらうには医師の処方箋が必要
ADHDの治療薬は医師が診察や検査を通して、一人ひとりの症状や状態に合わせて処方します。
そのため、医師の処方箋がなければ、手に入れることができません。
ADHDの治療薬は、薬局やドラッグストアなどでは販売されていないのです。
自己判断でADHDの薬を探すのではなく、医師に相談することが適切な治療への第一歩となります。
下記の記事ではADHDの薬がよくないと言われる理由や副作用を解説しているので、あわせてご覧ください。
ADHDの薬を処方してもらうまでの4ステップ
ADHDの薬を処方してもらうには、次の4つのステップがあります。
予約せず病院に行っても、受診できずに薬がもらえない可能性もあります。それぞれのステップを見ていきましょう。
STEP1:病院を探す
まずはADHDの診断や治療を行う病院を探しましょう。
受診する診療科は、精神科または心療内科です。これらの診療科には、こころの不調や発達に関する悩みを専門とする医師が在籍しています。
そのため、あなたの状況に合わせた適切なサポートが受けられるのです。
病院を選ぶ際には、各病院のホームページを確認するのが有効です。ホームページに「大人の発達障害」「ADHDの診療」などの記載があれば、専門的な治療が期待できます。
どの病院がよいか迷ったときは、お住まいの地域名と「精神科 ADHD」や「心療内科 大人の発達障害」などを合わせたキーワードで検索しましょう。
STEP2:受診する
受診する病院が決まったら、次は医師の診察を受けます。
その際に、現在抱えている困りごとを事前に整理しておくと、医師に状況をスムーズに伝えられます。
具体的には、下記のようなエピソードを書き出しておきましょう。
- 約束や締め切りを忘れやすい
- 片づけが苦手で部屋がいつも散らかってしまう
- 気をつけていても仕事でのケアレスミスが減らない
思い出せる範囲で子どもの頃の様子を伝えたり、家族に当時の様子を聞いておいたりすると診察に役立ちます。
ADHDは脳機能の発達によるものと考えられているため、診断では「子どもの頃から症状が続いていたか」が大切なポイントになるからです。[1]
また、病院へ行く前にはあらかじめ予約をしておくとスムーズです。
初診は診察時間が長くなるため、予約がないと長時間待ったり受診ができなかったりする可能性があります。
最近ではオンライン診療を導入している病院もあるため、病院に行く時間がないときに利用するのもよいでしょう。

困りごとをメモしていくのもよいですよ!
STEP3:診断に必要な検査を受ける
医師の問診に加えて、診断の精度を高めるために心理検査が行われるケースがあります。
検査はADHDの診断を確定させるためだけではなく、得意なことや苦手なことを客観的に把握できるのです。
そのため、今後の生活でどんな工夫をすれば楽になるのかというヒントを見つける機会にもなるのです。
たとえば、下記の心理検査が行われます。
- WAIS-IV知能検査
- CAARS(Conners Adult ADHD Rating Scale:コナーズの成人期のADHD評価尺度)
- ASRS(Adult ADHD Self-Report Scale:成人期のADHD自己記入式症状チェックリスト)
WAIS-IV知能検査では言語の理解や記憶力、作業の速さなど得意・苦手を見ていきます。
また、CAARSやASRSは、自分で質問に答えていくアンケートのような心理検査です。[2]
ただし、これらの検査はすべての医療機関で必ずおこなわれるわけではなく、医師が問診の内容から必要性を判断します。
こちらのサイトではADHDの心理検査を種類ごとに解説しているので、あわせてご覧ください。
STEP4:治療方針を医師と決める
問診や検査の結果を総合的に評価し、医師がADHDの診断をします。
診断が確定したら、次にどのような治療を進めていくかを医師と相談して考えていきます。
ADHDの治療は薬物療法だけではなく、一人ひとりの生活状況に合わせた治療の進め方を決めることが大切です。
まずカウンセリングや環境調整などの心理社会的治療をおこない、必要に応じて薬物療法を併用することが推奨されています。[3]
そのため、ADHDの薬をもらうためには医師と本人が十分に話し合い、納得した上で治療方針を決定することが大切です。
ADHDの薬の種類
ADHDの治療に用いられる薬にはおもに3種類あります。[4]
| 種類 | 効果 |
| コンサータ | ADHDの症状全般に有効で、とくに不注意に対する効果が期待できる |
| ストラテラ | ADHDの症状全般に有効である |
| インチュニブ | 多動や衝動性に対する効果が中心である |
ADHDの治療に使われる薬は、脳内の神経伝達物質のバランスをととのえることで、不注意や多動性などの症状をやわらげます。
医師は症状や本人の特性、ライフスタイルなどを考えてどの薬が適しているかを判断するのです。
また、薬には副作用が起こる可能性もあるため、服用を始めたら医師の指示を守りましょう。
定期的に通院して効果や副作用のチェックを受ける必要があります。
下記の記事ではコンサータについて詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
下記の記事ではADHDの薬を飲むと性格が変わるのかについて解説しているので、あわせてご覧ください。
薬に頼らずADHDの症状をやわらげる方法
ADHDの治療は薬物療法がすべてではありません。薬を使わずにADHDの症状をやわらげる方法には、次の3つがあります。
それぞれについて解説します。
環境調整
環境調整とは、集中を妨げるものを減らしたり、物事を管理しやすくしたりするなど生活や仕事の環境をととのえることです。[5]
ADHDの特性のひとつである「注意散漫」は、周囲の刺激に影響されやすいことが原因で起こります。
そのため、集中したいときに視界に余計なものが入らないようにするだけで、作業効率が上がるのです。
具体的な例としては、下記のものが挙げられます。
- 壁に向かって座る
- 机の上には必要なもの以外は置かない
- ノイズキャンセリング機能のついたイヤホンを活用する
すぐに実践できる簡単なものから試してみましょう。
認知行動療法
認知行動療法は心理療法のひとつで、物事の受け取り方や行動のパターンに働きかけて気持ちを楽にするトレーニングです。[6]
実際にADHDの治療ガイドラインでは、認知行動療法が治療法として推奨されています。[7]
ADHDの特性により、失敗体験を重ねると「どうせわたしはダメだ」といった否定的な考え方のクセがついてしまうことがあります。
たとえば、大事な約束を忘れてしまったときに「わたしは本当にダメな人間だ…」と自動的に考えてしまうのが考え方のクセです。
認知行動療法では、そのクセに対して「忘れたことは事実だけど次はどうすれば防げるだろう?」とより現実的でバランスの取れた考え方に切り替える練習をします。
認知行動療法を通じて、失敗を次の工夫に繋げる前向きな考え方を身につけ、ADHDの特性とうまく付き合っていくことを目指します。
ソーシャルスキルトレーニング
ソーシャルスキルトレーニングは、対人関係やコミュニケーションを円滑にするための実践的な練習です。[8]
ADHDの衝動性や不注意といった特性は、悪気なく相手を不快にさせてしまい人間関係の悩みにつながることがあるからです。
トレーニングでは、まず「上司に相談する」「友人の誘いを断る」など日常生活でよくある場面を設定します。
参加者同士でそれぞれの役になりきって会話の練習をします。練習が終わったら、講師や他のメンバーからフィードバックをもらい、自分だけでは気づきにくいコミュニケーションのクセを修正していくのです。
ソーシャルスキルトレーニングでは、対人関係への苦手意識をやわらげ、日々のコミュニケーションへの自信を取り戻すことを目指します。
まとめ
ADHDの薬をもらうには精神科や心療内科を受診し、医師の診断を受ける必要があります。
受診の際は日頃の困りごとを整理しておくと、診察をスムーズに進められます。
また、治療の選択肢は薬物療法だけではありません。環境調整や認知行動療法など薬に頼らない方法も有効です。
もし、ADHDの可能性があり日常生活で困難を感じていたら、ひとりで抱え込まずに病院へ相談してみてください。
おおかみこころのクリニックでは毎日夜22時まで診察しています。来院予約は24時間受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]ADHDタイプ”の方の対処策① | NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/rinshoshinri/rinshoshinri_blog20220228-1.html
[2]成人期のADHDのアセスメント|厚生労働科学研究成果データベース
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2018/182091/201817011A_upload/201817011A0010.pdf
[3]今村明先生に「ADHD」を訊く|公益社団法人 日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=39
[4]ADHDについて|信州大学医学部分子細胞生理学教室
https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/chair/i-2seiri/ja/adhd.html
[5]ADHD(注意欠如・多動症)|NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease07.html
[6]認知行動療法(CBT)とは|認知行動療法センター
https://cbt.ncnp.go.jp/contents/about.php
[7]大人の注意欠如多動症の認知行動療法,中島 美鈴
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjghp/36/3/36_200/_pdf/-char/ja
[8]東京都ソーシャルスキルトレーニング(SST)ガイド|東京都福祉局障害者施策推進部施設サービス支援課
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/fukushi/sst_guide