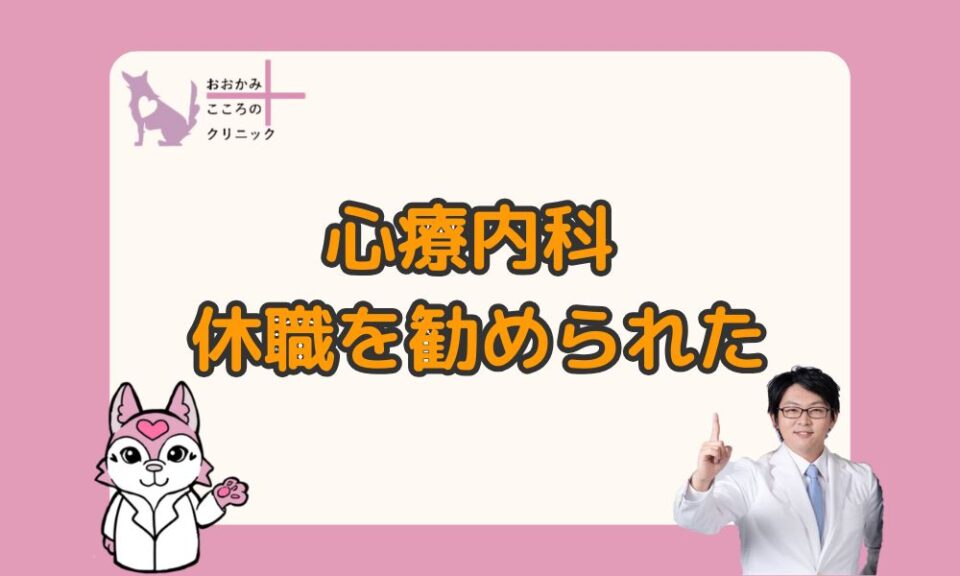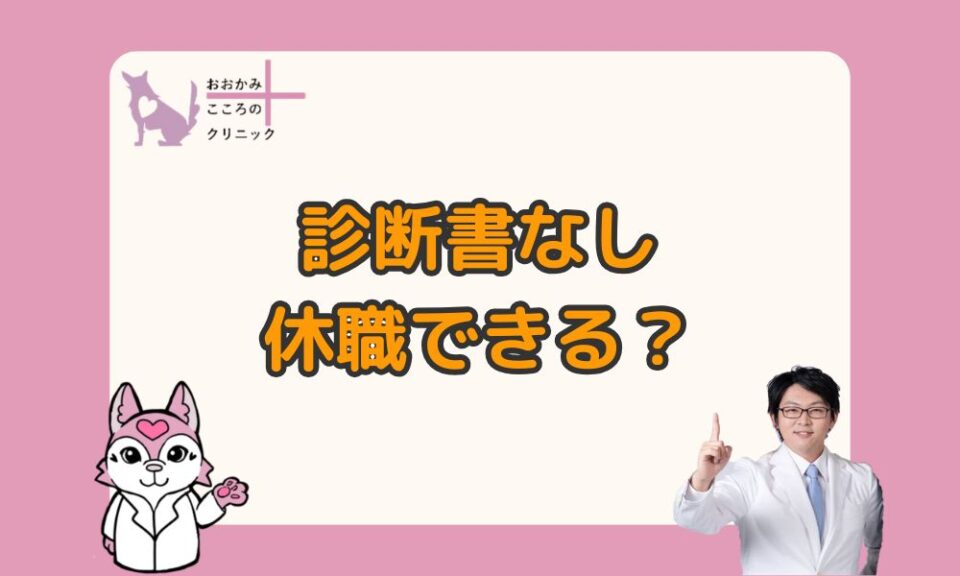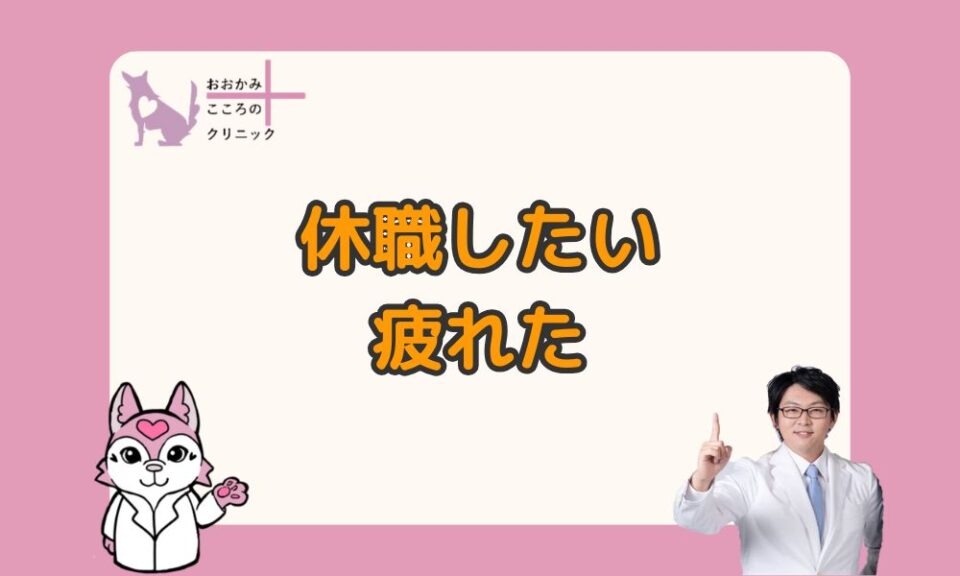心療内科の医師から「休職した方がよい」と勧められ、どうすればよいかと悩んでいませんか。
責任感が強い人ほど「わたしが休むと職場に迷惑がかかる」「今後のキャリアはどうなるのだろう」といった不安や罪悪感を抱えています。
ただし、医師からの休職の提案はこころと身体が限界を迎え、治療に専念すべきだというサインです。休職は特別なことではなく、回復して再びあなたらしく働くための選択肢です。
この記事では、心療内科で休職を勧められたときに休むべき理由や休職までの流れを解説します。安心して休養に入り、回復への一歩を踏み出すための参考にしてください。
心療内科で休職を勧められたときは休職すべき
心療内科で休職を勧められたときは、休職を前向きに検討しましょう。
医師が休職を勧めるのは「心身の不調が強いため治療に専念する必要がある」と判断したためです。
ムリをして働き続けると、症状が悪化してしまう可能性があります。
たとえば、集中力や判断力が低下し仕事でミスが増えたり、周囲とのコミュニケーションがうまくいかなくなったりするかもしれません。
そうなると、さらに自分を責めてしまい、回復が長引く悪循環になるおそれがあります。
あなたの健康を最優先に考え、医師の提案を受け入れることが回復への近道になります。休職は、元気に働くための必要な時間だと考えましょう。

これからの生活のために、今はゆっくり休むことが大切です
心療内科が休職を決める基準
心療内科の医師が休職の必要性を判断する際には、次の2つの基準があります。
- 日常生活や仕事に支障をきたしている
- 病気の原因が仕事や職場の環境にある
まず、症状によって日常生活や仕事にどの程度の支障が出ているかを確認します。
たとえば「朝起き上がれない」「仕事に集中できずミスが続く」などの状態は、休養が必要なサインと判断されるでしょう。
もうひとつの基準は、不調の原因が仕事や職場環境にあることです。
長時間労働や人間関係のストレスなどが原因で症状があらわれるときは、環境から物理的に離れる必要があります。
休職してストレスの原因から距離を置くことが、症状の緩和に有効です。
心療内科で休職を勧められた後の流れ
心療内科で休職を勧められた後には、次の3つのステップがあります。
焦らずにひとつずつ進めていきましょう。
STEP1:医師に診断書を発行してもらう
休職を会社に申し出るためには、まず医師に診断書を発行してもらう必要があります。
診断書は、休職の必要性を証明する書類です。会社側も診断書があることで、休職の手続きをスムーズに進められます。
医師に診断書を依頼する際には、現在の具体的な症状を正確に伝えましょう。
「夜眠れない日が続いている」「仕事中に急に涙が出ることがある」など、仕事にどのような支障が出ているかを具体的に話すと、医師も診断書を書きやすくなります。
費用は医療機関によって異なりますが、3,000~5,000円程度かかります。
診断書がなくても休職できるのかについては、下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
STEP2:会社に報告する
診断書を受け取ったら、会社に休職の意向を伝えましょう。
報告する相手は、まず直属の上司が適切です。
もし上司に話しにくいときは、人事部や労務担当者に直接相談するのもひとつの方法です。
報告の際は感情的にならず、医師の診断結果として「休職が必要である」という事実を冷静に伝えましょう。このとき、診断書の提出を求められるケースがほとんどです。
会社の就業規則には休職に関する規定が定められているため、手続きの方法や休職期間中の連絡方法などもあわせて確認しておきましょう。
STEP3:業務の引き継ぎを行う
休職に入る前には、担当している業務の引き継ぎを行います。
あなたの心身の負担にならないよう、上司と相談しながらムリのない範囲で進めてください。
後任の担当者が困らないように、現在進行中の業務の状況や取引先の連絡先、ファイルの保管場所などを一覧にしておくと親切です。
口頭での説明に加えて、業務手順をまとめた簡単なマニュアルを作成しておくと、休職中に問い合わせの連絡が来るのを防げます。
すべてを完璧に引き継ごうと気負う必要はありません。最低限必要な情報を整理し、残りの業務をスムーズに進めてもらえるように準備してください。
休職中のお金の不安を解消する方法
休職期間中は給与が支払われないケースが多く、経済的な不安を感じるかもしれません。しかし、生活を支えるための方法には、次の3つがあります。
制度をうまく活用すれば、お金の心配を減らしましょう。
労災保険
労災保険は、休職中の経済的な不安を解消するひとつの方法です。業務上や通勤による労働者の病気、ケガなどに対して保険給付を行います。
たとえば「極度の長時間労働があった」「上司から継続的に厳しい叱責を受けていた」など、業務による心理的負荷が原因で精神疾患を発症したと判断されると、労災認定されます。[1]
ただし、労災認定は労働基準監督署が判断するため、申請して必ず認定されるとは限りません。
認定されると、下記の種類が支給されるのです。[2]
- 療養給付:療養にかかる全額
- 休業給付:休業4日目から、1日につき給付基礎日額の60%
申請を検討する際は、会社の担当者や管轄の労働基準監督署に相談してみましょう。
傷病手当金
業務外の病気やケガで仕事を休むときは、傷病手当金を受給できます。傷病手当金は加入している健康保険から支給される制度で、休職中の生活を支える助けになります。[3]
傷病手当金を受給するには、下記の4つの条件をすべて満たす必要があります。[3]
- 病気やケガで休んでいる
- 仕事に就ける状態ではない
- 休んだ期間の給与が支払われていない
- 連続して3日間休み4日目以降も休んでいる
支給額はおよそ給与の3分の2です。傷病手当金を利用したいときは、加入している健康保険組合に申請しましょう。
会社独自の手当
企業によっては、独自の福利厚生として休職中の手当制度を設けている企業があります。
会社独自の手当の有無や内容は、それぞれの企業の就業規則や賃金規程によって定められています。
たとえば、給与の一部が補償されたり、見舞金が支給されたりするケースがあるのです。
まずは、あなたの会社の就業規則を確認したり、人事部や労務の担当者に問い合わせたりしましょう。
利用できる制度は積極的に活用し、安心して休養できる環境をととのえるのが回復への第一歩です。
休職の罪悪感をやわらげる考え方
休職への罪悪感を手放し、回復に専念するための考え方には下記の2つがあります。
- 休職を「治療に必要な期間」と捉える
- 心身の不調は意志の力だけで解決できないと理解する
1つ目は、休職を「治療に必要な期間」と捉えることです。
風邪をひいたら身体を休めるように、こころの不調にも休養が必要です。休職は、仕事から離れて治療に集中し、再び元気に働くための準備期間と考えましょう。
2つ目は、心身の不調は意志の力だけで解決できないと理解する点です。
こころの不調は脳の機能的な問題や環境など、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こります。
気力で乗り切ろうとせず、適切な治療と休養をとることが回復への近道です。
下記の記事では「休職したい疲れた」と思う原因を解説しているので、あわせてご覧ください。
まとめ
心療内科で休職を勧められたときは、こころと身体が休息を必要としているサインです。ムリに働き続けると症状が悪化し、回復が長引いてしまうおそれがあります。
まずは医師の診断を信頼し、あなたの健康を最優先に考え、休職を前向きに検討しましょう。
休職中の経済的な不安に対しては、労災保険や傷病手当金などの制度が用意されています。これらの制度をうまく活用することでお金の心配を減らし、治療に専念できる環境をととのえられるのです。
休職することに罪悪感を抱く必要はありません。休職はあなたらしく働くための大切な準備期間です。焦らずにゆっくりと休み、回復に努めましょう。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]精神障害の労災認定|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf
[2]1ー2各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください。|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000166858.html
[3]病気やケガで会社を休んだとき|全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139