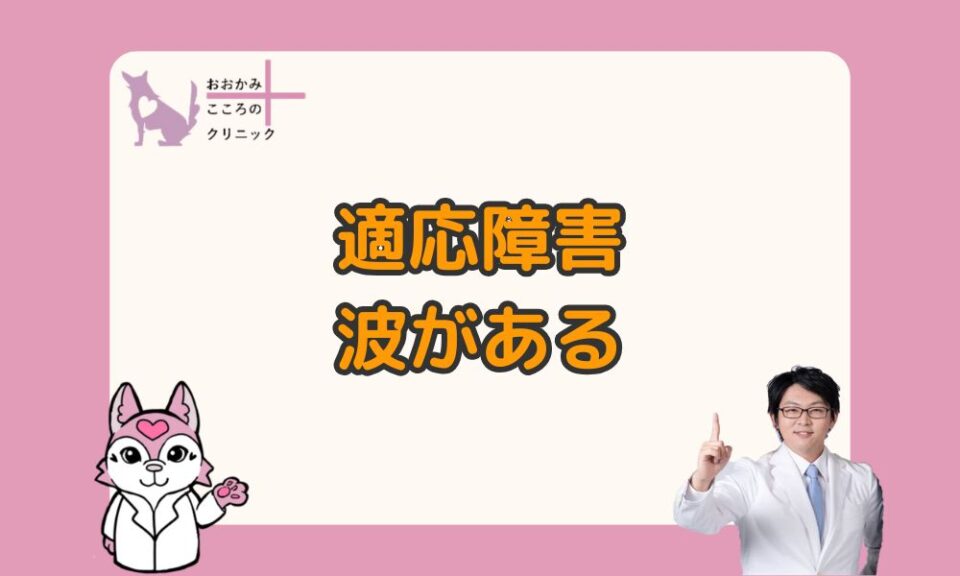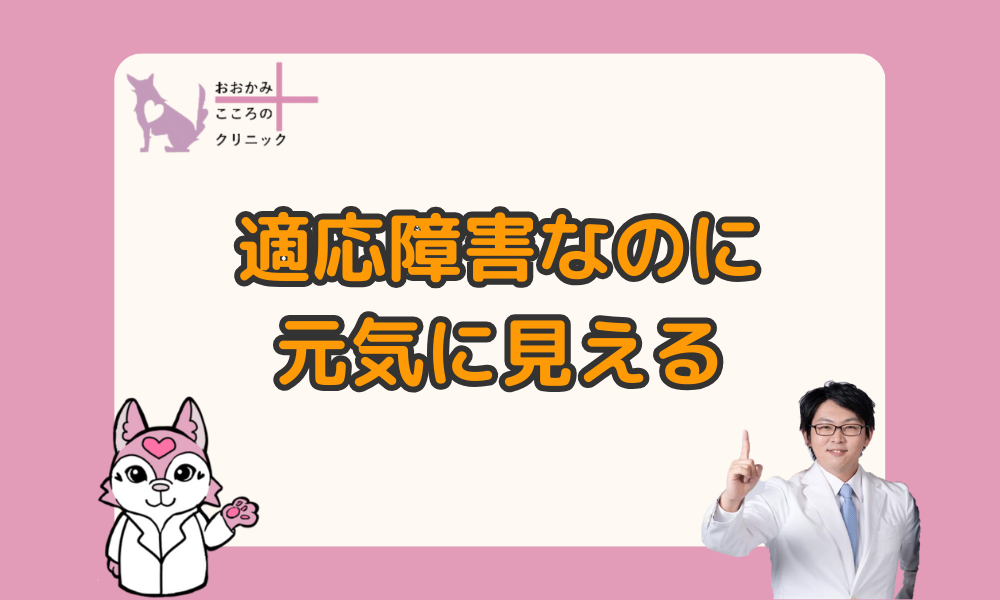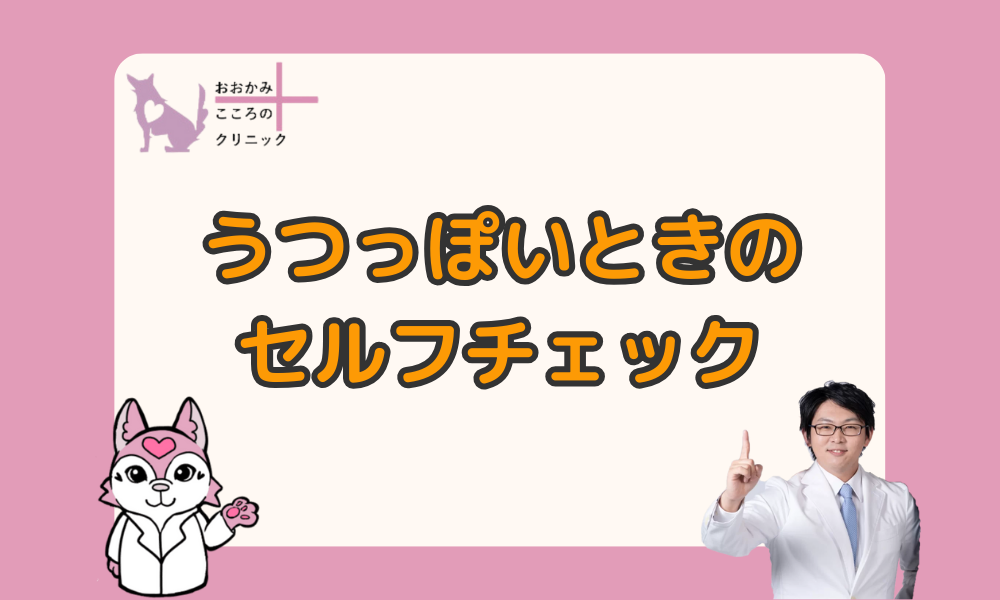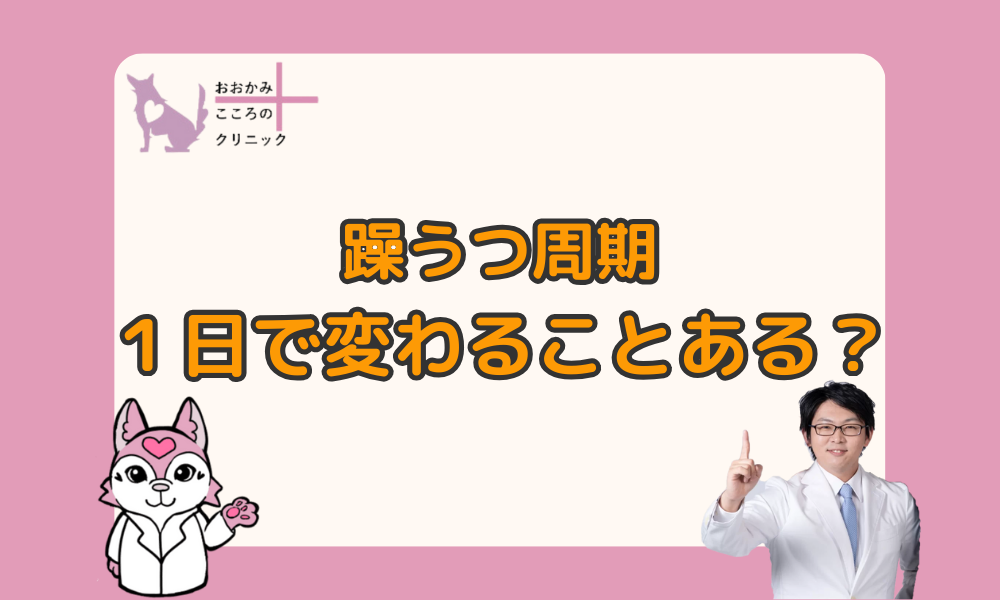「調子がよかったのに、仕事に行こうとしたら具合が悪くなってきた」
こころと身体の調子が安定せずに、不安を感じていませんか?
適応障害は、ストレスの原因から離れることによって症状が落ち着くため、気分や体調の波が起こることも少なくありません。
適応障害の波が起きる原因を理解することは、こころの安定につながり調子をととのえやすくなります。
この記事では、適応障害に波がある理由と具体的な対処法を解説します。気分や体調の波に悩む人のお役に立てれば幸いです。
適応障害に波がある原因
適応障害に波があるのは自然なことです。「よくなったと思ったのにまた落ち込んだ」と感じるのも、回復する過程のひとつと考えましょう。
適応障害に波がある原因は、次の3つです。
ここでは、なぜ適応障害に波があるのか詳しく解説します。
原因から離れると症状が落ち着く
適応障害に波があるのは、原因から離れると症状が落ち着くからです。
適応障害は環境や人間関係など、原因がはっきりとしていることが特徴です。[1]
たとえば、職場での上司との関係が原因であれば、仕事のあとや休日は症状が軽くなることがあります。
仕事中は不安や抑うつ気分があっても「原因から離れることで一時的に楽になる」のは、適応障害の特徴です。
心身ともに不安定な状態が続いている
不安定な状態が続くと、調子の波がでやすくなります。
適応障害では、こころも身体もエネルギーが減っている状態になるのです。
「少し元気になってきた」「治ったかも」と思って急に予定を詰めたり仕事をがんばりすぎたりすると、反動でまた調子を崩すこともあります。
適応障害は薬物治療を最小限にするため、回復にはストレスになりにくい環境も欠かせません。[1]
ストレスになりやすい環境にいると、気持ちが不安定になりやすいです。あなたがストレスを感じやすい状況を理解し、極力避けるもしくは考え方や感じ方を工夫しましょう。

いつも一定の気分で過ごせる人の方が珍しいでしょう
生活リズムや環境の変化に左右される
生活リズムがととのっていないと、気持ちの波が起きやすくなります。
気分の落ち込みは、睡眠不足の影響も受けやすいとされています。夜勤を含むシフト交代制の仕事をしている人は、抑うつ状態になりやすいと報告されているのです。[2]
適応障害になると、朝起きることがつらくなったり夜眠れなくなったりすることもあります。生活リズムがととのっていないと、気持ちに波がある状態となる可能性が高まるのです。
適応障害の代表的な症状
適応障害では、以下のような症状が見られます。
- 不安
- 抑うつ気分
- 頭痛やめまい
他にもそわそわと落ち着かなかったり、緊張しやすかったりする人もいます。涙もろくなる人、倦怠感や不眠などの症状を自覚する人も少なくありません。
適応障害はうつ病や不安症といった他のこころの病気と異なり、「ストレスの原因」が明確にあります。まずが、ストレスの原因に対する反応として症状が出ているかを考えてみましょう。[3]
適応障害で波があるときの対処法5選
適応障害で波があると感じるときの対処法は次の5つです。
それぞれ詳しく解説します。
気分転換をする
適応障害で波があると感じたら、気分転換をしましょう。
気分転換には、ストレスや不安から離れリフレッシュできる効果が期待されています。
たとえば、以下の方法から自分がすっきりするものを取り入れましょう。
- 入浴
- 音楽鑑賞
- アロマテラピー
- 軽い運動や散歩
感情の波があるときは、気分を変えることで落ち着くことも多くあります。
とくに、アロマテラピーは不安や抑うつ状態など、ストレスと関連する病気に対するリラクセーション効果が期待されています。[4]すっきりする香りや落ち着く匂いを見つけて、気持ちを落ち着かせてみてください。
こまめに休憩する
波があるときは、こまめに休憩をとりましょう。
「少し元気になってきた」と思っても、ムリをしてしまうと体力が追い付かず疲れやすくなります。
熱中する時間や活動的な行動が増えたら、「休む時間」も確保しましょう。ゆっくり過ごすだけでなく、軽いストレッチをすることも休憩のひとつです。
こまめな休憩をとれるようになると、復職後も過ごしやすくなります。詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
波を気にしすぎない
波があることを自然ととらえ、気にしすぎるのをやめましょう。
体調や気分の波に一喜一憂しすぎると、「また落ちたらどうしよう」と不安が膨らんでしまいます。
波があるのは自然なことだと認識し「今日は波がある日なんだな」と思う感覚をもつと、気持ちが軽くなることがあります。
また、波がどうしても気になってしまうときは、しっかり休んだあとで自己分析をしましょう。抑うつ状態にはバランスのよい考え方を身につける認知行動療法が有効です。[5]
たとえば、瞬間的に思い浮かんだ考えを整理するコラム法は、今後の対策を考えることに役立ちます。

そんな日もあるよね!ぐらいの気持ちも大切です
ムリして明るく振舞わない
波があると感じたら、ムリして明るく振る舞うのをやめましょう。
つらいときに「元気なふり」「周りが求めているであろう姿」でいようとすると、こころのエネルギーを余計に消耗します。
調子が悪い日は最低限のことだけ行い、あとは休むことを優先してください。不調を長引かせないためにも、休むことが大切です。
適応障害の人は、周囲から見ると元気に見えると思われることが多くあります。その理由については、こちらの記事を参考にしてください。
食事や睡眠のリズムをととのえる
食事や睡眠のリズムをととのえると、波が穏やかになります。
朝起きて夜眠るという自然なリズムがととのうと、少しずつこころも安定してきます。
休んだはずなのに疲れていたり睡眠がとれていなかったりするときは、日中に適度な運動をしましょう。
また、バランスのよい食事も適応障害の波を穏やかにする助けになります。[6]暴飲暴食にならないよう気をつけながら、身体にやさしい食事を意識してください。
適応障害以外にも考えられるこころの病気
適応障害は、ストレス原因から離れることで比較的早く回復するとされています。
しかし、半年以上にわたって症状の波が続いていたり、明確なストレス原因がなくても気分の落ち込みが強かったりしたときは、他のこころの病気も考えられるでしょう。
考えられる病気は、次の3つがあります。
適応障害からうつ病になる人や、適応障害とうつ病を併発するケースもあります。自己判断せず、次の内容を参考にしながら医師に相談してみてください。
うつ病
うつ病は気分の落ち込みや意欲の低下などが代表的な症状です。適応障害との違いは、原因が特定できないことです。また、適応障害からうつ病へ移行するケースもあります。
原因だと思っていたことから離れても症状が落ち着かないときは、うつ病や他のこころの病気の可能性も考えられるでしょう。
自分が「うつっぽいかもしれない」「気分が落ち込みやすい」と思ったら、下記の記事を参考にしてください。
双極性障害
双極性障害は活発になる躁状態と、憂うつで無気力なうつ状態を繰り返すこころの病気です。
波があるという点では適応障害と共通しています。双極性障害の波は人によって異なりますが、1日で変動する人もいれば年数回で切り替わる人もいるのです。
双極性障害とうつ病の区別も難しいとされているので、回復のためには定期的に通院をし、あなたの状態を包み隠さず医師に話すようにしてください。[7]
双極性障害の波については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
気分循環性障害
気分循環性障害は双極性障害と同様に波がありますが、症状の程度が比較的軽いといわれています。[8]
気分循環性障害では、気分の高揚や落ち込みは数日間しか続きません。ただし予期せぬタイミングで、頻繁に再発することが特徴です。症状が悪化すると、双極性障害に発展するケースもあります。
適応障害なのか気分循環性障害なのかを自分で判断することは難しいため、早めに医師に相談してください。
まとめ
適応障害に「波がある」のは、ごく自然なことです。
「自分はおかしい」と不安になったり自己否定したりすると、回復が遅れることもあります。
波を感じたときの対処法は、次の5つです。
- 気分転換をする
- こまめに休憩する
- 波を気にしすぎない
- ムリして明るく振舞わない
- 食事や睡眠のリズムをととのえる
休憩や気分転換を適度に行い、ムリをしないようにして波が落ち着くのを待ちましょう。
自分の状態を正しく知るためにも、医師を頼ることも選択肢のひとつです。気分の波がつらいと悩んだときは、一度おおかみこころのクリニックに相談にお越しください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]適応障害の診断と治療,平島奈津子
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1200060514.pdf
[2]睡眠・概日リズム機構が気分調節に及ぼす影響とその神経基盤,元村祐貴
https://chronobiology.jp/2023/journal/JSC2016-1-012.pdf
[3]適応障害 / 統合失調症|厚生労働省
https://kenkoukyouikusidousyakousyuukai.com/img/file214.pdf
[4]メディカル・アロマセラピー,今西次郎
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcam/1/1/1_1_53/_pdf
[5]うつ病の認知療法・認知行動療法(患者さんのための資料)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/04.pdf
[6]休養・こころの健康|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b3.html
[7]双極性障害の診断と薬物治療,久住一郎
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpm/60/8/60_707/_pdf/-char/ja
[8]気分循環性障害 – 10. 心の健康問題 – MSDマニュアル家庭版