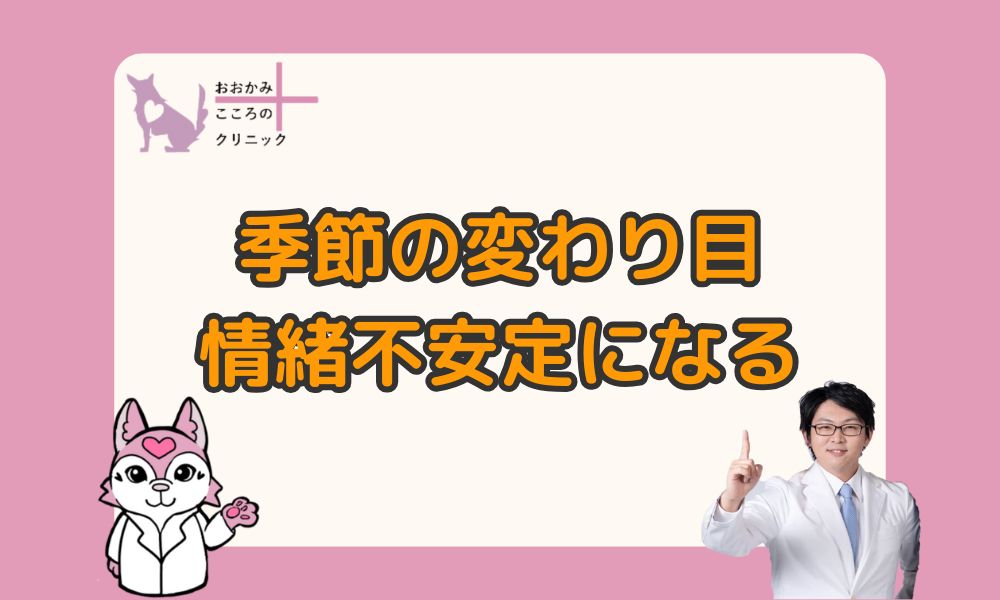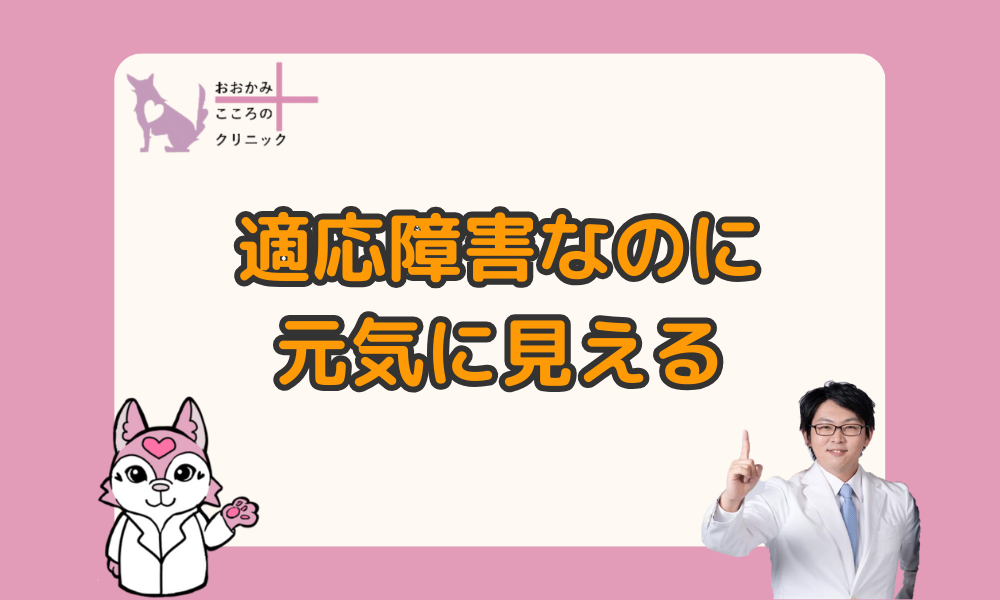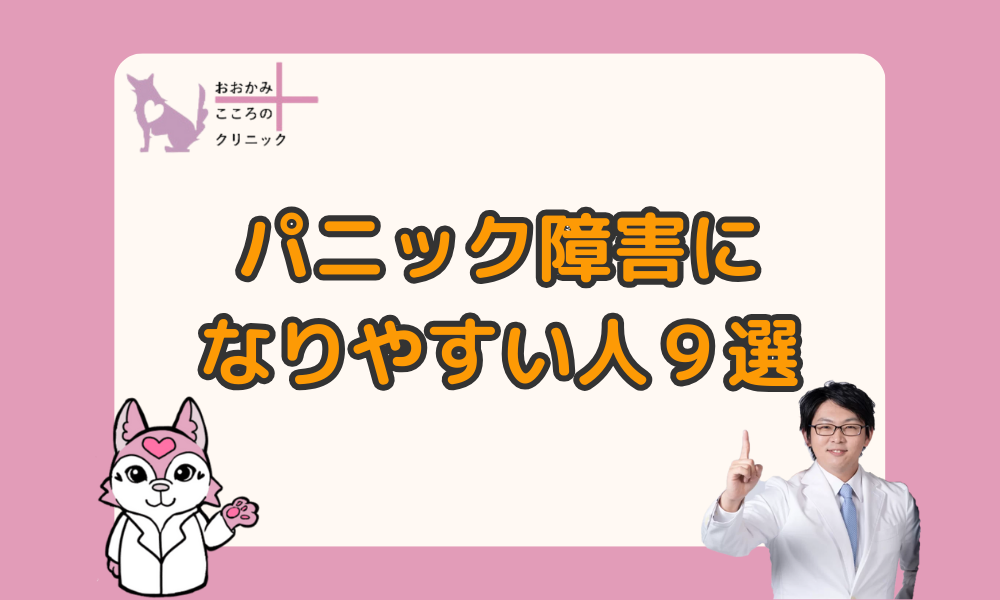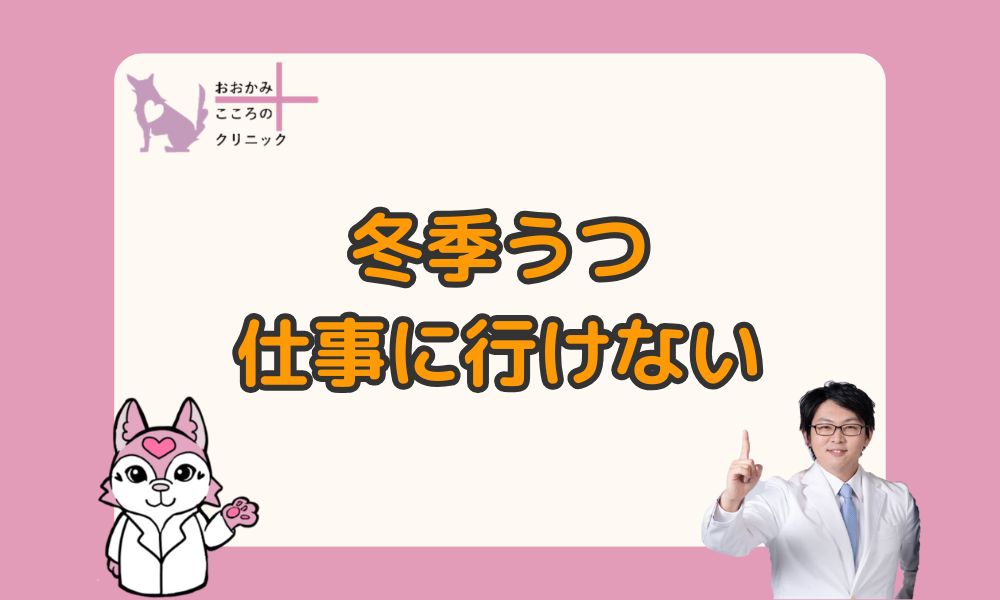季節の変わり目は寒暖差が激しく自律神経が乱れやすいため、風邪をひきやすくなる時期ですよね。
気温の変化に身体が対応できずに、のどの痛みや鼻水などの不調が出やすくなります。
精神的な不調も同じで、春から夏、夏から秋など季節の変わり目は精神不安定になることがあります。
以前は、情緒不安定になりやすい季節は春や冬といわれていましたが、実はどの季節も不調になりやすい原因があるのです。
対処法を知ることで、情緒不安定になる頻度を減らせるようになるでしょう。
この記事では、季節の変わり目に情緒不安定になるのはなぜか、不安定のサインや対処法を解説します。
季節の変わり目の情緒不安定さと、こころの病気との関係についても紹介しますので、病院へ行くか迷っている方の参考になれば幸いです。
季節の変わり目に情緒不安定になるのはなぜか
季節の変わり目に情緒不安定になる原因は、次の3つがあります。
- 環境の変化
- 自律神経の乱れ
- 天気や気圧の変動
季節の変わり目は、節目と変化の時期です。春は環境の変化に適応しようとした結果、自律神経の乱れが起きやすく身体のだるさや頭痛を感じることもあります。[1]
また、季節の変わり目は朝晩の気温差や気圧変動が激しく、自律神経が乱れやすいといわれています。天候の変化により、気持ちが高ぶるときに強まる「交感神経」と、リラックス状態のときに働く「副交感神経」の切り替えが難しくなる人が増えるのです。
自律神経の乱れは、内耳(ないじ)が気圧の変化を感じとることで生じます。[2]
「内耳」は、自律神経に気圧の変化を伝えるセンサーの役割を担います。自律神経の乱れが起きるとストレスや緊張を感じ、情緒不安定になりやすくなるのです。そのため、めまいと情緒不安定の関連性は深いとされています。[2]
梅雨の時期にふわふわしたり、くらくらしたりするめまいに悩むときは内科を受診しましょう。[3]

季節の変わり目って朝晩の寒暖差も激しくて、こころもよく体調崩しちゃいます💦
季節の変わり目に見られる情緒不安定のサイン
なぜか季節の変わり目には、普段は落ち込むことが少なくても情緒不安定になることがあるでしょう。
たとえば、次のような症状が情緒不安定のサインです。
- 突然涙が出てくる
- 感情の波が激しい
- 集中力が低下する
- 不眠や食欲不振になる
- 体調不良になりやすい
- 些細なことにイライラする
いつもなら気にならない些細なことも、気にしてしまうこともあります。不安感から他人の言動に敏感になり「嫌われた」「わかってくれない」と思うかもしれません。
また、情緒不安定さを責めてしまい「なぜこんなにもダメなのか」と考えることもあります。
季節の変わり目の情緒不安定への対処法
季節の変わり目の情緒不安定への対処法は、、次の5つが挙げられます。
できそうなことからはじめて、季節の変わり目を少しでも穏やかに過ごしましょう。
休養を優先させる
まずは、季節の変化に対応できるような身体をととのえることが大切です。
とくに、疲れを感じやすかったり身体症状があらわれたりしたら、まず休養を優先しましょう。
身体に負荷がかかっているとき、ムリに活動しようとするとかえって不調になってしまいます。ぼーっとする時間をつくったり、のんびり過ごすことを大事にしたりして、生活リズムをととのえる準備をしましょう。
不眠に悩むときは、よい睡眠のためにも日中に身体を適度に動かして、夜は早めに寝ることもおすすめです。

体調第一で休養しましょう
身体を冷やさない
身体を冷やさないことは、自律神経の乱れを防ぐ方法のひとつです。
人の身体は寒さを感じると血圧が上昇して、心臓に負荷がかかりやすくなります。身体は自然に体温を上げようとするため、身体ががんばりすぎる前に温める必要があるのです。[4]
1日20分を目安に身体を動かして温めましょう。とくにサイクリングや軽いランニングなどの有酸素運動がおすすめです。[5]
はじめのうちは軽い散歩から慣らしていきましょう。外出時は脱ぎ着ができる服装にして、体温調節してみてくださいね。
生活リズムをととのえる
朝起きて朝食を食べたり、午前中のうちに身体を動かしたりすることは、生活リズムをととのえることに役立ちます。
季節の変わり目の情緒不安定は、身体が気温や環境の変化に追いついていないことが原因です。規則正しく生活すれば、生活習慣の乱れをととのえ睡眠の質を高めることにもつながります。[6]
また、こころの病気のリスクも減るという報告もあります。[7]気持ちを安定させて日々を過ごせるようにしていきましょう。
自分の気持ちを吐き出す
自分の気持ちを吐き出すと、気持ちを整理したり発散したりすることが可能です。
ひとりで行なうときは紙に書いたりアプリに入力したりして、自分の感情のパターンを把握しましょう。ため込まずに吐き出すことで、自己理解を深めることにもつながり感情のコントロールに役立ちます。
また、身近な人や医師やカウンセラーに相談することも効果が期待できるでしょう。とくに医師やカウンセラーなどの専門家に相談すれば、一人ひとりの状態にあった治療方針を提案してもらえることもあります。
定期的にリフレッシュする
ストレスをためないように、適度に発散することも大切です。
たとえば、身体を動かしたり趣味や自分の好きなことを楽しんだりすると、こころと身体が喜ぶでしょう。リフレッシュには、頭のなかにあるモヤモヤをすっきりさせる働きがあります。
情緒不安定のときこそ、ムリのない範囲で自分にとって心地よい時間を見つけてください。
季節の変わり目の情緒不安定と精神疾患の関係
季節の変わり目に情緒不安定になるときは、以下の病気の可能性も考えられます。
それぞれの病気について、詳しく紹介します。
適応障害
適応障害とは、環境の変化などに対して不安感や倦怠感などが生じる病気です。
発症の原因がはっきりしているので「なぜ?どうして?」よりも「職場がつらいから」といった発症のきっかけに気づきやすいといわれています。
そのため、原因から離れているときは元気に過ごせることが多く、自分でも病気なのかがわからなくなる人も少なくありません。また、がんばって明るく振舞うこともできるため、周りに気づいてもらえないケースもあります。
下記の記事では、適応障害について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
不安障害
不安障害(不安症)とは、将来に対する不安やこれからできることに対する恐怖心が過度にあり、日常生活に支障をきたす病気です。[8]
不安障害のひとつであるパニック障害では、予期不安といって「もしも発作が起きたらどうしよう」と心配しやすくなることがあります。
ほかにも、パニック発作では恐怖や不安とともに、発汗や呼吸困難、動悸などが突然あらわれます。
たとえば、過去にパソコンで作業中に発作が生じていると、似た場面で「発作が起きるかも」とよぎり不安が増す人もいるのです。
下記の記事では、パニック障害について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
季節性感情障害
季節性感情障害は、病名に「季節」と入っているように、季節の変わり目に情緒不安定になる病気です。
特定の季節に気分の落ち込みや意欲低下などの症状があらわれ、季節が過ぎると落ち着くことが特徴といわれています。
冬の季節性感情障害のおもな症状は、過眠や過食です。甘いものを欲する人や眠気を感じやすい人が多いとされています。
下記の記事では、季節性うつ病の原因や治し方を詳しく解説していますので、参考にしてください。
まとめ
季節の変わり目に情緒不安定となる原因は、気圧や天気・環境の変化・自律神経の乱れなどさまざまです。
自分ではコントロールできない原因もあるからこそ、セルフケアで対策できるところは工夫しましょう。とくに運動や趣味などのストレス発散は、今よりも季節の変わり目のメンタル不調をやわらげてくれます。
生活リズムをととのえ、体を温めながら今より快適に過ごしていきましょう。
季節の変わり目で情緒不安定になりやすい人は、おおかみこころのクリニックにお越しください。休日や夜も診療を行っておりますので、お気軽にご相談くださいね。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]一般社団法人 ぎふ綜合健診センター
https://gghc.or.jp/wp-content/uploads/2022/08/2021.46%E6%9C%88%E8%87%AA%E5%BE%8B%E7%A5%9E%E7%B5%8C.pdf
[2]気圧の変化でなぜ体調不良が起こるの? 気圧が自律神経に与える影響と対処法 | 気象病の基礎知識 | 頭痛ーる:気圧予報で体調管理
https://zutool.jp/column/basic/post-16174
[3]公益社団法人 松阪地区医師会/健康アドバイス52『めまいの季節』
https://matsusaka.or.jp/advice/no94.html
[4]急激な温度変化にご注意 日本医師会 No.189
https://www.med.or.jp/dl-med/people/plaza/189.pdf
[5]体を動かす|こころと体のセルフケア|ストレスとこころ|こころもメンテしよう ~若者を支えるメンタルヘルスサイト~|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/self/self_01.html
[6]健康づくりのための睡眠ガイド2023 p25.
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
[7]セルフケアのポイント|こころの耳 厚生労働省
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/pdf/afterSC_selfcare_A3.pdf
[8]不安症|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=BLA9JV0KhiWPIMzX