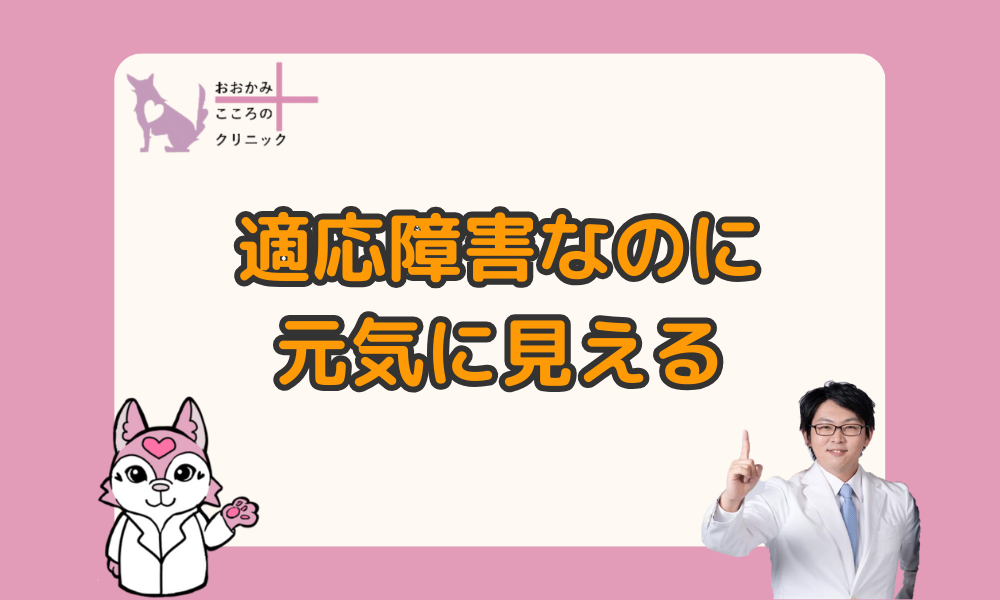「もしかして、あの人は適応障害と嘘をついているのでは?」
身近な人の様子を見て、そんな疑問を感じたことはありませんか。
適応障害は、特定のストレスが原因で心身に不調があらわれる病気です。
ときには症状のつらさが周囲に伝わりにくいため、本当に適応障害なのか疑うこともあります。
そのため、本人が本当に適応障害で悩んでいるかを判断するポイントを知っておけば、相手を疑わずに済むでしょう。
この記事では、適応障害を嘘だと感じる理由、嘘を見抜くポイントを解説します。適応障害の人と接するヒントにしていただければ幸いです。
適応障害とは
適応障害は、環境の変化や新しい状況からのストレスに対してうまく対応できずに発症するこころの病気です。[1]
適応障害の特徴は、ストレスの原因がはっきりしている点です。
具体的には、就職や転職、結婚、離婚など生活の変化がきっかけになります。原因となるストレスが解消されると、症状は6か月以内に落ち着くとされています。[2]
おもな症状は、以下のとおりです。
- 不安
- 焦り
- 抑うつ状態
- 過度な緊張
- 気分の落ち込み
症状によって、仕事や家事など普通にできていたことが難しくなるのです。日常生活に支障をきたすほどの不調が続くときは、適応障害が疑われます。
適応障害を嘘だと感じる理由
周囲の人が、適応障害の状況を「嘘ではないか」と感じてしまう理由には、次の2つがあります。
- ムリして明るく振る舞えるから
- ストレスの原因である人や環境から離れたから
一つ目の理由は、本人が周囲に心配をかけまいと、ムリに明るく振る舞うためです。
責任感が強い人や他人に弱みを見せたくない人は、内心ではつらい気持ちを抱えながらも、表面上は元気なふりをすることがあります。

ムリして明るく振る舞っちゃうんですね
二つ目の理由は、原因となるストレス要因から離れると、一時的に元気なように見えるからです。
職場にストレス原因があると、休職して自宅で過ごしているときは比較的落ち着いて見えるでしょう。
下記の記事では、適応障害なのに元気に見える理由を詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
適応障害と嘘をついているか見抜くポイント
適応障害と嘘をついているか見抜くポイントは、次の3つがあります。
身近な人の様子がいつもと違うと感じて、心配になることがあるかもしれません。
あくまで、本人の状態を理解するための材料として考えましょう。
表情
適応障害が嘘か見抜くポイントには、まず表情があります。適応障害を抱えていると、表情に次のような変化があらわられます。
- 疲れている
- 無表情になる
十分な睡眠がとれていても目の下にクマがあったり顔色が悪かったりすると、常に疲れているような印象を受けるのです。
また、以前と比べて喜怒哀楽が顔に出なくなります。笑顔が減ったり口数が少なくなったりしていないか、相手を気にかけてみましょう。
表情に元気がない状態が続いているときは、こころに負担がかかっているサインと考えられます。
態度
態度は、適応障害と嘘をついているか見抜くポイントのひとつです。たとえば、次のような変化がみられます。
- 無気力になる
- 緊張している
- 涙もろくなる
以前は熱心に取り組んでいた仕事や趣味に対して、興味を示さなくなったり億劫になったりすることもあるでしょう。
また、常に緊張し落ち着かない態度にもなります。人と話すときに視線を合わせなくなったり声が小さくなったりする変化も、緊張を表す変化です。
さらに、涙もろくなることもあります。感情的になるような不安定さが見られると、こころが敏感な状態と考えられるでしょう。
態度の変化は、こころのエネルギーが消耗しているサインです。本人が助けを必要としているサインとして、受け止めてください。

ふとした態度にもあらわれます
言動
適応障害か嘘かを見抜くポイントには、言動があります。
具体的には、次のような変化がみられます。
- 決断が遅くなる
- 否定的な発言をする
- アルコールやインターネットに依存する
たとえば、食事のメニューや洋服などをなかなか決められなかったり、重要な決断を先延ばしにしたりするでしょう。
自信の喪失や意欲の低下が関係するため、判断に時間がかかるのです。
ほかにも、「どうせうまくいかない」「自分には価値がない」といった否定的な言葉が増えます。なぜなら、物事の悪い側面ばかりに目が向きやすくなっているからです。
アルコールやインターネットなどに依存するケースもあります。これは、つらい現実から逃避しようとする行動の表れでしょう。
言動の変化に気づいたら、本人の不調を示しているサインとして捉えてください。サインを発見したら、適切なサポートへの協力をしましょう。
適応障害の診断書は簡単に書いてもらえるのか
適応障害の診断書は、誰でも簡単に手に入れられる書類ではありません。
医師の診察を通して、その人が適応障害の状態にあると医学的に判断したときに発行されるからです。
医師は患者さんの訴えを聞くだけでなく、症状のあらわれ方や期間、日常生活への支障の度合いなどを総合的に評価し診断基準に基づいて慎重に診断します。
適応障害と診断された後に患者さんが診断書の発行を求めれば、医師は正当な理由がない限り拒否できません。これは、医師法により医師の義務とされています。[3]
下記の記事では、適応障害は誰でも診断されるのかを詳しく解説しています。気になる人はあわせてご覧ください。
適応障害の人への接し方
適応障害の人への接し方には、次の3つがあります。
適応障害は本人の甘えや性格の問題ではなく、ストレスに対するこころの反応だと理解することが大切です。それぞれについて詳しく解説します。
休養を勧める
適応障害と診断された人には、休養を勧めましょう。[2]
まずはストレスの原因から距離を置き、こころを休ませることが回復への第一歩となります。仕事が原因であれば休職を、学校生活が原因であれば一時的な休学を検討するなどの休養が必要です。
本人が罪悪感を得ずに休養に専念できるよう「今はしっかり休むことが大切だよ」と伝え、安心できる雰囲気をつくりましょう。
ただし、こころの休養は必要ですが身体まで休ませるのは避けましょう。運動不足から心身の不調を招くこともあります。軽い散歩やヨガなど、できる範囲で身体を動かすことを勧めてください。
本人のペースを尊重しながら、心身のバランスが取れる休養を勧めましょう。
話に共感しながら聞く
適応障害の人に接するときは、話に共感しながら聞きましょう。
適応障害を抱えている人は、つらい気持ちや悩みを誰かに聞いてもらいたいと感じています。周囲の人が話をじっくりと聞き気持ちに寄り添う姿勢を示すことは、本人にとって大きな支えとなるのです。
話を聞くときは「つらいね」「大変だったね」のように、本人の感情に焦点を当てて言葉をかけましょう。本人が安心して気持ちを話せるような聞き役に徹することがポイントです。
話に共感しながら聞くことは、孤立感をやわらげエネルギーをためる手助けとなるのです。

周りの人が疲れすぎないようにしてくださいね
本人を責めないようにする
適応障害の人と話をするときは、本人を責めないようにしてください。[2]
適応障害は、気持ちや甘えが原因で起こるものではありません。ストレスに対するこころの反応であり、誰にでも起こりうる病気です。
周囲の人が「気持ちの問題だ」「もっと頑張れば大丈夫」といった言葉で責めるようなことは控えましょう。相手を深く傷つけ、回復を遅らせる原因になりえます。
焦らずに本人のペースに合わせて回復を待つ気持ちで接することが、早期の回復にもつながるでしょう。病気の状態にあると理解し批判的な態度を取らないことが、何よりのサポートとなります。
まとめ
適応障害の人が一時的に元気に見えたり、ムリに明るく振る舞ったりする様子で「適応障害なんて嘘だ」と決めつけるのは避けましょう。
嘘か本当かを見極めることよりも、本人が抱えるつらさに寄り添い適切なサポートを考えることが大切です。
適応障害は決して本人の甘えや性格の問題ではなく、ストレスに対するこころの反応であり、誰にでも起こりうる状態です。
もし、身近な人が適応障害かもしれないと感じたり、どう接すればよいか悩んだりするときはひとりで抱え込まずに病院へ相談しましょう。
おおかみこころのクリニックでは、適応障害に関するご相談や治療をしています。
身近な人がつらい気持ちで悩んでいるときは、お気軽にご相談ください。
早期に適切なサポートを受けることが、回復への大切な一歩につながります。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]適応障害:用語解説|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-1653
[2]新版 適応障害のことがよくわかる本,貝谷久宣,講談社
https://amzn.asia/d/i8sCJwt
[3]医師法|e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201