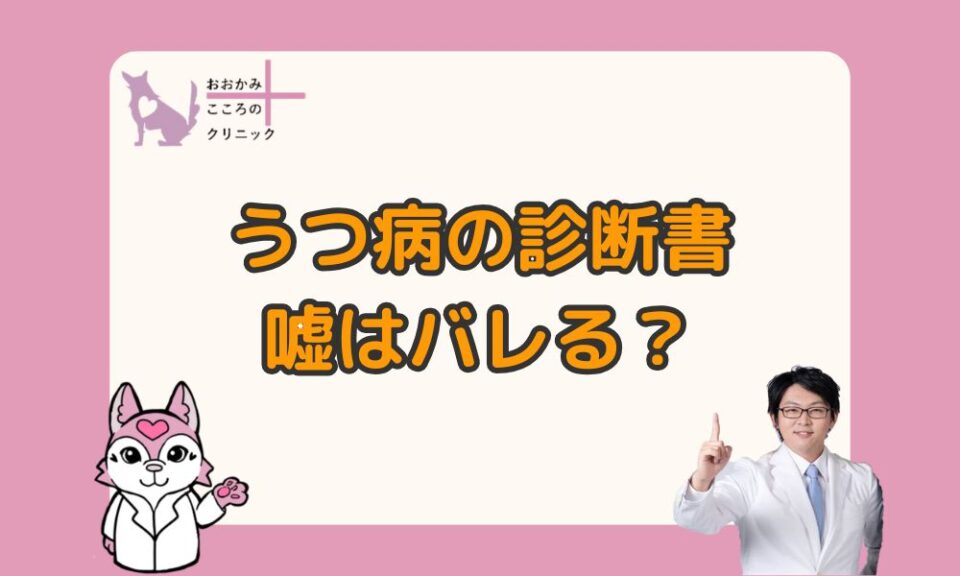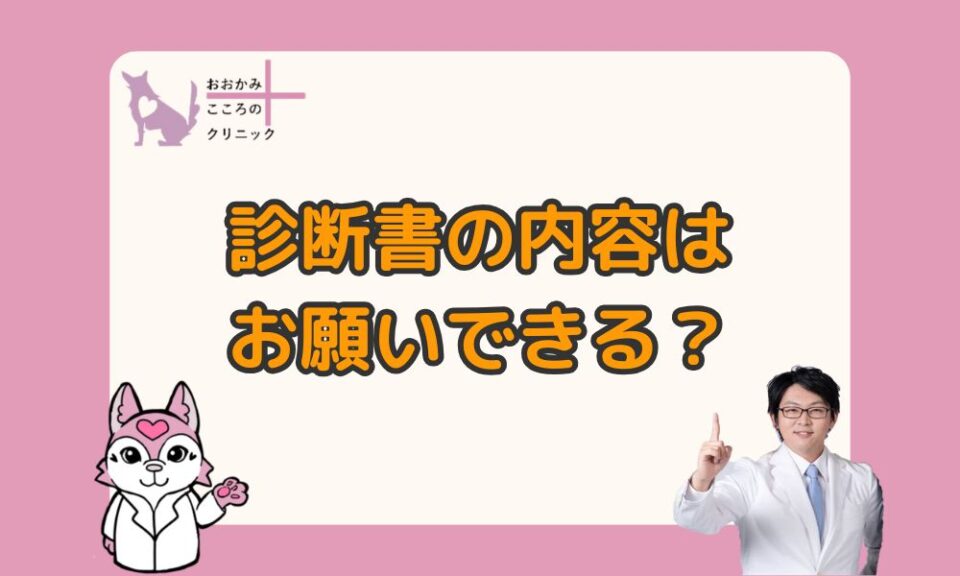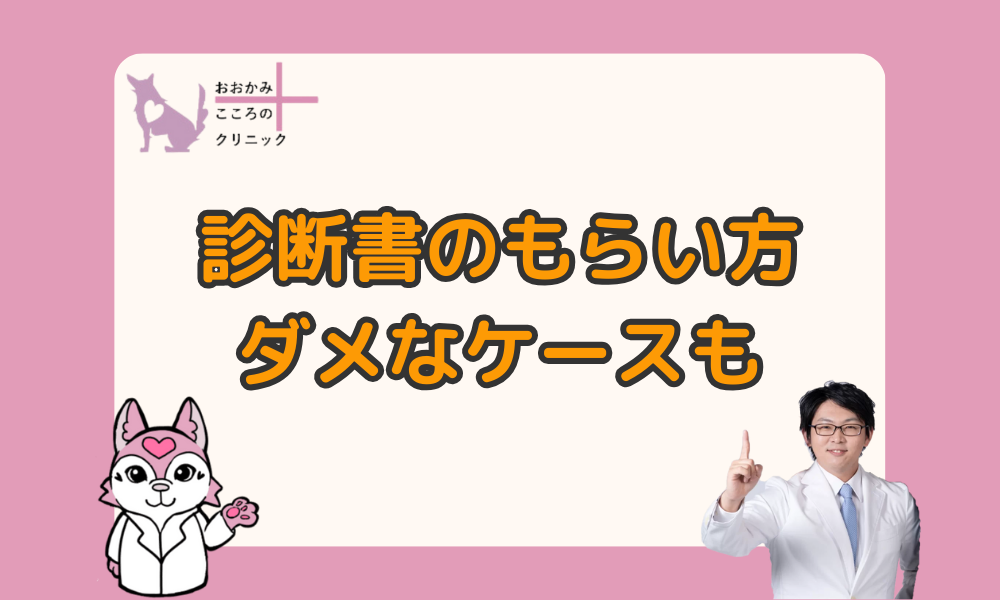仕事や人間関係によるストレスを抱えていると、「うつ病と嘘をついて休職したい」と考える方も少なくありません。
ただ、嘘の申告で診断書をもらおうとする行為は、懲戒解雇や詐欺罪などのリスクを伴う可能性があるのです。
まずは、嘘をついて診断書をもらうのではなく、なぜ「休みたい」と思うほど追い詰められているのかを考えましょう。
適切に対処することが、心身を休ませるための正しい道筋となります。
この記事では、うつ病と嘘をつくことで考えられるリスクや受診の際に正確に伝えるべきポイントを解説します。
その場しのぎの方法を探す前に、あなたのこころと向き合うきっかけになれば幸いです。
この記事の内容
うつ病と嘘をついても診断書はもらえない
うつ病の診断書は、医学的な根拠に基づいて作成されます。
仕事や人間関係のストレスから「休みたい」という気持ちで、嘘の申告を考えてしまうかもしれません。
しかし、医師は患者さんの様子を総合的に判断して診断するため、その嘘は見抜かれてしまうのです。
うつ病の診断で用いられる診断基準「DSM-5」では、「抑うつ気分や興味または喜びの喪失を含む9つの症状のうち5つ以上がほぼ毎日続く」といった明確な定義があります。[1]
そのため「気分が落ち込む」と訴えるだけでは、診断基準を満たすとは判断されないのです。
意図的に嘘をついた申告は治療の妨げにもなります。
本当に心身の不調で悩んでいたら、正直に医師へ相談するのが回復への第一歩です。

素直に今の症状を話すのがよいでしょう
嘘はいけませんが、診断書の内容はお願いできることもあります。詳しくは下記の記事をご覧ください。
うつ病と嘘をついても医師が見抜くポイント
うつ病と嘘をついても、医師は次の3つのポイントから見抜きます。
うつ病の診断は、専門的な知識と経験を持つ医師が慎重に行います。それぞれのポイントを見ていきましょう。
表情
うつ病の診断において、表情は判断材料のひとつです。
本当にうつ病を発症したときは、なにをしても楽しめない状態になることがあります。
そのため、表情が乏しくなったり感情の起伏が少なくなったりする傾向がみられるのです。[2]
一方で、うつ病のふりをしていると表情に不自然さが生じます。
たとえば、悲しい話をしながらも、表情は悲しそうではないかもしれません。また、うつ病らしく見せようと感情を抑えすぎるあまり、不自然な印象を与える可能性もあります。
医師は多くの患者と接する中で、本物の症状と演技の違いを経験的に理解しています。そのため、患者さんの細かな表情の変化から、話の信頼性を判断するのです。
声のトーン
声のトーンは、医師が診断時に観察するポイントです。
うつ病になると物事への興味が薄れ、気力も低下する傾向があります。
そのため、声を出すことも億劫に感じられ、聞き取りにくいほど小さな声になるケースもみられるのです。
嘘をついてうつ病を装っているときは、声の状態に一貫性がみられない傾向があります。
たとえば、抑うつ気分を訴えているにもかかわらず、特定の話題になると緊張から声のトーンが高くなったり、急に声が大きくなったりするかもしれません。
話の内容と声の状態との間に矛盾があると、医師は内容の信憑性に疑問を抱くでしょう。

医師は経験豊富なので気づくでしょう
曖昧な説明
診察の際に曖昧な説明をすると、嘘であると医師に見抜かれる可能性があります。
うつ病の症状は、気分の落ち込みや食欲の変化、意欲の消失など日常生活に支障をきたすものです。[2]本当に症状で苦しんでいるときは、つらい体験として具体的なエピソードを交えて説明できるのです。
しかし、表面的な知識だけでうつ病を装うと、説明が曖昧になりがちです。
たとえば、「なんとなく気分が落ち込んでいる」といった抽象的な訴えにとどまります。
医師に「具体的にどのようなときに感じますか」と質問されると、話のつじつまが合わなくなるのです。
症状の経過や状況についての質問に矛盾なく答えるのは難しいため、結果的に嘘がばれてしまうのです。
下記の記事ではうつ病だと自分で言う人の特徴を詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
うつ病と嘘をつくことで考えられるリスク
うつ病と嘘をついたときに考えられるリスクには、次の3つがあります。
軽い気持ちでついた嘘が、人生を左右する事態につながるリスクを理解しておきましょう。
懲戒解雇になる
うつ病と偽って医師から診断書をもらうことはできません。しかし、万が一不正な診断書を入手し、それを使って会社を休んでしまうと、懲戒解雇になる可能性があります。
会社は従業員との信頼関係に基づいて雇用契約を結んでいます。
嘘の申告によって会社との信頼関係を損なう行為は、雇用契約の根本を揺るがすものです。
就業規則には、従業員が守るべき規律や禁止事項が定められています。
嘘だと発覚したとき、厳重注意や減給といった軽い処分にとどまらず、懲戒解雇になる可能性があるのです。
懲戒解雇は、その後の再就職活動においても経歴に傷をつけることになるでしょう。
詐欺罪で罰せられる
嘘の申告で取得した診断書を利用して金銭的な利益を得ると、詐欺罪にあたる可能性があります。[3]
たとえば、健康保険から支給される「傷病手当金」を不正に受け取るケースがあります。
傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の生活を支えるための制度です。
嘘の診断書で休職し手当金を申請して受け取ったとき、保険者をだましたとして詐欺罪が成立する可能性があります。
また、障害年金を不正に受給したケースも同様です。詐欺罪が成立すると、10年以下の懲役が科せられます。
軽い気持ちの嘘が、犯罪行為につながる危険性を認識しなくてはなりません。
会社からの信頼を失う
うつ病と嘘をつくことで、会社からの信頼を失ってしまうでしょう。
うつ病と偽っていた事実が社内に知れ渡れば、上司や同僚は「裏切られた」と感じます。
その結果、職場での人間関係は悪化し、居心地の悪さを感じながら働かなければならなくなるのです。
重要な仕事を任せてもらえなくなったり、コミュニケーションを避けられたりと、職場で孤立状態になるかもしれません。
周囲からの視線に耐えられず、最終的に自主退職へ追い込まれるケースも考えられます。
職場での信頼は、誠実な勤務態度によって築かれるものです。たった1度の嘘が、これまで積み上げてきたキャリアや人間関係を台無しにする可能性があります。

復帰しにくくなっちゃいます💦
こころが追い詰められたときのサイン
「うつ病のふりをして休職したい」と考える背景には、心身の疲れが隠れています。
あなた自身は「まだ大丈夫」と思っていても、こころが限界に近いサインを発しているかもしれません。
うつ病のサインは精神的・身体的なものがあり、具体的には次のような症状があらわれます。[2][4]
- 精神的なサイン
- ・涙もろくなる
・表情が暗くなる
・憂うつな気分になる
・自分を責めがちになる
・人に会いたくなくなる
・行動が落ち着かなくなる
- 身体的なサイン
- ・眠れない
・疲れやすい
・食欲がない
・性欲がない
・身体がだるい
・寝過ぎてしまう
・頭痛や肩こりがある
・動悸やめまいがする
うつ病のサインに気づいたらひとりで抱え込まず、心療内科や精神科への相談を検討してください。
受診時に正確に伝えるべきポイント
心身の不調を感じて病院を受診する際は、あなたの状態を正確に伝える準備が大切です。次のポイントを整理しておくと診察がスムーズに進み、より適切な治療につながります。
- いつから症状があるか
- 日常生活に支障がでているか
- 過去にかかった病気はあるか
- 現在服用している薬はあるか
まず、いつから症状があるかを具体的に伝えましょう。
「1か月前から」と具体的な時期を伝えることで、医師が今後の治療方針を立てる手がかりになります。
次に、日常生活にどのような支障が出ているかを整理しましょう。
「仕事に集中できない」「好きな趣味を楽しめない」などのエピソードがあると、症状の程度を把握する助けになります。
また、過去にかかった病気や服用している薬があれば必ず伝えてください。
とくに、他の病院で処方されている薬があるときは、飲み合わせによっては副作用が出る可能性があるからです。
これらの情報を事前にまとめておけば、診察時に慌てずに漏れがなく伝えられます。
ただしあなたの状態を正しく伝えてもうつ病と診断されず、診断書をもらえないことがあります。
下記の記事ではもらえなかったときの注意点を解説しているので、あわせてご覧ください。
まとめ
うつ病の診断書は、医学的な根拠に基づいて作成されるものです。医師は患者の言葉だけでなく表情や声のトーンなどから総合的に診断するため、嘘の申告は治療の妨げになります。
もし嘘の申告で診断書を取得し手当金を受給すると、懲戒解雇や詐欺罪といった結果を招く可能性があります。
「うつ病と嘘をついてでも休みたい」と感じるほど追い詰められていたら、こころが発している危険なサインです。あなたの状態を見つめ直し、こころや身体にあらわれる不調のサインに気づきましょう。
つらいときはひとりで抱え込まず、病院を受診しましょう。ありのままの症状を正直に伝えるのが、体調を改善させる第一歩となります。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]うつ病の新しい考え方,大野 裕
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jhep/45/2/45_359/_pdf
[2]うつ病|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=9D2BdBaF8nGgVLbL
[3]刑法|e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045
[4]2.うつ病を知る|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/01/s0126-5b2.html
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック