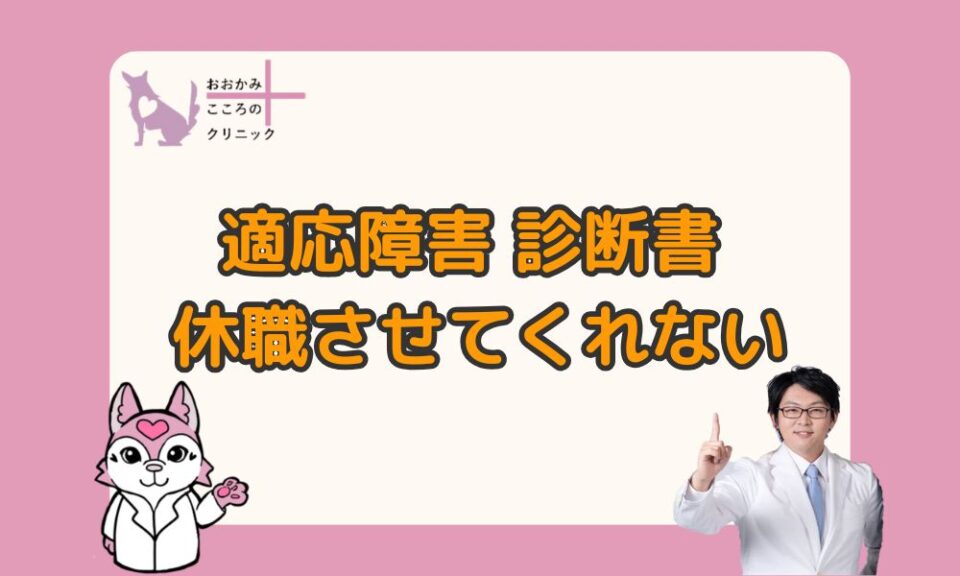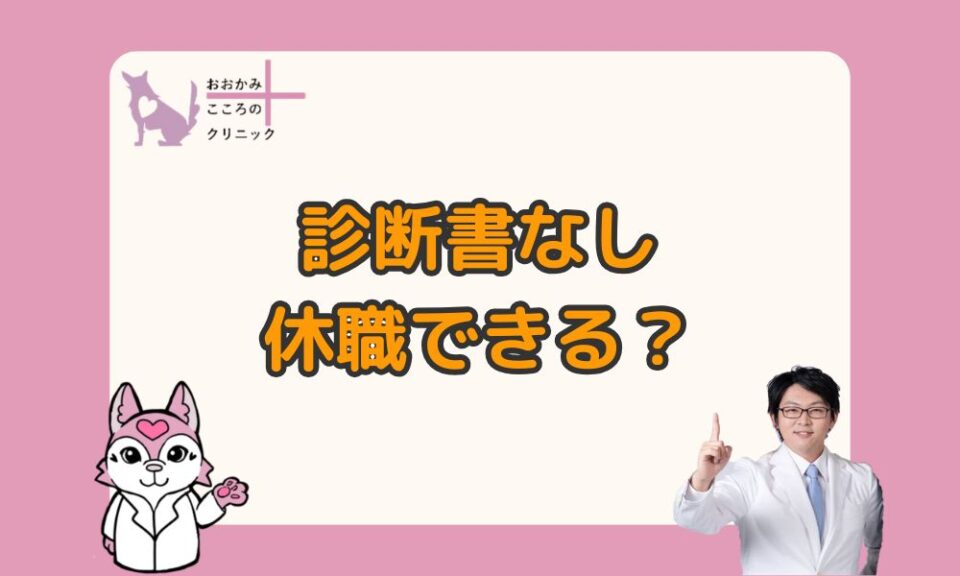「医師に診断書を書いてもらったのに会社が休職を認めてくれない」
「このまま働き続けると適応障害の症状が悪化しそうで不安だ」
適応障害による休職は決して「逃げ」ではなく、こころの回復にとって大切な第一歩です。
ただし、会社の制度や法的な基準によっては、休職を認めてもらえないこともあります。
この記事では、適応障害で診断書を出しても休職させてくれないときにやるべきことや円満に休職するための伝え方を紹介します。
ひとりで悩みを抱え込まず、適切なサポートを受けて回復への一歩を踏み出せる助けになれば幸いです。
適応障害で診断書を出しても休職させてくれないときにやるべきこと
適応障害で診断書を提出しても、会社が休職を認めないときがあります。
休職させてもらえないと症状が悪化するだけでなく、孤立や不安が強くなり仕事への自信が持てなくなるでしょう。
ムリに働き続けると回復がさらに遠のく可能性があるため、以下のような早めの対応が大切です。
まずは専門家への相談や労働基準監督署への申告、産業医との連携を検討しましょう。ひとりで悩まず、適切なサポートを受けることが回復への第一歩です。
弁護士に相談する
適応障害で診断書を提出しても休職を拒否されるときは、労働問題に詳しい弁護士への相談を検討しましょう。
上司に休職を伝えた後に、パワハラや退職の強要など不当な扱いをされたときは早めの対応が必要です。
弁護士に相談するときのおもな流れは、以下のとおりです。
- あなたの状況や会社とのやり取りの詳細を伝える
- 弁護士が労働契約や就業規則、診断書の内容を確認する
- 会社の対応が不当だと判断されれば、弁護士が交渉や書面でのやり取りを代行する
- 休職の正当性を主張し、必要に応じて法的手続きを検討する
日本弁護士連合会の法律相談センターでは、地域ごとに弁護士による相談を受け付けています。
弁護士には得意分野があるため、労働問題に強い弁護士を探す際は弁護士会の法律相談センターやひまわりお悩み110番などの全国共通相談窓口を活用しましょう。
弁護士はあなたの代理人として対応することで、精神的な負担がやわらぎ休養に専念できます。
また、復職の際に会社との関係が気まずくなり働きにくくなっても、弁護士が改善に向けてサポートを行います。
ひとりで悩まず、専門家のサポートを積極的に利用することが大切です。
産業医に相談する
適応障害で休職を希望する際は、産業医への相談が大切です。
産業医は職場と医療の橋渡し役として、従業員の健康管理をサポートする専門医です。
ムリなく休職や復職を進めるために労働者の健康状態を確認し、必要に応じて職場の勤務体制や業務内容の調整を提案します。[1]
なお、従業員数が50人未満では産業医がいない会社もあります。そのため、人事担当者や管理監督者、衛生推進者などが主治医と連携しながら対応するのが一般的です。
ひとりで抱え込まず、産業医や関係機関のサポートを受けて、ムリのない働き方を目指しましょう。

あいだに専門家が入るとスムーズに話が進むこともあるでしょう
有給休暇を利用する
適応障害で体調が優れないときは、有給休暇を申請して心身の回復させることも選択肢のひとつです。
有給休暇は労働者の権利であり、会社は有給休暇の取得を拒否できません。[2]
休職制度がない会社に勤めているときでも、有給休暇を活用して一定期間の休息を取ることが可能です。
ただし、申請のタイミングや手続きは就業規則に従う必要があるため、事前に確認しましょう。
また、有給休暇で休む間に主治医と連携し、今後の休職や治療方針について相談を進めることも大切です。ムリをせずに休むことが、回復への第一歩となります。
労働基準監督署に相談する
もし「診断書を出しても休職させてもらえない」「有給休暇が取れない」といった不当な扱いを受けたら、労働基準監督署への相談を検討しましょう。
労働基準監督署は、法律に基づいて会社に労働条件を守らせるための機関です。働く人の権利を守るために、企業への調査や改善指導を行います。[3]
労働基準監督署に相談する際の流れは、以下のとおりです。
- 最寄りの労働基準監督署に電話や窓口で相談の予約をする
- 状況や証拠(診断書、就業規則、会社とのやり取りの記録など)を持参し説明する
- 労働基準監督署が必要に応じて企業への指導や調査を行う
- 結果や今後の対応について案内を受ける
労働基準監督署に相談する際は、お住まいの地域の管轄へ問い合わせましょう。
相談は無料で、匿名での相談ができるケースもあります。所在地や連絡先は、厚生労働省の公式サイト「全国労働基準監督署の所在案内」から確認できます。
転職や退職を視野に入れる
診断書があっても休職させてくれないときは、転職や退職を含めて働き方を見直すことも選択肢のひとつです。
近年はフリーランスや在宅勤務、フレックスタイム制など、多様な働き方が広がっています。
精神的負担が少ない職場やあなたのペースで働ける環境を選ぶことが、長期的な回復や再発予防につながることもあります。
一方で、退職の前には傷病手当金や雇用保険の受給条件を確認し、生活面でのリスクを最小限に抑えることが大切です。
ムリに会社を辞めると経済的や社会的なデメリットが生じる可能性もあるため、転職エージェントや公的支援サービスを活用し、計画的に進めましょう。
以下の記事では、適応障害に向いている仕事を解説しているので参考にしてください。
また、傷病手当金や休業給付などの制度については、以下をご覧ください。
【例文あり】円満に休職するための伝え方
休職は決して「逃げ」ではなく、心身を回復させるための大切な選択です。
ただし、職場によっては上司や人事に切り出しづらいときもあるのではないでしょうか。
円満に休職するには、感情的にならず診断書とともに状況を端的に説明します。
伝え方のポイントは、以下のとおりです。
- 感情的にならず事実を伝える
- 診断書を添えて医師に相談していることを伝える
- 業務の引き継ぎや今後の連絡方法について触れる
ポイントを意識し、下記の例文のように伝えてみてください。
「主治医から適応障害と診断され、しばらくの間心身の休養が必要だという診断書をいただきました。
つきましては、業務に支障が出る前に一度休職させていただくことは可能でしょうか。引き継ぎは〇日までには責任を持って完了いたします。
復帰時期については医師と相談した上で、改めてご連絡させていただきます。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです。」
冷静かつ誠実に伝えることで、職場の理解を得やすくなります。
診断書があっても休職できないのは違法になるか
適応障害の診断書が出ているにもかかわらず会社が休職させてくれないとき、違法と判断される可能性があります。
労働契約法第5条では、会社が従業員の安全を確保しつつ働けるように、必要な配慮をするべきだと定められています。[4]
つまり、従業員が心身ともに健康な状態で仕事ができるよう、職場環境をととのえたり負担を軽減したりするのは会社の務めです。
医師が発行した診断書は「これ以上働き続けると心身の安全が損なわれる」と判断したものです。
診断書を無視して労働を強制することは、会社が安全配慮義務を果たしていないとみなされます。
そのため「適応障害の診断書があるのに休職させてくれない」という状況は、法律違反に該当する可能性があるのです。
会社が休職を拒否できるケース
会社が休職を拒否できるケースは、以下のとおりです。
- 診断書がない
- 会社の就業規則に休職に関する条項がない
多くの会社では診断書の提出を休職申請の条件としているため、診断書がないと休職を認めてもらえないケースもあります。
また、常時10人以上の事業所に対しては、厚生労働省より休職制度の明示が義務付けられています。[5]
ただし、小規模な会社では休職制度が定められておらず、会社が休職を拒否できる可能性があります。
休職を希望するときは、会社の休職制度の有無や内容を確認しましょう。
就業規則に休職開始の条件や期間、理由などの規定がないときは、会社によって対応が異なる可能性があるため注意が必要です。
診断書の取り扱いについて不安があるときは、以下の記事も参考にしてください。
まとめ
適応障害で悩む人は決してひとりではありません。
診断書を提出しても休職できない状況は深刻で、症状の悪化を招く恐れもあります。
ひとりで悩まず、産業医や労働基準監督署に相談することも選択肢のひとつです。
おおかみこころのクリニックでは、夜22時まで診察を受けられ、オンライン診療にも対応しています。
適切なサポートを受けられる環境をととのえ、安心して治療に専念できるよう、まずは専門医への相談を検討してください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]産業医について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf
[2]しっかりマスター労働基準法(有給休暇編)|厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf
[3]労働基準監督署の役割|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/131227-1.pdf
[4]労働契約法のあらまし|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001234797.pdf
[5]モデル就業規則について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html