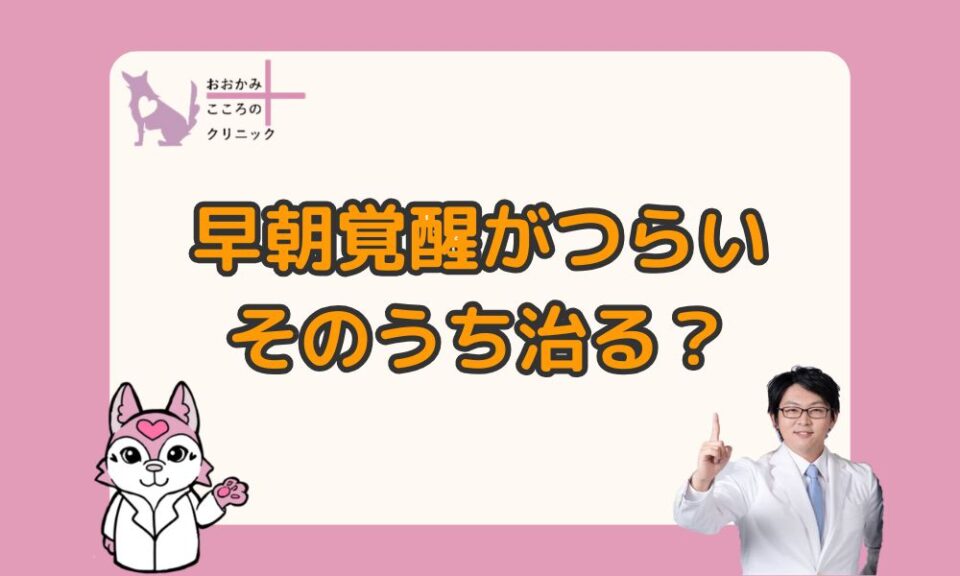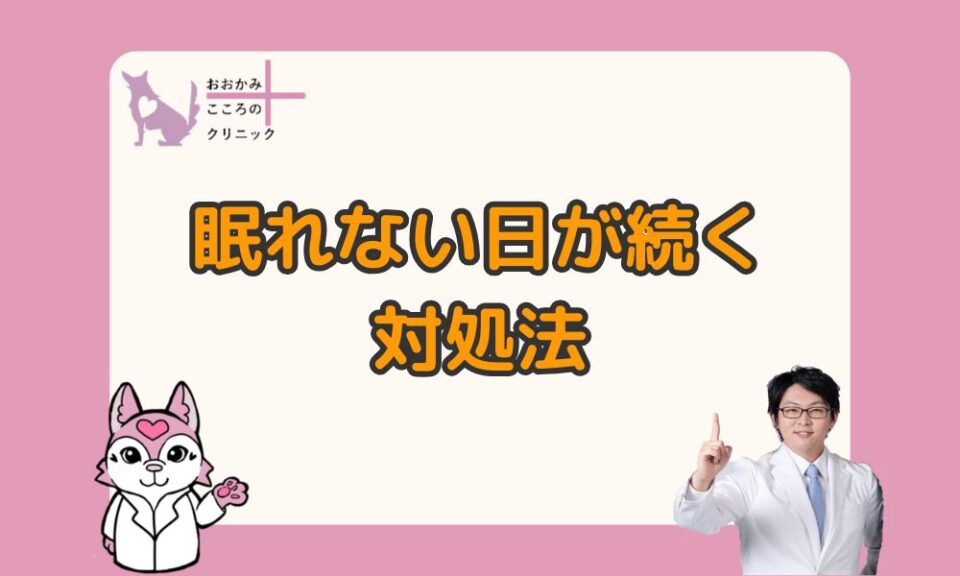「毎日朝4時に目が覚める」
「今日も寝不足で仕事がつらい」
予定より何時間も早く目覚めてしまう早朝覚醒。
日中の眠気や集中力の低下に悩まされながらも「そのうち治るだろう」と放置していませんか。
早朝覚醒は単なる睡眠不足とはちがい、心身の不調を示すサインかもしれません。
早朝覚醒はうつ病でよく見られる症状のひとつで、放置すると悪化したり長期化したりするリスクがあります。
この記事では、早朝覚醒を放置するリスクと適切な対処法をご紹介します。
つらい症状を我慢せず、一日も早く質の高い睡眠を取り戻しましょう。
早朝覚醒がつらい「そのうち治る」と放置するリスク
早朝覚醒はそのうち治ると放置すると、以下のようなリスクが伴います。
不眠が週3日以上、3か月以上続くときは治療が必要な不眠症の可能性があるので放置しないようにしましょう。[1]
身体的な不調が出る
早朝覚醒によって出てくる身体的な不調は以下のとおりです。
- 倦怠感
- 疲労感
- 免疫力の低下
「休んでも疲れが取れない」「常に身体が重い」といった状態が続き、日常生活の質が低下します。
睡眠不足が続くと免疫機能が十分に働かず、風邪をひきやすくなったり体調を崩しやすくなったりするでしょう。[2]
また、睡眠不足が高血圧や糖尿病、心疾患などの生活習慣病のリスクを高めることも明らかになっています。[3]
「そのうち治る」と放置しているあいだに、身体の不調が広がってしまうため早めに心療内科や不眠の治療ができる病院を受診してください。
おおかみこころのクリニックはオンライン診療も行ています。体調がわるく外出が難しいときでも安心して受診できます。まずは、お気軽にお問い合わせください。
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
こころの不調が長期化する
早朝覚醒は、うつ病をはじめとする精神疾患の初期症状のひとつです。
初期の段階で適切な対処をせずに放置すると、こころの不調が深刻化・長期化してしまう可能性があります。
うつ病では早朝覚醒が病気のサインとして早期に起こることが多く、早めに治療を始めれば比較的短期間で症状が落ち着きます。
ただし「そのうち治る」と放置すると抑うつ気分や意欲の低下といった他の症状も徐々にあらわれ病状が進行してしまうため注意してください。
また、眠れない日が続くと「また今日も早く目が覚めるのではないか」という不安や焦りが生まれます。
不安や焦りがさらに脳を覚醒させ「眠れない→不安になる→さらに眠れなくなる」という悪循環でこころと身体が疲れてしまいます。
おおかみこころのクリニックでは、うつ病に対する治療として近年注目されているrTMS療法も対応しています。
rTMS療法は薬物療法で効果が出にくい方や、薬の服用に抵抗がある方に検討されます。rTMS療法について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
仕事や日常生活に支障が出る
早朝覚醒による睡眠不足は、以下のように仕事や日常生活に支障をきたします。
- 生産性の低下:集中力や思考力が低下するため、重要な会議での判断ミスや資料作成での誤字脱字などのケアレスミスが起こり仕事の生産性が低下する可能性があります。
- 危険性の増加:自動車の運転や危険物を取り扱う作業時に、居眠りや注意散漫による事故のリスクが高まりやすくなります。
- 人間関係の悪化:イライラしたり無気力になったりして、同僚や取引先とのコミュニケーションがうまく取れずに人間関係のトラブルにつながる可能性があります。
このように早朝覚醒を放置すると、仕事で人間関係が悪くなったり、生活の質を低下させたりするリスクがあるので放置しないようにしましょう。

つらい状態でひとりで悩まずに、早めに相談してくださいね!
早朝覚醒する原因
早朝覚醒の原因は、ひとつとは限りません。
以下の原因のうち、複数の要因が絡み合って生じていることもあります。
それぞれ解説します。
こころの不調
早朝覚醒の注意すべき原因のひとつが、こころの不調です。
うつ病では睡眠障害を伴いやすく、中でも早朝覚醒は特徴的な症状のひとつです。[4]
たとえば、朝方に目が覚めた後、不安や焦燥感が強くなり「今日も仕事に行きたくない」「何もかもうまくいかない」といったネガティブな思考になるでしょう。
うつ病以外にも不安障害やパニック障害、適応障害などでも早朝覚醒が起こることがあります。
「うつ病かも…」と思ったら以下の記事で初期症状を詳しく解説しています。あわせご覧下さい。
睡眠環境や生活習慣
以下のような生活習慣や寝室の環境が、睡眠の質を悪くするケースもあります。
- 不規則な生活リズムで生活する
- 睡眠に不向きな室内環境で寝る
- 寝る前にお酒やカフェインを摂る
休日の寝だめや夜勤などの不規則な生活リズムも、早朝覚醒が起こる原因になります。
早朝の光や騒音、寝室の温度が不快で目が覚めてしまうことがあるため、睡眠環境をととのえることも必要です。
また、寝る前のアルコールやカフェイン摂取は睡眠の質が低下するため避けましょう。
寝酒は一時的に寝つきをよくしますが、深い眠りが減り早朝覚醒が増加します。[5]
夕方以降のカフェイン摂取も同じように覚醒作用を持つので避けてください。
加齢や身体的な病気
加齢による変化やその他の病気が原因で早朝覚醒が起こることもあります。
- 加齢
- 更年期障害
- 睡眠時無呼吸症候群
年齢を重ねると必要な睡眠時間が短くなり、自然と早寝早起きになります。[6]
加齢に伴う夜間頻尿や関節の痛みなども睡眠中に覚醒する原因となるでしょう。
また、更年期に起こる自律神経の乱れやホットフラッシュ(夜間のほてりや発汗)が早朝覚醒の原因かもしれません。[7]
いびきをかいていたり、睡眠中に呼吸が止まっていたりするときは睡眠時無呼吸症候群が早朝覚醒の原因として考えられます。[5]
早朝覚醒したときの注意点
早朝覚醒したときは以下のことに注意をして、眠気を感じたら再度眠るようにしましょう。
- 明るい光を浴びない
- スマートフォンを見ない
- 「早く眠らないと」と焦らない
電気をつけたりスマートフォンを見たりせず、リラックスして穏やかにすごすことが大切です。
「早く眠ろう」と焦るとそのストレスから余計に目が覚めてしまうため「そのうち眠くなるだろう」と目を閉じてこころ穏やかに過ごしてみましょう。
もし、眠れないときは次で紹介する眠れないときの過ごし方を参考にしてください。
早朝覚醒して眠れないときの過ごし方
早朝覚醒してしまった後、15〜20分経っても再度眠れないときは思い切って寝床から出て次のように過ごしましょう。[3]
- 温かい飲み物を飲む
- 深呼吸や軽いストレッチをする
- ヒーリング音楽や環境音を聴く
ノンカフェインのハーブティーやホットミルクを飲んだり、深呼吸や軽いストレッチで身体をほぐしたりしてください。
小さな音量でゆったりとした音楽や森のせせらぎ、小鳥のさえずりなどの環境音を聴くのもリラックス効果があります。
リラックスした状態で自然な眠気が戻ってきたら、すぐに寝床へ戻りましょう。
早朝覚醒がつらいときの治し方
早朝覚醒がつらいと感じたら、放置せずに以下の治し方を試してください。
まずはセルフケアを試し、治らないときは専門の治療を受けましょう。
セルフケアの方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
生活習慣を見直す
早朝覚醒がつらいときは、以下のような点を意識して生活しましょう。
- 規則正しい食事
- 適度な運動習慣
- 就寝前のリラックスタイム
食事は規則正しく3回食べるように心がけてください。
朝食を食べないと体内時計が遅れて寝つきが悪くなり、睡眠不足を生じやすくなります。[3]
寝る前の夜食は消化活動のために内臓が働き、眠りが浅くなる原因となるので避けましょう。
また、ウォーキングや軽いストレッチなどの有酸素運動を日中または夕方にすることで、適度な疲れを感じ質の高い睡眠が得られやすくなります。
入浴は就寝1~2時間前に40度前後のお湯にゆっくり浸かると効果的です。[8]
就寝前には深呼吸を繰り返し、リラックスできる状態で眠りにつきましょう。
睡眠環境をととのえる
寝室の睡眠環境をととのえて早朝覚醒を予防しましょう。
- 寝室の遮光:早朝の光が入らないよう遮光カーテンを利用し、寝室を暗く保ちます。
- 温度の管理:暑すぎず寒すぎない快適な状態(20℃前後が目安)を維持します。[5]
- 寝具の見直し: 身体に合った枕やマットレスを使用し、不快感なく寝返りが打てるようにしましょう。
睡眠を妨げている原因がないか、あなたの寝室環境を一度見直してみてください。
専門の医療機関を受診する
セルフケアを2〜3週間続けても、早朝覚醒が治らないときや日中の不調(気分の落ち込み、強い倦怠感など)を感じるときは専門医を受診しましょう。
受診する医療機関はあなたの症状に合わせて選択してください。
- 心療内科・精神科:不安や焦燥感、気分の落ち込みや強いストレスを感じているとき
- 睡眠外来・耳鼻科:いびきがうるさい、睡眠中に呼吸が止まっている、日中に強い眠気を感じるとき
- 婦人科:更年期の年齢(45〜55歳前後)、生理不順や無月経がある、ほてりやのぼせがあるとき
受診先を迷ったら、まずかかりつけ医に相談してみてください。
ひとりで悩まず、早めに対応するようにしましょう。
まとめ
早朝覚醒を「そのうち治る」と放置すると、仕事や日常生活に支障をきたし症状を長期化するかもしれません。
まずは、生活習慣や睡眠環境の見直しなどのセルフケアから始めてみましょう。
セルフケアで治らないときや気分の落ち込みや強い不安を伴っているときは専門的なサポートを受けてください。
とくにうつ病による早朝覚醒は、早期からの専門的な治療が大切です。
早朝覚醒のつらさを乗り越え、穏やかな日常を取り戻すためにまずは専門医に相談し、あなたの状態を正しく把握することから始めましょう。
おおかみこころのクリニックでは、自宅で診察を受けられるオンライン診療を実施しています。
眠れない日々から抜け出してすっきりとした朝を迎えるために、まずはお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【参考文献】
[1]不眠症(睡眠障害)|こころの情報サイト 厚生労働省
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=XpsDJBKfyaGD0mIx
[2]7時間睡眠の人が「ウイルスに強い」決定的証拠|東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/articles/-/383085
[3]健康づくりのための睡眠ガイド2023|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf
[4]患者のための最新医学 うつ病 改訂版 | 高橋書店
[5]不眠症 健康日本21|厚生労働省
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-02-001
[6]高齢者の睡眠障害|日本睡眠学会
https://jssr.jp/basicofsleepdisorders7
[7]更年期女性の不眠 ―その特性と対処法について|寺内 公一
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspog/22/3/22_210/_pdf/-char/ja
[8]快眠と生活環境 健康日本21|厚生労働省
https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-01-004
- この記事の執筆者
- すみこ
作業療法士歴13年の経験を活かし、医療記事を中心に活動するWebライター。 読者の皆様のこころと身体の健康をサポートし、前向きな気持ちになれる文章を心がけています。