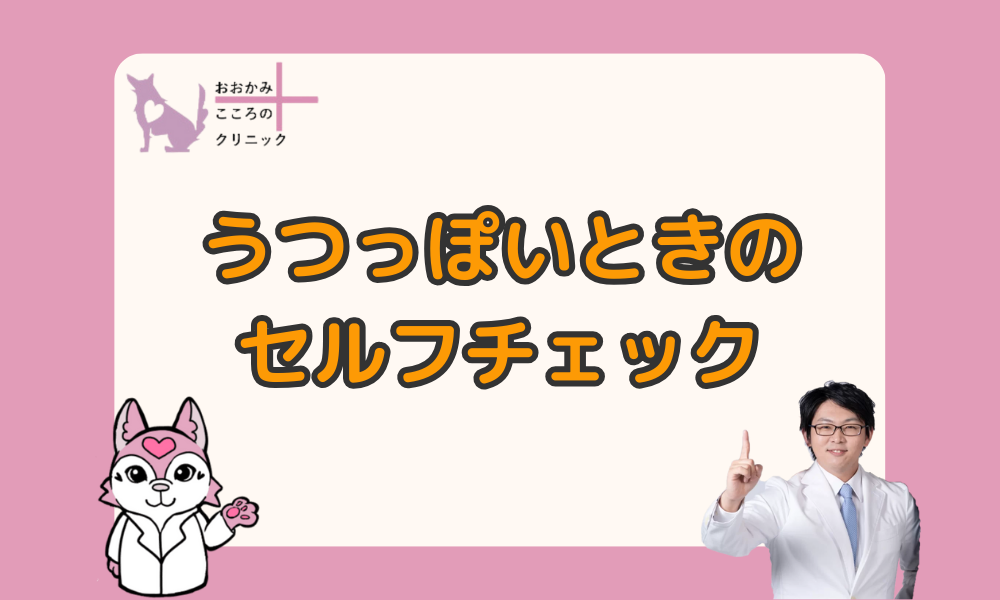気分の落ち込みや不安を感じる状態は、適応障害やうつ病のサインかもしれません。
ストレスで仕事や学校に行くのがつらくなったり、はっきりした理由がないのに何をしても楽しめなかったりすると「適応障害とうつ病のどちらにあてはまるのか」と疑問を感じるでしょう。
適応障害とうつ病の違いを理解することは、あなたの状態を客観的に把握し、どう対処すればよいかを考える参考になります。
また、違いを知ることで漠然とした不安がやわらぐ可能性もあるのです。
この記事では、適応障害とうつ病の違い、適応障害やうつ病による症状への対処法などを解説します。適応障害とうつ病の違いを知り、適切な対応を考えるために役立てていただければ幸いです。
適応障害とうつ病の違い
適応障害とうつ病の違いには、おもに次の3つがあります。
それぞれについて詳しく解説します。
自分が適応障害か気になるときは、下記の記事をご覧ください。
症状
適応障害とうつ病では、おもに次の症状があらわれます。
| 症状 | |
| 適応障害 | ・抑うつ気分 ・不安 ・緊張 ・焦り など |
| うつ病 | ・気分の落ち込み ・意欲の低下 ・食欲不振 ・疲れやすさ など |
適応障害の症状は、ストレスの原因となる状況に直面したときに強くあらわれる傾向があります。
一方で、うつ病の症状は1日を通して気分が沈んだり、以前は楽しめていた趣味や活動に興味や喜びを感じられなくなったりするのが特徴的です。
周囲からも見て「いつもと様子が違う」と気づかれやすいです。
適応障害とうつ病には、身体的な症状もあります。
どちらも食欲不振や過食、不眠や過眠、動悸などさまざまな不調があらわれます。人によっては、飲酒量が増えるといった行動の変化も見られるのです。
ただし、症状がどのように出るのかは個人差があるため、自己判断せず医師に相談しましょう。

「なんだか最近元気ないね?」と言われることが増えたら気をつけてください。
発症のきっかけ
適応障害とうつ病は、発症のきっかけに違いが見られます。
適応障害の発症には、明確なストレス要因があります。[1]
たとえば、職場での人間関係の悩みや転勤・異動による環境の変化などが、発症の引き金となるのです。特徴は、症状を引き起こす原因がはっきりと自覚できる点です。
一方、うつ病の発症のきっかけは、適応障害ほど明確ではありません。
たとえば、仕事や就職、結婚といった人生の転機がきっかけとなることもあります。[2]
適応障害は特定の要因がきっかけで発症するため、原因が自覚しやすいです。一方で、うつ病はさまざまな要因が関係し、必ずしもきっかけが明確ではないケースがあります。
回復までの期間
適応障害とうつ病では、回復までにかかる期間に違いがあります。
適応障害では、ストレスの原因がなくなると通常6か月以内に症状は回復するとされています。[1]たとえば、職場の人間関係が原因であれば、部署異動や転職によって環境が変わると回復に向かうこともあるのです。
一方、うつ病の回復には1~2年ほどかかります。うつ病の治療は、大きく分けて急性期・回復期・再発予防期の3つの段階で考えられます。
- 急性期(1か月~3か月):薬物療法や休養によって症状の緩和を目指す
- 回復期(4か月から6か月):症状が安定し、少しずつ活動量を増やす
- 再発予防期(1年以上):症状がなくなった後も、再発を防ぐために治療を継続する
3つの期間を合計すると、うつ病の回復には少なくとも1~2年程度かかるのです。[3]
適応障害は原因となるストレスがなくなれば約6か月での回復が期待できます。
一方で、うつ病には段階的な治療が必要で年単位の時間がかかります。ただし、回復期間はあくまで目安であるため、回復するまでには個人差があることを理解しておきましょう。

個人差はあります
うつ病と適応障害の共通点
適応障害とうつ病の共通点は、治療法が似ている点です。どちらの病気も、治療の柱となるのは休養・薬物療法・心理療法です。[1][2]
第一に、十分な休養をとりましょう。心身を休ませることで症状の悪化を防ぎ、やわらげることができます。とくに適応障害では、原因となるストレスから離れることも有効な手段です。
次に、薬物療法があります。気分の落ち込みや不安などの症状をやわらげるために、抗うつ薬や抗不安薬などが用いられます。
心理療法も大切な治療法です。カウンセリングを通して、ストレスへの対処法を学んだり、考え方の偏りを修正したりすることを目指します。心理療法のひとつである認知行動療法は症状をやわらげるだけでなく、再発予防の効果が期待されます。[4]
医師とよく相談しながら、あなたに合う治療方針を決めていくことが回復への近道です。
適応障害やうつ病による症状への対処法
適応障害やうつ病による症状への対処法には、次の3つがあります。
あなたに合う方法から少しずつ試してみましょう。
こころを休ませる
適応障害やうつ病の回復には、こころをしっかり休ませることが大切です。[1][5]
不安や気分の落ち込みなどの症状によりこころは疲れているため、意識的に休息の時間を作ることが回復への第一歩となります。
具体的な方法としては「何もしない時間」を作りましょう。ソファに座ってぼーっとしたり、窓の外を眺めたりするだけでもかまいません。頭の中を空っぽにするようなイメージで過ごしてください。
また、あなたが楽しめる趣味や活動に時間を使うことも、こころの休息につながります。音楽を聴いたり散歩をしたりするなど、気分が少しでもやわらぐようなことを見つけましょう。
焦らずゆっくりと、あなたのペースでこころを休ませることを最優先に考えてください。

あなたのこころがホッとする時間を作りましょう
生活リズムをととのえる
生活リズムをととのえることは、症状をやわらげるための対処法のひとつです。[1]
乱れた生活リズムは心身の不調を悪化させ、適応障害やうつ病からの回復を妨げる要因となります。
とくに大切なのは食事と睡眠のリズムを一定に保つことです。毎日なるべく同じ時間に食事をとるように心がけましょう。栄養バランスの取れた食事は身体の調子をととのえるだけでなく、精神的な安定にもつながります。また、毎日同じ時間に就寝・起床することを目標にしましょう。
少しずつでよいので、規則正しい生活を意識してみてください。
マインドフルネスを取り入れる
適応障害やうつ病の症状を緩和させるためには、マインドフルネスを取り入れましょう。[1]
マインドフルネスとは「今、この瞬間」に意識を向け、ありのままを受け入れる心の状態を目指します。
心理検査を用いた研究では、マインドフルネス瞑想などを取り入れたプログラムに参加した人々において、マインドフルネスを実施すると不安やうつの指標が改善したという報告もあります。[6]
マインドフルネスには瞑想があります。静かな場所に座り目を閉じて、自分の呼吸に意識を集中させます。呼吸するときの空気の流れ、お腹や胸の動きなどを感じましょう。
短い時間からでも始められるため、日常生活に取り入れやすい方法です。
適応障害からうつ病に移行する割合
適応障害と診断されても、うつ病など他の精神疾患の診断に変わるケースがあります。
適応障害と最初に診断された人が、5年後には40%以上の人がうつ病や他の不安障害などの診断名に変更されたと報告されています。[7]
適応障害は原因となるストレスが明確で、ストレスがなくなれば6か月以内に回復することが期待される病気です。
症状が長引いたり、ストレス要因が解消されないまま慢性化したりすると、より深刻なうつ病の状態へと進行するケースがあります。
定期的に医師の診察を受け、状態の変化を正確に把握してもらうことが必要です。
精神科や心療内科を受診する目安
適応障害やうつ病は、早期に適切なサポートを受けることが回復への近道です。
適応障害が疑われるときは、はっきりとしたストレスの原因があるかを考えましょう。
ストレスに直面し始めてから、気分の落ち込みや不安感、焦りなどの心身の不調があらわれ、日常生活に支障が出ているときは受診を検討してください。
うつ病が疑われるときは、気分の落ち込みや意欲の低下などが2週間以上続いているか確認しましょう。
さらに、食欲不振や不眠などの症状が見られるときも、うつ病の可能性があります。下記の記事では、うつ病のセルフチェックができるため参考にしてください。
症状はあくまで目安であるため、自分で判断するのは難しいと感じることもあるでしょう。
「適応障害やうつ病かも?」と思ったら、まずは精神科や心療内科の医師に相談しましょう。早く相談することで、適切な診断と治療につながります。
まとめ
適応障害は特定のストレスが原因で発症し、通常6か月ほどで回復します。うつ病は気分の落ち込みや意欲低下が見られ、回復に1~2年ほどの時間がかかります。
それぞれの病気に発症のきっかけや症状、回復期間に違いがあります。基本的な治療法は似ていますが、適切な治療のためには医師の診断が必要です。
もし、あなたの状態について判断に迷うときは、ひとりで抱え込まず精神科や心療内科などの医療機関へ相談しましょう。
おおかみこころのクリニックでは、24時間来院予約を受け付けています。また、オンライン診療も行っているので、忙しくて病院に行く時間がないときはお気軽にご利用ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]新版 適応障害のことがよくわかる本,貝谷 久宣,講談社
https://amzn.asia/d/6kcnkoN
[2]うつ病|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=9D2BdBaF8nGgVLbL
[3]2 うつ病の主な症状と原因:ご存知ですか?うつ病|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad002
[4]日本精神神経学会 精神療法委員会に「精神療法について」を訊く|公益社団法人 日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=58
[5]3 うつ病の治療と予後:ご存知ですか?うつ病|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad003
[6]不安症・うつ病に対するマインドフルネスー外来心療内科における実践報告ー,本田由美,小松智賀,野田昇太,長谷川洋介,長谷川明日香,三塚志歩子,川副暢子,貝谷久宣
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsad/15/1/15_58/_pdf
[7]適応障害/統合失調症|厚生労働省
https://kenkoukyouikusidousyakousyuukai.com/img/file214.pdf