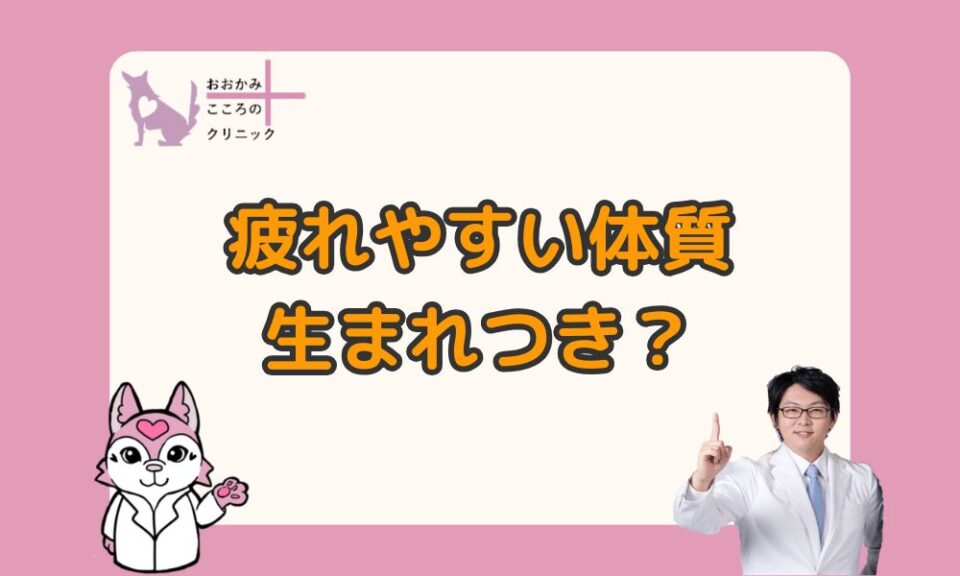「なんでわたしは人より疲れやすいの?」
「この疲れやすさって生まれつきなのかな…」
「やらなきゃいけないことがあるのに疲れすぎて動けない」
このように、気づけばため息ばかりついていませんか?
周りの人は元気に働いたり子育てや家事をこなしたりしているのに、自分だけがうまくできずに不安や自己嫌悪を抱えている方も少なくありません。
その疲れやすさは、生まれつきの体質によるものかもしれません。
この記事では、疲れやすい体質の原因や理由、日常生活の中でできるセルフケアについて解説します。
生まれつきの体質でも自分を責めすぎず、あなたらしく毎日を過ごしていくためのヒントになれば幸いです。
疲れやすい体質の原因は生まれつきだけではない
疲れやすい体質には「生まれつきの原因」と「環境や習慣の原因」があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
生まれつきの原因
疲れやさを感じやすい方の中には、生まれつきの体質や気質が関係しているケースもあります。
なかでも、虚弱体質やHSP(Highly Sensitive Person)の人は、こころや身体に疲れを感じやすいでしょう。
虚弱体質とは医学的な言葉ではなく、以下のような体質の人をいいます。[1]
- 疲れやすい
- 体調を崩しやすい
- ストレスや環境の変化に反応しやすい
ある研究で「虚弱」と診断された人を対象に問診した結果、全員が「疲れやすい、だるい」という項目にチェックをつけているほどです。[2]
一方で、HSPとは生まれつきの気質で、周囲の人に比べて感受性が高く繊細な気質を持ち合せている人です。
とくにHSPの人は、精神的な疲れを感じやすい傾向があります。
ただ、虚弱体質やHSPであっても、誰もが疲れやすいわけではありません。
HSPの敏感さはネガティブな側面だけでなく、強みとして働くこともあるのです。
たとえばHSPの人は、細かな変化に気づく力や人の気持ちを汲み取る力があるため、周りから信頼されたり、安心感を与えたりする存在として活躍する場面があります。
自分の体質や気質を理解することは、ムリをせずに自分らしく過ごすためのヒントにもなるでしょう。
あなたがHSPか知りたいときは、下記の記事もあわせてご覧ください。
環境や習慣による原因
環境や習慣による原因は、以下のとおりです[3]
- 環境による原因
- ・人間関係での気疲れや緊張状態
・自分のペースに合わない忙しすぎる毎日
- 生活習慣の乱れによる原因
- ・睡眠の質やリズムの乱れ
・栄養バランスが偏った食事
・運動不足や体を動かす機会の少なさ
これらの原因を日々積み重ねることで、こころと身体の疲労を深めてしまうことがあります。[4]
たとえば、人間関係のストレスが続くと、常に気を張ってしまい自律神経が休まらなくなります。すると夜にしっかり眠れなかったり、ちょっとしたことでどっと疲れを感じたりするのです。
また、睡眠不足や偏った食事、運動不足などの生活習慣も、疲労感の回復に関係します。
ゆっくりと一晩休めば回復するような疲れでも、ストレスや生活習慣の乱れが重なると長く続く疲れやすさへとつながってしまうのです。
疲れやすさを感じているときには「自分の生活や環境がどんな状態か」と考えてみてください。
体質だけでなく、日々の過ごし方やまわりの状況が、今のつらさに関係していることもあるのです。
疲れやすい体質の人に見られる特徴
疲れやすい体質の人には、以下のような特徴がみられます。[5]
- 完璧主義
- 刺激に敏感
- 自己否定が強い
- 人に気を遣いすぎる
- 頭の中で考え事が多い
完璧主義の人は、相手に対しても自分に対しても完璧を求める傾向にあります。
その結果、疲れていても休めずに常に気を張って生活することが多くなり、疲れやすい体質になるのです。
ほかにも、自己否定が強い人も疲れやすいでしょう。
たとえば、少し休んだだけで「サボっていると思われるかも」と不安になったり、うまくできなかったことに対して「自分はダメだ」と何度も頭の中でくり返してしまったりすることがあります。
以下の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
また、HSPの特性である刺激への敏感さや人に気を遣いすぎる傾向は、頭の中で考えごとが多くなりやすく、こころが疲れやすくなるのです。
HSPの女性の特徴は、下記の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
あなた自身が疲労を溜めているかチェックしてみるのもよいでしょう。
厚生労働省が出している働く人の疲労蓄積度セルフチェック2023(働く人用)です。
約5分でできますので、試してみてください。
疲れやすい体質をととのえる5つの方法
疲れやすい体質をととのえる方法は、以下のとおりです。[6]
それぞれ詳しく解説します。
あなたが「これならできそう」と思うものをムリのない範囲で試してください。
食生活を見直す
身体のだるさや疲労感があるなら、栄養バランスのよい食事を意識することが大切です。
とくに必要となる栄養素は以下のとおりです。[7]
- 鉄:レバー・鰹・牡蠣・ひじき・ほうれん草・枝豆
- 炭水化物:ご飯・パン・めん・ 果物・はちみつ
- ビタミン:焼き海苔・大葉・人参・大豆・ウナギの蒲焼・レバー
- たんぱく質:肉・魚・卵・牛乳・チーズ・ヨーグルト
- カルシウム:小魚・海藻・木綿豆腐・ひじき・小松菜
疲れやすい体質の人に不足しがちなビタミンは、ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンDなどです。
いつもの食事に、ヨーグルト+はちみつ+果物を追加してみたり、おやつにチーズを食べたりなど、日常生活に取り入れてみましょう。
また、ある研究では、かつお出汁を摂取すると精神的疲労やストレス状態によいという報告があります。[6]
夕飯に味噌汁やお吸い物などを追加してみるのもよいでしょう。
まずは、あなたの生活にムリがない程度に食事の栄養バランスを見直してください。
軽い運動をする
激しい運動をする必要はありません。
疲れやすい体質の人は、ムリのない範囲で体を動かすことが大切です。[8]
たとえば、朝や夕方に近所を10分ほどウォーキングするだけでも、血行が促され自律神経のバランスがととのいやすくなります。
また、深呼吸やストレッチ、軽いヨガなど、呼吸と身体の感覚に意識を向ける運動は、こころのリラックスにもつながります。
「なんとなく重だるい」「頭がぼんやりする」というときこそ、少し身体を動かしてみてください。

「これくらいならできそう!」と思えるほどで大丈夫ですよ♪
カウンセリングを受ける
必要に応じてカウンセリングを受けるのもよいでしょう。
身体だけでなくこころも疲れやすい人は、日々のストレスや不安をひとりで抱え込んでいることが少なくありません。
カウンセリングを受けると、自分では気づきにくかった「考え方のクセ」や「思い込み」に気づけたり、今の疲れやすさの背景を少しずつ整理できることもあります。
また、誰かに気持ちを打ち明けるだけでも、こころが少し軽くなるでしょう。
疲れやすさに悩んでいる自分を否定せず「相談してみようかな」と思えたときは、おおかみこころのクリニックへお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
過ごしやすい環境をととのえる
あなたの過ごしやすいように、環境をととのえることも大切です。
とくにHSPの人は、周囲の音やニオイ、光によって疲れを感じることがあります。[5]
そのため、以下のように環境をととのえるとよいでしょう。
- 負担に感じる人との距離をとる
- 静かな空間で過ごす時間をつくる
- 明るすぎる照明を落ち着いた灯りに変える
このように環境を工夫するだけでも、日常の疲れ方が変わってくることがあります。
また、自分のペースを大切にし「がんばりすぎ」を手放すだけでも気持ちは軽くなるでしょう。
睡眠リズムと体内時計をととのえる
疲れやすさを感じるとき、睡眠の質やリズムが乱れていることがあります。
夜更かしや寝つきの悪さ、眠りの浅さが続くと、どれだけ寝ても疲れが取れず日中の集中力や気力も落ちやすくなります。
以下のように、生活リズムを意識することが大切です。[9]
- 寝る1~2時間前にお風呂に入る
- 夜はスマホやテレビの光を避ける
- 朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びる
体内時計をととのえることは、自律神経の安定にもつながります。
まとめ|疲れやすい体質をムリなくととのえよう
疲れやすさは甘えではなく、体質や環境、生活習慣が重なって起こるものです。
「疲れやすい体質をどうにかしたい」と思ったら、以下の方法を試してみましょう。
- 食生活を見直す
- 軽い運動をする
- カウンセリングを受ける
- 過ごしやすい環境をととのえる
- 睡眠リズムと体内時計をととのえる
まずは「わたしは疲れやすい体質なんだ」とやさしく受けとめて、できるところからムリなく取り入れてみてください。
大切なのは、あなたのペースでムリをしないことです。
ふとしたときに、周りのことを考えすぎてしまったり気にしすぎてしまったりして、こころが疲れているなら、おおかみこころのクリニックにお話にきてください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]Ⅳ虚弱者の指導|国立教育研究所
https://erid.nier.go.jp/files/COFS/s28ep/chap4-4.htm
[2]虚弱体質に多い自覚症状—初診時の問診票より—p4|盛岡 頼子 佐藤 弘
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kampomed/60/3/60_3_371/_pdf/-char/ja
[3]ここまでわかった!疲労の正体|倉恒弘彦
https://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/guide/efforts/research/kuratsune/sum/kurashitokenkou.pdf
[4]食品摂取と自律神経活動変化―気分状態の変化を捉える―|山 崎 英 恵
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience/53/5/53_301/_pdf
[5]HSPの心を理解する―当事者と私たちにできること―|渡邊 真代
https://www.keiwa-c.ac.jp/wp2021/wp-content/uploads/2021/08/vt028-5.pdf
[6]こころと体のセルフケア|こころもメンテしよう 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/self/index.html
[7]健康と美を食べるもので叶える!~ 肌や髪、爪も美しく ~|働く女性の心とからだの応援サイト 厚生労働省
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/meal.html
[8]体を動かす|こころもメンテしよう 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/self/self_01.html
[9]健康づくりのための睡眠ガイド2023 p25|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf
- この記事の執筆者
- 柚木ハル
作業療法士として精神科で17年の臨床経験を積み、現在は訪問リハビリに従事。経験を生かしメンタルヘルスを中心に、やさしく寄り添う文章を心がけて執筆しています。