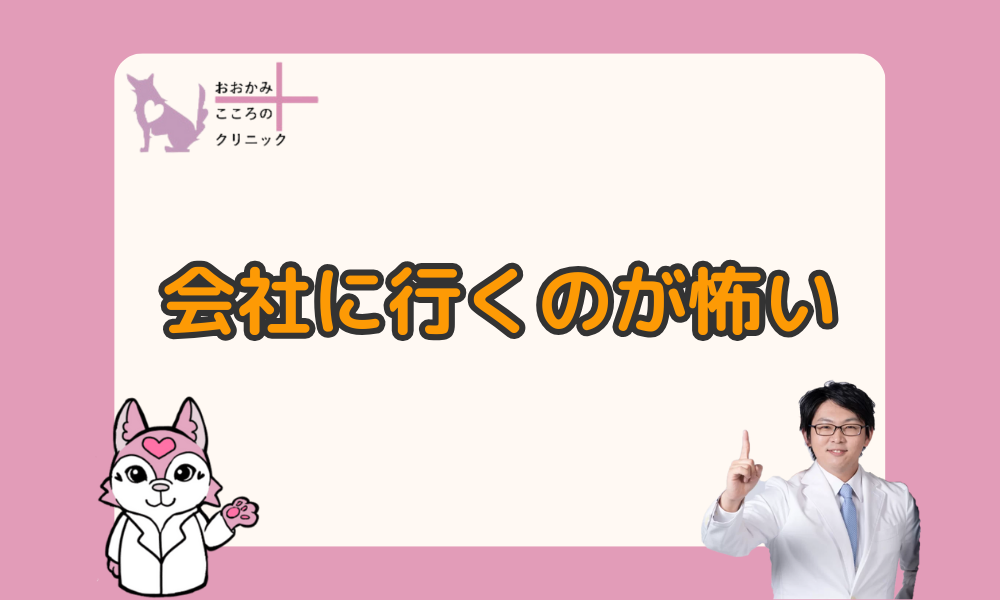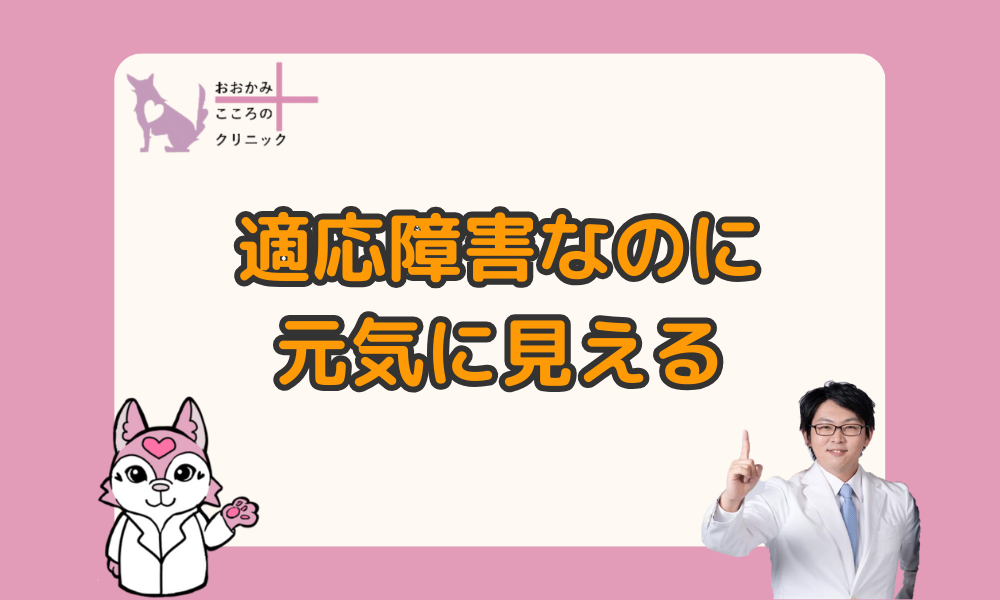「落ち込みや不安はもしかしたら適応障害のせい?」
「適応障害かどうか分かる方法はある?」
仕事や学校など、特定の状況で気分が落ち込んでしまうことに悩んでいませんか。
適応障害は特定のストレスに対して、こころや身体に不調があらわれる病気です。
ストレス要因から離れると症状は回復しますが、気持ちの落ち込みが続くと回復までに時間がかかることがあります。[1]
あなたが適応障害か知っておくことで、どのように対処すればいいかを判断できるようになるでしょう。
この記事では、適応障害のセルフチェックや原因、症状などを解説します。適応障害かどうかチェックしたいときは、チェックシートを役立ててください。
この記事の内容
適応障害の原因
適応障害のおもな原因を3つ解説します。
適応障害は、特定のストレスによって食欲不振や不眠、表情のくもりなどが見られるストレス障害のひとつです。うつ病と症状が似ていますが、原因となるストレスから離れると症状がやわらぐ特徴があります。
うつ病との違いについては、以下の記事をご覧ください。
それぞれについて見ていきましょう。
仕事のストレス
仕事のストレスは、適応障害の原因のひとつです。
2023年に株式会社ベクトルが500名に行った調査によると、仕事に行きたくないと思った経験がある方は全体の95%でした。[2]ほとんどの方が、仕事に行きたくないと考えながら働いているといえます。
具体的なストレスの内容は、以下のとおりです。
- 長時間労働
- 責任の重さ
- 過度な仕事量
- 異動や転職、転勤
- パワハラ、セクハラ
とくに、転勤や異動、転職などは環境の変化が大きいためにストレスを感じやすいのです。たとえば、海外赴任をきっかけに従業員だけでなく配偶者にも精神の不調をもたらした事例があります。[3]
適度なストレスは、やる気の源となりスキルアップにつながります。一方で、ストレスがその人の許容量を超えると、心身の不調を引き起こす可能性も考えられるのです。
適応障害でも会社で働き続けられる方法について詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてご覧ください。
人間関係の悩み
適応障害の原因に、人間関係の悩みも挙げられます。[1]
おもな人間関係の悩みを、下記にまとめました。
- 恋愛:失恋
- 学校:転校、いじめ
- 職場:上司や同僚との関係
- 家庭:結婚や離婚、家族間の不仲、引越し、介護
人間関係が悪化すると精神的な負担がかかり、こころの不調を招きます。とくに、家族内のトラブルやいじめ・嫌がらせなどを受けると、こころの傷を深く負うリスクが高まります。

人付き合いってストレスになりますよね💦
病気による心理的負担
慢性疾患やがんなどの病気による心理的な負担は、適応障害のリスクを高める要因となります。
厚生労働省によると、日本での末期がん患者における適応障害の有病率は16.3%とされています。[1]がんをはじめとする重大な病気は、病気が分かったときのショックや孤立感、今後の漠然とした不安など精神的な負担を感じやすいです。
そのため、健康問題は身体面だけでなく、精神面にも支障をきたします。
適応障害の症状
適応障害の代表的な症状について、3つの側面から紹介します。
適応障害は、ストレスの原因から離れると症状がやわらぐことが特徴です。[3]
ストレスの原因に差し迫ったときに、どのような症状がみられるかみていきましょう。
情緒面
適応障害の症状は情緒面にあらわれます。おもな情緒面の症状は、以下のとおりです。[1]
- 不安
- 怒り
- 焦り
- 緊張
- 憂うつ
ほかにも、判断力が低下し計画を立てて行動できなかったり、仕事の継続が難しくなったりすることがあります。
ストレスの原因となる場所や状況で不安な気持ちや緊張を感じるときは、適応障害を疑ってみましょう。
身体面
適応障害の症状は、身体面にあらわれます。[1]おもな身体面の症状は、以下のとおりです。
- 動機
- 発汗
- めまい
- 吐き気
- 手の震え
不安を強く感じると自律神経が乱れ、交感神経が活性化します。交感神経は身体を活発にさせる神経で、心臓や血管に働きかけ脈拍数の増加や血管の収縮、発汗などを引き起こします。
そのため、ストレスを強く感じると情緒が不安定になるだけでなく、身体の不調もみられることがあるのです。
行動面
適応障害の症状は行動面にもあらわれます。おもな行動面の症状を、下記にまとめました。
- 暴飲・暴食
- 無断欠席
- 過度な飲酒
- 無謀な運転
- 物品の破壊
ストレスが溜まると、脳内の安定を司る「セロトニン」とやる気を司る「ノルアドレナリン」のバランスが崩れます。セロトニンとノルアドレナリンのバランスが崩れると、感情のコントロールが難しくなります。その結果、イライラして攻撃的になったり、暴飲・暴食をしたりすることがあるのです。
普段よりも行動が極端に活発になっているときは、適応障害の可能性が考えられます。下記の記事では、適応障害なのに元気に見える理由を解説しているので、あわせてご覧ください。
適応障害のセルフチェック
適応障害かどうかを確認できるチェックリストを以下に作成しました。[1]
- 食欲がない
- 過呼吸になる
- 涙もろくなった
- なかなか眠れない
- めまいや頭痛がする
- 憂うつな気分が続く
- 不安を感じることが多い
- 動悸や息苦しさを感じる
- 疲れを感じ、身体がだるい
- 暴飲暴食するようになった
- 死にたいと思うことがある
- 繊細なことを過剰に心配する
- 感情のコントロールが難しい
当てはまる項目が多いと、適応障害の可能性があります。
適応障害はストレス要因が生じてから3か月以内に症状があらわれるのが一般的です。[4]しかし、ストレスの原因から離れられないときは、症状が長く続くことがあります。
日常生活に支障をきたすときは、心療内科や精神科を受診しましょう。おおかみこころのクリニックでは、自宅にいながらオンラインでの診療も可能です。お気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
適応障害の症状への対処法
適応障害の症状への対処法を紹介します。
気持ちに余裕があるときに、できることから始めてみましょう。
生活習慣を見直す
適応障害の症状への対処法として、生活習慣の見直しは有効です。とくに見直したい内容は以下のとおりです。
- 適度な運動
- 質のよい睡眠
- 栄養バランスのよい食事
適度な運動をすると、こころに穏やかな幸福感をもたらす「セロトニン」の分泌が促されます。つらいときにムリをする必要はありませんが、ウォーキングやサイクリングなどできる運動から少しずつ始めてみましょう。
また、脳の疲れをとるのに十分な睡眠は欠かせません。1日8時間を目安に睡眠をとりましょう。[5]
栄養バランスのよい食生活は、セロトニンの生成に必要です。肉や魚、野菜、きのこ、海藻などバランスよく摂取してください。
医療機関を受診する
学校や会社の欠席など日常生活に支障をきたしたり、適応障害の症状が1~2週間続いたりするときは、精神科や心療内科の受診を検討しましょう。
精神科と心療内科は、患者さんの症状によってどちらの受診が適切か異なります。両者の違いを、下記にまとめました。
- 精神科:憂うつな気分、焦り、不安などの気持ちが不安定な方
- 心療内科:不眠や頭痛・吐き気、震え、緊張などの身体の不調にお悩みの方
精神科・心療内科のどちらにも対応する病院もあるので、受診の前に調べてみましょう。もし受診する診療科を間違えても、診察してくれる病院もあるため心配はいりません。

どっちに行っても間違いはないので安心してくださいね
周囲に協力をお願いする
適応障害の症状への対処法として、時には家族や友人、職場の上司や同僚に状況を共有し理解を得ることも大切です。
通院の付き添いや業務量の調節など、あなたの気持ちを理解してもらうと早期の症状回復につながります。
家族や職場に相談しづらいときは、相談窓口を活用するのもひとつの手です。おもな相談窓口は、以下のとおりです。[6]
不安や悩みを誰かに聞いてもらうと、こころにたまっていたものを吐き出せて気持ちの整理ができます。ひとりで問題を抱え込まずに、気軽に相談窓口を活用しましょう。
ストレスの原因を遠ざける
ストレスの原因を遠ざけるのも、適応障害の症状への大切な対処法です。
一般的に適応障害は、ストレス要因から離れると症状が回復するからです。ストレスから離れる方法を、いくつかまとめました。
- 休職
- 休学
- 帰郷
- 部署移動
- 業務量の調整
職場の環境を調節したり、苦手な人物との距離を置いたりするなどして一時的に離れてみるとよいでしょう。
また、気持ちが落ち込んでいるときは大きな決断は避けてください。[5]精神的に追い込まれた状況では判断力が低下しているため、学校や会社はすぐに辞めずに休学・休職し気持ちが落ち着いてから考えましょう。
リラクゼーション法を行う
適応障害の症状への対処法として、ヨガや瞑想などのリラクゼーション法を行うのもひとつの手です。[7]
リラクゼーション法とは、ストレス反応とは反対の作用である「リラックス反応」を身体にもたらす手法で、不安やストレスの軽減に有効とされています。リラックス反応とは、ゆっくりした呼吸や血圧の低下、心拍数の低下などです。
たとえば、ヨガや瞑想で深い呼吸をすると、気持ちが落ち着く効果が見込めます。[7]
リラクゼーション法を日常に取り入れて、不安な気持ちをやわらげましょう。
まとめ
適応障害は、強いストレスが原因で日常生活に支障をきたす状態です。特定の状況で不安や焦りを感じたり、めまいや頭痛などの症状があったりするときは適応障害を疑ってみましょう。
適応障害はストレスの原因から離れると症状がやわらぎますが、対処が遅れると慢性化する恐れがあります。日常生活に支障をきたす前に、心療内科や精神科の受診を検討しましょう。
おおかみこころのクリニックは「どんな些細なことでも気軽に相談できる場所になれたら」という思いで、日々診察をしています。オンライン診療も受け付けていますので「適応障害かもしれない」と悩んだときは当院までお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]適応障害/統合失調症|厚生労働省
https://kenkoukyouikusidousyakousyuukai.com/img/file214.pdf
[2]仕事に行きたくない理由ランキングを発表|株式会社ベクトル
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000112674.html
[3]海外赴任を契機に従業員と配偶者の両者にメンタルヘルス不調をもたらした事例|こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/case/698
[4]新版 適応障害のことがよくわかる本,貝谷 久宣,講談社
https://amzn.asia/d/6kcnkoN
[5]脱うつのトリセツ,三浦暁彦,扶桑社
https://amzn.asia/d/hlZh0hb
[6]相談窓口案内|こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/agency/#anc5
[7]リラクゼーション法 | 厚生労働省eJIM
https://www.ejim.mhlw.go.jp/public/overseas/c02/11.html