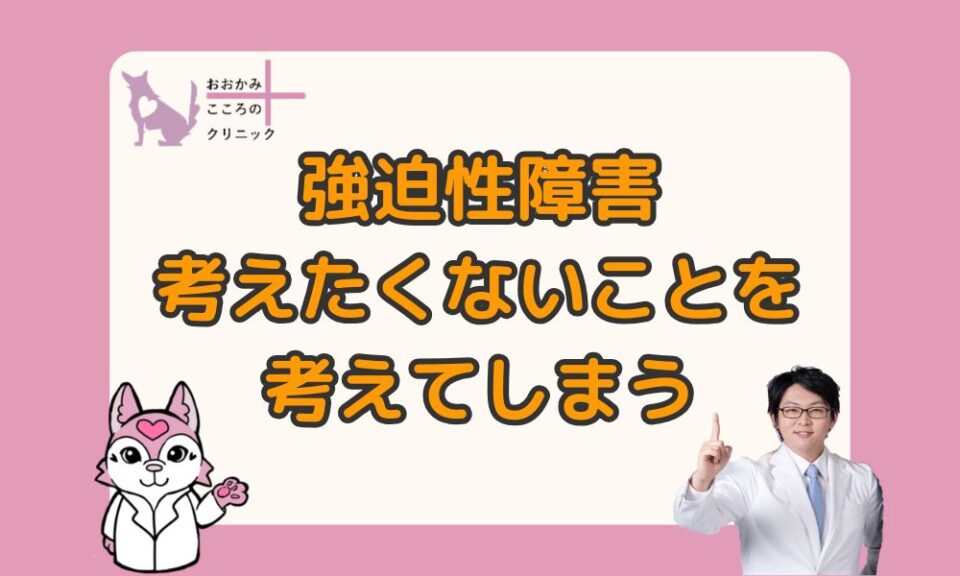「強迫性障害を治すコツはあるのかな?」
「何度も確認しないと不安になるのが嫌だ」
強迫性障害は、自分の意思に反して不安な考え(強迫観念)が浮かび、不安を打ち消すための行動(強迫行為)を繰り返してしまう病気です。
強迫性障害を治すコツを知らずにひとりで抱え込んだり対処しようとしたりすると、症状が悪化するかもしれません。回復には、治療とあわせてあなた自身で取り組める工夫があります。
この記事では、強迫性障害を治すためのコツや治療法を解説します。強迫性障害の症状をやわらげるヒントとして、ぜひお役立てください。
強迫性障害を治すコツ5選
強迫性障害は、医師と相談しながら治療を行うのが基本です。
強迫性障害を治すために日常生活で意識できるコツが5つあります。
あなたが「できそうだな」と思うものから試していきましょう。
考えたくないことを考えてしまいつらいときは、下記の記事を参考にしてください。
回復を焦らない
回復を焦らないことは、強迫性障害を治すコツのひとつです。
強迫性障害の回復過程は、一直線に進むとは限りません。症状がよくなったり、一時的に悪化したりを繰り返しながら、少しずつ快方に向かう傾向があります。[1]
たとえば、「症状がよくならない」と焦ってしまうと、不安になり治療をやめてしまうかもしれません。
そのため、回復には波があることを理解し長期的な視点で治療に取り組む姿勢が、結果的に回復につながるのです。
完璧を目指さない
強迫性障害を治すためには、完璧を目指さないことを習慣にしましょう。
「〜でなければならない」という完璧主義な考え方は、強迫観念や強迫行為のきっかけになりやすいためです。[2]
たとえば、仕事や家事において完璧な状態を求めすぎると、強迫行為がエスカレートしやすくなります。
意識的に「まあいいか」「7割くらいできていれば大丈夫」といった、柔軟な考え方を取り入れる練習をしてください。
完璧な状態を目指さないことで、強迫観念にとらわれにくくなります。

「このくらいでいいか!」ぐらいの気持ちで過ごしてみましょう!
行動日記をつける
強迫性障害を治すコツには、行動日記をつけることがあります。
どのような状況で強迫症状が出やすいのかというパターンを理解することは、対策を立てるのに有効です。
具体的に日記には、いつ・どこで・どのような状況で強迫観念や強迫行為が出たかを記録しましょう。そのときの不安や不快感の強さを、0(まったくない)から100(最も強い)の数値にします。[3]
下記のように、書いてみてください。
| 時間 | 場所 | 状況 |
| 9時 | 家 | ごみ箱に触った(20) |
| 12時 | コンビニ | 商品のお金を払った(60) |
| 19時 | 家 | トイレを使う(80) |
記録した内容は医師やカウンセラーと共有することで、より効果的な治療計画を立てるための助けとなります。
規則正しい生活を心がける
規則正しい生活を心がけることは、強迫性障害を治すコツのひとつです。
強迫性障害は、引きこもりや生活リズムの乱れによって悪化しやすい傾向があります。[1]
とくに、昼夜逆転の生活は脳内ホルモンの働きを悪くしてしまうのです。[4]
脳内ホルモンのバランスが崩れると、強迫症状への歯止めが効かなくなり、症状のコントロールがさらに難しくなる可能性があります。
なるべく同じ時間に起床・就寝し、食事も3食とるようにしましょう。規則正しい生活を心がけることで、症状の悪化を防ぎます。
「自分のために治す」と意識する
「自分のために治す」という主体的な意識は、強迫性障害を治すコツです。[1]
「自分のため」と意識することで治療に対して受け身ではなく、主体的にかかわれるようになります。
たとえば、日々の症状を記録する宿題に取り組んだり、医師やカウンセラーに自ら積極的に症状を報告・相談したりするなど、治療への参加度が高まるのです。
「自分のために治す」という意識を持つことが、困難な治療を続ける力になります。

目的をもって取り組むことは大切です
強迫性障害が回復する確率
強迫性障害は、適切な治療を受けることで改善が期待できる病気です。
2006年の研究(Catapanoら)では、強迫性障害の患者さんを追跡調査したところ、3年後までに症状が完全になくなった状態(寛解)は38%でした。また、症状がやわらいだ状態(部分的な寛解)を含めると、65%に改善がみられたと報告されています。[5]
もちろん、回復までの期間や程度は、用いられる治療法や症状の重さによって一人ひとり異なります。
研究結果からわかるように治療を粘り強く継続することが、強迫性障害の回復において大切です。
強迫性障害を自力で克服するのは難しい
強迫性障害を自力で克服するのは困難です。
強迫性障害は性格の問題ではなく、脳機能の不調もかかわっていると考えられています。そのため、あなたの意志だけでコントロールできるものではありません。
とはいえ、病院を受診する前に不安を感じると、治療への決断が難しいでしょう。
治療へ踏み出すために、あなたの動機を整理してみるのもよい方法です。
たとえば、下記の視点で考えると考えがまとまりやすくなります。[4]
- わたしにとって
- 【治療を受けた方がよい理由】
・外出や旅行を自由に楽しみたい
・不安や確認行為から解放されたい
・仕事や勉強に集中できるようになりたい
【治療をためらう理由】
・治療費が心配
・本当に治るか不安
・通院が面倒くさい
・治療に時間がかかりそう
- 家族や周囲にとって
- 【治療を受けた方がよい理由】
・心配をかけたくない
・家族や友人と穏やかに過ごしたい
・家族を強迫行為に巻き込むのをやめたい
【治療をためらう理由】
・周囲にどう思われるか気になる
・家族に病気のことを知られたくない
治療への動機を明確にすることが、治療への決断を後押しするでしょう。
ひとりで抱え込まず、まずは病院に相談することが回復への近道です。
「通院が面倒」「時間がとれない」といった理由でためらっていたら、自宅から受診できるオンライン診療も検討してください。
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
強迫性障害の治療法
強迫性障害のおもな治療法には、次の3つがあります。
- 薬物療法
- 心理療法
- rTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激療法)
薬物療法では、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)という種類の抗うつ薬を使用します。[6]脳内のセロトニンのバランスを調整し、強迫観念や不安をやわらげる効果が期待されるのです。
心理療法では、おもに曝露反応妨害法が行われます。あえて不安を感じる状況(曝露)に身を置き、強迫行為をしない(反応妨害)練習を繰り返す治療法です。[3]
rTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激療法)は磁気により脳を刺激し、症状をやわらげる方法です。ただし、強迫性障害の治療においては保険が適用されないため、治療を受ける際は注意しましょう。[7]
どの治療法が適しているかは、症状や状態によって異なります。医師とよく相談し、あなたに合う治療を進めてください。
まとめ
強迫性障害を治すためには「回復を焦らない」「完璧を目指さない」などを意識しましょう。
強迫性障害は自力での克服は難しい一方で、適切な治療によって症状がやわらぐ病気です。おもな治療法には、薬物療法や心理療法などがあります。
ひとりで悩まず、まずは精神科や心療内科などへ相談し、あなたに合う治療を始めてください。
おおかみこころのクリニックでは、オンライン診療を実施しています。症状のために外出が難しいときでも、自宅からスマホひとつで診察を受けられます。朝8時~夜22時まで開院しているので、仕事や家事で忙しいときでもお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【参考文献】
[1]松永寿人先生に「強迫性障害」を訊く|公益社団法人 日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=22
[2]強迫性パーソナリティ症(OCPD)|MSDマニュアル プロフェッショナル版
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/professional/08-精神疾患/パーソナリティ症/強迫性パーソナリティ症-ocpd
[3]強迫性障害(強迫症)の認知行動療法マニュアル (治療者用)|厚生労働省
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2015/153091/201516018B_upload/201516018B0018.pdf
[4]こころのクスリBOOKS よくわかる強迫症,有園正俊,上島 国利,主婦の友社
https://amzn.asia/d/bStoHZb
[5]Obsessive-compulsive disorder: a 3-year prospective follow-up study of patients treated with serotonin reuptake inhibitors OCD follow-up study|PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16904424
[6]強迫性障害|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=MiyHEH6ZUZDxDeYX
[7]反復経頭蓋磁気刺激療法(rTMS)の臨床と基礎,朴秀賢
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1150090967.pdf