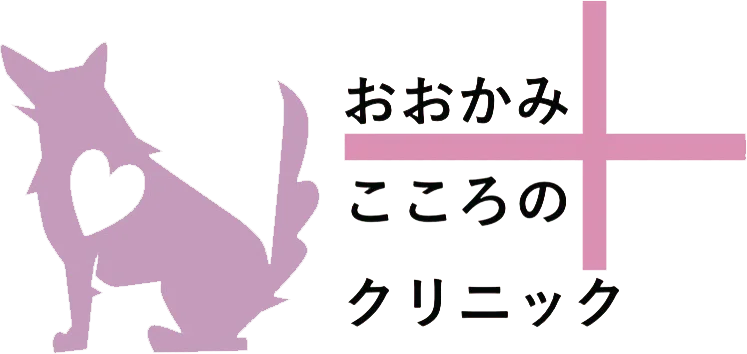「双極性障害の原因は母親なのかな?」
「幼少期の過ごし方が関係しているかも」
「わたしの子どもにも遺伝するのかな…」
このように思う人は少なくありません。
双極性障害の発症には、遺伝が関係していると言われていますが家庭環境やストレスなども関係しています。
「母親が原因かもしれない」と悩んでいるのなら、双極性障害について正しい知識をもつことで、あなた自身を責めることなく家族ともよい関係を築くきっかけになるでしょう。
この記事では、双極性障害の原因は母親にあるのか、育て方が関係しているのかについて解説します。
「双極性障害の原因は母親かもしれない」と考えてこころが苦しくならずに、母親と向き合えるきっかけになりますと幸いです。
ひとりで悩まずに新宿・秋葉原・横浜・大阪梅田・博多にあるおおかみこころのクリニックにご相談ください。
双極性障害のおもな原因
双極性障害の原因は明確に解明されていませんが、おもな原因は遺伝と環境と言われています。
ただし、ひとつの原因で双極性障害を発症する訳ではありません。
複数の原因が絡み合い発症するのです。
遺伝
双極性障害を発症しやすい体質には、遺伝が関係しています。[1][2]
ある双生児研究では、双極性障害の遺伝率は70~90%という報告があり、遺伝要因が大きく関与していることが示されています。[1]
両親のどちらかが双極性障害と診断されていると、子どもも発症する可能性があるため「双極性障害の原因は母親だ」と言われる要因になるのです。

遺伝なのでお父さんも関係しています
環境
「この環境で育つと双極性障害を発症します。」このような特定の環境はありません。
ただ、双極性障害の直接の発症原因ではありませんが、ストレスが発症や再発のリスクを高めます。
そのため、ストレスが高い環境で生活していると、双極性障害の発症リスクは高くなるのです。[1]
ストレスの感じ方は一人ひとり違いますが、ある調査結果では、おもに双極性障害を発症するきっかけとなるのは、結婚・就職・身近な人の死・出産のような人との関わりによるストレスと報告されています。[3]
ストレスのかかりやすい環境で生活していると、双極性障害の発症リスクは高くなるのです。
双極性障害の原因になる母親の育て方
双極性障害の原因になる母親が関係しているできごとは、以下のとおりです。[1][4]
それぞれ詳しく解説します。
逆境体験
双極性障害に限らず、幼児期の逆境体験により成人後こころの病気になるリスクが高まると報告されています。[1]
逆境体験とは、幼児期に虐待や機能不全家族(子どもが本来の子どもらしさを出せない家庭)との生活を体験することです。[5]
たとえば、家族に大切にされていない以下のような体験が挙げられます。
- 暴力
- 暴言
- ネグレクト
- 家族の仲が悪い
家庭内で「誰にも守ってもらえない」と感じることも逆境体験です。
ただし、母親の育て方だけが原因で、双極性障害を発症する訳ではありません。
「双極性障害を発症したひとつの要因」程度に考えましょう。
家が安心できる環境でないと、こころが不安定なまま日常を送ることになります。
その結果、ストレスを感じたり自分らしく過ごせなかったりして双極性障害や他の精神疾患の発症につながるのです。
母親の抑うつ
ある研究で母親が抑うつ傾向だと、子どもが双極性障害傾向になると報告されています。[4]
子どもの健康な成長には、母親の安定した情緒が必要です。
しかし、母親が抑うつ傾向だったからといって母親を責めてはいけません。
母親のこころの安定は、父親から大切にされていると感じる気持ちや、子育て中のこころのサポートが大きく関係しているのです。[6]
母親ばかりに着目するのではなく、家族がどのような関係だったのかが重要になります。
双極性障害の原因になる母親の妊娠中の過ごし方
母親の妊娠中の過ごし方が、双極性障害に関係しているという報告があります。[7]
- 喫煙
- 飢餓(きが)
- インフルエンザ感染
ただし、妊娠中に喫煙したりインフルエンザに感染したりすることで、必ず双極性障害になるとは限りません。双極性障害の発症には個人差や育った環境も関係します。
双極性障害をもつ母親の子どもとの接し方
双極性障害には遺伝要因があるため「わたしの子どもも双極性障害になるのかも」と気になるでしょう。
現在、精神疾患で病院を受診している方は日本に約603万人(令和5年時点)いるため、精神疾患を持つ母親が珍しい訳ではありません。[8]
しかし、双極性障害は遺伝要因が大きいため遺伝する可能性はあります。
双極性障害の発症を避けるためには、子どものこころの健康を意識した接し方が大切です。
- 子どもの意思を尊重する
- 家を休憩できる場所にする
- 話を聞き気持ちに寄り添う
自宅が肩の力を抜いて安心して過ごせる場所であることにより、社会(学校やお友だち関係)で頑張る気力を養うことができます。
そのためにも、子どもの意思を尊重したり、ゆっくりと向き合い話を聞いたりすることが大切です。「困ったときはお母さんが話を聞いてくれる」という安心感が、子どものこころの安全基地になるのです。
まとめ
双極性障害の明確な原因は分かっていませんが、遺伝要因が大きいことが明らかにされています。そのため、母親が双極性障害の場合は子どもに遺伝する可能性は高くなるのです。
環境的な要因も発症に関係しており、幼少期の虐待や暴力などの逆境体験や母親の抑うつは子どもの精神疾患発症リスクを高めます。
あなた自身が親になったとき、子どもが安心して過ごせる家庭環境を作ることが大切です。
子どもと向き合い、ゆっくりと話を聞くことで「お母さんがいたら大丈夫」と思えるようになるでしょう。
新宿・秋葉原・横浜・大阪梅田・博多にあるおおかみこころのクリニックでは、病気の相談だけでなくあなたの悩み相談も受けております。「こんなこと相談してもよいのかな?」と思うことでもお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【参考文献】
[1]日本うつ病学会診療ガイドライン 双極性障害(双極症)2023|日本うつ病学会
https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/iinkai/katsudou/data/guideline_sokyoku2023.pdf
[2]小児と青年における双極性障害|MSDマニュアル家庭版
[3]双極性障害(躁うつ病)とつきあうためにp30|日本うつ病学会 双極性障害委員会
https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/gakkai/shiryo/data/bd_kaisetsu_20180727.pdf
[4]母親の抑うつが子どもの自己制御と双極性障害傾向に及ぼす影響 子どものADHD傾向の有無による違い|田中 麻未・髙橋 雄介
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/83/0/83_3C-027/_pdf/-char/ja
[5]逆境的小児期体験が子どものこころの健康に及ぼす影響に関する研究| 研究分担者 山崎 知克 研究協力者 野村 師三 (浜松市子どものこころの診療所)
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2019/192011/201907005B_upload/201907005B0011.pdf
[6]母親の抑うつが子どもに及ぼす影響|五味美奈子・杉山崇
https://www.jstage.jst.go.jp/article/pacjpa/71/0/71_3AM147/_pdf/-char/ja
[7]太陽光と双極性障害の発症年齢との関係─ 23 カ国 36 施設の国際共同研究─|中野谷貴子、楯林 義孝、田形 弘実、針間 博彦
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjghp/29/2/29_143/_pdf/-char/ja
[8]精神保健医療福祉の現状等について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf
- この記事の執筆者
- 柚木ハル
作業療法士。精神科16年の臨床経験を生かして執筆を担当。現在は訪問リハビリに従事しながら幅広いジャンルにて執筆中。