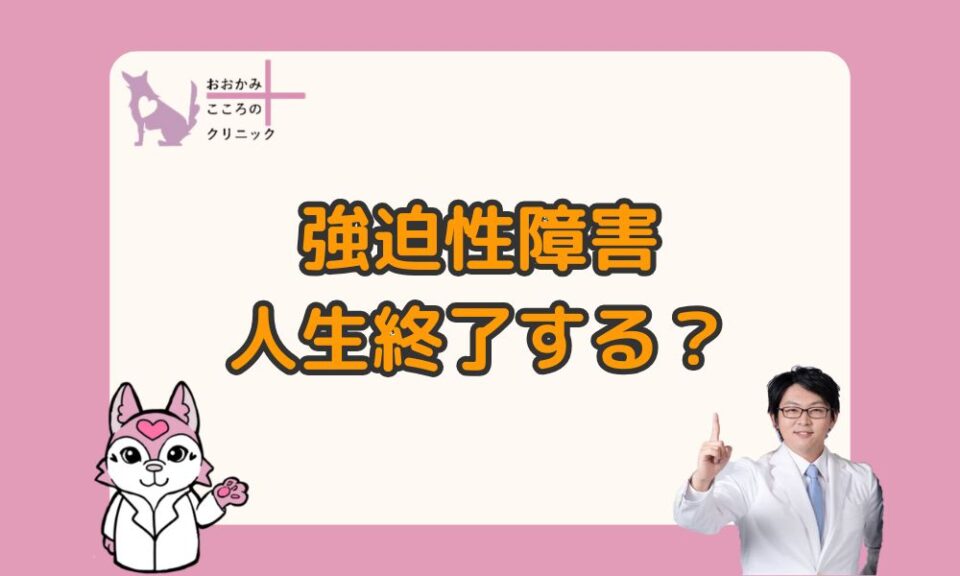「強迫性障害のせいでもう人生終わりだ…」
「この苦しみは一生続くのかもしれない」
頭から離れない不安に支配され、将来に希望が持てなくなっていませんか。
強迫性障害について正しく知らないまま諦めてしまうと、症状がやわらぐ可能性を見逃してしまいます。
苦しみから抜け出すためには今あなたを悩ませている正体を知り、回復への道筋を一緒に見つけていきましょう。
この記事では、強迫性障害が人生終了でない理由や強迫性障害とともに生きる方法を解説します。
不安をやわらげ、希望を見つけるための助けとなれば幸いです。
強迫性障害になっても人生終了ではない
強迫性障害は適切な治療を続けることで、症状がやわらぐ可能性がある病気です。
Catapanoらの研究によれば、症状が完全になくなった状態は3年目で38%まで増加しました。
また、症状がやわらいだ状態(部分的な寛解)を含めると3年目で65%に改善がみられたと報告されています。[1]
もちろん、すぐに症状が消えるわけではなく、回復の早さには個人差があります。
ただ、治療に取り組めば、つらい症状に振り回されない生活を取り戻せる見込みはあるのです。
ひとりで抱え込まずに回復への道を歩み始めることが、つらい毎日から抜け出すための第一歩となるでしょう。

「人生終わったかも…」という悩みを先生に相談しましょう!
強迫性障害とは
強迫性障害とは、あなたの意思に反した考え(強迫観念)が繰り返し頭に浮かんでしまう状態です。
その考えを打ち消すための行動(強迫行為)をやめたくてもやめられなくなるのです。
強迫性障害について、次の3つのポイントから解説します。
強迫性障害を正しく理解することで、回復への道筋がみえてきます。
原因
強迫性障害の原因はひとつに特定されているわけではなく、複数の要因が絡み合って発症すると考えられています。具体的には、下記のものがあります。[2]
- 脳の働き
- こころの性質
- 家庭や職場の環境
まず、感情や思考のコントロールに関わる「セロトニン」が、脳内でうまく機能していない状態が関係しているのです。[3]
セロトニンがうまく働かず不安を処理できなくなると、強迫観念や強迫行為につながります。
また、物事の考え方のクセやストレスへの対処法などの心理的な要因も関係します。
ほかにも学校や職場での環境変化、家庭内での問題といった環境的な要因もストレスとなり、発症につながるケースがあるのです。
このように複数の原因が重なり合うことで、強迫性障害は発症すると考えられています。
症状
強迫性障害の症状は、具体的に次の5つに分類されます。[4]
| 症状の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 不潔恐怖 | 何時間も手を洗い続ける |
| 加害恐怖 | 車の運転中に「人をひいたかもしれない」と不安になる |
| 確認行為 | 家の鍵やガスの元栓を閉めたかを、何十回も確認する |
| 儀式行為 | 物事をおこなう際に、特定の順序や回数にこだわる |
| 数字や物の配置へのこだわり | 物の配置が左右対称でないと気が済まない |
「やりすぎだ」と頭ではわかっているのに、やめようとすると不安に襲われるため繰り返さずにはいられないのです。
理性と感情の板挟みこそが、強迫性障害のつらい部分です。

やめたくてもやめられないのはツラいですよね💦
治療法
強迫性障害のおもな治療法には、次の3つがあります。[4]
- 薬物療法
- 心理療法
- rTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激療法)
薬物療法では不安やこだわりの強さをやわらげる効果が期待できますが、効果があらわれるまでに数週間から2か月ほどかかります。
心理療法の中でも強迫性障害に有効なのが、曝露反応妨害法です。
専門家のサポートのもと、あえて不安を感じる状況に身を置き、不安を打ち消すための強迫行為をしない練習をします。
また、rTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激療法)という磁気を用いて脳の特定領域を刺激する治療法もあります。
薬物療法で効果があらわれない人に向けた治療法です。
どの治療法が合うかは一人ひとり状態によって異なるため、まずは医師と一緒に治療の計画を立てることが大切です。
強迫性障害の治療法を詳しく知りたいときは、下記の記事もあわせてご覧ください。
rTMSについては下記の記事でご覧ください。
強迫性障害とともに生きる方法
強迫性障害とともに生きる方法には、次の3つがあります。
治療と並行しながら、日常生活で少しずつ実践してみましょう。
症状を客観視する
強迫観念に襲われたときは、あなたの考えや感情から距離を置く練習をしましょう。
たとえば、何度も手の汚れが気になってしまうときに「これは不潔恐怖のパターンだ」とこころの中で呟きます。
あなたの考えを「症状」として客観視することで、考えとあなた自身との間に距離が生まれます。[2]
この距離感が、不安にかられてすぐに行動に移す悪循環を断ち切る助けとなるのです。
不完全な状態を許す
強迫性障害の背景には、完璧主義が隠れている可能性があります。[5]
そのため、あえて「不完全な状態」に慣れることが症状をやわらげる助けとなります。
たとえば、下記のような状態にしてみましょう。
- 机の上の本をわざと斜めに置く
- 洗濯物をきれいに畳まずに収納する
- 友人へのメッセージで誤字をしてもそのままにする
最初は「直したい」「完璧にしたい」という衝動に駆られ、不安になるでしょう。
大切なのはすぐに行動に移さず、ザワザワした気持ちをあえてそのままにしておくことです。
練習を繰り返すことで「完璧でなくても大丈夫だ」という感覚が積み重なり、強迫観念にとらわれにくくなります。
どんな病気かを理解する
強迫性障害について正しい知識を持つことは、回復につながる方法になります。
病気のメカニズムや症状のあらわれ方を知ると、あなたに起きていることを理解できるようになるからです。
また、どのような症状があり、どのような治療法が有効なのかを理解すれば、適切な方法で対処できるようになります。
厚生労働省や住んでいる地域の自治体など信頼できる情報源から強迫性障害について学び、あなたの状態を把握していきましょう。
下記の記事では強迫性障害を気にしない方法を解説しているので、あわせてご覧ください。
強迫性障害の症状がやわらいだ人の体験談
実際に強迫性障害の症状がやわらいだ人の体験談を紹介します。
3、4年前私も強迫性障害を患っていました。
私はその時受験に直面していて過度なストレス、不安、プレッシャーで引き起こされていたので受験が終わったと同時にだんだん緩和していきました。
でも1番大事なことは「意識しすぎないこと」だと思います。
受験直前は自分に自信がなくてコンロの火を止めたか確認する時、何回も近くで火が消えてるのは確認してるのに無意識に自分の手が火をつけてしまってるかもしれないと思って毎回手を縛ってコンロを確認しに行ったぐらいでした。
しかし受験が終わってストレスに解放されて気づいたら症状はなくなってました。意識しないって難しいことだと思います。
あと私は自分に自信を持つように頑張ってました。
さっきのコンロの件でも一回確認したあと声を出して「火消えてる!消えてる!」とかずっと言い聞かせて慣れるようにしてました。
私の場合は行動療法で頑張ってました。
引用:Yahoo!知恵袋
体験談からは、受験が症状の引き金になりうること、ストレス源から解放されると症状がやわらぐケースがあることがわかります。
ストレスに対処するために、できることを試す姿勢が回復への力になることを教えてくれています。
まとめ
強迫性障害はを発症しても、人生が終了するわけではありません。
治療を受けて症状と向き合う方法を学ぶことで、回復への道は開けます。
症状を客観視したり不完全な状態を許したりする練習を重ねれば、症状に振り回されない生活を送れるようになります。
もしひとりで抱え込んでいたら、まずは精神科や心療内科などの専門機関に相談しましょう。
おおかみこころのクリニックでは毎日夜22時まで診察しています。来院予約はいつでもできるので、お気軽にお問い合わせください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]Obsessive-compulsive disorder: a 3-year prospective follow-up study of patients treated with serotonin reuptake inhibitors OCD follow-up study|PubMed
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16904424
[2]こころのクスリBOOKS よくわかる強迫症,有園 正俊,主婦の友社
https://amzn.asia/d/isirmPb
[3]強迫性障害 細かいことが気になりすぎて|さいたま市
https://www.city.saitama.lg.jp/008/016/009/p007250_d/fil/kokoro-hr10.pdf
[4]強迫性障害|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=MiyHEH6ZUZDxDeYX
[5]The Search for Imperfection: Strategies for Coping with the Need to be Perfect|Beyond OCD