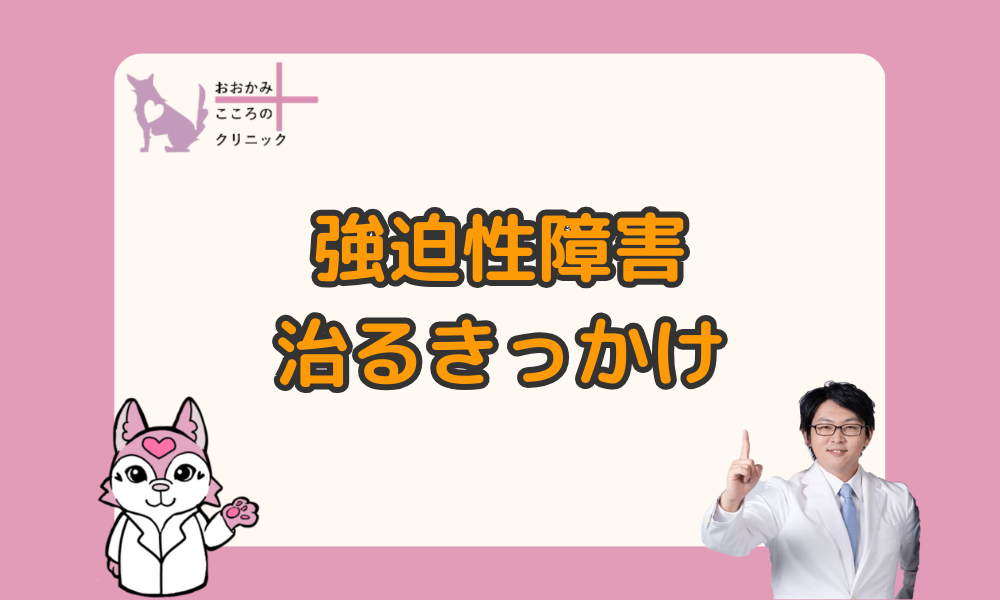「家の鍵を閉めたか気になり何度も玄関に戻ることがある」
「やめたいのに何度も同じ行動を繰り返してしまう…」
そのつらい症状は性格のせいではなく、強迫性障害が関係しているかもしれません。
症状に気づいても、どうすれば治るのか分からずひとりで悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
強迫性障害の正しい治し方を知ることで、不安や苦しみをやわらげていくことができます。
症状が起こる仕組みを理解し、回復に向けた一歩を踏み出しましょう。
この記事では、強迫性障害の治し方やきっかけの作り方を解説します。不安をやわらげ、あなたに合う治療法を見つける助けとなれば幸いです。
強迫性障害は一生治らないのか
強迫性障害は、適切な治療によって症状をやわらげることができる病気です。
決して一生治らないと決まっているわけではありません。
強迫性障害の長期的な経過に関する研究では、治療を続けることで症状がほとんどなくなる「寛解」という状態になる人が約50%いると報告されているのです。
一方で、一度症状が落ち着いても再発しやすいという特徴も指摘されています。[1]
強迫性障害の治療を通して症状の波をコントロールする方法や、不安への対処法を身につけられます。
「一生治らない」と諦めるのではなく、まずはどのような治し方があるのかを知っていきましょう。

知ることで見えてくる未来があります
強迫性障害の治し方
強迫性障害のおもな治し方には、次の3つがあります。
どの治療法が合うかは、症状の重さや生活環境によって異なります。
それぞれの治療法がどのようなものかを詳しく見ていきましょう。
薬物療法
薬物療法は薬の力を借りて、つらい強迫症状や不安をやわらげる治療法です。
薬物療法では、おもに選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)と呼ばれる抗うつ薬が用いられます。
SSRIは強迫症状と抑うつの両方に効果が期待できる薬です。[2]
脳の中には、感情のコントロールや衝動を抑える神経伝達物質「セロトニン」があります。
SSRIがセロトニンの働きを助けることで、何度も家の火元や鍵を確認するといった強迫症状をやわらげるのです。[3]
治療では医師が体調の変化を丁寧に確認しながら、少ない量から飲み始めます。
薬の効果を感じられるまでには個人差があり、数週間から2か月ほど時間がかかります。
焦らずに医師の指示を守り、服薬を続けることが回復につながるのです。

お薬のことで不安があったら先生に気軽に相談してくださいね
曝露反応妨害法
曝露反応妨害法は薬に頼らず不安と向き合う練習を通して、症状の克服を目指す心理療法です。
不安や恐怖を感じる状況に身を置き、その不安を消すためにしていた強迫行為をあえて行いません。[4]
たとえば「汚い」と感じるものに触れると不安になり、安心するまで何十回も手を洗ってしまうという症状があるとします。
治療として「あえてドアノブのような汚いと感じるものに触り、その後は手を洗わずに過ごす」という課題に取り組むのです。
最初は強い不安や不快感に襲われますが、時間とともに不安感が自然に弱まっていくのを実感できます。
この経験を繰り返すことで「強迫行為をしなくても大丈夫だ」と考えられるようになり、次第に不安が湧きにくくなっていくのです。
ただし、曝露反応妨害法を行うときは、医師やカウンセラーなど専門家のサポートのもとで進めてください。
rTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激法)
rTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激法)は、強迫性障害の新しい治し方のひとつです。
専用の機器を使って脳に磁気の刺激を与え、脳の活動を調整することで症状の緩和を目指します。[5]
椅子に座ったまま受けられる治療で、麻酔も必要ありません。
薬物療法で十分な効果が得られなかったときや、副作用で薬が使えないときの選択肢となります。
rTMS 療法は、抗うつ薬によって十分な効果が得られなかったうつ病患者さんの40〜50%に効果がみられたと報告されているのです。[6]
rTMS療法は2019年6月から一部の医療機関で保険適応で受けられるようになりました。[7]まだ新しい治療法のため実施している医療機関は限られていますが、治療の選択肢として検討しましょう。
下記の記事ではrTMS療法を詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
強迫性障害が治るきっかけの作り方
強迫性障害の症状をやわらげるきっかけの作り方には、次の3つがあります。
もちろん、これから紹介する方法がすべての人にあてはまるわけではありません。
できそうなものから、ムリのない範囲で試してみてください。
不安階層表を作る
不安階層表を作ることは、強迫性障害の症状をやわらげるきっかけ作りのひとつです。
作り方は、まずあなたが強い不安や不快感がある状況を想像し、そのときの気持ちを100点とします。
次に、その100点を基準にして、他の状況が何点くらいになるかを0〜100の間で点数をつけてみましょう。[4]
たとえば、汚れへの恐怖が強いときは下記のようにリストを作ります。
- 100点:公衆トイレの便座に座る
- 70点:電車のつり革を握る
- 50点:自宅のごみ箱に触れる
- 20点:部屋の床に落ちたものを拾う
不安を見える化することで、漠然とした恐怖の正体が明確になります。
あなた自身の状態を客観的に知るだけでも、こころが軽くなるでしょう。
完璧主義を手放す
強迫性障害が治るきっかけの作り方には、完璧主義を手放すことがあります。
強迫性障害の症状に悩む人は、物事を白か黒かで判断する完璧主義が隠れています。
完璧主義を手放し「まあ大丈夫だろう」という曖昧さを受け入れることを意識しましょう。
たとえば「ドアの鍵をかけた」という100%の確信が得られるまで、ドアの施錠を何度も確認してしまうとします。
そのときに「施錠したときの記憶はあるし、もし閉め忘れていても泥棒が入る可能性は低いだろう」と、あいまいな状態を受け入れてください。
考え方のクセをすぐに変えるのは難しいので、焦らずに「今日は少しだけ意識してみよう」くらいの気持ちで取り組むことが大切です。
下記の記事では強迫性障害が治るきっかけを解説しているので、あわせてご覧ください。
生活リズムをととのえる
生活リズムをととのえることは、強迫性障害の症状をやわらげるきっかけ作りのひとつです。
強迫性障害の症状に振り回されると、心身のストレスや疲労が溜まります。
とくに、家に引きこもりがちになったり昼夜逆転したりするなど生活リズムが乱れると、症状が悪化する恐れがあるのです。[8]
具体的には下記のポイントがありますが、まずは「意識してみる」ことから始めてみてください。
- 毎日同じ時間に起きて寝る
- 朝起きたら太陽の光を浴びる
- 日中に軽い運動を取り入れる
- 栄養バランスの取れた食事を3食摂る
規則正しい生活は、不安定なこころを支える土台となります。
すぐに完璧な生活を送ろうとするのではなく、まずは「いつもより10分早く起きる」のように、あなたができそうなことから始めてみましょう。
強迫性障害との向き合い方
強迫性障害の症状と付き合っていく上で、向き合い方の3つのポイントを紹介します。
- 強迫性障害について理解する
- 小さな目標を立てて達成感を得る
- 症状があらわれても自分を責めない
まずは、強迫性障害を正しく理解しましょう。
強迫性障害は、脳の問題が関係している病気であり、性格や意志の弱さが原因ではありません。症状や原因を知れば、不安がやわらぐきっかけになります。
症状があらわれたときは、自分を責めないように意識しましょう。
症状には波があるものと捉え、ムリに気分を変えようとせずあなたの状態をただ受け止めてください。
回復のモチベーションを保つために、達成できる小さな目標を設定しましょう。
「確認を10回から9回に減らす」といった達成しやすい目標を立て、できたらあなた自身をたくさん褒めてあげてください。
まとめ
強迫性障害のおもな治療法には、薬物療法や曝露反応妨害法、rTMS療法などがあります。
これらの治療と並行して、不安階層表の作成や生活リズムの見直しなどに取り組むと、回復を後押しするきっかけになります。
強迫性障害の症状は、ひとりで抱え込んでいるとつらくなるでしょう。
症状に悩んだときは主治医に相談することで、対処法が見つかります。
おおかみこころのクリニックでは毎日夜22時まで診察しているため、平日の仕事帰りでも受診できます。
来院予約は24時間受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。まずはあなたのお話を聞かせていただくことから、一緒に始めましょう。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]強迫性障害の臨床像・治療・予後 ー難治例の判定、特徴、そして対応ー,松永 寿人
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1150090967.pdf
[2]強迫性障害|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=MiyHEH6ZUZDxDeYX
[3]こころのクスリBOOKS よくわかる強迫症,有園 正俊,主婦の友社
https://amzn.asia/d/isirmPb
[4]強迫性障害(強迫症)の認知行動療法(患者さんための資料)|厚生労働省
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2015/153091/201516018B_upload/201516018B0018.pdf
[5]鬼頭伸輔先生に「反復経頭蓋磁気刺激療法(rTMS)」を訊く|公益社団法人 日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=62
[6]反復経頭蓋磁気刺激装置適正使用指針|日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/Guidelines_for_appropriate_use_of_rTMS_202404ver2.pdf
[7]治療抵抗性うつ病に対する rTMS 保険診療の 実施状況調査からみえてきた適切な普及にとっての 問題点と今後取り組むべき課題,髙橋 隼,松田 勇紀,鬼頭 伸輔,中村 元昭,伊津野 拓司,野田 賀大
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1260090589.pdf
[8]松永寿人先生に「強迫性障害」を訊く|公益社団法人 日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=22