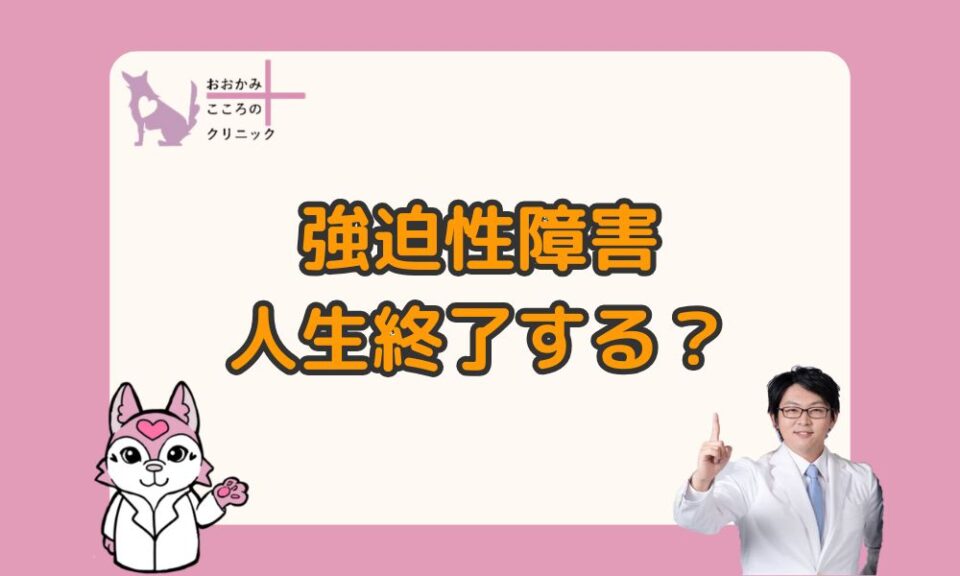「もうやめたい」と思っているのに、どうしても確認行為がやめられない。
そんな自分を責めて、ひとり苦しい思いをしていませんか?
「強迫性障害の症状かもしれない」と頭ではわかっていても、気になってしまうのは本当につらいものですよね。
不安が拭いきれない苦しみは、あなたの意志が弱いからでも性格のせいでもありません。
この記事では、強迫性障害の症状が苦しい理由や、あなたのつらい症状をやわらげる対処法を紹介します。
完璧を目指さなくてもこころを軽くできる方法を知ることで、回復への一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
強迫性障害の苦しみを長引かせる悪循環とは
強迫性障害で苦しい背景には、自分ではコントロールが難しい「悪循環」があります。
悪循環を理解することが、あなたの状況を客観的に捉え回復への糸口を見つけるための第一歩になります。
具体的には「強迫観念→不安→強迫行為→一時的な安心」という、以下の4つのステップがぐるぐると回り続けている状態です。
- 強迫観念:「手が汚れているかもしれない」「鍵を閉め忘れたのではないか」などの強い不快感をともなう考えが、繰り返し頭に浮かぶ。
- 不安:強迫観念によって、いてもたってもいられないほどの強い不安や恐怖、焦りが生まれる。
- 強迫行為:不安を打ち消すために、手洗いや確認など「やめたいのに、やめられない」行動をとってしまう。
- 一時的な安心:強迫行為を行うと、その瞬間だけは不安がやわらぎ、ほっとする。
4つのステップのうち「一時的な安心」が苦しみを長引かせる原因です。
強迫行為をすることで少しでも楽になる経験を繰り返すと、脳は「不安になったら、この行動をすれば大丈夫」と誤って学習してしまいます。[1]
その結果、また強迫観念が浮かんだときに強迫行為をせずにはいられなくなってしまうため、強迫性障害の苦しみが長引くのです。

悪循環から抜け出すために病院で相談してみるのもよいでしょう
強迫性障害で「辛い」「苦しい」と感じる3つの理由
強迫性障害の症状は、単に「気になる」だけではありません。背景には、ほかの人には理解されにくい、特有のつらさがあります。
強迫性障害を「つらい」「苦しい」と感じてしまうのは、以下の3つの理由からです。
それぞれの理由について解説していきます。
自分でも止められない
強迫性障害の苦しみで一番辛い点は「止めたくてもどうしてもやってしまう」ことです。
頭の中では「こんなことをしても意味がない」とわかっているにもかかわらず、強い不安からどうしてもその行動を止められないのです。
「わかっているのに、やめられない」という葛藤は「自分はなんてダメなんだろう」という自己嫌悪や無力感につながり、あなたを深く苦しめてしまいます。
周囲に理解されにくい
強迫性障害の症状は、他人からはわかりにくいことに加え特殊なものであるため、周囲に打ち明けにくい側面があります。
相談しても、家族や友人から「気にしすぎだよ」「考え方の癖じゃない?」といった言葉で片付けられ、つらい思いをした経験があるかもしれません。
あなたの抱える苦しみの深刻さが伝わらず、理解されない孤独感は、症状の苦しみ以上にあなたを追い詰めてしまいます。

理解されないから…と、ひとりで抱え込まずに先生に相談してくださいね
エスカレートしてしまう
強迫性障害の症状の多くは、時間とともにエスカレートしていく傾向があります。
強迫行為による一時的な安心感に脳が慣れてしまい、前と同じ行為では不安を打ち消せなくなっていくためです。
たとえば、最初は数回だった確認行為が数十回になったり、守るべき「儀式」のルールが複雑で厳しくなったりします。
症状がエスカレートするにつれて、学業や仕事、家事などの日常生活に大きな支障をきたすようになります。
その結果「このままでは人生がダメになってしまう」という強い焦りや絶望感につながってしまうのです。
強迫性障害でつらく苦しい症状をやわらげる対処法
先の見えない不安や苦しみの中にいると「もうどうしようもない」と感じてしまうかもしれません。
それでも、あなたのつらい症状を少しでもやわらげるために、今日からできることがあります。
具体的には、以下の3つの対処法です。
あなたのペースで、できそうなものから取り組んでみてください。
趣味や運動に没頭する
頭の中で同じ考えがぐるぐると回り続けてしまう状態から抜け出すには、意識を別のことに向けるのが有効です。
音楽を聴く、映画を観る、絵を描く、料理をするなど、あなたが「好きだな」と感じることに没頭する時間を作ってみましょう。
とくに、ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、強迫性障害の症状を緩和させる効果が報告されています。[2]
まずは「5分だけ散歩してみよう」という気持ちで、気軽に試してみてはいかがでしょうか。
深呼吸や瞑想でこころを落ち着ける
強迫性障害の症状で強い不安に襲われると、心拍数や呼吸などをコントロールしている自律神経のバランスが乱れがちです。
自律神経のバランスをととのえるためには、以下の2つの方法が有効です。
- 腹式呼吸
- お腹を意識して、ゆっくり深く息をする方法です。
息を吸うときにお腹をふくらませ、吐くときにへこませることで、こころと身体をリラックスさせる効果が期待できます。
- マインドフルネス瞑想
- 「今、この瞬間」に静かに意識を向ける、こころの練習です。
たとえば、自分の呼吸や身体の感覚に注意を向け、何か考えが浮かんできても、それを追いかけたり否定したりせず、ただ「考えが浮かんだな」と気づいて、再び呼吸に意識を戻します。
強迫性障害や抑うつ症状を緩和させる効果があります。[3]
2つの方法は、不安の波が押し寄せてきたときに、その場でできるお守りのような方法です。
自分の症状や感情をノートに書き出す
頭の中だけで同じ悩みを考え続けていると、ますます不安が大きくなってしまいがちです。
悩みや不安をひとりで抱え込まず、今感じている気持ちや頭に浮かんでいる考えを、ただノートに書き出してみましょう。
どのようなときに症状が出やすいか、自分のパターンを知るきっかけになります。
ある研究では、長い間ずっと不安な気持ちを抱えているとき、感情や思考を書き出すことで、それに振り回される状態から少し距離を置けるようになることがわかっています。[4]
「こんなことを考えた」「今、こんな気持ちでつらい」と文字にすることで、あなたの状況を少し客観的に見つめ直してみましょう。
強迫性障害の治療法
セルフケアを試しても症状がやわらがないときや日常生活への支障が大きいときは、専門家の力を借りることが大切です。
強迫性障害のおもな治療法には、心理療法と薬物療法があり、組み合わせて行うのが一般的です。
- 薬物療法
- おもにSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)という種類の抗うつ薬が用いられます。[5]
強迫観念の強さや不安感をやわらげます。
- 曝露反応妨害法(ERP)
- 強迫性障害に対する心理療法の中で、もっとも効果が高いとされている標準的な治療法です。[1]
カウンセラーと相談しながら、あえて少し不安な状況に挑戦し、強迫行為をせずに過ごす練習をします。
「儀式をしなくても大丈夫なんだ」と脳が新しい安心感を学習し、つらく苦しい悪循環から抜け出すことを目指します。
- rTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激療法)
- 磁気の力で脳の特定の部分を刺激し、脳の働きがスムーズになるようにととのえる治療法で、強迫性障害にも一定の効果が認められています。[6]
より詳しい治療法については、こちらの記事も参考にしてください。
rTMSについては、下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
まとめ
「やめたいのにやめられない」という葛藤や、症状が理解されにくい孤独感は、決してあなたのせいではありません。
強迫性障害のつらい苦しみは、一歩ずつ回復に近づけるよう取り組むことで、徐々に軽くしていけるものです。
まずはムリのない範囲でセルフケアを試しつつ「どうしてよいかわからない」「誰かに話を聞いてほしい」と感じたら、専門家に相談してみましょう。
おおかみこころのクリニックでは、夜22時までの診察やオンライン診療を行っておりますので、お気軽にご予約ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]強迫性障害(強迫症)の認知行動療法 マニュアル (治療者用) │厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000113840.pdf
[2]Bottoms L, Prat Pons M, Fineberg NA, et al. Effects of exercise on obsessive-compulsive disorder symptoms: a systematic review and meta-analysis. Int J Psychiatry Clin Pract. 2023;27(3):232-242.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36541901
[3]Riquelme-Marín A, Rosa-Alcázar AI, Ortigosa-Quiles JM. Mindfulness-based psychotherapy in patients with obsessive-compulsive disorder: A meta-analytical Study. Int J Clin Health Psychol. 2022 Sep-Dec;22(3):100321.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35892041
[4]Schroder HS, Moran TP, Moser JS. The effect of expressive writing on the error-related negativity among individuals with chronic worry. Psychophysiology. 2018;55(2):10.1111/psyp.12990.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8543488
[5]強迫症の診療ガイドライン│日本不安症学会・日本神経精神薬理学会
https://jpsad.jp/files/OCD_guideline.pdf
[6]Rehn S, Eslick GD, Brakoulias V. A Meta-Analysis of the Effectiveness of Different Cortical Targets Used in Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) for the Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Psychiatr Q. 2018;89(3):645-665.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29423665
- この記事の執筆者
- 片桐 はじめ
公認心理師、臨床心理士として精神科病院・クリニックで精神疾患を抱える方のカウンセリングや心理検査に従事。臨床経験をもとに、身近な例からわかりやすく説明する文章を心がけています。