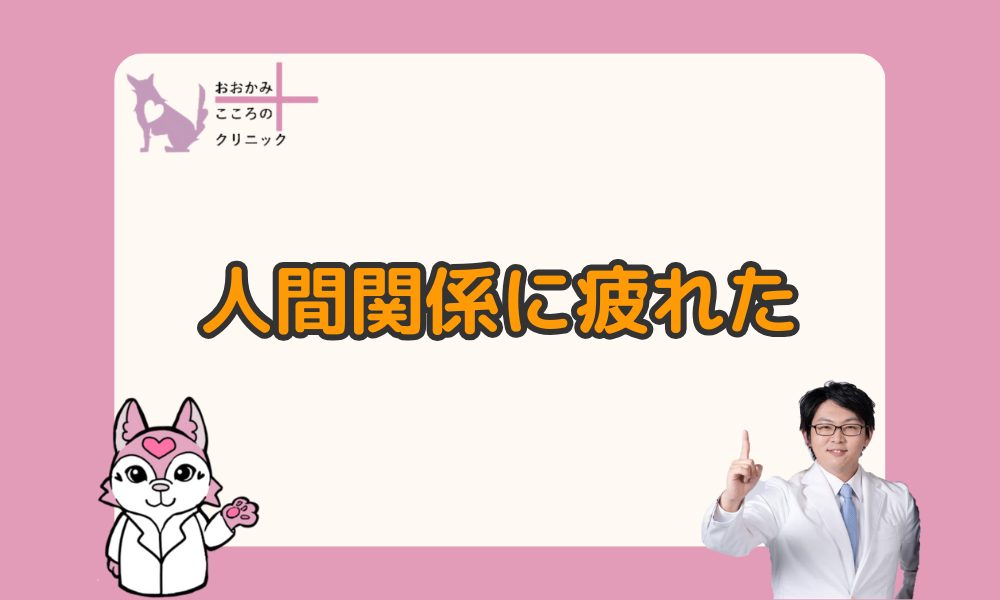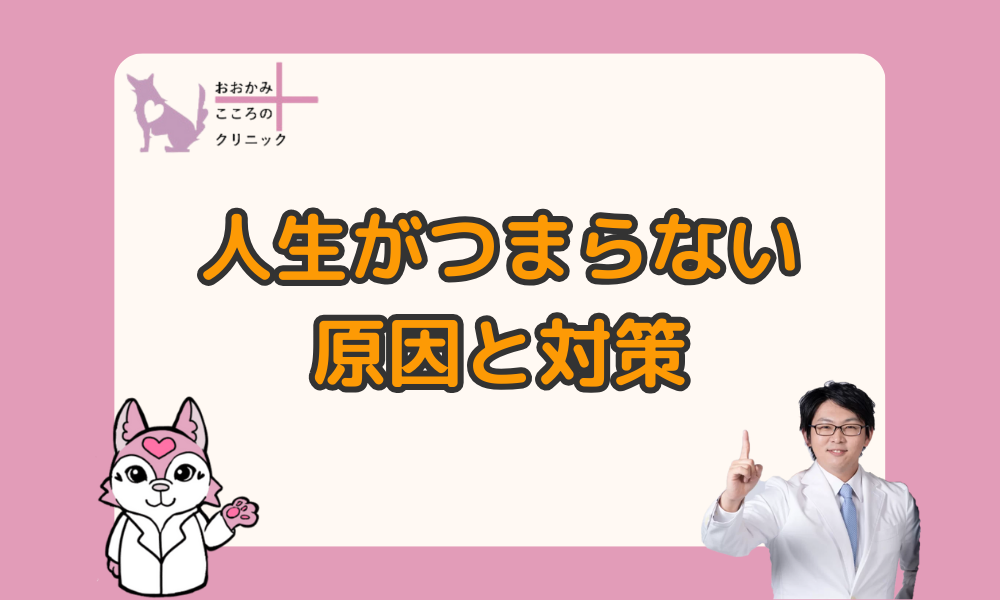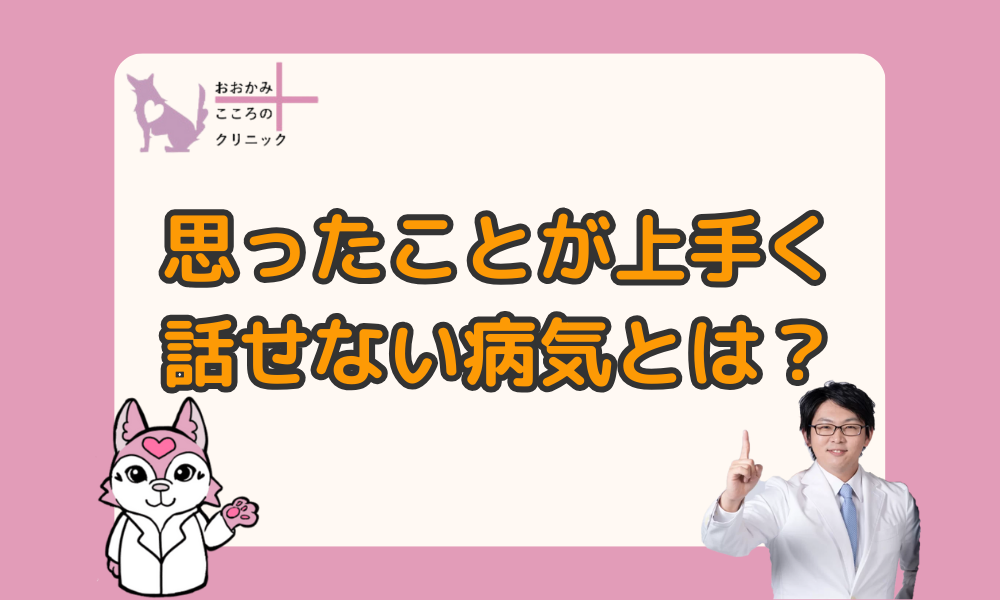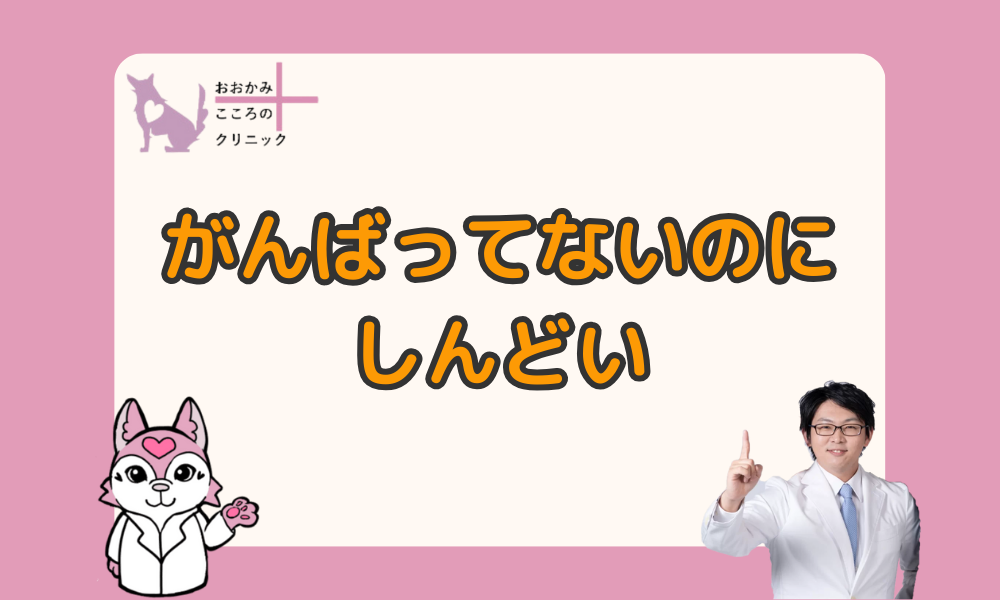「人間関係に疲れた」「もう、今日は人と関わりたくない」と思うことは誰にでもありますよね。
人間関係に疲れないようにするには、まずは自分の特徴を知り、人間関係に対する考えかたを見直すことが大切です。
この記事では、人と関わりたくないときの対処法や考えかたをご紹介します。
「もっと気楽に人と付き合いたい」という人はぜひ参考にしてくださいね。
この記事の内容
人と関わりたくない・人間関係に疲れたと感じる原因5つ
人と関わりたくない・人間関係に疲れたと感じる原因は5つあります。
順番に解説していきますね。
精神的にも体力的にも疲れ切っているから
長時間労働をしたり、仕事を押し付けられたりすると身体も心も疲れ切ってしまいます。
疲れやストレスが溜まると体力や心に余裕がなくなり、誰とも関わりたくないと感じてしまうのです。
疲れが回復しないと、慢性疲労や病気につながる可能性があるので注意が必要です。

疲れたときは何もかも投げ出したくなっちゃう
NOと言えないから
自分が嫌だと思っているのに断れないと、ストレスが溜まるものです。
とくに断るのが苦手な人は、断ると相手に悪い、失礼ではないかと思う傾向にあります。NOと言えないのが原因で、相手の無理な要求やお願いを受けすぎてしまう人もいるでしょう。[4]
その結果、ひとりで抱え込んでしまい自分自身が疲れ切ってしまうのです。
相手の言葉が気になってしまうから
相手の言葉が気になる人は、言葉の裏まで深読みしてしまいます。
「嫌味を言われたのかな」「それってどういう意味?」とネガティブに考えてしまうのです。
その結果、相手の言葉が気になり続けてしまい、次第に疲れてしまいます。
ぐるぐるとマイナス思考になってしまっている場合は、下記の記事もご覧ください。
相手にどう思われているか気になるから
自分がどう思われているか気になる人は、他人にマイナスなイメージを持たれたくない、否定されるのが怖いと思っています。
そのため、自信がない人が多く、なかなか自分の意見が言えません。
他人の目ばかり気にしてしまうので、本当の自分が出せなくなり結果的に疲れてしまいます。

まわりの目って気になりますよね💦
他人と比較してしまうから
他人と比較してしまう人も人間関係に疲れやすいです。
人はもともと、自分の能力を評価したいという思いを持っています。しかし、自分を客観的に評価できないときには、身近な人と自分を比べてしまいます。[6]
そのため、「周囲の人は自分よりすごいな……」と感じ、落ち込んでしまうのです。
人と関わると疲れてしまう人の5つの特徴
人と関わると疲れてしまう人の特徴は以下です。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
気を遣いすぎる
周囲に気を遣いすぎる人は、ストレスが溜まりやすく疲れやすい傾向があります。
自分の気持ちよりも人の気持ちを優先するので、ときには嫌なこともグッと我慢してしまうのです。
気を使いすぎる人の性格は、基本的に優しく心配しすぎる面もあります。
その性格ゆえ、自分自身が消耗し気疲れしていることも珍しくありません。

優しい人なので、周りに人が集まってくることもあるでしょう
感受性が強い
感受性の強い人は、相手のちょっとした感情にも左右されてしまいがちです。
場の空気を読み取る能力が高いので、周囲の変化にも敏感です。
上司がなんとなく不機嫌だと、「原因は自分かもしれない」と思い込んでしまいます。
その結果、委縮したり顔色を伺ったりして気疲れしてしまうことも少なくありません。
コミュニケーションが苦手
コミュニケーションが苦手な人は会話自体が苦手なので、とっさに話を振られても何を話したらいいかわかりません。[5]
話すことに自信がなく、急に話しかけられると緊張してしまうのです。
会話がなかなか続かないので、「つまらない人だと思われたかも」と落ち込んでしまうこともあるでしょう。
一人行動が好き
一人行動が好きだという人は、他人に干渉されたり意見を押し付けられたりするのが苦手です。
一人でいたほうが楽、面倒くさい人間関係は避けたいと思っているからです。
仲良しグループで出かけたり、毎日ランチに行ったりするのは、もってのほか。
人に意見や行動を合わせるのが苦手なので、息苦しく感じてしまうでしょう。

一匹オオカミみたいでカッコいいですね
過去の人間関係がトラウマ
過去の人間関係でトラウマになった人は、「またこうなるかもしれない」と恐れて人と親しくなるのを避けようとします。
そのため過度に緊張してしまい、人間不信になりやすい傾向があります。
「また昔のようになったらどうしよう」と、恐怖を感じてしまうのも特徴です。
人と関わりたくない・疲れたと感じたときの3つの対処法
人と関わりたくない・疲れたと感じたときの対処法を3つご紹介します。
具体的な方法も解説しているのでぜひ参考にしてくださいね。
一人の時間を持つ
人と会って疲れたら、人と会わずに一人きりで過ごし、心と体を労わってあげましょう。
心身共に疲れていると人と会う元気はおろか、やる気が起きず、何もしたくないと感じます。
一人になる時間は、誰にも気を遣わない自分自身と向き合う大切な時間です。
美容室に行って気分を変えたり、マッサージに行ったりするのもいいですね。睡眠時間が十分に取れていない人はまず、睡眠をとり、身体を十分に休めましょう。
SNSから離れる
余裕がないときや、疲れているときはSNSから離れましょう。
『SNS疲れ』という言葉があります。
自分の投稿に反応があるか、フォロワーが減っていないかなど、ソワソワした経験はありませんか?
そのようなときは思い切って通知を切ってみたり、アプリ自体を消去して簡単にログインできないようにしたりするのもよいでしょう。
他人の投稿に嫌気がさしたり落ち込んだりする場合は、ミュート機能を使って自分の目に触れないようにするのも効果的です。
疲れた自分がさらに消耗しないように、SNSと適度な距離で付き合うことが大切です。

SNSとは無理なく上手く付き合いましょう
距離を上手にとる
特定の関わりたくない人がいる場合は、距離を上手にとりましょう。
嫌な思いをしながら、付き合い続けるのは苦痛でしかありません。
プライベートなことを聞かれたら、「どうですかね〜」と笑顔でとぼけてみせるのも効果的です。
以下の距離を取る方法も参考にしてくださいね。
- 同じ空間にいる時間を極力減らす
- 相手から話しかけたら話す
- 自分からは話しかけない
- 敬語を崩さない
- 必要なこと以外、連絡はしない
人間関係の疲れを溜めない5つの考えかた
他人を変えることはできません。
しかし、考えかたひとつで自分の心を軽くすることはできます。
ここでは、人間関係に疲れないようにする考えかたを5つご紹介します。
人間関係に疲れて自己嫌悪になる必要はありません。下記の記事では自己嫌悪の対処法を紹介しています。合わせてご覧ください。
いい人になろうと思わない
人間関係で疲れやすい人は、自分の中で人間関係の線引きをしておくことをおすすめします。みんなにとっていい人になろうとすると、自分を見失ってしまいます。
「職場は仕事をしに来る場所、同僚と仲良くなれなくてもかまわない」くらいのスタンスで取りかかりましょう。
仕事上、お互いをフォローすることは大切です。しかし、断れないがために仕事を安請け合いしてしまうと自分自身が疲弊してしまいます。
誰にとってもいい人になろうとせず、ときには断ることも大切です。

自分が疲れないぐらいにしましょうね
相手に期待しない
相手が期待通りの行動を返してくれないと失望したり、不満に思ったりすることがあります。
しかし、「自分がやりたいからやった」と思えば、相手から反応がなくても気になりません。
無意識に「あの人の仕事を手伝ってあげたのだから、きっと私の仕事も手伝ってくれるはず」なんて思ってはいませんか?「お返しをするのが当たり前」と思わず、「返してくれたらラッキー」くらいのスタンスで日々を過ごしましょう。
悪口には参加しない
人が集まって悪口を言っていると、自分の悪口を言っているのではないかと思い余計に疲れてしまいますよね。
悪口やネガティブな言葉は人を疲れさせるので、参加しないのが一番です。
しかし、敵だと思われたくなくて、いつの間にか一緒に悪口大会に参加していることはありませんか。悪口を言いたがる人が近くにいる場合は、以下のことを試してみてくださいね。
- 悪口が始まったら、トイレなどを理由に自然と席を外す
- 「ふーん」や「そうなんですね」と当たり障りのない反応をする
- 悪口が聞こえてきたら耳栓をする
- 「そういえば……」と話題を変える
スルースキルを身に付ける
スルースキルとは言葉の端々をいちいち重く受け止めず、サラリとかわすスキルのことです。
相手の言葉に消耗しないためには言葉を深読みせず、表面だけで受け取ることが大切です。
たとえば、「あなたは○○だからいいよね」や「本当に天然だよね」と言われたときには「よく言われます」「そうなんです〜」と笑顔で返してしまいましょう。
コミュニケーションは受け止める側の解釈でずいぶん変わります。
自分の心を守るために、言葉を深読みしないスルースキルを身に付けましょう。

スルースキルは大切です✨
自己中心になってみる
ここでいう自己中心は、自分の気持ちに素直になり自分の気持ちを大切にすることです。
自分はどうしたいかをはっきりさせておくと、他人に振り回されなくなります。
人に疲れてしまう人の主語はいつだって、他人。
「自己中心だなぁ」と思う人は、人の顔色を気にすることなくのびのび生きている人が多いはず。
あなたが思う自己中心的な人を、観察してみるのもいいかもしれませんね。
人と関わりたくないと感じる病気と気質
「人と関わりたくない、恐怖すら感じる」という場合は、もしかしたら病気や自分の気質が関係しているのかもしれません。
ここでは、人と関わりたくないと感じる病気や気質について解説します。

気になる症状があったら、お気軽にご相談くださいね
うつ病
うつ病の特徴は気持ちの落ち込みや、何もする気になれないなど、意欲が低下する病気です。
人と話す気力も湧かないので、引きこもりがちになることも珍しくありません。
食欲不振(あるいは増進)や、眠れない、生気がないなどの身体面の症状も見られます。
双極性障害
双極性障害はハイテンションが続く躁状態と、気持ちが落ち込むうつ状態が交互に訪れます。
躁状態は自信に満ち溢れているため、悩むことはありません。
しかし、うつ状態に突入すると、躁のときとは人が変わったように落ち込みます。
人と関わるどころか「生きることすら疲れた」と思い込むこともあるのです。
適応障害
適応障害はある一定のストレスに対応しきれなくなり、「不安」「動悸」「息切れ」「不眠」などを発症します。
ストレスの原因が人間関係だった場合、その人間関係から離れると症状はおさまります。
社会不安障害
社会不安障害は大勢の人に注目されたり、見られたりすることを苦痛に感じる病気です。[1]
面識のない人との会話や、上司など緊張する人との会話でも同様です。
「発汗」や「顔の紅潮」「腹痛」「ふるえ」などの症状があらわれるため、できるだけ大勢の人と関わるのを避ける傾向があります。
回避性パーソナリティ障害
回避性パーソナリティ障害は、自分が好かれている確証が得られないと他人との交流を拒みます。[2]
他人から嫌なことを言われたり、否定されたりすることに耐えられないからです。そのため、人間関係を新しく構築したり、新しく活動に参加したりすることを意図的に避けようとする傾向があります。
HSP
HSP(ハイリーセンシティブパーソン)とは感受性が強く、人一倍繊細過ぎる人のことです。[3]
病気ではなく、その人の気質ともいわれています。
他人の言葉や雰囲気に影響されやすく、ささいな変化にも気づくため、本人は生きづらいと感じます。
まとめ
社会で生きる以上、人間関係は切っても切り離せません。
「人間関係に疲れた」や「人と関わりたくない」と思うことは誰でもあり得ます。
「疲れた」と感じたらまずは、一人の時間を作ってゆっくりと休みましょう。自分の考えかた次第で人間関係のとらえかたはグッと楽になります。
しかし、「人と関わるのが怖い」「人が怖くて会社に行けない」という場合は、病気が潜んでいる可能性があります。そんなときは小さなことでもかまいませんので、当院にご相談くださいね。
24時間予約受付中
(参考サイト)
[1]不安障害|こころもメンテしよう|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_02.html
[2]回避性パーソナル障害|MSD マニュアル
[3]『HSP』をご存知ですか?|生駒市
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000028156.html
(参考文献)
[4]日本人は「NO」と言えないか|坂本 恵
https://kanagawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2222/files/%E9%BA%92%E9%BA%9F7%E5%8F%B7-04.pdf
[5]関わりを回避する若者たち|—1997年調査と2019年調査を比較しながら—|岡林 春雄
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tokusimabunriu/103/0/103_27/_pdf/-char/ja
[6]対人比較が生じる仕組みについての心理学的検討|吉川裕子・佐藤安子https://kbu.repo.nii.ac.jp/record/915/files/KJ00007415959.pdf
- この記事の執筆者
- 小久保有希
医療ライター。看護師経験15年。4年間精神科に勤務し、病棟・訪問看護に携わる。相手の気持ちに寄り添う記事が得意。