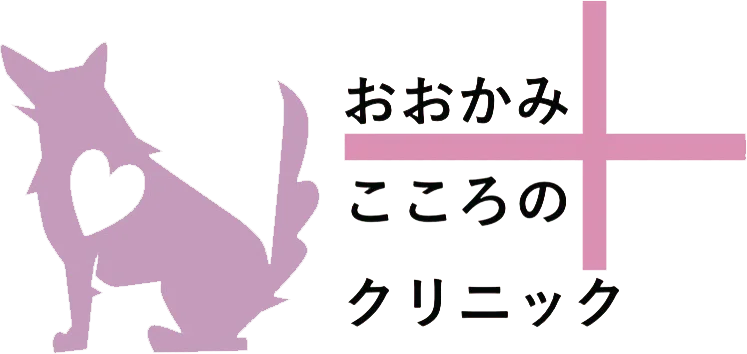「聴覚情報処理障害(APD)の可能性がありますと言われても、どうやって治したらよいの?」
「初めて聞く病気だし、具体的な治し方が知りたい」
APDと診断されても、治し方に悩みますよね。
APDは聴覚自体に異常がないにもかかわらず、聞き取りができなかったり耳のみでの理解が難しかったりします。
具体的な治し方を知ることで、コミュニケーションストレスをやわらげることができるでしょう。
この記事では、APDの具体的な治し方や自分でできる工夫について詳しく解説します。
APDの治し方の参考になり、前向きな気持ちで過ごせるきっかけになりますと幸いです。
APDの診断テストについては下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
この記事の内容
APDの治し方
APD自体を治すための、はっきりとした治療法は確立されていません。
そのため、どのような状況で困っているのかを把握し、適切に対応することが大切です。[1]
現段階では、以下の4つの治し方が有効とされています。[2]
それぞれ詳しく解説します。
環境をととのえる
APDは雑音が多い環境での聞き取りが難しいため、できるならば静かな環境をととのえることが大切です。
しかし、静かな環境を作れないことは多くあります。
そのようなときは、以下のような環境をととのえてみるとよいでしょう。
- 話し相手との距離を縮める
- 話す前に声かけをしてもらう
- 会議や授業では資料を用意してもらう
会話を始める前に声かけをしてもらうことで、会話に意識を向けることができます。
また、会社や学校では、会議の資料や板書など目で見て読み取れる情報を併用するのもよいでしょう。会議の際に、議事録作成者の隣の席に座るのも有効です。
静かな環境をととのえることが難しい状況でも、会話に意識を向けたり視覚情報を併用したりするなど、聞き取りやすい環境をととのえることが大切です。
機械やアプリなどを活用する
APDは聞き取りが困難なため、聞き取る情報を強くしたり視覚化したりする工夫が必要になります。
そのために用いるものは以下のとおりです。[3][4]
- 補聴器
- 補聴援助システム
- ノイズキャンセリングイヤフォン
- 情報を視覚化する機能やアプリ
ある研究では、どのような補聴器がAPDに有効か報告されています。
効果なし:無指向性補聴器(360度すべて同じ感度で聞こえやすくする)
効果あり:騒音抑制機能や指向性機能(前からの音を聞こえやすくする)のついた補聴器を約10dBに調節
ただし、聴覚は正常であるため、補聴器の導入は慎重に行う必要があります。
ノイズキャンセリングイヤフォンは、会議や携帯のマイクとして活用すると、周囲の雑音を遮ることができ会話が聞き取りやすくなるでしょう。
情報を視覚化する機能やアプリの活用も有効です。音声を視覚情報に変換してくれるため、聞き取りが難しい状況でも目で見て読み取ることができるようになります。

あなたが使いやすいものを見つけてください
聞き取りトレーニングをする
聞き取りのトレーニングは、子どもと大人で方法が異なります。[3]
子どものトレーニングでは、語彙力を高めることが大切です。
知っている語彙が多いほど、聞き取れた会話から推測して理解することができるため、語彙力ドリルや本を読んで語彙力を高めましょう。
大人の聞き取りトレーニングでは、聞き取る力を高めます。
話を聞くための集中力を鍛える方法は、以下のとおりです。
- 雑音の中でも定期的に自分から会話に注意を向ける
- テレビや音楽を活用して聞くことへの自信をつける
- 流行りの言葉や語彙もすぐに理解できるように新聞やニュースを見る
このように、日常生活の中でもトレーニングできるため、できそうなものから取り組んでいきましょう。
こころのケアをする
APDは「聞こえない」のではなく「聞き取れない」ため周囲の人に理解されにくく、トラブルに繋がることもしばしば見られます。[3]
たとえば、何度も聞き返して友人にイヤがられたり、聞き取りミスで業務上の問題が発生し上司に怒られたりすることも少なくありません。
何度も繰り返すうちに「どうせ聞き取れないし」と人とのかかわりを避けたり、人とかかわることに強い不安を感じたりするのです。
不安を抱えたまま生活するのではなく、以下のように不安をやわらげましょう。
- 聞き取りが難しい状況を受け入れ、生活しやすくなる工夫をする
- 家族や職場の同僚、学校の友人にAPDの症状を説明し理解を求める
- 不安が長く続くときは専門家のカウンセリングを受けるか考える
不安を抱えたまま生活をしていると、APDだけでなくうつ病や不安障害などのこころの病気を発症する可能性もあります。
「聞き取りにくいことで生活がつらい」と思ったら、あなたができる工夫をしてみましょう。
この記事の後半では、自分でできるAPD治し方の工夫を紹介しています。こちらからすぐに読むこともできます。
APDを治すための考え方
APDを治すはっきりとした治療法は確立されていません。
しかし、聞き取りが難しくても過ごしやすいようにするポイントはあります。
以下のようなことを意識して、生活を送ることが大切です。[3]
- 特性を理解する
- 得意なことを活かす
- 自分でできる対処法や手段を考える
- 会社や日常生活の中で理解してもらえる方法を考える
雑音下で聞き取りにくいのは、あなたのせいではありません。APDという病気の特性であることを理解しましょう。
また、聞き取りにくい状況でも、あなたが得意とすることや自分でできる工夫を考え生活しやすいように調整することも大切です。
たとえば、会話をする際はジェスチャーを取り入れてみると、相手も合わせてジェスチャーをしてくれるかもしれません。
「聞き取れない」「分からない」にばかり目を向けずに、「この状況を変えるにはどうしたらよいのか」に目を向けてみてください。

困っている状況を変える方法を考えましょう!
「この悩みどこに相談すればよいか分からない」と悩んだときは、新宿・秋葉原・横浜・大阪梅田・博多にあるおおかみこころのクリニックにご相談ください。
オンライン診療も行っており、自宅にいながら医師の診察を受けられ、利便性のよい立地で通院しやすさも大切にしています。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
自分でできるAPD治し方の工夫
APDは、はっきりとした治し方が分かっていないため、自分でできる工夫をして日常生活を送っていくことが大切です。
以下のような場面では、自分でさまざまな工夫ができます。
それぞれ具体的に解説しますので、できそうなものから試してみてください。
自宅でできる工夫
自宅では、以下のような工夫ができます。[4]
- テレビを字幕表示にする
- 大切なことは何度も繰り返し確認する
- 体調を崩さないように規則正しい生活を心がける
APDの方は耳で聞き取るよりも目で見た方が理解しやすいため、テレビは字幕表示の設定をするとよいでしょう。
あなた自身の体調管理も大切です。夜更かしをしたり朝食を抜いたりすると、昼間に頭がぼーっとして仕事や勉強に集中できなくなります。その結果、さらに周囲の話を聞き取りにくくなるのです。
家族とできる工夫
家族に協力してもらうことで、以下のような工夫ができます。[4]
- 静かな環境をととのえてもらう
- 話しかけるときは、先に名前を呼んでもらう
- 3人や4人で話すときは話が被らないように順番に話してもらう
掃除機をかけているときや、食洗器が回っているときに話しかけられると、話を聞き取りにくくなります。そのため、一旦止めて静かな環境で話しかけてもらう工夫をするとよいでしょう。
ほかにも、数名で話すときは話すタイミングが被らないようにしてもらうことで、一人ひとりの話が聞き取りやすくなります。
このように、家族に協力してもらうことで、コミュニケーションストレスをやわらげることができるのです。
職場や学校でできる工夫
職場や学校では、以下のような工夫ができます。[4]
- APDであることを事前に伝える
- 話が聞き取りやすい静かな席に移動する
- 文字変換アプリやレコーダーを活用する
上司や先生に、事前にAPDであることを伝えると配慮してもらえることがあります。
たとえば、扉付近の席で廊下の音が入ってくるなら静かで話が聞き取りやすい席に移動したり、学校では先生に近い前の方の席に替えてもらうとよいでしょう。
ほかにも、音声を文字に変換する携帯のアプリを用いたり、レコーダーで録音して後で聞き返せる工夫も大切です。
まとめ
APDのはっきりとした治し方は、確立されていません。しかし、聞き取りにくい状況を乗り越えるためにできる工夫は多くあります。
APDを治すには以下の4つが大切です。
- 環境をととのえる
- 機械やアプリなどを活用する
- 聞き取りトレーニングをする
- こころのケアをする
聞き取りにくい状況で生活を送っていると、こころが疲れてしまいます。
自分で工夫することも大切ですが、工夫する元気もでないときもあるでしょう。どうしたらよいのか悩んだら、おおかみこころのクリニックへお気軽にお問い合わせください。
オンライン診療も行っておりますので、忙しく来院が難しいときは活用してくださいね。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【参考文献】
[1]聴覚情報処理障害(auditory processing disorders, APD)の評価と支援|小渕 千絵
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlp/56/4/56_301/_pdf
[2]4)LiD/APD の支援|岡山大学 岡山大学病院 聴覚支援センター 片岡 祐子https://apd.amed365.jp/doc/202403-seika.pdf
[3]LiD / APD診断と支援の手引き(2024 第一版 )
https://apd.amed365.jp/doc/202403-seika.pdf
[4]当事者の方へ対処法-補助機器の活用
https://apd.amed365.jp/party/party05.shtml
- この記事の執筆者
- 柚木ハル
作業療法士。精神科16年の臨床経験を生かして執筆を担当。現在は訪問リハビリに従事しながら幅広いジャンルにて執筆中。