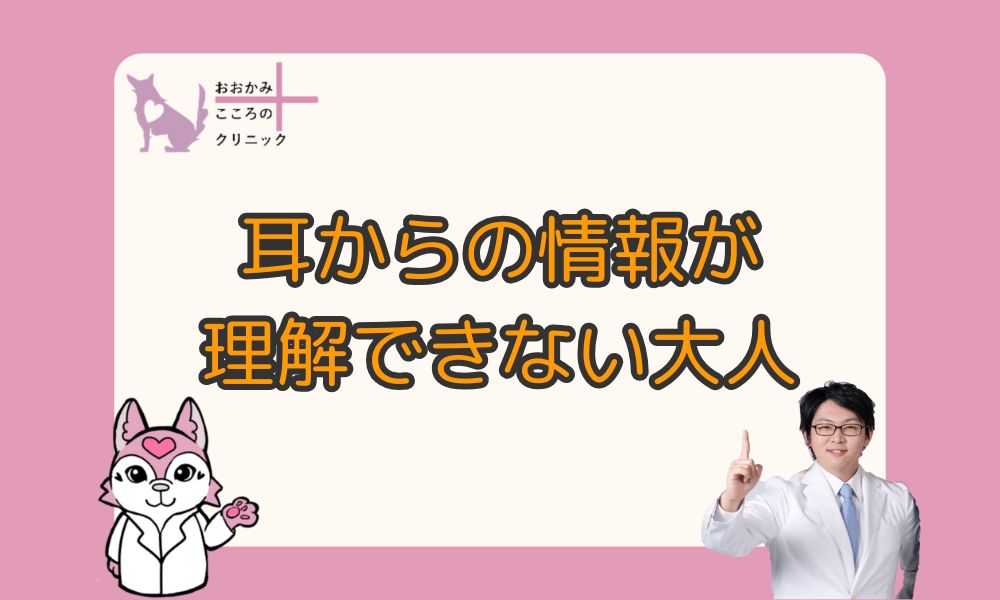「話は聞こえているのに、内容が理解できない」
「人の説明が理解できず、何度も聞き返してしまう」
このように、大人になってからも「耳からの情報が理解できない」とコミュニケーションにストレスや不安を感じていませんか。
その症状は、もしかすると聴覚情報処理障害(APD)かもしれません。
どのような状況で耳からの情報の理解が難しいかを考え、工夫することが大切です。
この記事では「耳からの情報が理解できない」と感じる大人のために、背景にある理由や、他の人がどのようなことに悩んでいるのか、日々の生活を少しでもラクにするための対処法などを解説します。
人とのコミュニケーションに不安やストレスを感じずに、以前のように過ごせるきっかけになりますと幸いです。
耳からの情報が理解できない理由
話は聞こえるけど、聞き取れなくて理解ができない状態は、聴覚情報処理障害(APD)かもしれません。
APDにははっきりとした診断基準はありませんが、以下のようなときに疑われます。[1]
- 聴力に異常がない
- APDの症状がある
- 耳からの情報をどのように処理するのかを検査して1つ以上の低下がある
APDの診断については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
また、APDのように耳からの情報が理解できない大人には、以下のような背景要因があります。[2]
それぞれ詳しく見ていきましょう。
発達障害
耳からの情報が理解できずに悩んでいる方の多くは、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害があることが分かっています。
自閉スペクトラム症では、中枢統合(ものごとを全体的に把握する能力)が弱いため、耳からの情報が理解ができないことがあります。
注意欠如・多動症では、注目を向けたり集中を持続したりすることが苦手な特徴があり、聴覚情報はとくに影響されやすいのです。
APDと発達障害の関係については、下記の記事で詳しく解説します。
認知的な偏り
耳からの情報が理解できないのは、記憶力や注意力の低下のせいかもしれません。
APDの背景因子は複雑で、記銘力検査(新しいことを記憶する、体験したことを思い出すなどの検査)で低下が見られたり、原因不明の方もいたりします。
ものごとの捉え方の偏りや記憶力、注意力の低下により、日常生活で聞き取りの困難さが生じていると考えられるのです。
心理的な要因
精神疾患や睡眠障害を抱えている方も、耳からの情報が理解できないことがあります。
適応障害やうつ病などの精神疾患では、抑うつ気分により頭がぼーっとしてしまい、人の話を理解できない状態になりがちです。
また、睡眠障害による寝不足で覚醒状態が悪いときも、人の話を理解しにくいことがあります。
耳からの情報が理解できないのは、疲れやストレスなど、そのときの精神面や覚醒状態が原因かもしれません。

小さなストレスも積み重なると、大きなストレスになります。
早めに発散しましょう。
耳からの情報が理解できない大人の悩み
639人の聴覚情報処理障害(APD)当事者を対象としたアンケートで、聞き取り困難で困っている人の割合は、20代の女性が71%ともっとも多いという結果がでています。[3]
就職やアルバイトをきっかけに、職場での電話や指示の聞き取りが難しくなり受診されるケースがほとんどです。
耳からの情報が理解できない大人は、以下のような症状で悩んでいます。[4]
- 耳のみでの指示理解困難:52.6%
- 雑音下での聞き取り困難:31.6%
- 複数人との会話困難:10.5%
耳のみでの指示理解が難しく悩んでいる方がもっとも多く、周囲に相談しても理解されずに苦しんでいる方は少なくありません。
たとえば、「集中してないだけだ」や「やる気がないだけだろ」など心ない言葉を浴びせられた経験がある方もいます。
身近に同じ悩みを持つ方がおらず、ひとりで抱え込んでしまうことも多いでしょう。
聞き取りが難しいなら耳鼻科の受診が第一ですが、聞き取れないことによる職場の人間関係でストレスを抱えているなら、おおかみこころのクリニックにご相談ください。一緒に解決方法を考えましょう。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
耳からの情報が理解できない大人が向いている仕事
耳からの情報が理解できないなら、以下のような仕事が向いているでしょう。
- 視覚情報が多い仕事:ライター、デザイナー、プログラマー
- 静かな環境で働ける仕事:在宅ワーク、経理、会計、図書館や博物館のスタッフ
- コミュニケーションが少なめな仕事:技術職、工場作業員、物流系の仕事
視覚情報が多い仕事では、メールやチャットなどの文字を使ったコミュニケーションが多いため耳での情報が理解できなくても働きやすいでしょう。
静かな環境で集中できる仕事は、聞き取りを邪魔する騒音がないため、聞き取りに集中しやすい環境といえます。また、耳からの情報が理解できないなら、人とのコミュニケーションが少なめな仕事を選ぶことも1つの手です。
技術職や作業員は黙々と作業に取り組むことが多いため、作業中のコミュニケーションによるストレスも少なくてすむでしょう。

在宅ワークできるか、今の職場に確認するのもよいでしょう!
耳からの情報を理解できないときの対処法
耳からの情報が理解できないときは、以下の方法を試してみてください。[5]
- 話す前に声をかけてもらう
- 話が聞き取れないことを周囲に伝える
- ノイズキャンセリング機能付きイヤフォンを使う
話す前に名前を呼んでもらったり肩を叩いてもらったりすると、話に注目できるため理解しやすくなります。
事前に上司や同僚に症状を伝えることで、電話対応を避けられたり静かな席に移動させてもらえたりなどの配慮をしてもらえるでしょう。
周囲の雑音が気になり話が聞き取れない状況を防ぐためには、ノイズキャンセリング機能の付いたイヤフォンが有効です。
下記の記事では、環境調整や自分でできる工夫などさまざまな治し方を詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
まとめ
「耳からの情報が理解できない」と感じる大人は、聴覚情報処理障害(APD)かもしれません。
APDには以下のような背景があります。
- 発達障害
- 認知的な偏り
- 心理的なストレス
職場でのコミュニケーションに困難を抱え、ストレスや孤立を感じる方も少なくありません。あなたに合った仕事を選んだり周囲へ配慮をお願いしたりすることで、日常生活のストレスを軽くすることができるでしょう。
ほかにも、ノイズキャンセリング機能付きイヤフォンの活用や、聞き取れないことを素直に伝えることも有効です。
まずはあなたの状態を知り、ムリのない方法で生活をととのえましょう。
耳からの情報が理解できずにストレスを感じたら、おおかみこころのクリニックへお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]聴覚情報処理障害(APD) |松 本 希
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibi/66/5/66_190/_pdf/-char/ja
[2]聴覚情報処理障害(auditory processing disorders, APD)の評価と支援|小渕 千絵
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlp/56/4/56_301/_pdf
[3]当事者ニーズに基づいた聞き取り困難症(LiD)/聴覚情報処理障害(APD)研究の現状と展望|阪本浩一
https://www.jstage.jst.go.jp/article/audiology/66/6/66_511/_pdf
[4]聴覚情報処理障害(Auditory processingdisorder, APD)の現状と対応|小渕 千絵
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shonijibi/40/3/40_225/_pdf
[5]対処法-人とのかかわり・日常の工夫
https://apd.amed365.jp/party/party04.shtml
- この記事の執筆者
- 柚木ハル
作業療法士。精神科16年の臨床経験を生かして執筆を担当。現在は訪問リハビリに従事しながら幅広いジャンルにて執筆中。