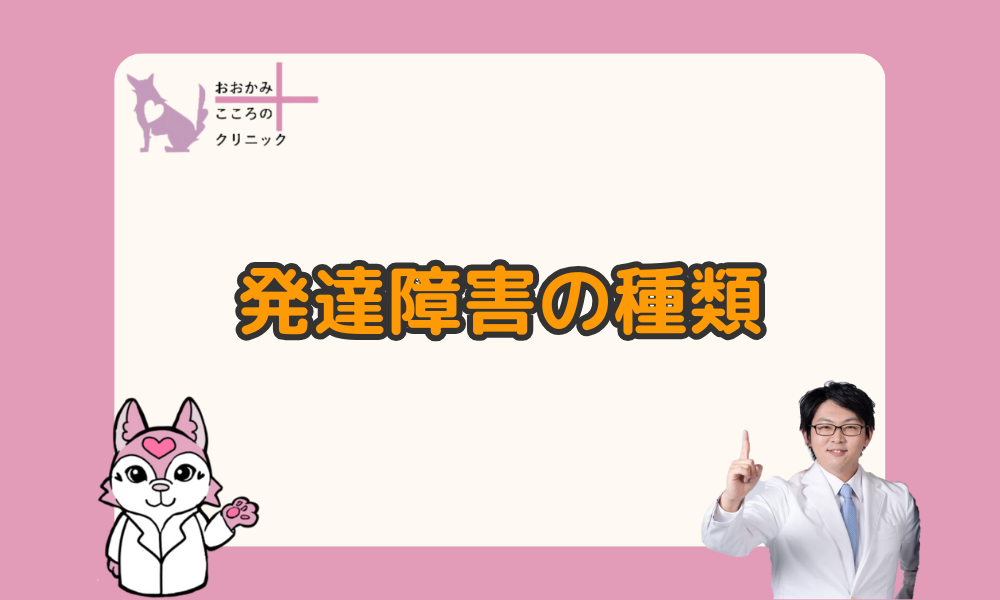「どうして伝わらないの」
「なぜ何度も聞き返すのかな」
子どもとやり取りをしているときに、話を聞きとれているのか違和感を得ることはありませんか。
耳鼻科を受診しても聴力に異常がないならば、発達障害や聴覚情報処理障害(APD)が疑われるでしょう。
この記事では、APDと発達障害の違いやAPDを併発しやすい発達障害について解説します。
APDの子どもとの具体的なかかわり方や、過ごしやすくなる工夫も紹介します。子どもに合った支援や対応を知るきっかけになりますと幸いです。
APDと発達障害
APDと発達障害の違いを知るために、まずはAPDと発達障害について知っておく必要があります。
APD
聴覚情報処理障害(APD)は、聴力に異常がないにもかかわらず、話を聞いたり理解したりが難しい状態です。
APDでは、以下のような症状が現れます。
- にぎやかな所で話が聞き取りにくい
- 早口や小声で話されると分からない
- 一度の指示で聞き取れず何度も聞き返す
- 長い話は注意して聞いても理解できない
APDにはっきりとした診断基準はありませんが、耳からの情報をうまく処理できていないことが原因と言われています。
APDの診断に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
発達障害
発達障害は生まれつき脳の働き方に特徴があり、ものごとの捉え方や行動パターンに違いが生じることで、日常生活で戸惑いを感じやすい状態です。[1][2]
自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)、注意欠如・多動症(ADHD)などがあり、注意力やコミュニケーション、行動などそれぞれ異なる特徴が見られます。
また、発達障害と聴覚障害を併発している子どもの割合は高く、全国の聾(ろう)幼稚園部では発達障害とその傾向の子どもが約19%いると言われています。[3]
発達障害については下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
APDと発達障害の違い
APDと発達障害の違いは以下のとおりです。[2][4]
| APD | 発達障害 | |
|---|---|---|
| 原因 | 耳からの情報処理の問題 | 脳の発達 |
| 聴力 | 正常 | 低下することもある |
| 特徴 | 言葉の聞き取りや理解が苦手 | 注意力・コミュニケーション・行動など幅広い困りごと |
| 重なり | 発達障害を併発することもある | APDに似た症状が生じることもある |
APDは、耳から入った情報をうまく処理できず聞き取れないために生じます。
一方で、発達障害は生まれつき脳の発達に問題が生じている状態です。
発達障害では、会話に集中できなかったり、雑音の多い環境が苦手だったりすることで聞き取れていない可能性もあります。

違いを知ることで、適切なサポートをすることができます
しかし、APDと発達障害は併発することも多いと言われているため、次で詳しく解説します。
APDと併発しやすい発達障害
APDと併発しやすい発達障害は以下のとおりです。[4]
・自閉スペクトラム症(ASD)
・注意欠如・多動症(ADHD)
自閉スペクトラム症をはじめとする発達障害では、苦手な音があったり雑音が多い環境で疲れやすかったりと、耳からの刺激に敏感という特徴があります。
注意欠如・多動症では、会話に集中できずに聞き取りが難しく、APDを併発するケースが多いと言われています。[4]
ただし、APDの症状が見られても必ず自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症であるとは限りません。
どのような症状で日常的に困っているのかを、主治医とともに丁寧に分析することが大切です。
APDの子どもとのかかわり方
APDの子どもとの具体的なかかわり方は以下のとおりです。
- 静かな環境で話す
- 確認しながら話す
- 聞き返しても叱らない
- TODOリストを活用する
- 長く話さず短く区切って話す
- 話しかけるときは目を見て話す
- ジェスチャーを使いながら話す
- ゆっくりと口をはっきり動かしながら話す
- 聞き取れないことに関して、子どもと一緒に考える
確認しながら話すときには、気をつけるポイントがあります。
毎回「わかった?」と確認すると、子どもも気分がよくありません。「じゃあ次はなにするんだっけ?」と次の行動を尋ねるように確認しましょう。
また、日常的に親子で「聞き取りにくさで困ること」について話し合うことも大切です。
親が先回りをしてサポートするよりも、子どもと一緒に考えてください。
どんな場面で困っているのか、どうすると楽になるのかなど、困っているのは子ども自身です。
ここが明確になると、今後の支援にも役立ちます。

子どもと一緒に考えましょう
APDの子どもが過ごしやすくなる工夫
APDの症状によって子どもが困ることは、年齢によって異なります。
ここでは、以下の生活場面に分けて見ていきましょう。
- 幼稚園
- 小学校
- 家庭内
幼稚園
幼稚園で過ごしやすくするには、以下のような工夫があります。
- 先生にAPDであることを伝える
- 本読みや作品作りなどのときは先生の近くに座らせてもらう
- 話しかける前に名前を呼んだり肩を叩いたりして気づかせてもらう
未就学児は、APDの症状によって聞き取りが難しくなっている状況を「普通のこと」と思ったまま成長するため、言葉の発達は遅れてしまいます。
その結果、「言葉の発達が遅い」と受診し、会話での対応がよくないという理由で間違えて発達障害と診断されることがあるのです。[5]
小学校
小学校で過ごしやすくするには、以下のような工夫があります。
- 前の方の席に移動させてもらう
- 先生や友だちにAPDであることを伝える
- 授業内容のプリントを用意してもらえるか相談する
前の方の席は、先生との距離が近くなり話が聞き取りやすくなります。
友だちにも伝えるかは親子で話し合いましょう。
小学校高学年ぐらいになると、子どもが「お友だちには知られたくない」と言うかもしれません。
今後の治療や親子関係を良好に保つためにも、子どもと相談しながら工夫していくことが大切です。
家庭内
家庭内で過ごしやすくするには、以下のような工夫があります。
- 絵本をたくさん読む
- 話しかける前に名前を呼ぶ
- 話しかけるときは静かな環境にする
絵本をたくさん読むことで、語彙力を伸ばしましょう。
知っている言葉の数が増えることで、聞き取れないときに「似たような言葉を知ってる…なんだったかな?」と考えやすくなります。[6]
また、話しかける前は掃除機をやめたりテレビを消したりして静かな環境をととのえましょう。静かな環境で名前を呼ぶと、話に注意を向けることができ聞き取りやすくなるのです。
まとめ
子どもが何度も聞き返したり話が伝わりにくいと感じるときは、耳の問題だけでなく聴覚情報処理障害(APD)や発達障害が関係していることがあります。
APDと発達障害は似ている症状があったり併発したりすることもありますが、原因が違います。
発達障害との違いや似ているところを正しく理解し、静かな環境づくりやわかりやすい伝え方など、かかわり方を工夫することで子どもが過ごしやすくなるサポートができるでしょう。
子ども自身の「聞きにくさ」に寄り添い、一緒に子どもの生活環境に合わせた工夫を考えていくことが大切です。
「子どもの生活をどうにかしたい」と悩み気分が沈みそうになったら、おおかみこころのクリニックにも相談にきてくださいね。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]発達障害の理解のために|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/seisaku/17.html
[2]発達障害(神経発達症)|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=MbkmLbVbTEhSpxyE
[3]1.発達障害児と難聴|守本倫子
https://tokyo-mc.hosp.go.jp/wp-content/uploads/2022/01/000166478.pdf
[4]聴覚情報処理障害(auditory processing disorders, APD)の評価と支援|小渕 千絵
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlp/56/4/56_301/_pdf
[5]聴覚情報処理障害の診断と対応|県立広島病院小児感覚器科 益田 慎
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkoka/123/3/123_275/_pdf
[6]LiD / APD診断と支援の手引き(2024 第一版 )
https://apd.amed365.jp/doc/202403-seika.pdf
- この記事の執筆者
- 柚木ハル
作業療法士。精神科16年の臨床経験を生かして執筆を担当。現在は訪問リハビリに従事しながら幅広いジャンルにて執筆中。