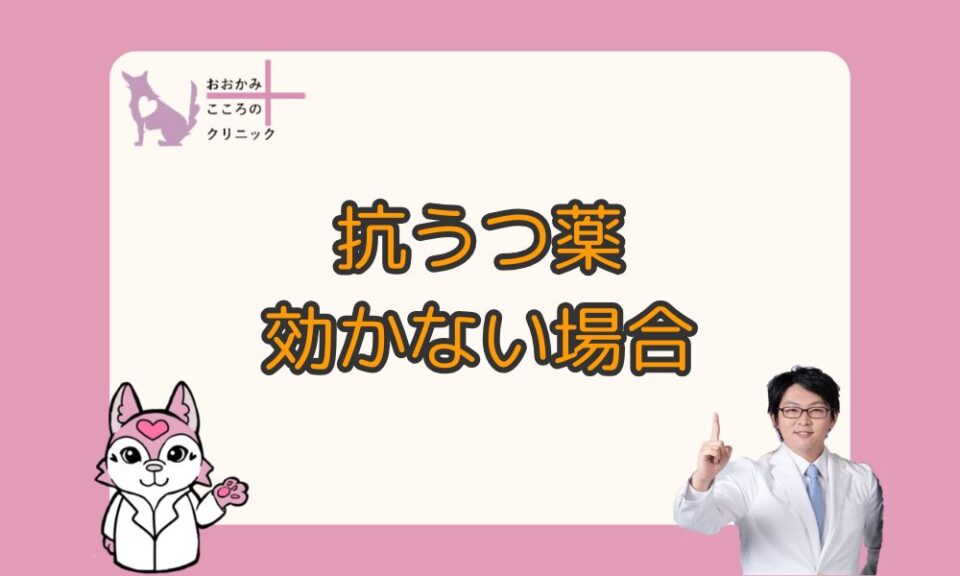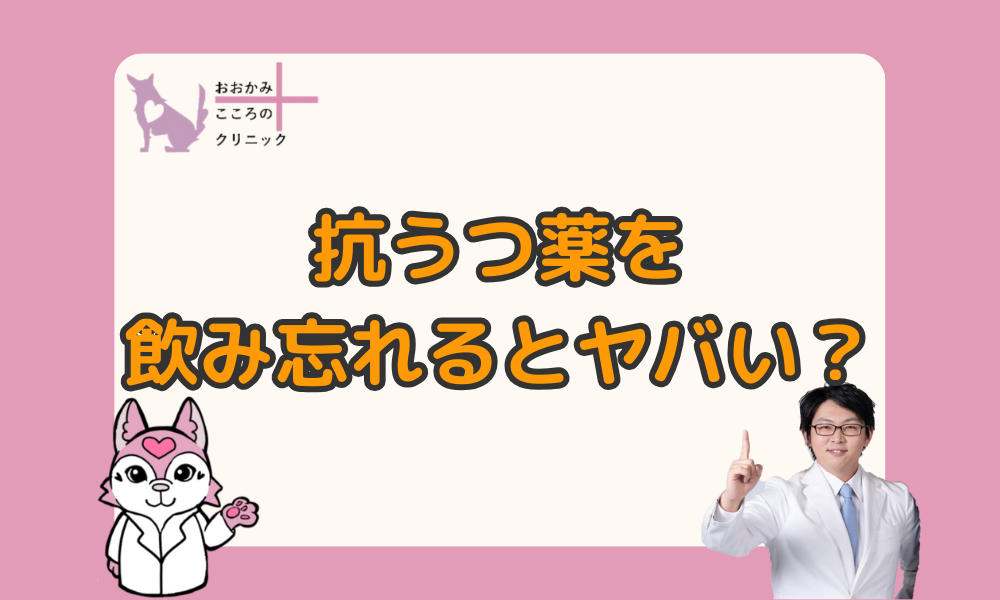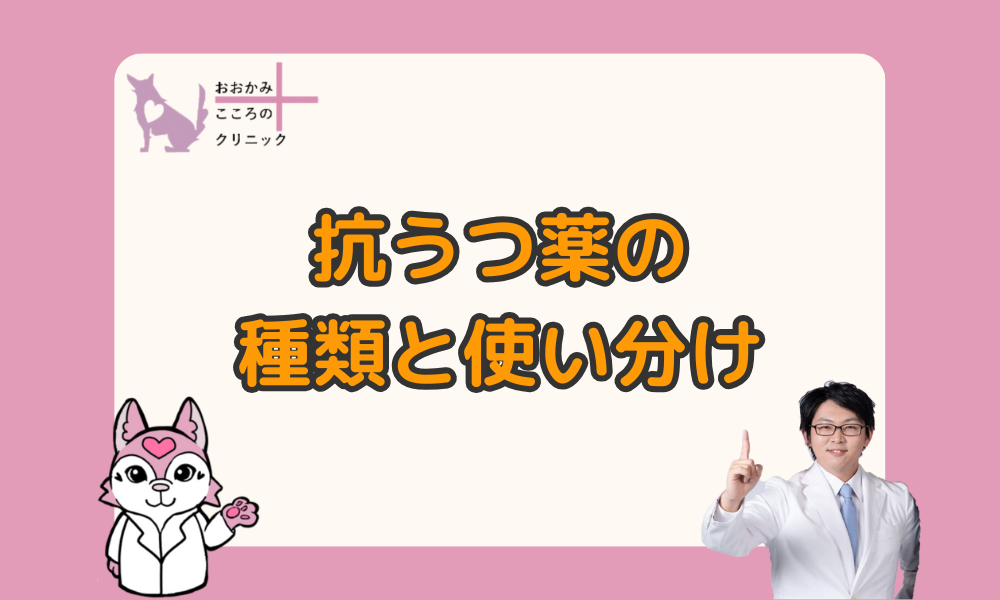「抗うつ薬を飲み続けているのに、なかなかよくならない」
「副作用ばかりで、本当にこのままでよいのだろうか?」
抗うつ薬を効かないと感じるとき、原因は薬の特性や飲み方などが考えられます。
ただ、期待していた効果がみられないと、治療への意欲が薄れたり不安になったりしますよね。
焦って自己判断で服薬をやめてしまうと、かえって症状が悪化する可能性があります。
まずは効かないと感じる原因を理解し、適切な対処法を知っていきましょう。
この記事では抗うつ薬が効かないときの原因や対処法を紹介します。
薬以外の治療法や注意点も解説するので、主治医と一緒に治療法を見つける助けとなれば幸いです。
抗うつ薬が効かない場合の原因
抗うつ薬を服用しても効果が実感できないとき、次の3つの原因が考えられます。
- 飲み始めて2週間未満である
- 薬の用法・用量が適切でない
- 症状が似た病気が隠れている可能性がある
抗うつ薬は、効果があらわれるまでに2週間ほどかかります。[1]
飲み始めてすぐに変化がないからといって、効かないと判断するのは早いでしょう。
また、薬を飲み忘れたり中断したりすると、効果が出にくくなります。[2]
決められた用法・用量を守ることが、効果を得るために大切です。
さらに、うつ病と症状が似ている病気も考えられます。
たとえば、気分が上下しやすい「双極性障害」はうつ症状がみられるため、うつ病と間違われやすいといわれています。[3]
うつ病と双極性障害では治療薬が異なるため、主治医に現状を詳しく伝え、改めて診断を確認してもらいましょう。
抗うつ薬を飲み忘れたらどうしたらよいのかは、下記の記事をご覧ください。
抗うつ薬が効かない場合の注意点
抗うつ薬が効かないときの注意点には、次の2つあります。
- 服用を中止したり量を変えたりしない
- 副作用があるときは主治医に相談する
まず、自己判断で薬の服用を中止したり、量を変えたりしないようにしましょう。
急に服薬をやめると、めまいや吐き気などの離脱症状があらわれる可能性があります。[2]
また、症状がつらいときや長く続くときは、我慢せずに主治医に相談しましょう。副作用をやわらげる薬を処方してもらえたり、副作用が出にくい薬への変更を検討してもらえたりします。
治療を効果的に進めるためには、医師とコミュニケーションをとり、あなたの状態を正確に伝えることが大切です。

なんでも相談して大丈夫ですよ♪
抗うつ薬が効いてくるときのサイン
抗うつ薬の効果は、少しずつ穏やかにあらわれます。具体的には、下記のように心身に変化が出てくるのです。
- 食欲が湧いてくる
- 朝すっきりと起きられる
- ぐっすり眠れるようになる
- 漠然とした不安や焦りがやわらぐ
- 趣味への興味や喜びが戻ってくる
ただし、効果はすぐにあらわれるわけではありません。抗うつ薬は飲み始めてから2週間ほどで変化がみられ、1か月経つと効果を実感できるようになります。[4]
一方で、吐き気や眠気などの副作用は飲み始めた段階で出るため「効かない」と不安に感じるかもしれません。
副作用でつらいときは我慢せず、まずは主治医に相談しましょう。
抗うつ薬が効かない場合の対処法3選
抗うつ薬が効かないときの対処法には、次の3つがあります。
抗うつ薬の効果がなかなか感じられず、不安な日々を過ごしているかもしれません。
医師と相談しながら、ムリのない範囲で対処法を取り入れるようにしてください。

症状をやわらげる別の方法も試してみましょう!
運動を始める
運動習慣を取り入れることは、抗うつ薬が効かないときに有効な方法です。
じっとしていると考え込んでしまう不安な気持ちも、身体を動かすことで気分転換になり、こころが軽くなることがあります。
ウォーキングや水泳などの有酸素運動は、不安の緩和に有効であると報告されています。
運動の強度が高いほど抑うつ症状が減る傾向はありますが、散歩のような軽い運動でも効果が期待できるのです。[5]
たとえば「いつもより少しだけ歩く時間を長くする」「エレベーターではなく階段を使ってみる」といった小さな工夫から始めてみましょう。ヨガやストレッチなども気分の緩和につながります。
あなたが「心地よい」と感じられる範囲で、身体を動かしていきましょう。
リラクゼーション法を取り入れる
リラクゼーション法を取り入れると心身の緊張がほぐれ、不安な気持ちをやわらげる助けになります。
リラクゼーション法とは意識的に心身をリラックスさせる方法で、実践すると呼吸がゆっくりになり血圧が下がる「リラックス反応」が身体に起こります。
具体的には、下記の種類があります。[6]
| 種類 | 特徴 |
| 呼吸法 | ゆっくりと呼吸に集中する |
| 自律訓練法 | 自己暗示の練習をし、身体の緊張を解いて心身の状態を調整する |
| 漸進的筋弛緩法 | 身体のさまざまな筋肉に力を入れ、ゆるめる |
リラクゼーション法は特別な道具もいらず、自宅で手軽に試せる点が魅力です。
また、不安や抑うつなどに有効である可能性が示されています。
ただし、効果を裏付ける研究はまだ十分ではない点も指摘されているため、あくまで治療の補助として捉えましょう。
医師に違う種類の薬を検討してもらう
現在服用している薬で十分な効果が得られないときや、副作用がつらくて続けられないときには、主治医に相談しましょう。
抗うつ薬には、作用の仕方が異なるさまざまな種類があります。
薬には人との相性もあるため、服用した薬では効果が出なくても別の薬に変えたら症状がやわらぐケースもあるのです。
どの薬が合うかは個人差があるため、医師は症状の経過や副作用の出方を見ながら、慎重に薬の種類や量を調整します。現在の状況を主治医に伝え、今後の治療方針について一緒に検討してください。
抗うつ薬以外の治療の選択肢
抗うつ薬による治療で効果がみられないとき、下記のような他の治療法が検討されます。
- 心理療法
- カウンセリング
- rTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激療法)
心理療法では、カウンセラーとの対話を通じて物事の考え方のパターンを見直す治療法です。
とくに、物事を客観的に捉えるように練習する「認知行動療法」は、うつ病への有効性が示されています。[7]
また、カウンセリングでは、カウンセラーのサポートを受けながらあなたの気持ちを整理し、ストレスへの対処法を学びます。
rTMS療法とは、磁気の力で脳の特定の部分を刺激し脳の活動を調整する治療法です。うつ病や強迫性障害で薬物療法の効果がみられなかった成人の患者さんに有効です。[8]
どのような治療を進める上でも、治療の基本は休養です。心身をしっかりと休ませる環境をととのえることが、回復につながります。[1]
まとめ
抗うつ薬の効果はすぐにはあらわれず、実感できるまでには2週間から1か月ほどかかります。
副作用が先にあらわれやすいため、焦らずに服用を続けましょう。
もし抗うつ薬が効かないと感じても、ひとりで抱え込まないでください。まずは主治医にあなたの状態を伝えることが、よい方向に向かうためのステップです。
自己判断で服薬を中断することは、かえって症状を悪化させる危険があるため絶対に避けましょう。
おおかみこころのクリニックでは、土日祝も夜22時まで診察しています。お仕事帰りや休日でも立ち寄りやすいので、不安なことがあればお気軽にお問い合わせください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]3 うつ病の治療と予後:ご存知ですか?うつ病|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad003
[2]くすりの効果は、どのくらい続きますか。|くすりの情報Q&A | 日本製薬工業協会
https://www.jpma.or.jp/about_medicine/guide/med_qa/q14.html
[3]双極性障害(躁うつ病)|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=RM3UirqngPV6bFW0
[4]抗うつ剤の種類・特徴とその限界,坂本将俊
https://www.jstage.jst.go.jp/article/faruawpsj/53/7/53_663/_pdf
[5]運動によるうつ病・うつ状態の予防に関する基礎知識|健康・体力づくり事業財団
https://www.health-net.or.jp/etc/pdf/utsu.pdf
[6]リラクゼーション法[各種施術・療法 – 一般]|厚生労働省eJIM
https://www.ejim.mhlw.go.jp/public/overseas/c02/11.html
[7]認知行動療法、深刻なうつにも効果ー重いうつにも投薬以外の治療選択肢を示唆ー|京都大学
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2017-01-27
[8]鬼頭伸輔先生に「反復経頭蓋磁気刺激療法(rTMS)」を訊く|公益社団法人 日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/modules/forpublic/index.php?content_id=62