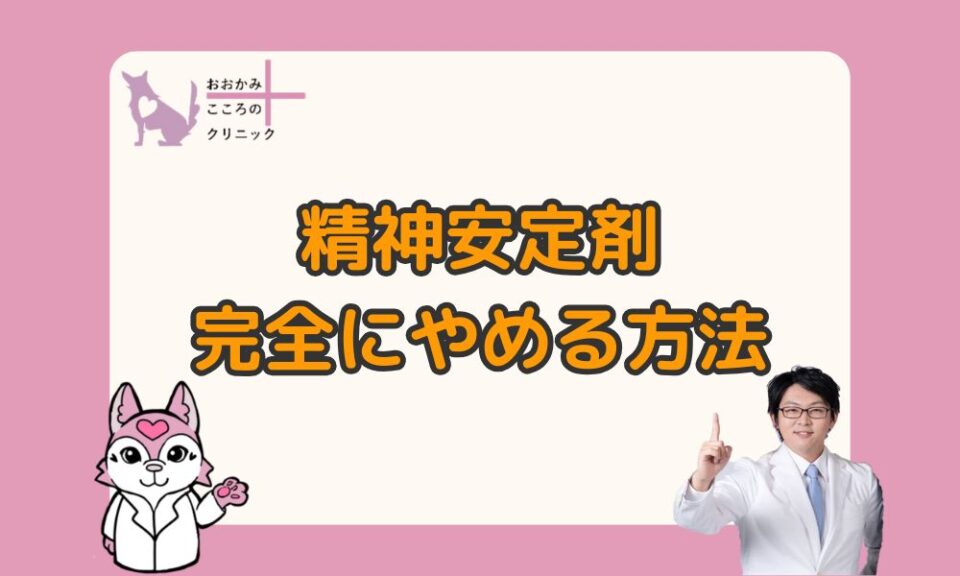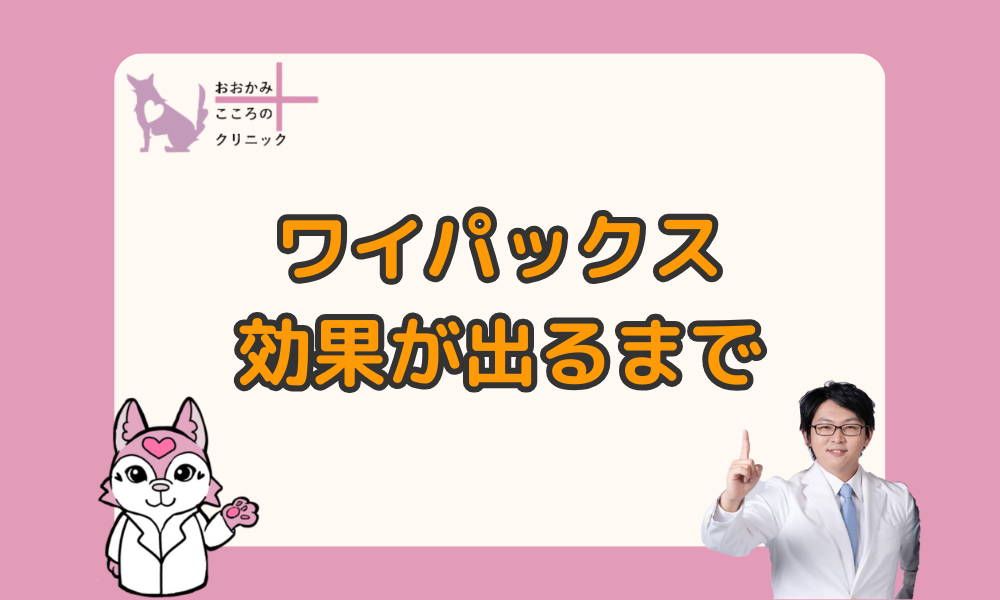「精神安定剤を完全にやめる方法はあるかな?」
「自己判断で服用をやめても大丈夫かな…」
精神安定剤の服用を続ける中で、薬なしの生活を目指したいと考える人も多いのではないでしょうか。
ただし、やめ方がわからなかったり急にやめることへの不安を感じたりしますよね。
精神安定剤をやめるには、適切なタイミングと正しい方法があります。知識がないまま自己判断で中断してしまうと、減量・断薬することで生じるつらい離脱症状や病気の再発につながるかもしれません。
この記事では、精神安定剤を完全にやめる方法や適切なタイミングを解説します。医師と相談しながら服薬をやめる助けとなれば幸いです。
精神安定剤をやめるタイミング
精神安定剤をやめるタイミングは、症状が安定してから少なくとも半年から1年以上経過した後です。自己判断でやめるのではなく、必ず医師の指示を守りましょう。
薬を飲み始めてすぐにやめてしまうと、病気が再発するリスクが高まるためです。
うつ病や双極性障害では薬物治療を始めると4〜6週間で効果があらわれ、3か月ほどで症状が落ち着くケースが多くみられます。[1]
症状が落ち着いた後も半年以上、再発経験があるときは2年以上服薬を続けると、安定した状態を維持しやすいと考えられています。
「もう症状は落ち着いたから大丈夫」と焦らず、まずは主治医に「薬をやめることを考えている」と相談することから始めましょう。
下記の記事では精神安定剤のひとつであるワイパックスのやめ方を解説しているので、詳しく知りたいときは参考にしてください。
精神安定剤を完全にやめる方法
精神安定剤を完全にやめる方法には、次の3つがあります。
どの方法をどのくらいのペースで進めるかは、薬の種類やあなたの状態によって異なります。
自己判断で行うのではなく、必ず医師と一緒に計画を立てて進めるようにしてください。

心配事や気になることは何でも相談してくださいね!
服用間隔を延ばす
服用間隔を延ばすことは、精神安定剤を完全にやめる方法のひとつです。
毎日飲んでいたものを1日おき、次に2日おきへと移行させます。身体が薬の無い状態に少しずつ慣れることを目指す方法で、隔日法(かくじつほう)とも呼ばれているのです。
どのようなペースで間隔を広げるかは、薬の種類やあなたの状態によって異なります。
自己判断で延ばしてしまうと薬の減量や中止したときにあらわれる「離脱症状」を招く恐れがあるため、必ず医師のもとで慎重に進めてください。
薬の種類を変更する
精神安定剤を完全にやめる方法には、薬の種類を変更することがあります。置換法(ちかんほう)とも呼ばれ、依存や離脱症状が出にくい薬へ切り替える方法です。
作用時間が短い薬ほど、急にやめた際の離脱症状が出やすい傾向があります。[2]
作用時間が長い薬は、成分がゆっくりと身体から抜けていきます。それにより、身体にある薬の量が急激に変化するのを防げるため、離脱症状をやわらげるのです。
たとえば、作用時間の短い薬Aから長い薬Bへ変更し、身体が慣れた後に薬Bの量を減らしていきます。
どの薬に切り替えるかは医師の判断が必要です。自己判断で変えると体調を崩す原因となるため、必ず医師と相談しましょう。
薬の量を少しずつ減らす
薬の量を少しずつ減らすことは、精神安定剤を完全にやめる方法のひとつです。
漸減法(ぜんげんほう)とも呼ばれ、1日あたりの服用量を段階的に減らしていきます。
薬を減薬・中止する際に、推奨されている方法です。[3]
急に服用を中止すると、離脱症状が起こる可能性があるため、時間をかけて慎重に進めます。
たとえば、1日に2錠飲んでいた薬を1錠にし、数週間から数か月間様子を見ます。
「体調が安定していることを確認してから薬をやめる」と進めるのが一般的です。
減量のペースは、一人ひとりに合わせて細かく設定されます。自己判断でペースを変えず、必ず医師の指示を守りましょう。
精神安定剤を完全にやめたいときの伝え方
医師に精神安定剤をやめたいと伝えるときは、現在の状態とやめたい理由を具体的に説明できるように準備しておきましょう。
医師はあなたの状態を正確に把握でき、安全な減薬プランを一緒に考えやすくなるからです。
たとえば、下記のように医師に伝えてみましょう。
「おかげさまで、ここ半年ほどは気分の波もなく安定して過ごせています。仕事も問題なくできており、夜も眠れています。ゆくゆくは薬に頼らず生活したいと考えているので、減薬についてご相談できないでしょうか。」
もし副作用の心配や妊娠の希望など具体的な理由があれば、ありのまま伝えてください。
事前に伝えたいことをメモにまとめておくと落ち着いて話せます。
精神安定剤をやめた後の注意点
精神安定剤をやめた後の注意点には、次の3つがあります。
再発を防ぐためにも、意識して毎日を過ごしてください。
規則正しい生活を心がける
薬をやめた後は、再発を防ぐために規則正しい生活を心がけましょう。
生活リズムが乱れると、自律神経のバランスが崩れてしまいます。[4]
「しっかり休んだはずなのに疲れが抜けない」という状態は気づかぬうちにストレスとなり、再発のきっかけになることがあるのです。
とくに、睡眠リズムをととのえましょう。
毎日同じ時間に起床・就寝することで、体内時計が正常に働きます。[5]
朝に日光を浴びると精神を安定させるセロトニンの分泌が促され、夜の自然な眠りにもつながります。
また、昼寝するときは午後3時までに30分以内にとどめ、夜の睡眠に支障がないようにしましょう。[6]
まずは起床時間を固定することから始めてみてください。
自己判断で薬を飲み始めない
薬をやめた後に体調が変化しても、自己判断で残っている薬を飲み始めるのは避けましょう。
病気による症状にみえても、離脱症状か再発の兆候かは医師でなければ判断が難しいからです。また、必要な薬の種類や量が以前とは異なる可能性もあります。
自己判断で服薬を再開してしまうと症状を悪化させたり、薬が効きにくくなったりするなど、回復を遅らせるリスクが伴います。
つらい症状が出たときは主治医に連絡し、現在の状態を正確に伝えて指示をもらいましょう。病院に行くべきか迷うときには、オンライン診療も活用してください。
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
体調が悪化したら医師に相談する
もし薬をやめた後に体調の悪化を感じたら、なるべく早く医師に相談しましょう。
薬をやめると、めまいや吐き気などの離脱症状が起きる可能性があります。[3]
数日から数週間続くこともあるため、再発のサインと間違えやすいものです。
しかし、医師でなければ離脱症状の原因を正確に判断するのは難しいでしょう。
「病院に行くのは大げさかな」と我慢してしまうと、症状が悪化したり長引いたりするかもしれません。
些細な変化でも遠慮せず、早めに受診して医師に相談してください。

「こんなこ相談していいのかな?」と遠慮せずに気軽に相談してくださいね!
精神安定剤を使わない治療法
精神安定剤での治療だけでなく、薬に頼らない方法も回復には必要です。
精神安定剤を使わない治療法は、症状の根本にある考え方のクセに働きかけるからです。ストレスへの対処スキルを身につけることで、安定したこころの状態を目指せます。
代表的な方法は下記のとおりです。[7][8][9][10]
| 認知行動療法 | 物事の受け取り方や考え方に働きかけ気持ちを楽にし、ストレスにうまく対応できるこころの状態をつくる。 |
| 曝露反応妨害療法 | 苦手な状況にあえて直面し、不安を減らすための行動をしない。パニック障害や強迫性障害の治療で使われる。 |
| 支持的精神療法 | カウンセラーとの対話を通じて、日常生活のストレスに対処する力を高める。 |
| rTMS療法 | 磁気で脳の特定部位を刺激し、脳の活動を変化させる。薬で効果がみられない成人のうつ病患者さんが対象。 |
たとえば、認知行動療法では失敗したときに「全部わたしのせいだ…」と考えてしまう考えのクセに気づき「次はこうしてみよう」と、より柔軟に物事を捉える練習をしていきます。
薬に頼らない治療法を組み合わせることで、症状を安定させることが期待できます。あなたに合う方法を、医師と相談しながら見つけてください。
まとめ
精神安定剤を完全にやめる方法には服用間隔を延ばしたり、薬の量を減らしたりする方法があります。
離脱症状や病気の再発を防ぐため、自己判断で中断するのは避けましょう。
薬をやめるには医師の指示のもと、時間をかけて計画的に進めることが大切です。不安な点は遠慮せず、医師に相談してください。
おおかみこころのクリニックでは、オンライン診療を受け付けています。当日に受診でき、予約から薬の受け取りまで自宅で完結できます。薬との付き合い方で悩んでいたら、お気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【参考文献】
[1]薬局における疾患別対応マニュアル~患者支援の更なる充実に向けて~|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001409761.pdf
[2]重篤副作用疾患別対応マニュアル ベンゾジアゼピン受容体作動薬の治療薬依存
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/000842887.pdf
[3]向精神薬を適切に減量・中止するための薬剤師の役割に関する研究|厚生労働科学研究成果データベース
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2019/192131/201918030A_upload/201918030A0010.pdf
[4]睡眠とストレスの関係 | 専門家コラム|働く女性の心とからだの応援サイト
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/column-7.html
[5]健康づくりのための睡眠ガイド 2023|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf
[6]睡眠薬や抗不安薬を飲んでいる方に ご注意いただきたいこと|東京女子医科大学病院
https://www.twmu.ac.jp/PSY/suimin-koufuanyaku.pdf
[7]認知行動療法(CBT)とは|認知行動療法センター
https://cbt.ncnp.go.jp/contents/about.php
[8]強迫性障害(強迫症)の認知行動療法 マニュアル (治療者用)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000113840.pdf
[9]包括的な介入法としての支持的精神療法ー特化された精神療法の技法や治療的工夫の組み入れー,山下達久,宮岡等
https://journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1260080521.pdf
[10]反復経頭蓋磁気刺激装置適正使用指針|公益社団法人 日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/Guidelines_for_appropriate_use_of_rTMS_202308.pdf