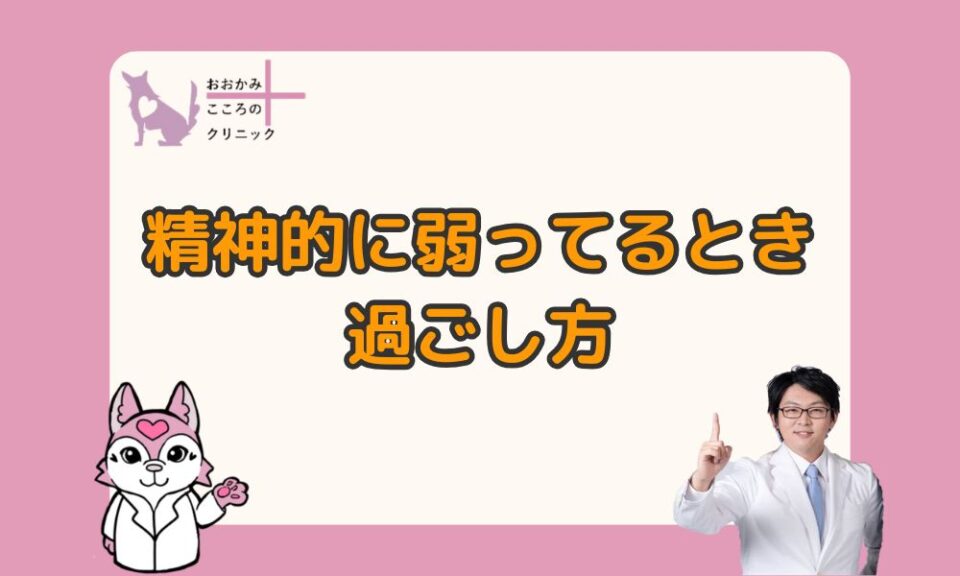「カウンセリングで話を聞いてもらえば、少しは楽になるはずだったのに…」
「なぜか終わった後の方が気持ちが落ち込んで、つらくなってしまった」
このように、ひとりで悩んでいませんか。
カウンセリングの後に落ち込むのは、決してあなただけではありません。
むしろ、あなたがこれまで向き合えなかった課題に真剣に取り組もうとしている大切なサインかもしれません。
この記事では、カウンセリングの後に気持ちが落ち込むおもな5つの理由を掘り下げていきます。その上で、つらい気持ちとどのように向き合い乗り越えていけばよいのか具体的な対処法をあわせて解説します。
あなたがカウンセリングを続けるかどうかを判断をする参考になれば幸いです。
この記事の内容
カウンセリング後に落ち込む5つの理由
カウンセリングの後に気分が落ち込むことは、決して珍しいことではありません。
ある研究では、カウンセリング(心理療法)を受けた人の約65%が、なにかしらの「副作用」を報告していることがわかっています。カウンセリングで起こる副作用として、悩みの理解が深まることで、気持ちが落ち込んだりイライラしたりする可能性が示されています。[1]
ここでは、カウンセリング後に落ち込む5つの理由についてみていきましょう。
まずは、何が落ち込みの原因になっているのかを知ることが大切です。
カウンセリング後に落ち込んで「心療内科を先に行くべきだったのかな…」と、悩んだときは下記の記事をご覧ください。
つらい感情や記憶に直面している
カウンセリングが進むと、これまで無意識に蓋をしていたこころの深い部分に触れていきます。
たとえば、幼少期の親子関係や意識しないようにしていた自分の少し嫌な部分、醜いと感じる部分などです。
あなたが意識しないようにしていたものに直面するとき、一時的にこころの痛みやしんどさを感じるかもしれません。
しんどく感じるのは、カウンセリングを通して悩みごとの理解が深まった結果、悩みが複雑に思えて「自分には解決できない」という感覚を生むからです。[1]
そのため、カウンセリング後の落ち込むのです。
ただ、カウンセリング後の落ち込みは、ケガの手当てをするために傷口に直接触れるのと同じで、回復に向かうための必要なプロセスだといえるでしょう。
話すことで疲れを感じやすくなる
これまで自分の感情を抑えることが多かった人が、自分の内面を言葉にして表現する作業は、想像以上に気力を使います。
とくに、相手に気を遣ってしまう人や責任感が強い人ほど「きちんと話さないといけない」と考え、話すことに疲れを感じやすいでしょう。
「うまく話そう」と気を張ってしまう緊張感が、カウンセリング後の疲れとなり落ち込む原因になってしまうのです。

人と話すと疲れますよね💦
カウンセリングに期待しすぎている
「お金と時間をかけているのだから、楽になるはず」という期待と「カウンセリング後につらくなる」という現実とのギャップが、落ち込みを大きくしている可能性もあります。
カウンセリングを受けるとすぐによくなるわけではありません。
実際には落ち込みと回復を繰り返しながら、ゆっくりと進んでいくものです。
期待とは裏腹に気持ちがよくならないことで、落ち込むことがあるでしょう。
カウンセラーとの相性に問題がある
「何度伝えても話が噛み合わない」「悩みを軽く扱われたように感じる」など、カウンセラーとの相性が合わないことも、カウンセリング後に落ち込む原因になります。
カウンセリングの効果は、カウンセラーとの信頼関係に大きく左右されます。
相性は「よい・悪い」ではなく「合う・合わない」の問題であり、あなた自身を責める必要はありません。
もし違和感が続くのであれば、カウンセラーの変更を検討することも選択肢のひとつです。
うつ病や適応障害などほかの病気の可能性がある
カウンセリング後の落ち込みが、実はうつ病や適応障害の可能性もあります。
もしカウンセリング後の落ち込みが2週間以上続くときは、一時的な落ち込みとは言えません。
そのようなときは、カウンセリングだけでは対応が難しいでしょう。精神科や心療内科といった医療機関での専門的な診断や治療が必要です。

他の病気かもと気になったら、先生に相談しましょう!
カウンセリング後の落ち込みと症状の悪化を見極めるポイント
カウンセリング後の落ち込みが、回復に向けた一時的なものなのか、それとも症状の悪化なのかを自身で見極めるのは難しいことです。
心理療法(カウンセリング)を受けた人の約5〜10%は、症状が悪化してしまうことが研究で指摘されています。[2]
もし以下のサインがみられるときは、症状が悪化している可能性があるため注意が必要です。
- 気持ちの落ち込みが2週間以上続く:カウンセリングの後1〜2日程度で落ち着くのではなく、憂うつ感や虚しさが2週間以上続いている。
- 自己否定感や無力感が強くなっている:自分の短所や過去の体験を振り返る中で一時的に落ち込むのではなく「自分はダメな人間だ」「自分には価値がない」と強く責めてしまう。
- 日常生活への支障が出ている:仕事や学校を休みがちになったり夜眠れなくなったりするなど、日常生活に支障が出ている。
3つのサインのうち、ひとつでもあてはまるときは、ひとりで抱え込まず専門の医療機関に相談してみましょう。
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
精神的に弱っているなと感じたら下記の記事を参考にしてください。
カウンセリング後に落ち込んでも続けるメリット
つらい時期を乗り越えてカウンセリングを続けると、症状をやわらげるだけでなく、あなたの人生をより生きやすいものに変えていけるでしょう。
カウンセリングを続けるメリットとして、以下の3つが挙げられます。
- 根本的な問題解決につながる
- 対人関係のパターンを見直せる
- 自己理解が深まり生きやすくなる
カウンセリングを通じて、あなたを苦しめてきた「漠然とした不安」の正体である捉え方や感情のクセに気づけると、自己理解が深まります。
その結果、無意識に繰り返していた対人関係のパターンを見直し、より安心できる人間関係を築くスキルが身につくでしょう。
カウンセリング後の落ち込みから抜け出す3ステップ
カウンセリング後のつらい落ち込みを感じたときは、次の3つのステップに沿って行動してみましょう。
それぞれの対処方法について解説します。
①落ち込むことをカウンセラーに伝える
大切なのは、あなたが感じているつらさを、ありのままカウンセラーに伝えることです。
以下のように、正直な気持ちを話してみてください。
「前回のカウンセリングの後、〇〇という気持ちで数日間つらかったです」
「カウンセリングを続けることで、悪化しているのではないかと不安です」
信頼できるカウンセラーであれば、あなたの話を否定することなく受け止め、カウンセリングの進め方を見直してくれるでしょう。
②カウンセラーの変更も視野に入れる
あなたのつらさを伝えても、カウンセラーが否定的な態度をとったり、協力的な話し合いができなかったりしたときは、カウンセラーを変えることも考えましょう。
ほかのカウンセラーを探す際には、以下の点を確認してください。
- 資格:「公認心理師」や「臨床心理士」といった、信頼性の高い国家資格や民間資格を持っているか。
- 専門分野:あなたの悩みに合った専門分野(トラウマ治療、認知行動療法など)を持っているか。
- 相談先:通院先の精神科・心療内科からの紹介や信頼できるプラットフォーム(例:『臨床心理士と出会うには』)などから探す
現在のカウンセラーに変更を伝えるときは「少しの間カウンセリングをお休みしたいです」のように、あなたの負担が少ない伝え方をするとよいでしょう。
③つらい状態が続くときは専門的な治療も検討する
カウンセラーを変更しても、落ち込みが続くときは専門的な治療を検討しましょう。
たとえば、薬物療法ではこころのバランスをととのえる薬を使い、不眠や食欲不振、強い不安感などの症状をやわらげます。
また、お薬に頼らない治療としてrTMS療法という選択肢もあります。これは、磁気の力で脳の特定の領域の働きをととのえる治療法です。
専門的な治療でまずこころと身体を安定させることで、安心してカウンセリングに取り組み、効果を得やすくなるでしょう。
rTMS療法については下記の記事で詳しく紹介しています。あわせてご覧ください。
まとめ
カウンセリングの後に気持ちが落ち込んでしまうのは、決して珍しいことではありません。
以下のような理由があり、回復に向けた大切な過程の一部です。
- つらい感情や記憶に直面している
- 話すことで疲れを感じやすくなる
- カウンセリングに期待しすぎている
- カウンセラーとの相性に問題がある
- うつ病や適応障害などほかの病気の可能性がある
カウンセリング後の落ち込みが回復へのプロセスなのか、それとも専門家に相談した方がよいサインなのかをあなたひとりで判断するのは、難しいでしょう。
つらい気持ちが続くとき、あるいは「これは普通の落ち込みではないかもしれない」と感じるときは、どうかひとりで抱え込まないでください。
おおかみこころのクリニックでは、オンラインでのご相談も可能です。あなたが感じている落ち込みがどのような状態なのかを一緒に考え、あなたに合った回復への道を探すお手伝いをします。まずはお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【参考文献】
[1]Muschalla B, Müller J, Grocholewski A, Linden M. Effects of talking about side effects versus not talking about side effects on the therapeutic alliance: A controlled clinical trial. Acta Psychiatr Scand. 2023 Aug;148(2):208-216.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36905373
[2]佐藤美保・田所摂寿(2025)「心理療法の悪化に関する実証的知見と臨床的対応―研究の歴史と今後の展望―」作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部,51–76p.
https://sakushin-u.repo.nii.ac.jp/records/2000505
- この記事の執筆者
- 片桐 はじめ
公認心理師、臨床心理士として精神科病院・クリニックで精神疾患を抱える方のカウンセリングや心理検査に従事。臨床経験をもとに、身近な例からわかりやすく説明する文章を心がけています。