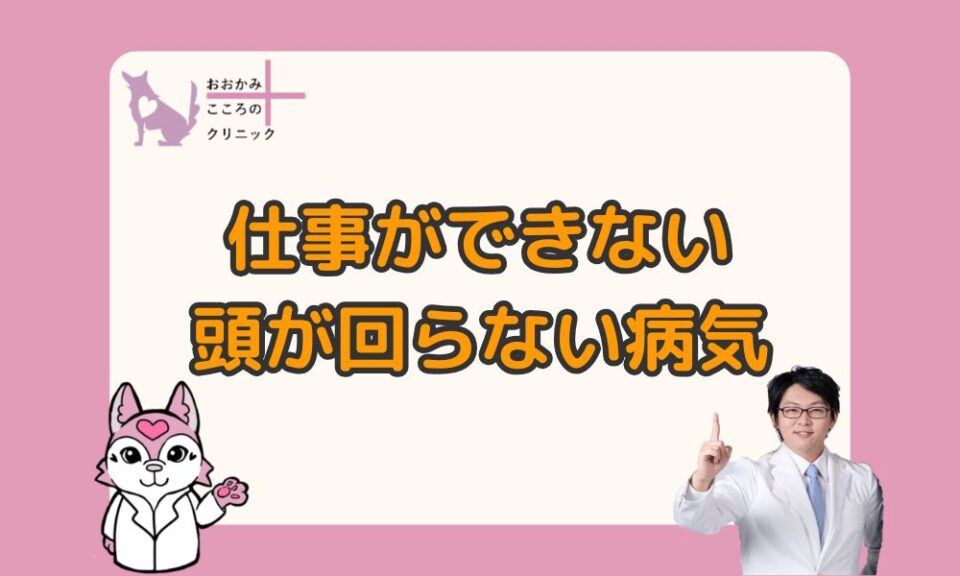「最近集中力が続かず物事を深く考えられない」
「簡単な判断もできなくなったのは病気のサインかな?」
物事を深く考えられない状態は疲れのせいだけではなく、うつ病や適応障害などこころの病気が関係しているケースがあります。
ただ、その不調のサインに気づいても、どう対処すればよいか悩みますよね。
物事を深く考えられない原因を知らないまま放置してしまうと、仕事や日常生活への支障がさらに大きくなる可能性があります。
あなたの状態を正しく理解し、原因に応じた適切な対処しましょう。
この記事では、物事を深く考えられないときに考えられる病気や、病気以外の原因を解説します。改善策も紹介するので、不安をやわらげ次の一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。
物事を深く考えられない症状
物事を深く考えられないときの症状には、おもに下記のものが挙げられます。
- ミスが増える
- 集中力が続かない
- 言葉が出てこない
- 思考がまとまらない
- 理解力や記憶力の低下を感じる
集中力が続かなかったり考えがまとまらず言葉が出てこなかったりすると、日常生活や仕事に次のような支障が出てしまいます。
- 日常生活
- ・本を読んでも内容が頭に入らない
・人と話そうとしても適切な言葉が出てこない
・テレビを見ていても話の流れについていけない
- 仕事
- ・書類の記入ミスが増える
・意見をうまく伝えられなくなる
・複数の作業を同時に進められなくなる
これらはあくまでも例ですので、症状は一人ひとり異なります。あてはまる項目が多いときは「物事を深く考えられない状態」になっていると考えましょう。
下記の記事では仕事ができないほど頭が回らない原因や対処法を解説しているので、あわせてご覧ください。
物事を深く考えられない病気
思考力や集中力の低下は、さまざまなこころの病気の症状としてあらわれます。
ここでは、物事を深く考えられない状態と関連のある代表的な3つの病気を解説します。
それぞれの特徴を知ることで、あなた自身の状況をより客観的に捉えることができるでしょう。
うつ病
うつ病を発症すると、物事を深く考えられない状態になることがあるのです。感情や意欲を司る脳の働きに不調が生じていると考えられています。[1]
うつ病のおもな症状は気分の落ち込みですが、それだけではありません。判断力が鈍り些細なことが決められなくなったり、これまで楽しめていた趣味に興味がなくなったりするのも症状です。[1]
もし気分の落ち込みとともに物事を深く考えられない状態が続いていたら、うつ病の可能性も考えましょう。
下記の記事ではうつ病の症状をチェックできるので、あわせてご覧ください。
適応障害
適応障害は、物事を深く考えられない原因のひとつです。特定のストレスが原因で心身のバランスが崩れ、抑うつ気分や不安感などの症状があらわれます。[2]
たとえば、職場の環境や人間関係、家庭内の問題などがストレスの原因となります。
強いストレスにさらされ続けると、思考力や集中力が低下してしまうのです。[2]
その結果、仕事の計画を立てられなくなったり、本を読んでも内容を理解できなくなったりします。
適応障害の特徴は、原因となるストレスから離れると症状がやわらぐ点です。
休日は頭がすっきりするのに職場に行くと再び考えがまとまらなくなる、というケースは適応障害の可能性が考えられます。
適応障害の初期症状は、以下の記事を参考にチェックしてください。
発達障害
生まれつきの脳機能の発達に偏りがある発達障害の特性によって、物事を深く考えるのが苦手なケースがあります。
たとえば、ADHD(注意欠如・多動症)の特性があると、注意が散漫になりやすくひとつの物事に集中し続けるのが困難になりやすいです。[3]
次から次へと考えが移り変わるため、ひとつのテーマをじっくり掘り下げられません。
また、ASD(自閉スペクトラム症)の特性があると、特定の分野に驚くほどの集中力を発揮します。[4]
一方で物事の全体像を捉えたり、複数の視点から考えたりするのが苦手な傾向があります。
ADHDやASDは環境調整や特性に合う仕事を選ぶと、日常を過ごしやすくなります。
発達障害と仕事の向き合い方については、以下の記事を参考にしてください。
物事を深く考えられないときの病気以外の原因
物事を深く考えられないときは、病気以外の原因が関係しているケースもあります。具体的には、HSP気質やブレインフォグです。
HSP(Highly Sensitive Person)は生まれつき感受性が強く、繊細な気質を持つ人のことです。周囲の環境や人の感情といった刺激を敏感に察知するため、無意識のうちに多くの情報を処理しています。その結果、脳が情報過多で疲れてしまい、思考が停止したり物事を深く考えられなくなったりするのです。
一方、ブレインフォグとは頭に霧がかかったようにぼんやりして、思考や記憶がはっきりしない状態を指します。[5]集中力や記憶力が低下するため、物事を順序立てて考えるのが難しくなるのです。
HSPとブレインフォグについては、以下の記事も参考にしてください。
物事を深く考えられないときの改善策
物事を深く考えられない状態をやわらげるための対処法を3つ紹介します。
それぞれ詳しく解説します。
頭を休ませる
物事を深く考えられないと感じたら、まずは頭を休ませましょう。
スマートフォンやパソコンから次々と情報が入ってくると、脳が常に働き続けている状態になります。また、群馬大学の調査によるとスマートフォンをよく利用する高校生は、心身のや目の疲れを感じやすいとわかっています。[6]
意識的にスマートフォンから離れるデジタルデトックスの時間を作りましょう。
たとえば、デジタルデトックス中は瞑想や散歩など、リフレッシュできる行動をしましょう。1日5分でもデジタルデトックスするだけで、頭を休ませることができます。
生活リズムをととのえる
思考力や集中力を回復させるためには、生活リズムをととのえましょう。
規則正しい生活は心身の疲れを回復させ、脳が安定して機能するためのエネルギーを供給します。
とくに、睡眠は脳内の情報を整理し、記憶を定着させるための大切な時間です。[7]
睡眠不足が続くと脳の働きが鈍り、物事を深く考えられなくなります。まずは同じ時間に起きて寝ることから始めてみましょう。
また、興味や関心のある趣味を楽しむ時間も、こころのバランスをととのえるために必要です。趣味に没頭する時間はストレスを発散させ、こころをリフレッシュさせてくれます。
趣味の時間を確保できていないと過食や寝不足につながり、心身の不調を招く可能性があるのです。[8]
意識的に好きなことに取り組む時間をスケジュールに組み込んでみてください。

こころの健康に生活リズムは大切です✨
2週間以上症状が続いたら受診する
セルフケアを試しても物事を深く考えられない状態が2週間以上続いたら、心療内科や精神科などへの受診を検討してください。
「2週間」は、うつ病や双極性障害など多くのこころの病気で診断の目安とされる期間です。
とくに、思考力の低下によって仕事でミスが続いたり、日常生活に明らかな支障が出たりしているときは、早めに受診するのが望ましいです。
症状が軽いからと放置してしまうと、状態が悪化し回復までに時間がかかってしまう可能性があります。
病院では医師が話を聞き、現在の状態がなぜ起きているのかを判断してくれます。薬による治療だけでなく、カウンセリングや生活習慣の指導など、一人ひとりに合う対処法を提案してもらえます。
病院を受診することは、あなたの心身を回復させるために必要なステップです。
まとめ
「物事を深く考えられない」という悩みは、心身からの重要なサインです。原因には、うつ病や適応障害といった病気、HSP気質やブレインフォグなどが考えられます。
まずは、脳を休ませるためにデジタルデトックスを取り入れたり、睡眠や食事などの生活リズムをととのえたりするなどの対処法を試してみてください。脳の疲労を回復させ、思考力を取り戻す助けになるでしょう。
もし、症状が2週間以上続いたり日常生活への支障が出たりしたら、心療内科や精神科を受診してください。医師やカウンセラーの力を借りることで対処法が見つかり、回復への道筋が見えてきます。
少しでも心配な点があれば、お気軽におおかみこころのクリニックへお問い合わせください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]うつ病|こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=9D2BdBaF8nGgVLbL
[2]3.ストレス,適応障害,新開 隆弘 p1-2
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jser/84/1/84_1/_pdf/-char/ja
[3]ADHD(注意欠如・多動症)|NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease07.html
[4]援助関係をつくりにくい人への支援~生活困窮者支援に必要と考えられる視点|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/soudan_3_kougi-siryo1_8.pdf
[5]COVID-19の後遺症「ブレインフォグ」が生じるメカニズム
https://www.jstage.jst.go.jp/article/faruawpsj/59/5/59_438/_article/-char/ja
[6]伊藤 賢一.青少年のネット長時間利用と心身の疲労 大規模アンケート調査からの考察 群馬大学社会情報学部研究論集
https://gunma-u.repo.nii.ac.jp/record/2000240/files/31-P1-1.pdf
[7]睡眠と記憶に関する近年の知見,鈴木 博之
https://www.ncnp.go.jp/mental-health/docs/nimh54_29-36.pdf
[8]ストレス対処法としての生活習慣 - 食う・寝る・遊ぶの充電法
https://kokoro.mhlw.go.jp/lifestyle