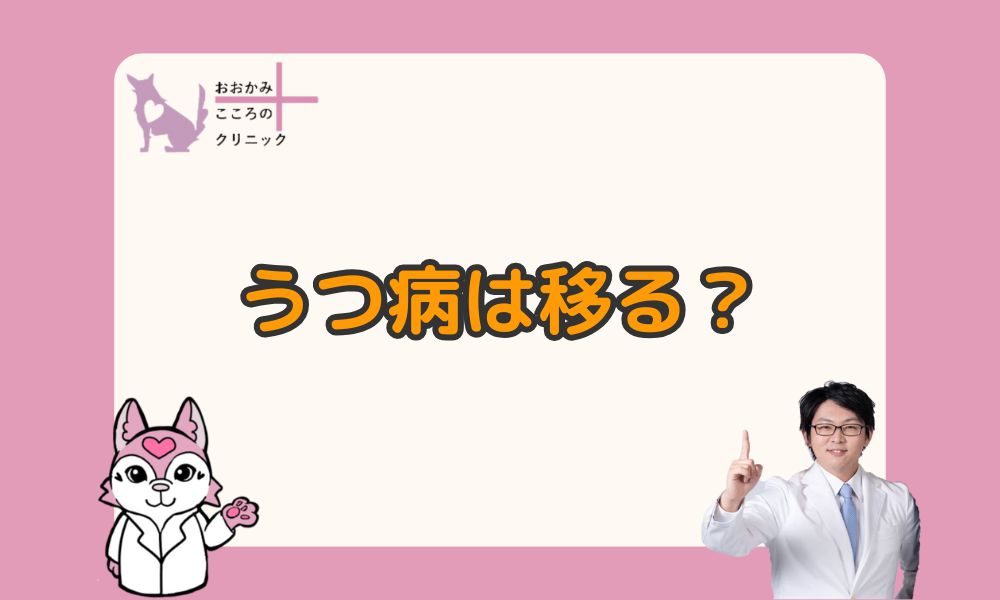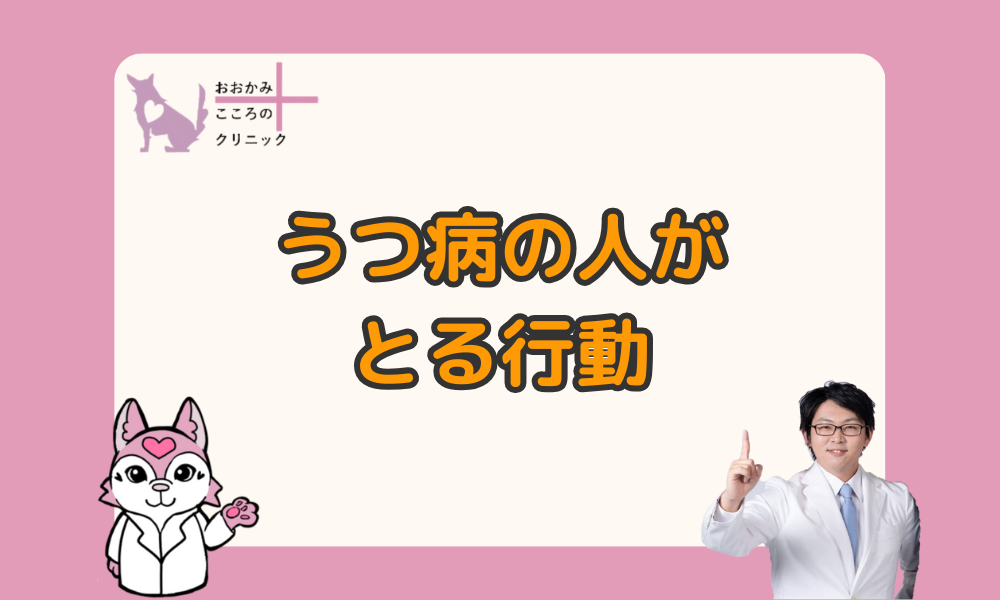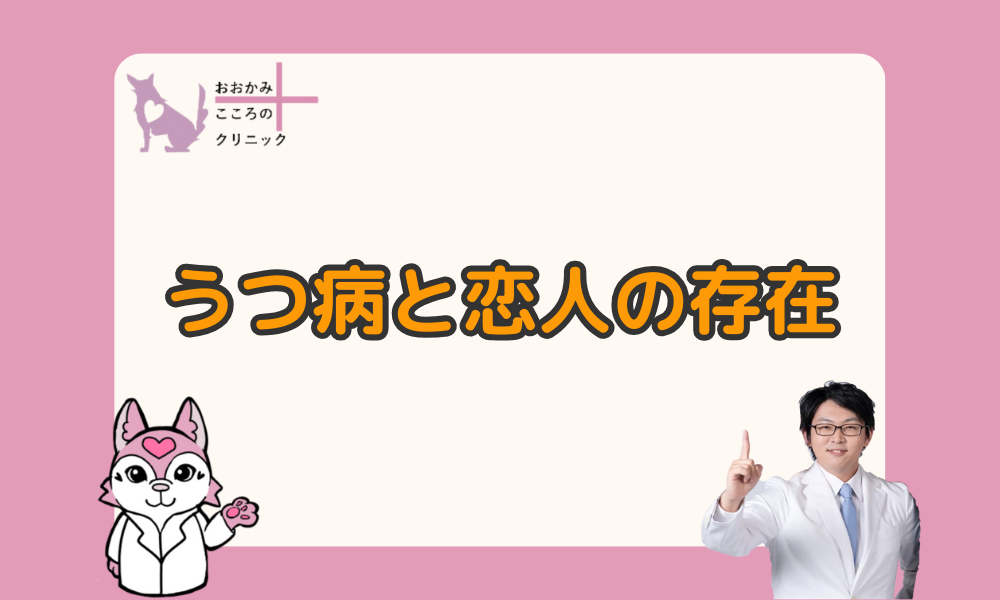うつ病の家族や恋人を支えていると、相手の話や言動に心が引きずられ、自分も気持ちが落ち込んでしまった経験はありませんか。
うつ病の人の家族や恋人が頑張りすぎると、一緒に気持ちが落ち込むことがあります。
「うつ病が移った」と感じないためには、対策やうつ病の人と接するポイントを知ることが大切です。
今回の記事では、うつ病が移る可能性やうつ病の人への対処法などを解説します。うつ病の人との関係や、あなたのメンタルの改善に役立てれば幸いです。
うつ病は移る可能性がある
うつ病の人と一緒に生活することで、感応精神病や適応障害を発症する可能性があります。
感応精神病とは、家族や恋人がうつ病の人と同じような精神症状や妄想に悩まされる病気です。
実際に、恋人同士で妄想を共有する事例があると報告されています。[1]うつ病の人の話に共感するのは大切ですが、話に共感しすぎると疲れてしまうことがあるのです。
また、人は似た性格の人物に親近感を抱きコミュニティを作る傾向にあるため、うつ病になりやすい性格の方同士で過ごしていると、症状によってストレスが高まりうつ病が移る可能性があります。
うつ病が移ったと感じないためにも、移らない対策や支えるポイントを把握しましょう。

身近な人だと親身になりすぎちゃいますよね💦
うつ病が移らないための対策
うつ病の人を支えるのに疲れ精神的に負担を感じる状態が続くと、気持ちが落ち込むことがあります。うつ病が移らないための対策は、以下のとおりです。
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
ひとりの時間を作る
うつ病が移らないための対策として、ひとりの時間を作ることが有効です。
うつ病の人に付きっきりでなく、適度に距離を置くことがお互いにとって大切です。趣味の時間を作ったり、ウォーキングや水泳などの運動をしたりしましょう。
とくに、適度な運動は心身をリラックスさせる効果が期待できます。運動は、1日20分程度からできる範囲で始めてみましょう。[2]

ひとりの時間を思いっきり楽しんじゃいましょう!
診察時に医師に相談する
うつ病が移ったと感じるほど精神的に疲れてしまった際は、受診に付き添い診察時に医師に相談しましょう。
医師によっては、本人抜きで話す時間を作ってもらえることがあります。
たとえば、次のような点について伝えてください。
- うつ病の人がどのような状況か
- どのように接すればよいか
- どのような声かけをしたらよいか
- どのような言動に疲れを感じるのか
うつ病の人をサポートするときに、気を付けるべきポイントが分かるメリットもあります。[3]
毎回の付き添いは必要ありません。もし、あなたの体調に不安を感じたり、サポート方法が気になったりしたら、受診時に医師に相談しましょう。
ひとりで抱えずに相談する
うつ病の人の対応に疲れを感じているならば、ひとりで抱えずに相談しましょう。
おもな相談先は、以下のとおりです。
- 信頼できる友人
- 公的機関の相談窓口
- 似た境遇の方が集まるコミュニティ
うつ病を支える方は、周囲の人に大変な状況を話しづらいこともあります。信頼できる知人やコミュニティに悩みを共有できれば、つらい気持ちがやわらぐでしょう。
コミュニティは自治体やクリニック、カウンセラーなどが主催しています。「みんなねっとサロン」や「うつ病患者の家族向けコミュニティサイトエンカレッジ」などがありますが、お住まいの地域にもコミュニティがあるか調べてみてください。
うつ病の人と接するポイント
うつ病の人と接するポイントを知ることも、うつ病が移らないための対策です。
それぞれを解説していきます。
共感しすぎない
うつ病が移らないためには、うつ病の人の話に共感しすぎないようにしましょう。
うつ病の人と接するのに、共感を示すのは重要です。しかし必要以上に共感しすぎると、あなたの気持ちが落ち込んでしまうことがあります。
うつ病の人に共感しながら、相手と自分は違う存在であると認識し「自分だったらどうするだろう?」と考えると距離を保ちやすくなります。あなたのムリのない範囲で、話を聞いてサポートしましょう。
安心できる言葉をかける
うつ病の人には、安心できる言葉かけが重要です。
ありのままを尊重するような声かけは、自己肯定感を高める効果が期待できます。うつ病になった自分を責めてしまう方もいますが、「そのままでいいんだよ」と存在を認める言葉をかけてみましょう。
以下の記事では、うつ病の人が言ってほしい言葉や言ってはいけない言葉を具体的に紹介しています。悪気なく放った一言が、うつ病の人にとってはプレッシャーになったり、傷つけたりすることもあります。言葉かけについてもっと知りたいときは参考にしてください。
病気によるものと理解する
うつ病の人の言動は病気によるものと理解することは、重要なポイントです。
うつ病は、脳内にある神経伝達物質「セロトニン」「ノルアドレナリン」が減っている状態です。セロトニンやノルアドレナリンは精神を安定させたり、やる気を起こさせたりする働きがあるため、減ると無気力で憂うつな状態になります。以下のような症状は、本人の意思ではなく病気によるものです。[4]
- 否定的に考える
- 楽しみや喜びを感じない
- よいことが起こっても気分が晴れない
病気の特徴を理解すると対応の仕方が分かり、不安をやわらげることができます。
以下の記事では、うつ病の人がとる行動について詳しくまとめていますので、参考にしてください。
関係別うつ病の人と接するポイント
うつ病の人と接するポイントを関係別に紹介します。
ポイントをおさえて接してみましょう。
家族
家族がうつ病の際に気を付けたいポイントは、以下のとおりです。
- 身体的、精神的な距離を適度に保つ
- 原因に過労やハラスメントが考えられる際は窓口に相談する
家族がうつ病になると、心配や焦りから親身になりすぎることもあるでしょう。しかし、うつ病の人が必要なときに助けを求められる距離感が理想です。
ひとりの時間を作ったり、話に共感しすぎないようにしたりして、適度に距離を保ちましょう。
相談窓口は、お住まいの地域の保健所や精神保健福祉センター、こころの健康相談統一ダイヤルなどでサポートを受けられます。最後に紹介する「うつ病を支える人のための相談窓口」では、それぞれの特徴を解説します。
恋人
恋人がうつ病になったら、会えない時期でも気持ちに寄り添って待つことが大切です。
うつ病になると思考力や判断力が低下し、LINEのやりとりやデートが難しくなることがあります。うつ病の恋人がとりがちな行動は、具体的には以下のとおりです。
- 連絡先をブロックされる
- 会いたくない気持ちになる
- 会えないけど趣味は楽しんでいる
恋人がひとりで居たいと伝えてきたら、自分の趣味を優先して楽しむようにしましょう。
以下の記事では、うつ病の恋人がとる行動やサポートの際に大切なことをまとめています。うつ病の恋人とのかかわり方の参考にしてください。
うつ病を支える人のための相談窓口
うつ病を支える人が利用できる相談窓口を紹介します。
| 相談窓口 | 特徴 | サイト |
| 保健所 | 地域の相談窓口を担う | 保健所所管区域案内 |
| 精神保健福祉センター | 保健所より精神保健に特化する | 全国の精神保健福祉センター|厚生労働省 |
| 総合労働相談コーナー[3] | 長時間労働やハラスメントが考えられる際に相談できる | 総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省 |
| こころの健康相談統一ダイヤル | 無料かつ匿名で利用できる | 困った時の相談方法・窓口|まもろうよ こころ|厚生労働省 |
とくに、こころの健康相談ダイヤルでは、電話だけでなくLINEやチャットでも相談できます。電話での相談が難しい方は活用してみてください。
まとめ
うつ病の人を必要以上に親身にサポートすると「うつ病が移った」と感じることがあります。
うつ病が移らないためにはひとりの時間を作り、話に共感しすぎないようにして適度な距離を保ちましょう。また、主治医や窓口に相談したり、似た境遇の人と悩みを共有したりするのも有効です。
おおかみこころのクリニックでは自宅にいながらオンラインでの診察もできます。仕事が忙しくて通院する時間がない方もお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]恋人を発端者として出現した感応精神病の一例|関西医大精神神経科学教室
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jkmu1956/42/2/42_146/_pdf/-char/en
[2]体を動かす|こころもメンテしよう ~若者を支えるメンタルヘルスサイト~
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/self/self_01.html
[3]ご家族にできること|こころの耳
https://kokoro.mhlw.go.jp/families
[4]うつ病とは|働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト(厚生労働省)
https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad001