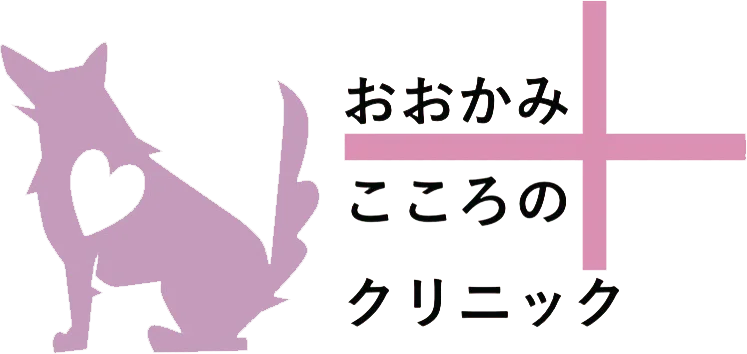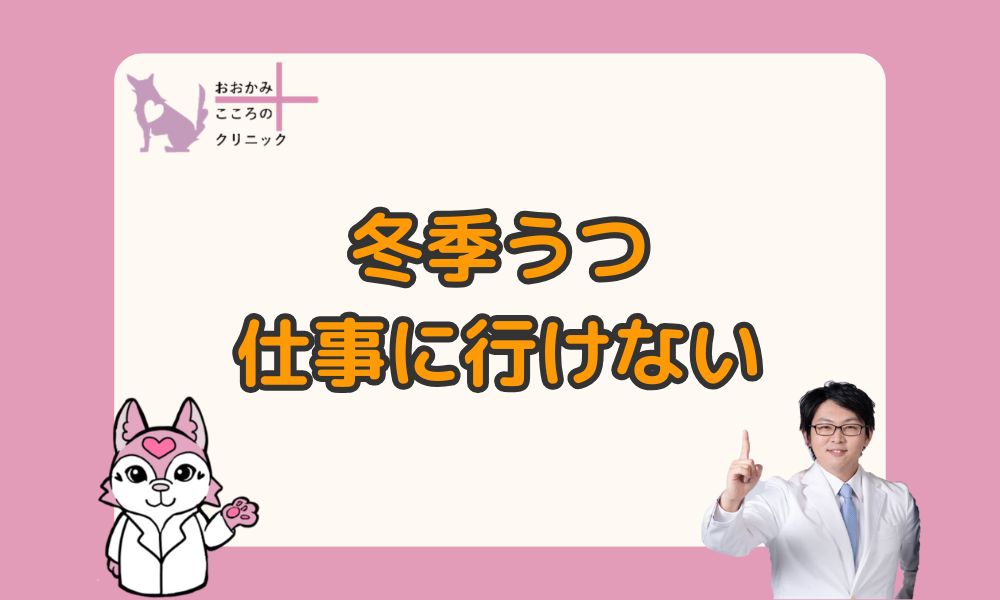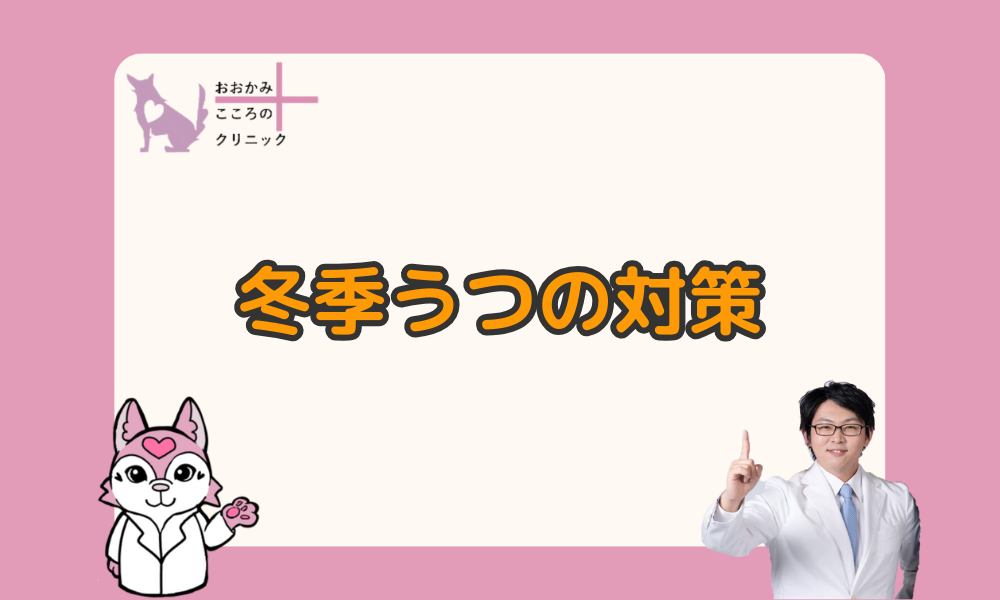「寒くなるとなかなか起きられない」
「冬はやる気がなくなりやすい…」
秋から冬にかけて心身に不調が出て、仕事に行けず悩んでいませんか?
特定の季節に抑うつ状態になることを、季節性感情障害といいます。なかでも、秋から冬にかけてのメンタル不調は「冬季うつ」と呼ばれているのです。
冬季うつでは、睡眠時間が長くなったりひどい倦怠感になったりするため、仕事に行けない人も少なくありません。しかし、対策がわかれば冬に不調で悩むことがなくなるでしょう。
この記事では、冬季うつで仕事に行けない理由や対処法を解説します。冬季うつで働けない悩みをもつあなたの参考になれば幸いです。
この記事の内容
冬季うつで仕事に行けないのは怠けではない
冬季うつは怠けや甘えではありません。
冬季うつは、季節性感情障害という診断名のあるこころの病気です。冬季うつの人の多くは、仕事に行けないけど「行かなきゃ」と感じたり働けない自分を責めたりします。
また、冬季うつはまだ知らない人も多い病気で、周囲に「怠けている」と誤解されることもあるでしょう。
冬季うつの対策ができるようになれば、症状を今より緩和させ毎年悩まなくて済むようになります。

つらい症状を「このくらい大丈夫」と我慢する必要はありません。
まずは、受診をして先生に相談しましょう!
「どこに相談すればよいか分からない」と悩んだときは、新宿・秋葉原・横浜・大阪梅田・博多にあるおおかみこころのクリニックにご相談ください。
オンライン診療も行っており、自宅にいながら医師の診察を受けられ、利便性のよい立地で通院しやすさも大切にしています。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
冬季うつで仕事に行けない理由と症状
冬季うつで仕事に行けない理由と、おもな症状を紹介します。
働けない理由と症状を理解することで、あなたに合う対処法も考えやすくなるでしょう。
仕事に行けなくなる理由
冬季うつで仕事に行けなくなるのは、日照時間の影響があります。[1]
仕事に行けない理由は「朝起きられない」「しっかり休めていない」などです。
人間の身体は体内時計に従って、ホルモンが分泌されています。
抑うつ状態となる原因のひとつは、気分の安定に重要な神経伝達物質(セロトニン)や睡眠の質に重要な神経伝達物質(メラトニン)の不足です。
冬はほかの季節と比較して日照時間が短くなるので、朝起きたくても起きられなくなるといわれています。
ほかにも、冬は年末の処理業務で仕事が忙しくなります。ストレスや疲労がたまることで、仕事に行けず働けない状態になりやすいのです。

忙しいとなかなか休めないし、疲れもたまりますよね💦
冬季うつのおもな症状
冬季うつのおもな症状は次のとおりです。
- 睡眠時間が長くなる
- ひどい倦怠感がある
- 食欲が増加する(体重が増える)
季節性感情障害の症状は、季節によって異なります。たとえば、夏季うつは食欲がなくなりますが、冬季うつは食欲が増す症状が見られるのです。
また、冬季うつでは炭水化物などを求めやすい傾向もあるといわれています。
冬季うつでは仕事に行けなかったり、食欲や睡眠欲が増えたりするため、かえって身体が疲れやすくなる人も少なくありません。
冬季うつの症状については、下記の記事で詳しく解説しています。参考にされてください。
冬季うつとほかの気分障害との違い
気分障害には、うつ病や双極性障害が含まれます。
うつ病と冬季うつの症状の違いは、食欲や睡眠、体重などにあらわれます。
下記の記事で詳しく違いを解説しているので、参考にされてください。
双極性障害と冬季うつも以下のような似ている症状があり、間違われやすいといわれています。
- 朝起きられない
- 気分に波がある
このような特徴から、双極性障害の人も仕事を休みがちになったり転職を繰り返したりします。
また、季節性感情障害だと思っていたら双極性障害だったケースもあるため、自己判断せず医師に相談してみましょう。
冬季うつで仕事に行けないときの対処法
冬季うつで仕事に行けないときは、次の対処法を試してみてください。
それぞれ具体的にみていきましょう。
日光浴をする
冬季うつになる原因のひとつは、日照時間の短さによるホルモンバランスの乱れです。日光浴をして、太陽の光を浴びるのも対処法のひとつです。[2]
一部の研究では冬季うつには光治療が有効といわれていますが、どの医療機関でも行えるものではありません。[3]
まずは、積極的に太陽の光を浴びる時間を増やしてください。
現在仕事に行けない状態ならば、いきなり予定を作って外出するよりも、次の方法を試してみましょう。
- ゴミ出しで少し外にでる
- 通院時間を午前中にする
- 室内でカーテンを開けて日光浴をする
今よりも症状をやわらげるために、できそうなことからはじめてみてください。
生活習慣を見直す
疲れにくい身体やこころづくりのためにも、生活習慣を見直しましょう。
生活習慣を見直すために、規則正しい生活を送らなければいけない訳ではありません。
規則正しくが理想の生活ですが、まずは日光浴と以下の2つのポイントを意識しましょう。[4][5]
- リズム運動
- 食生活の見直し
運動にはストレスを緩和したり、睡眠の質を高めたりする効果が期待されています。とくに抑うつ状態には、ジョギングやエクササイズなど一定の動きを繰り返すリズム運動がおすすめです。
また、食生活もメンタルヘルスに大きく関係します。バランスのよい食事や就寝の2時間以上前に夕食を食べることを意識してみましょう。

ラジオ体操もおすすめです!
職場に相談して働き方を見直す
自分の状態を職場に話すのは、働きやすさを手に入れるためにとても大切です。
職場の人に話すときは、次のポイントを意識してみてください。
- 診断書を持っていく
- 話しやすい上司に相談する
- 自分にできる対処法を伝える
冬季うつはあまり知られていないため、あらかじめ診断書をもらうと話を進めやすいです。
相談するなら、まず話しやすい上司や信頼できる人に話してみてください。あなたの症状を伝えたうえで、勤務時間の調整やリモートワークの活用などができないか相談してみましょう。
今の職場で働き続けるときは、できる限りあなたの働きやすい職場環境をととのえることが冬季うつの対策につながります。
冬季うつの対策はほかにもありますので、こちらの記事も参考にされてください。
職場でできる冬季うつ予防
職場でできる冬季うつ予防には、おもに次の4つがあります。
- こまめに席を立つ
- ストレッチをする
- 昼休みは少しでも外に出る
- 社内に相談室があるか確認する
こまめなストレス発散や相談場所の確保は、冬季うつに限らずこころの病気の予防にもつながります。
定期的に身体を動かしたり、少しでも日光を浴びたりする時間をつくってみましょう。イスに座ってできるストレッチをする時間やデスクを離れて歩く時間など、身体を動かす時間を使い分けてもいいですね。
毎年冬の時期になると、やる気がなくなる人は試してみてください。
冬季うつで仕事に行けない状態が続いたときの注意点
冬季うつが毎年のように生じている人や、仕事に行けなくてつらい思いをしている人は「休職」もひとつの選択肢です。
まずは治療に専念し疲れにくい身体を手に入れ、再発予防のための準備をしていきましょう。
冬季うつはひどい状態が続くと、春になっても症状が治まらなくなり、ほかのこころの病気になるケースもあります。うつ病や双極性障害以外にも、抑うつ状態が続くと発症するこころの病気は多いです。
早めにしっかり休養し、医師とともに冬季うつの正しい治し方を実践して、毎年悩まないようにしましょう。
まとめ
冬季うつは決して怠けや甘えではありません。適切な治し方や対処法を知っていれば、今よりも生活しやすくなるでしょう。
冬季うつの治し方は、日照時間の影響を理解し、生活習慣を見直すことです。また、職場の理解を得るために受診して、医師とともにあなたに合う治療法を見つけていくことも重要となります。
寒くなると朝起きられず仕事を休みがちになる人は、新宿・秋葉原・横浜・大阪梅田・博多にあるおおかみこころのクリニックへお気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【参考文献】
[1]季節性感情障害に気づいて治療をするためのヒント – MSDマニュアル家庭版
https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/news/editorial/2023/03/21/19/24/seasonal-affective-disorder
[2] 「世界と日本と自分のうつ病」p11「●復職に必要な準備は?」
https://japan-who.or.jp/wp-content/themes/rewho/img/PDF/library/061/book6402.pdf
[3]厚生労働省eJIM | 季節性情動障害に対する補完療法について知っておくべき6つのこと[コミュニケーション]
https://www.ejim.ncgg.go.jp/pro/communication/c03/48.html
[4]セルフケアのポイント|こころの耳 厚生労働省
https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/pdf/afterSC_selfcare_A3.pdf
[5]健康づくりのための睡眠ガイド2023 睡眠に関する参考情報 p22
https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf