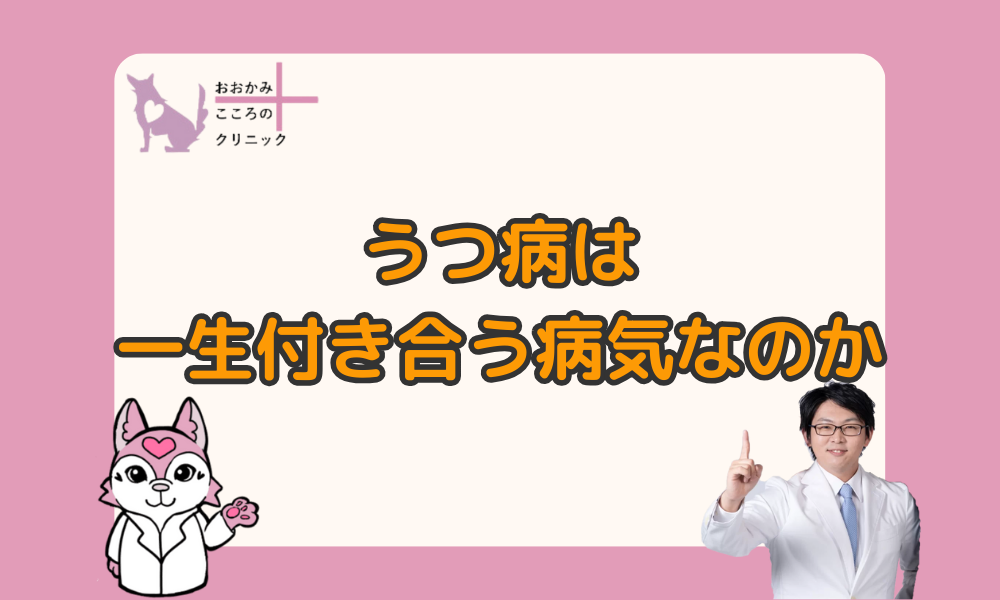「うつ病が治らないで、もう10年以上になる…」
「わたしだけ治らないのかな…どこか悪いのかも」
治療を続けても症状に波があり、自分をせめたりマイナスに考えたりして眠れない夜を過ごしていませんか。
うつ病は「完治」ではなく「寛解」を目指す病気です。
そのため、治らないと感じるときも、あなたらしく生きる道を探すことが大切になります。
この記事では、うつ病が10年以上治らない理由や、どのように生活していくとよいのか、薬が効きにくいときの新しい治療法(rTMS)について紹介します。
「もうどうしたらいいか分からない」と思ったときの、新たな一歩のきっかけになりますと幸いです。
うつ病が10年以上治らない理由はひとつではない
うつ病が長引く理由は、決してひとつではありません。
「うつ病が10年以上治らない」と感じるときに考えられる理由として、以下の3つが挙げられます。
うつ病の経過には個人差があり「こんな症状だから〇年で治ります」のような正解は存在しません。
大切なのは、あなたのこころと身体に合った治療法を見つけながら、あせらずに向き合っていくことです。
うつ病は一生つき合う病気なのか知りたいときは、以下の記事をあわせてご覧ください。
ストレスや生活環境
日常生活で常にストレスにさらされ続けていると、うつ病の症状がやわらぎにくくなります。
たとえば、以下のような環境はうつ病が治りにくい環境といえるでしょう。
- 経済的な不安
- 家族の仲が悪い
- 職場の人間関係が悪い など
こうしたストレスが続くと、治療の効果を実感しにくく再発をくり返すきっかけにもなります。
また、以下のような性格傾向の人は、日常生活の中でストレスを感じやすいでしょう。[1]
- 真面目
- 完璧主義
- 自分に厳しい
- 気を使いすぎる
人に頼ったり適度に手を抜いたりできずに、自分でも気づかないうちにストレスを抱えこんでしまうのです。
環境そのものや性格を変えることが難しいときは、カウンセリングやこころの相談窓口のような支援機関を活用して、少しでも負担を軽くする工夫をしましょう。
治療の中断や医師との相性
うつ病の治療は症状の変化を見ながら進めていくため、長い時間がかかることもあります。
だからこそ、医師との相性や治療方針にあなたが納得しているかが大切なのです。
たとえば、以下のようなできごとがあると治療へ不安がつのり通院がつらくなってしまうことがあります。[2]
- 説明が不十分なまま診察が終わる
- 診察時に話を十分に聞いてもらえない
- 薬の副作用や気になっていることについて質問しにくい
こうした不安が続くと「このままで大丈夫かな…」という気持ちになり、治療から足が遠のいてしまうこともあるでしょう。
また、治療や医師への不信感が募ると、自己判断で薬をやめてしまったり症状が長引いたりする原因にもなりかねません。
治療に迷いや不安があるときは、我慢をせずに話しやすい医療スタッフに相談したりセカンドオピニオンを検討したりしてください。

安心して治療を受けられる環境が大切です
薬が合っていない・効きにくい
うつ病の治療は、おもに薬物療法が中心になります。
薬の効果の出方には個人差があり「飲んでいるのに効かない…」と感じることも少なくありません。
また、うつ病には薬の効果を感じにくいタイプがあります。[3]
たとえば、以下のようなうつ病です。
- 長期間、複数の薬を試しても改善が見られない
- 薬の種類や量を変えても症状に大きな変化がない
- 「なんとなく楽になる」けれど根本的につらさが続いている
このようなときは、もしかすると薬物療法だけでは限界なのかもしれません。
心理療法や環境調整など他の治療法を検討してみることも大切です。
近年、rTMSという磁力で脳を刺激し、こころの不調をやわらげる治療法が注目されています。この記事の後半でも紹介していますので、すぐに知りたいときはこちらからご覧ください。
10年以上治らないうつ病を抱えて生活する方法
10年以上続くうつ病を抱えているなら「なんで治らないのかな」と悩み続けるよりも、あなたにとって生活しやすい方法を見つけることが大切です。
たとえば、以下のような工夫は生活がしやすくなるヒントになるでしょう。[4]
それぞれ詳しく解説します。
ムリのない予定を立てる
うつ病が長引いていると「今日も何もできなかった…」と落ち込む日が増えることがあります。
大切なのは「あなたに合ったペース」で予定を立てることです。
たとえば、以下のような工夫が役立ちます。
- 「休む日」という予定をつくる
- こころの調子に波があることを前提にする
- 「今日はこれだけできたらOK」と小さな目標をつくる
予定が詰まりすぎていると、誰もが疲れてしまいます。そのため「休む日」を最初から予定して「こころの休養日」を作りましょう。
また「わたしは調子の波がある」ことを前提としておくと「今日は調子が悪い日だったのか」と割り切って考えやすくなります。
あなたの調子がよくなる時間帯や季節、逆に落ち込みやすいパターンを知ることも大切です。

余裕のあるスケジュールを立てましょう
安心できる環境をととのえる
長くうつ病と向き合うなかで、ストレスの多い環境に身を置き続けることは、こころと身体の負担につながります。
だからこそ、安心して過ごせる環境をととのえることが大切です。
たとえば、以下のような工夫で日々のストレスをやわらげましょう。
- リラックスできる空間をつくる
- 落ち着く生活リズムをととのえる
- 不安になりやすい情報と距離をとる
- 安心できる人との関係性を意識する
- 疲れやすさを減らすために刺激を少なくする
意識して取り入れてみることで、ストレスをやわらげたり気持ちが落ち着く瞬間を増やしたりできます。
たとえば、疲れた日には、お気に入りの音楽を流してみたりアロマを焚いてみたりするだけでも、こころと身体が少し楽になることがあります。
今のあなたにとって心地よいと感じる工夫をして、少しずつ「安心できる環境」を見つけてください。
つらいときの「対処法リスト」を作る
つらいときにどうすれば少しラクになれるのかを考えておくことで、不安やしんどさに押しつぶされそうなときに落ち着けるきっかけになります。
たとえば、気分が沈んできたときにやってみることを、以下のようにリスト化してください。
- 人と話す
- 音楽を聴く
- とにかく寝る
- 深呼吸をする
- 軽くストレッチする
- あたたかいお風呂に入る
- あたたかい飲み物を飲む
- 散歩に出て外の空気を吸う
- ひとりになる時間をつくる
- アロマをたいて香りを楽しむ
そのときの気分に合わせて、誰かと話したり寝たりしてすごしたりしましょう。
大切なのは「わたしはこうすれば少しラクになるかも」という感覚をつかむことです。
うつ病が10年以上治らないときの治療法
うつ病の治療を10年以上続けても、なかなか良くならないと感じている方は少なくありません。
そうしたときは、これまでとは少し違った治療法を試してみるのもひとつの手です。
たとえば、次のような治療法が考えられます。[1][5][6]
- カウンセリング
- カウンセリングを受けると、気持ちを聞いてもらったり言葉にしたりするだけで少しこころが軽くなることがあります。カウンセリングでは、過去のできごとや今のつらさについて、あなたのこころの中を整理していくイメージです。
- 認知行動療法
- 認知行動療法では、無意識の「自分はダメだ」「きっとうまくいかない」といった思考のクセに対して、別の視点を持つ練習をします。実際の行動を少しずつ変えていくステップも含まれているため、日常の中で取り入れられる工夫を増やしていくことができます。
- rTMS(反復経頭蓋磁気刺激療法)
- rTMSとは、脳に磁気の力で刺激を与えることでうつ症状をやわらげることを目指す治療法です。副作用が出にくく、抗うつ薬が効きにくかった方にも効果が期待されると言われています。最近では保険適用となるケースも増えており、身体への負担が少ない選択肢として注目されています。
うつ病が10年以上治らないと「もう治らないのでは」と思ってしまう日もあるでしょう。
もしかすると、まだあなたに合う治療法に出会えていないだけかもしれません。
rTMSは近年注目されている、薬に頼らない治療法です。
おおかみこころのクリニックでは治療時間の短いiTBSを用いて治療を行います。
「rTMSってどんな治療なの?」と思ったら、まずはお気軽にお問い合わせください。
rTMSについて詳しくは下記の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。
まとめ|10年以上治らなくても、まだ選べる道はある
うつ病が長引くと「もう治らないかも」と感じる日もあるでしょう。
10年以上うつ病が治らない原因はひとつではありません。
ただし、原因にとらわれすぎずに、あなたがこころ穏やかに過ごせる工夫が大切です。
たとえば、安心できる空間をととのえたり、つらいときの対処法リストを作ったりしましょう。
もし、薬が効きにくいと感じるならrTMSのような新しい治療法についても考えてみてください。
長い時間うつ病とともに歩んできたあなたには、その分だけ自分自身をいたわる方法を見つける力があるはずです。
ひとりで抱えきれないと感じたときは、おおかみこころのクリニックを頼ってください。
あなたの症状やお気持ちに寄り添いながら、一緒にこれからの過ごし方を考えていきましょう。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]うつ病の認知療法・認知行動療法 (患者さんのための資料)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/04.pdf
[2]コラム1: 電話相談における精神障害者への基本的な対応-うつ病を中心に|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/01/s0126-5g.html
[3]なかなか治らないうつに対し,どの様に捉え,どの様に対処すべきだろうか|渡邊 衡一郎
https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyorinmed/49/1/49_83/_pdf
[4]うつ状態での過ごし方|医学情報・医療情報UMIN
https://square.umin.ac.jp/tadafumi/CBT.html
[5]カウンセリングについて カウンセリングの概要やメリットとは|こころもメンテしよう 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/counseling/index.html
[6]日本精神神経学会 反復経頭蓋磁気刺激装置適正使用指針 令和6年4月(改訂)ver2|公益社団法人 日本精神神経学会 ECT・rTMS 等検討委員会rTMS 適正使用指針作成ワーキンググループhttps://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/Guidelines_for_appropriate_use_of_rTMS_202404ver2.pdf