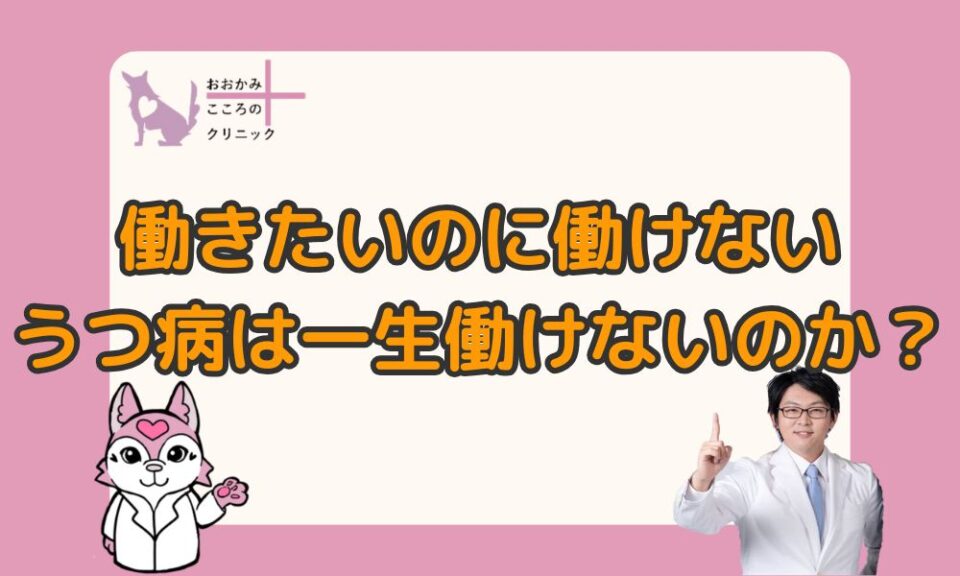「働きたいのに働けない」
「このまま一生、仕事に戻れないのかもしれない」
そんな不安や焦りを感じていませんか。
うつ病で働けずに、周りの目が気になったり家族との関係で気まずくなったりすることもあるでしょう。
この記事では、うつ病になると一生働きたいのに働けないのか、働けないことに対する考え方、家族との関係を再構築するための具体的な方法や考え方について解説します。また、利用できる支援制度も紹介します。
あなたの不安が少しでもやわらぐきっかけになれば幸いです。
この記事の内容
うつ病になると一生働きたいのに働けないのか
うつ病だからといって「一生働けない」わけではありません。
うつ病を抱えていても、次のような工夫で働けるケースもあります。[1]
- 症状に合わせて職場に勤務時間や業務内容を相談する
- 短時間勤務や在宅などあなたに合った働き方から始める
- 段階的に働く準備ができるリワークや就労支援を利用する
うつ病で働けなくなっても、すぐに以前のような働き方をする必要はありません。
今のあなたに合ったペースの働き方を見つけることから始めましょう。
たとえば、リワーク(職場復職支援)では「職場に戻るのがこわい」「また休職したらどうしよう」という気持ちに寄り添いながら、少しずつ働く準備ができる仕組みがととのっています。[2]
ほかにも、少しずつ働くための制度やサポートについては、この記事の後半でも紹介しています。すぐに知りたいときはこちらからご覧ください。

ムリのないあなたのペースで働ける環境を見つけましょう
働きたいのに働けないことへ焦りや罪悪感を抱えたときの考え方
うつ病で「働きたいのに働けない」と感じる方は少なくありません。
「働けないわたしはダメだな…」と思うのは、こころが疲れているときや、うつ病の症状のひとつで生じる感情です。
うつ病で働けないときには、次のような状態が見られます。
- 今までできていたことにも取り組めない
- 働きたい気持ちはあるのに身体が動かない
- 起き上がる気力がわかずずっと寝ていたくなる
たとえば「明日は動こう」と思って寝たのに、朝になると身体が鉛のように重く布団から出られないようなこともあるでしょう。
これはあなたの意志の弱さではなく、うつ病によってマイナス思考になったり行動できなくなったりしている状態なのです。[3]
また、社会の中には「仕事をしていないと価値がない」という雰囲気があるかもしれません。
そのようなときは「今の状況は人生において必要な時間なんだ」と、次のように考えましょう。
- 今抱えているつらさには意味がある
- これまで積み上げてきた努力や経験がある
- 働きたいと思っていること自体が前を向こうとしている
今は「働けない」のではなく「回復のために休んでいる」と考えてください。
何もしない時間も、あなたのこれからの人生のために必要なのです。
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【家族関係】うつ病で働きたいのに働けないときにできる工夫
働けないことで、家族との関係がぎこちなく感じてしまうことも少なくありません。
とくに、次のような場面では気まずさを感じるでしょう。
- 「家のことぐらいやってよ」と言われるのがこわい
- 休んでいるときに家族が働いていると申し訳なくなる
- 家族が何も言わなくても責められているように感じる
たとえば、あなたがソファで休んでいるときに家族が仕事や家事をしていると「わたしばかり何もしていない…」と罪悪感を抱いてしまうこともあります。
働きたいのに働けずに家族と気まずいときは、以下のような工夫が助けになるでしょう。
- 「ありがとう」「ごめんね」をこまめに言葉にする
- 「〇〇ぐらいならできそう」とできる範囲を先に伝える
- 「今日は体調が落ち着かなくて何もできないけど、よくなったら少しずつやっていきたい」と今の気持ちや状況を伝える
気まずさを完全になくすのはむずかしいかもしれません。
うまく言葉にできなくても「伝える努力」や「感謝の一言」を意識するだけでも、関係性は変わっていきます。
大切なのは、すぐに完璧な関係を目指すのではなく、少しずつ理解し合えるように努力する姿勢です。
経済的に不安なときに使える支援制度
うつ病で休職中や無職になってしまったとき、経済的な不安はとても大きなストレスになります。
日本には病気やケガで収入が途絶えたときに利用できる制度が多くあります。
あなたの状態や働いていた期間などに応じて、以下のような制度の利用を検討しましょう。
- 傷病手当金
- 障害年金
- 自立支援医療
会社員で働いていて休職しているなら、まず「傷病手当金」を利用するケースが多くあります。
傷病手当金は健康保険加入者向けの制度で、休職中でも一定の条件を満たせば給与の約2/3が最長1年6か月支給されます。[4]
障害年金は、病気やケガで仕事や生活が制限されるときに申請できる制度です。[5]
症状や生活への支障度に応じた年金が支給されます。
もし医療費が心配なら、自立支援医療を活用すると心療内科や精神科での通院医療費が原則1割負担になり、収入に応じて月額上限も設定されます。[6]
経済的な不安が少しでもやわらぐことで、こころにもゆとりが生まれるでしょう。
制度によって申請のタイミングや必要書類が異なるため、住んでいる地域の市区町村窓口に相談してください。
また、経済的サポートについては下記の記事でも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
少しずつ働けるようになるための制度やサポート
働きたいのに働けないという不安があると、仕事に復帰するこころのハードルが高くなっている可能性があります。
そのようなときは、段階的に社会とのつながりを取り戻せる制度や支援を利用してみましょう。
ムリなく少しずつ働くためには、次のような選択肢があります。
- 就労移行支援
- 合理的配慮の申請
- リワークプログラム
たとえば「まだ毎日の通勤は難しいけど、少しずつ人とかかわる練習がしたい」というときは、週に数回のリワークプログラムや就労移行支援から始めましょう。[2]
練習期間を設けることで、ムリなく今までの仕事につなげることができます。
また、合理的配慮とは、働くうえで必要なサポート(短時間勤務、業務内容の調整など)を職場に求めることができる制度です。[7]
焦らずあなたのペースで「働く準備」をととのえましょう。
リワークプログラムにつては下記の記事で詳しく解説しています。
もし薬の副作用がつらかったり、思うように効果を感じなかったりして「働くのは難しい」と感じるときは「rTMS療法」もあります。
rTMS療法とは、脳の特定の部位を磁気で刺激し、うつ病の症状をやわらげることを目指す治療法です。[8]
副作用も少なく外来通院でも治療ができるため「働きながら治療したい」と考えるときにも有効な治療法としても注目されています。
rTMS療法について詳しくは、下記の記事をご覧ください。
うつ病で働きたいのに働けないときは使える支援やサポートを探そう
うつ病で働けない日々が続くと、自分のことを責めたくなったり、将来が見えなくなってしまうこともあるでしょう。ただ、働きたいのに働けないのは、あなたが弱いからではありません。
今はこころと身体が「休みたい」と伝えているだけなのです。
あなたが「働きたい」と思っている今こそ、少しずつ準備を始められるタイミングなのかもしれません。
焦らず、あなたのペースでできることから始めていきましょう。
もし「どうしたらいいかわからない」と感じたら、医師に相談することも大切です。
おおかみこころのクリニックでは、ご自宅から受けられるオンライン診療も行っています。「病院に行くのがしんどいな…」というときでも、オンライン診療を活用して気軽に相談してください。
24時間予約受付中
当日予約・自宅で薬の受け取り可能
【参考文献】
[1]地域障害者職業センターの精神障害者総合雇用支援のご案内|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
https://www.jeed.go.jp/disability/employer/om5ru80000000690-att/om5ru80000000cz1.pdf
[2]職場復帰支援(リワーク支援)-ご利用者の声-|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
https://www.jeed.go.jp/disability/employer/om5ru80000000690-att/om5ru80000000czl.pdf
[3]うつ病の認知療法・認知行動療法(患者さんのための資料)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/kokoro/dl/04.pdf
[4]病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会 協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139
[5]障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
[6]自立支援医療制度の概要|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
[7]合理的配慮指針(概要)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000083347.pdf
[8]反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)による治療抵抗性うつ病への維持療法|鬼頭 伸輔
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsbpjjpp/33/2/33_67/_pdf/-char/ja
- この記事の執筆者
- 柚木ハル
作業療法士として精神科で17年の臨床経験を積み、現在は訪問リハビリに従事。経験を生かしメンタルヘルスを中心に、やさしく寄り添う文章を心がけて執筆しています。