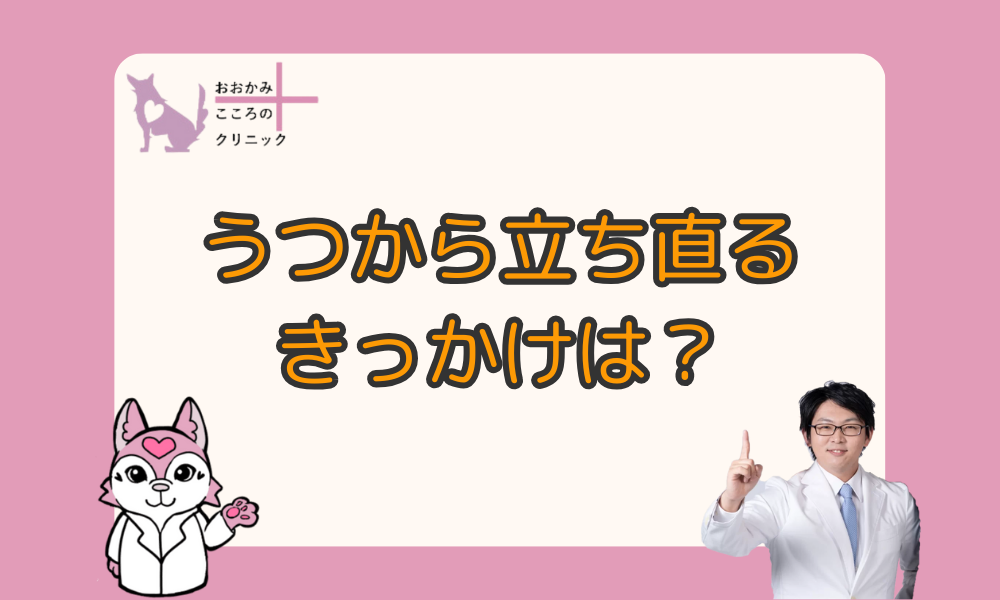「いつになったら治るんだろう…」
うつ病の渦中にいると、終わりが見えないトンネルをさまよっているような気持ちになるかもしれません。
真面目で責任感が強い人ほど「早く治さなければ」「周りに迷惑をかけている」と自分を追い込んでしまいがちです。
うつ病の本質を理解して焦らずゆっくりと休むことが、回復への一番の近道になります。
この記事では、うつ病を「治したい」と願うあなたへ回復までの期間の目安や、日々の生活で実践できる考え方、回復を実感するきっかけをお伝えします。
焦らずあなたのペースで治療に取り組み、うつ病のトンネルから明るい未来へ抜け出しましょう。
うつ病を治すまでの期間の目安
うつ病の治療は一般的に「急性期」「回復期」「再発予防期」の3つに分けられ、それぞれに必要な期間は以下のとおりです。[1]
- 急性期:1~3か月
- 回復期:4~6か月
- 再発予防期:1年以上
■急性期
急性期は症状がもっとも重い時期で、こころと身体をしっかり休ませることが最優先です。
抗うつ薬は効果があらわれるまでに2~4週間程度かかるため、すぐに効果を実感できなくても継続しましょう。
■回復期
回復期は少しずつ症状が安定し、活動できるようになってくる時期です。
外出したり趣味を再開したり、できることからはじめましょう。
薬物療法に加えて、カウンセリングや認知行動療法などの精神療法を併用することも多い時期です。
■再発予防期
再発予防期は、再発を防ぐために治療を続けます。
ストレスとの向き合い方や考え方のクセを見直し、病気になりにくいこころと身体を作っていきます。
回復期や再発予防期には「よくなったから」と自己判断で薬を中断してしまいがちです。
自己判断で薬をやめることは、再発リスクを高めるため必ず医師と相談しながら治療を続けましょう。[2]
治療期間は個人差が大きく、数か月で回復する方もいれば年単位での治療が必要な方もいます。
大切なのは焦らずに、あなたのペースで治療に取り組むことです。
うつ病から立ち直ったきっかけについては下記の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
うつ病を治したいときの考え方
うつ病の治療は薬や休養だけでなく、あなたの考え方や気持ちの持ち方も深くかかわります。
こころが少しでも軽くなるための考え方を3つご紹介します。
焦らずに開き直る
うつ病になる人は、真面目で責任感が強い傾向にあります。[2]
「早く治さなければ周りに迷惑をかけてしまう」「仕事に復帰しなければ」と焦ってしまいがちです。
休養中は周りへの罪悪感を抱きやすい時期ですが、今はあなた自身が元気になることが一番の仕事です。
「まぁ、いいか」「今は仕方ない」という開き直りの精神を持ってみましょう。[3]
「今日は何もできなかった」と落ち込む日があっても「まぁ、休めたからいっか」と受け止めることで、少しずつこころが楽になっていきます。
うつになりやすい人の特徴について詳しくは以下の記事をご覧ください。
つらい気持ちを表現する
つらい気持ちを言葉にして表現すると、こころが整理できます。
頭に浮かんだことやこころに感じたことをひたすら紙に書き出す「ジャーナリング」も効果的です。
書き出すことで今抱えている悩みと距離をとって、客観的に見られるようになります。[4]
信頼できる家族や友人、パートナーに正直な気持ちを話してみるのもよいでしょう。
気持ちを言葉にして話すことで頭の中が整理され、こころが楽になります。
つらい気持ちはあなたの正直なこころの声です。つらいと思うことを否定せず、ありのまま受け入れることが回復への第一歩です。

つらい気持ちをため込まないでくださいね
小さなしあわせも感じ取る
うつ病のときはうまくいかないことばかり気になりがちですが、日常生活の中に隠れた「小さなしあわせ」に意識を向けてみましょう。
「今日のコーヒーはいつもよりおいしいな」「窓から入ってくる風が気持ちいいな」といった些細なことでも構いません。
今日できたことを日記に書き出すのもおすすめです。
「朝起きて顔を洗えた」「買い物に行けた」など、小さなことでも「できたこと」を認めてしあわせを感じましょう。
うつ病が治るきっかけと感じるとき
うつ病の回復には波があり、一進一退しながら少しずつよくなっていきます。
回復の過程で「もしかして、うつ病が治ってきたのかな?」と感じる瞬間は以下のようなときです。
具体例を見ていきましょう。
人間関係がよくなったとき
うつ病の原因が特定の人間関係や職場環境にあるケースでは、そこから離れることで大きく回復に向かうことがあります。
たとえば、以下のようなときです。
- 引っ越して環境が変わった
- 転職や異動で職場が変わった
- うつ病に対する理解者ができた
引っ越しや転職、異動によってストレスの原因と離れることで、こころの負担が軽減し、症状がよくなったと感じやすくなります。
家族や友人、パートナー、同じ病気を経験した仲間など、あなたの苦しみを理解し、支えてくれる人ができたと感じるときも、安心感から症状がやわらぐこともあるでしょう。
ひとりで抱え込まず、周囲の人に頼りながら人間関係をよくすることが大切です。

人間関係は大切です
治療効果を感じられたとき
「自分に合う薬が見つかった」と感じる瞬間も、回復への大きな一歩です。
薬の効果が出てくると、以下のような変化が出てきます。
- 朝起きられるようになった
- ぐっすりと眠れるようになった
- 食事を美味しいと感じるようになった
これらの変化は、治療が順調に進んでいるサインです。
焦らず治療を続けることで、さらに変化を実感できるようになるでしょう。
前向きな考え方ができたとき
カウンセリングや精神療法を通じて、考え方のクセや過去の出来事に対する捉え方に気づくことも、回復を実感するきっかけになります。
たとえば「完璧でなければならない」「いつも自分が悪いのだ」という思考のクセに気づけたり、つらい体験を「自分を成長させてくれた経験」として捉え直したりできたときにこころが軽くなるでしょう。
うつ病になりやすい思考パターンを客観視し、より柔軟な考え方ができるようになることで、生きづらさが軽減していくのです。
うつ病を治したいときの選択肢|rTMS療法
近年、うつ病の治療法として注目されているのがrTMS療法(反復経頭蓋磁気刺激)です。
rTMS療法は脳の特定の部位に磁気刺激を与え、こころの不調をやわらげることが期待される治療法です。
薬物療法で十分な効果が得られなかった方や、副作用で服薬が難しい方にとって、新たな選択肢となっています。[5]
個人差はあるものの治療時間は以下のとおりです。
- rTMS(反復経頭蓋磁気刺激):1回あたり約40分
- iTBS(シータバースト刺激法):rTMSの一種で1回あたり3〜6分
おおかみこころのクリニックでは、このiTBSを導入しています。iTBSは短時間で行えるため、外来通院でも継続しやすいのが特徴です。
rTMS療法について詳しくは以下の記事をご覧ください。
まとめ
うつ病は急性期から回復期、再発予防期までそれぞれの段階に合った治療を焦らずに継続することが肝心です。
「早く治したい」と焦る気持ちを抑え「今は休む時期だ」と割り切って焦らずにゆっくりと過ごしてください。
つらい気持ちを受け入れ、小さなしあわせに目を向けながら「まぁいいか」の精神で開き直ることも回復への一歩につながります。
人間関係の変化や治療効果の実感、前向きな思考の獲得など、回復のきっかけは人それぞれです。
専門家のサポートを受けながらあなたに合った治療法を見つけていきましょう。
従来の治療法で効果を感じられない場合は、rTMS療法という選択肢もご検討ください。
おおかみこころのクリニックでは、自宅から医師の診察を受けられるオンライン診療を行っております。些細なことでもひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]うつ病の治療と予後|こころの耳 厚生労働省
https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad003
[2]患者のための最新医学 うつ病 改訂版|坪井 康次
[3]うつ病の理解と対応|野村 総一郎
https://www.p.u-tokyo.ac.jp/soudan/070nenpo/pdfs/2010nomura.pdf
[4]今の気持ちを書いてみる|こころもメンテしよう 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/self/self_02.html
[5]反復経頭蓋磁気刺激装置適正使用指針|日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/Guidelines_for_appropriate_use_of_rTMS_202404ver2.pdf
- この記事の執筆者
- すみこ
作業療法士歴13年の経験を活かし、医療記事を中心に活動するWebライター。 読者の皆様のこころと身体の健康をサポートし、前向きな気持ちになれる文章を心がけています。