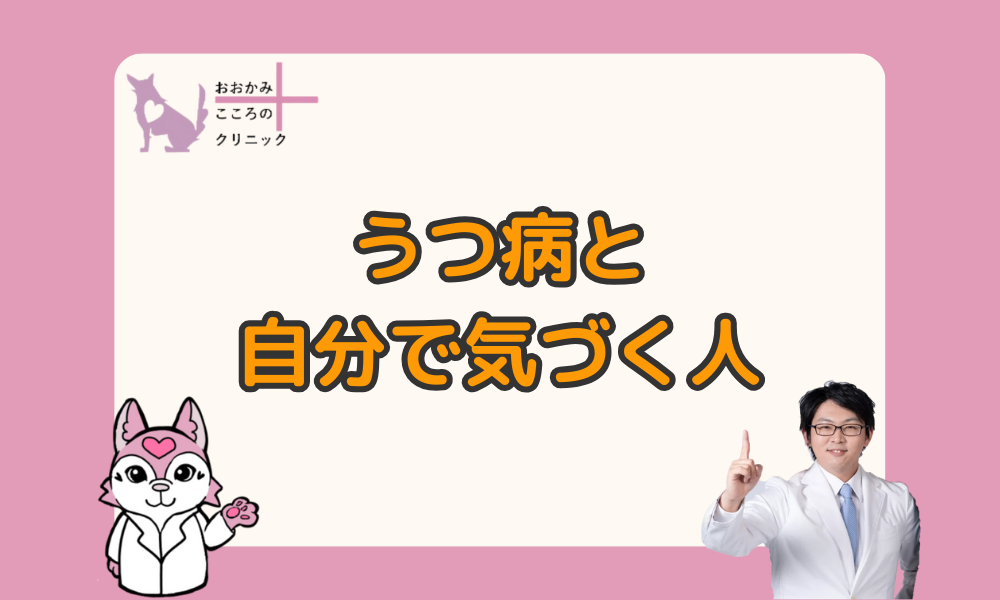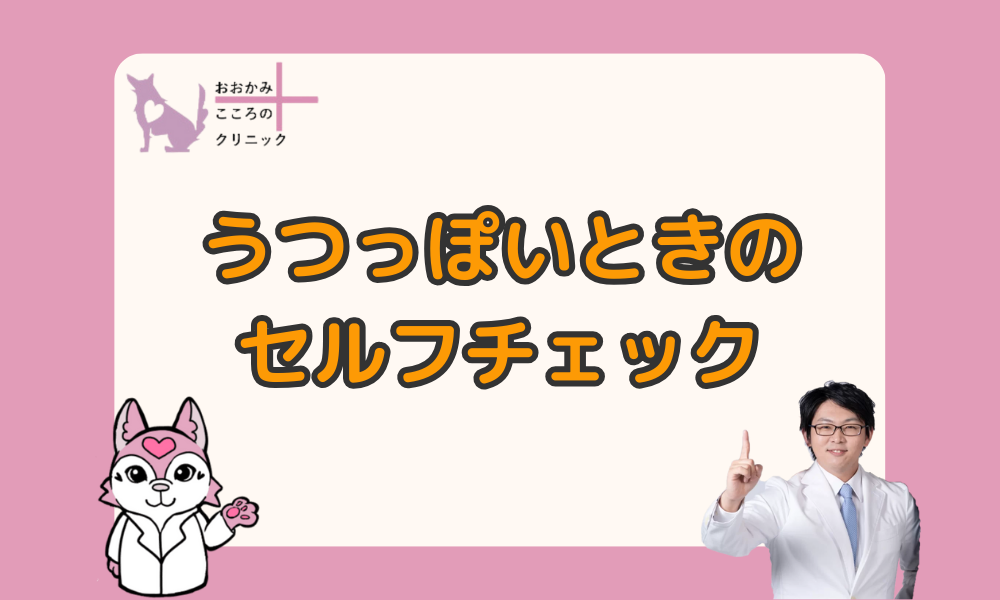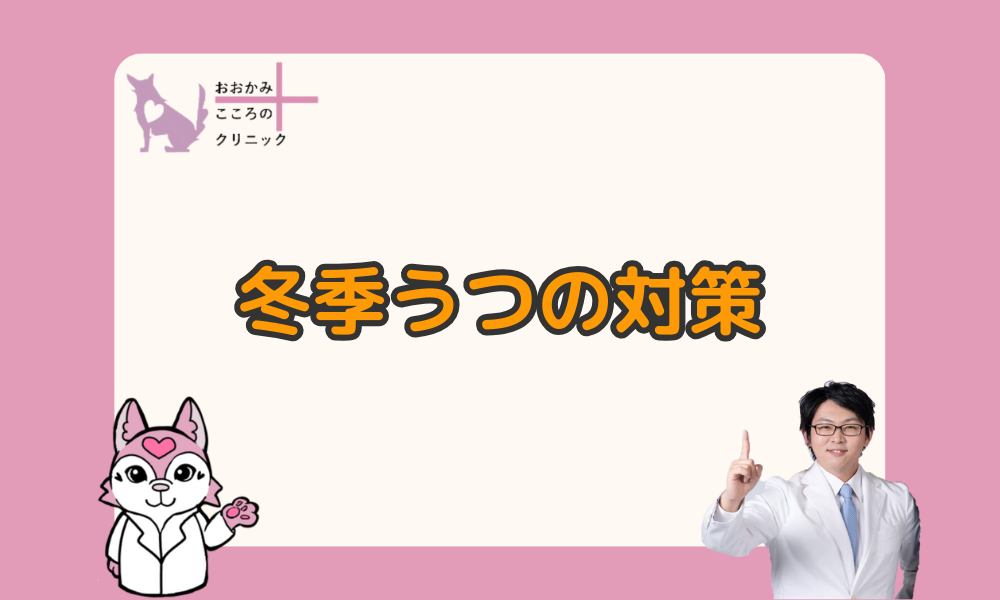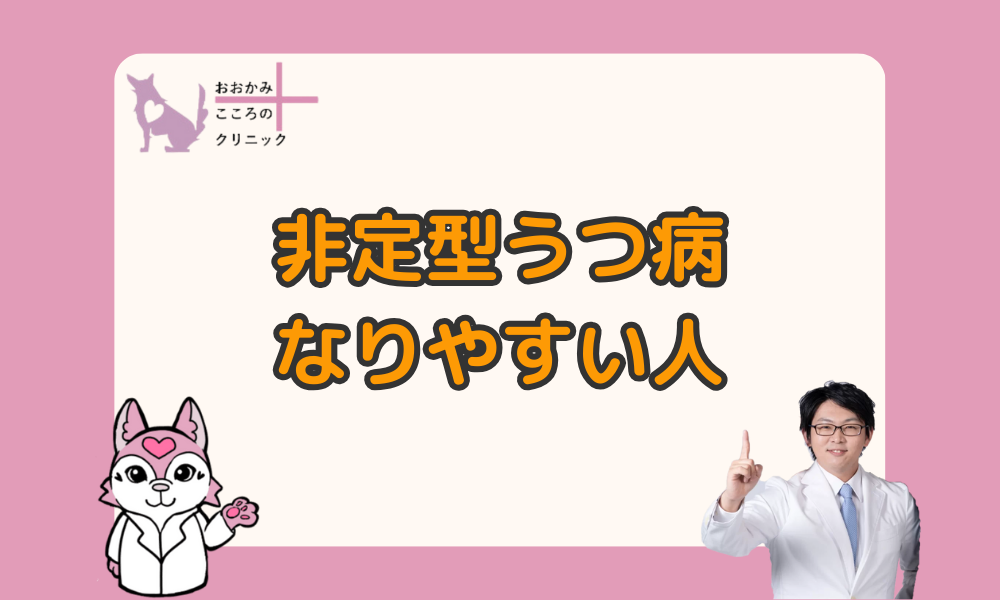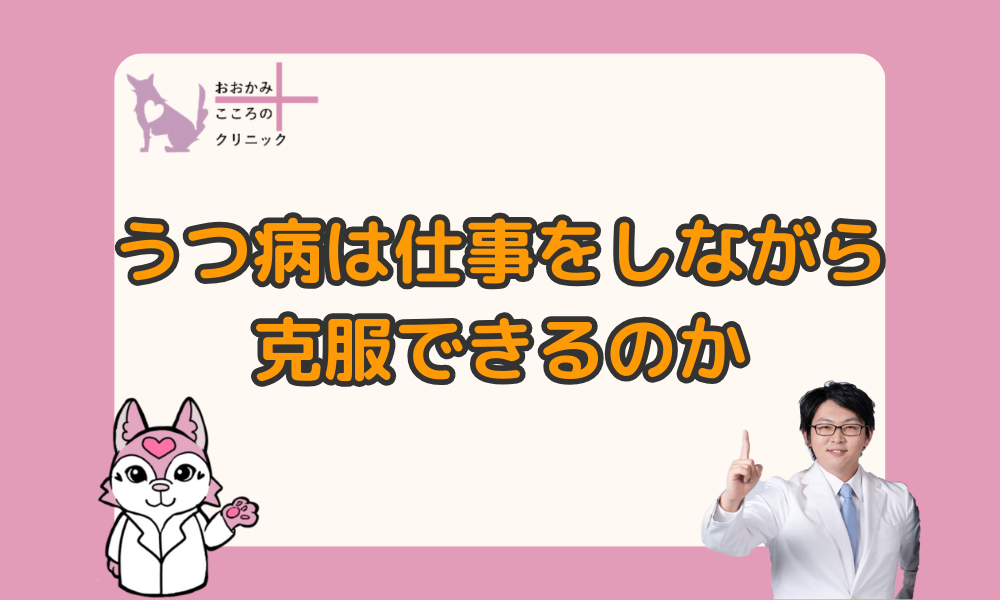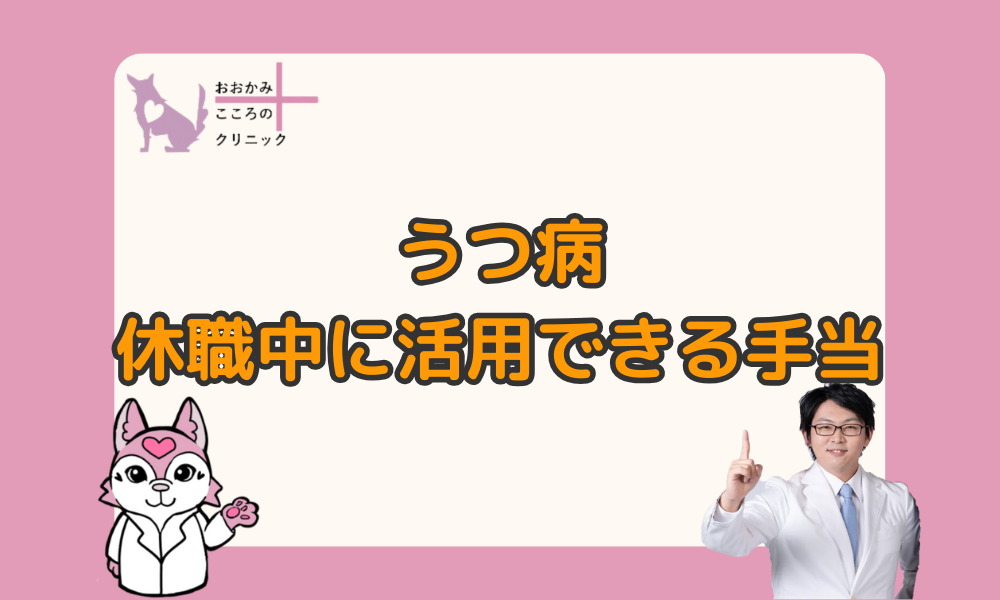「何をしても楽しくない」
「仕事中に涙が止まらなくなる」
こうした症状が、2週間以上続くとうつ病の可能性があります。
ですが、実際に自分で「うつ病かも」と思う人は多くありません。心身がつらい状態だと、冷静に病気を疑うことは難しいものです。
「最近の自分はおかしいのでは」と気づけたのは、それだけ自分に向き合えている証拠です。
疲れた心をケアして毎日を穏やかに過ごすためには、ひとりで悩まず周りの人や専門家に話を聞いてもらったり、これからの過ごし方について相談したりするのもよいでしょう。
うつ病の種類や症状はさまざまです。もしも自分がうつ病かもしれないと思ったら、まずどのようなパターンがあるのか確認してみましょう。
うつっぽいな…と感じたら、下記の記事も合せてご覧ください。
この記事の内容
うつ病の種類と症状
うつ病は2週間以上憂うつな気分が続き、発症のタイミングや症状のあらわれ方によって分類されます。[1][2][5]
順番に見ていきましょう。
仮面うつ病
頭痛や倦怠感、肩こりといった身体症状が強く出るうつ病です。身体症状という「仮面」をかぶって精神症状を隠しているため、この名がついています。
うつ病は精神症状が前面に出るイメージがありますが、仮面うつ病では身体症状の方が目立ちます。そのため内科などで受診しても、これといった原因が分からないことがよくあります。

気になる症状があったら、受診してみましょう。
産後うつ病
産後4週間以内に発症するうつ病で、原因はホルモンの影響や子育てのプレッシャーなどです。出産後に孤独を感じたり、育児のプレッシャーなどの影響でネガティブになったりイライラを感じます。
妊娠・出産は女性の心身に大きな変化をもたらします。不安定になるのも自然なことです。通っている産婦人科や心療内科、精神科などの医療機関に遠慮せず相談しましょう。
産後うつについては、以下の記事も参考にしてみてください。
微笑みうつ病
うつ病の大きな特徴として、気分の落ち込みや表情の乏しさなどが挙げられます。
微笑みうつ病は、家庭や職場など、他の人がいる時は比較的明るく振る舞えるうつ病です。
表面上は明るく見えるので、周囲の人たちはうつ病だと思わないでしょう。自分自身でさえ、自分の変化を感じにくいかもしれません。
微笑みうつ病については、こちらの記事を読んでみてください。
季節型うつ病
季節の変化に応じて、うつの発症と回復を繰り返すのが季節型うつ病です。日照時間に関係しているという説があります。
日照時間が短い季節に起こる冬季うつがよく知られています。冬季うつは秋冬に始まり春に回復するのが特徴で、過食・過眠などの症状が見られます。
冬季うつに関してはこちらの記事もご覧ください。
非定型うつ病
一般的なうつ病は、良いことがあっても気分が晴れず憂うつな状態が続きます。
しかし非定型うつ病は、楽しいことをしていると気分が晴れ、明るく元気に見えます。そのため、一見するとうつ病とは分かりづらいのです。
周囲から理解を得るのが難しいといえますが、疲れを感じやすいのも非定型うつ病の特徴です。普段の憂うつ感や疲労感が強いなら、医療機関に相談してみましょう。
非定型うつ病はこちらの記事が参考になります。
メランコリー型うつ病
メランコリー型うつ病は、典型的なうつ病を指します。このような症状があれば、うつ病の可能性があります。
- 動作が緩慢
- 食欲がない
- 体重が減る
- 心が晴れない
- 罪悪感が強い
- 早朝に目が覚める
- 朝が最も気分が落ち込む
うつ病は、2週間以上気分が落ち込みや憂うつ感が続くといった診断の基準があります。しかし、自分で「何かおかしい」と感じたら症状の期間を考える必要はありません。ためらわずに医療機関を受診しましょう。
うつ病は、早めの対処と適切な治療を継続することが大切です。
「うつ病かも……」と思ったら、ひとりで抱え込まないで、おおかみこころのクリニックに相談してくださいね。
24時間予約受付中
うつ病に自分で気づくポイント
自分の心と体の状態にアンテナを張りましょう。日ごろから自分自身をケアする気持ちを持つのが大切です。[3][4][6]
- 勝手に涙が出てくる
- 便秘や下痢の症状がある
- 何をしていても楽しくない
- 自分は価値がないと考える
- 食欲が減った、または増えた
- 眠れない、または眠り過ぎる
- 良いことがあるときだけ元気になれる
このような症状に気づけたら、自分に向き合えたことを「よくできた」と考えてみてください。カウンセラーや医師に現在の状態を伝え、今後どうすべきかを相談するとよいでしょう。

気づけるってスゴイことなんですよ!
うつ病とわかったときの対処法
医療機関でうつ病と診断されたら「職場や家族に言うべきか……」と悩むかもしれません。以下のステップに沿って、落ち着いて行動しましょう。[3][5]
順番に解説します。
① 今後の治療について医師と相談する
うつ病には色々なものがあります。医師の診断内容をきちんと聞き、どのように治療するべきかを知りましょう。
うつ病の治療は、薬物療法や精神療法などがあります。医師の指示に従って、適した治療を受けることが大切です。働き方について相談し、これからの生活について考えていきましょう。職場への伝え方については後ほど解説します。
② 家族に伝える
次に、うつ病の診断を受けたと家族に伝えましょう。
うつ病の治療には家族の理解と協力が不可欠です。可能であれば、家族と一緒に医師の話を聞きましょう。暮らしの中で気をつけること、知っておいた方がいいことを共有し、あなたが過ごしやすい環境を作るのです。
「メンタルが弱いからうつ病になった」と考える人もいますが、そういうわけではありません。
誰にでも心があります。心が弱ってうつ病に至る可能性は誰もが持っているのです。
この点を本人も家族も、きちんと理解しておく必要があります。
③ 職場の上司に伝える
家族に伝えたら、次は職場の上司に病院の診断書を提出します。
このとき、取り繕わずにありのままを伝えましょう。「うつ病になってしまって申し訳ない」といった自責の念や罪悪感は必要ありません。
職場の人全員に話さなくても大丈夫です。ただ、協力を得るためにも同じ部署の人に今の状態を伝えておくとよいでしょう、業務が進めやすくなります。
職場環境や業務のストレスでうつ病となるケースも多いです。自分なりに原因がわかっている場合は、この機会に上司に相談してみましょう。

上司に相談するタイミングも、主治医と相談できるので安心してくださいね!
④ 働き続けるか休職するか決める
うつ病を抱えたまま働くか、それとも休職するか。その決断はとても勇気のいることです。
医師の診断書を提出したら、多くの職場では面談が行われます。心が不安定な状態での面談はつらいと感じるかもしれません。しかしこれから先、今までのように元気な自分に戻るためには適切な治療と休養が必要です。
働くのが苦痛なら、休職を申請してもよいでしょう。もし周囲のサポートが得られる状況なら、医師に相談し無理のない範囲で働くのも可能です。
うつ病でも働き続ける方はこちらの記事が参考になります。
休職を考えるならこちらの記事を読んでみてください。役立つ制度が詳しく説明されています。
まとめ
うつ病にかかったら、心と身体の両方に症状が表れます。とても不安定な状態になるため「自分の身に何が起こっているか」を冷静に分析するのは難しいでしょう。
そんな中、自分の変調をキャッチできるのは素晴らしいことです。気づくのが早ければ早いほど、治療を始めるのが早くなります。初期のころにアプローチできれば、それだけ症状が和らぐのも早まる可能性が高まるでしょう。
もしうつ病でないとしても「いつもと違う」と感じたら早めに医療機関を受診してみてください。少しためらうかもしれませんが、今の気持ちを聞いてもらうだけでも十分です。
心の中を整理整頓するような感覚で、気軽に相談してみてください。
24時間予約受付中
【参考文献】
[1]厚生労働省 こころの耳「うつ病とは」
https://kokoro.mhlw.go.jp/about-depression/ad001/
[2]厚生労働省 こころの耳「用語解説・仮面うつ病
https://kokoro.mhlw.go.jp/glossarycat/mentalhealth/
[3]こころの情報サイト「うつ病」
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=9D2BdBaF8nGgVLbL
[4]こころもメンテしよう「うつ病」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/stress/know/know_01.html
[5]MSDマニュアル「うつ病」
[6]国立精神・神経医療研究センター「うつ病
https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease01.html
- この記事の編集者
- 佐藤恵美
介護福祉士・社会福祉士保有。リハビリ病棟にて介護職を7年経験し、デイサービスや介護老人保健施設の相談職に従事。現在はフリーのWebライターとして活動中。