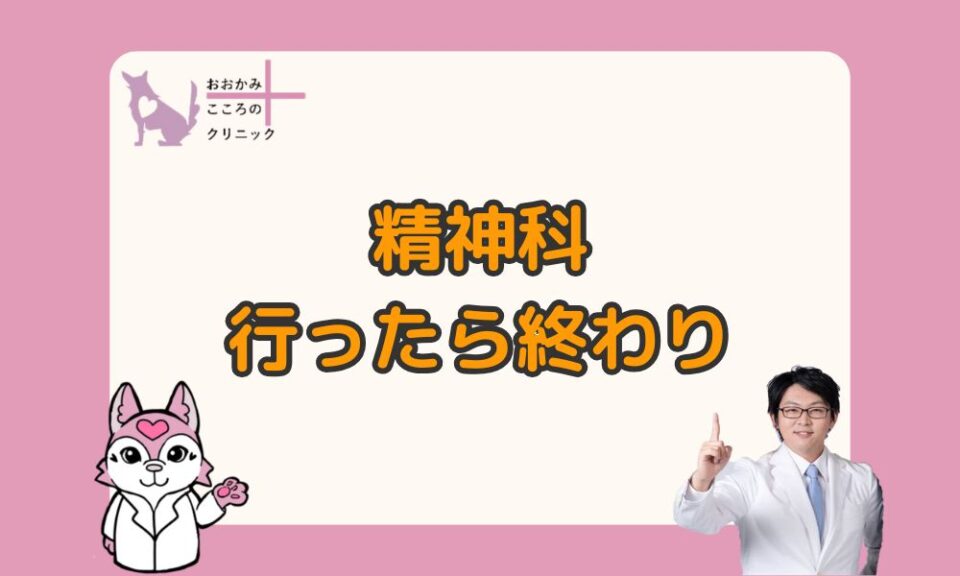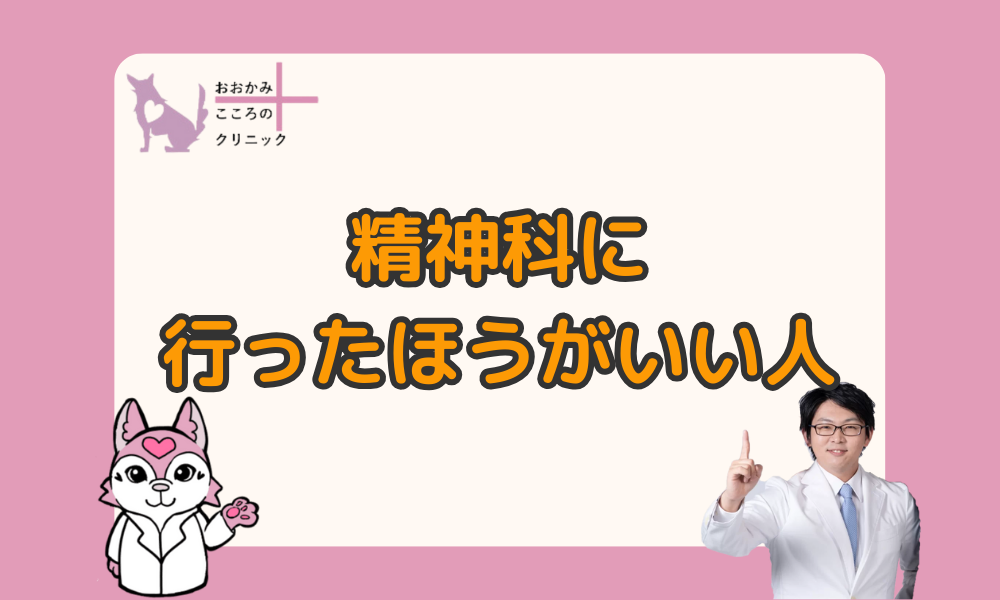「精神科に行ったら終わりかもしれない」という強い不安から、受診をためらっていませんか。
周囲の目が気になったり将来に影響したりするのではないかと考えると、精神科の受診をためらってしまうでしょう。
精神科は決してあなたの人生を終わりにする場所ではありません。医師やカウンセラーの力を借りて、つらい状態から抜け出すための場所です。
この記事では「精神科に行ったら終わり」と言われる理由や、行くメリット・デメリットを解説します。まずは精神科に対する誤解を解くことから一緒に始めてみましょう。
この記事の内容
「精神科に行ったら終わり」と言われる理由
「精神科に行ったら終わり」と言われる理由には、大きく分けて2つあります。
- 周囲の目や社会的な偏見への不安
- 就職や結婚にかかわるという思い込み
まず1つ目は、周囲の目や社会的な偏見への不安です。
精神疾患にマイナスイメージを持っていると、専門家のサポートを避けようとする傾向があると指摘されています。[1]このような社会的な偏見が、受診への不安につながるのです。
2つ目は、通院歴が将来にかかわるという思い込みもあります。
たとえば「就職や転職で不利になるのではないか」「結婚できなくなるのではないか」といった心配が挙げられます。
しかし、医師には守秘義務があるため、あなたの同意なく通院の事実が職場や家族に伝わることはありません。
頭では理解していても「もしも」の可能性を考えると、不安が消えないでしょう。将来への漠然とした不安が、受診への壁となってしまうのです。

先生が勝手に他の人に話すことはないので安心してください!
精神科に行くメリットとデメリット
精神科の受診によって得られるメリットと、考えられるデメリットの両方を解説します。
よい面と注意点の両方を知ることで漠然とした不安が解消され、あなた自身が納得して一歩を踏み出しやすくなるでしょう。
メリット
精神科を受診するメリットには、次の3つがあります。
- 医師による正確な診断を受けられる
- 症状の重症化・慢性化を防ぎやすくなる
- 悩んだときに医師やカウンセラーに相談できる
診断名がつくことに、怖さを感じるかもしれません。しかし、医師から正確な診断を受けることは、不安から抜け出すための手がかりになります。
自ら調べたインターネットの情報だけで症状を判断しようとすると、かえって不安が増してしまうでしょう。医師の診察を受ければ、現在の状態や原因を客観的に把握できるのです。
また、早期に受診すれば、症状の重症化や慢性化を防ぎやすくなります。
身体の病気と同じで、こころの不調も放置すると悪化する可能性があるのです。
そして、悩みを相談できる専門家がいるという安心感が得られます。
定期的に通院し、医師やカウンセラーにあなたの状態を話すことで、こころの状態も安定しやすくなります。
デメリット
精神科への通院にはメリットだけでなく、次の2つの注意点もあります。
- 治療費がかかる
- 薬を飲むと副作用が出るケースがある
1つ目のデメリットは、治療費がかかることです。
定期的な通院や薬代は、家計への負担が心配になるかもしれません。
ただし、うつ病や統合失調症などの精神疾患の診断を受けた人は「自立支援医療制度」を利用すれば、自己負担額を原則1割まで抑えることができます。
利用する際は、お住まいの市区町村の窓口に相談しましょう。
2つ目は、薬の副作用が出る可能性があることです。
処方される薬によっては、眠気やだるさ、口の渇きなどの副作用があらわれることがあります。
もし副作用がつらいと感じたら、我慢せずに担当の医師へ伝えてください。相談すれば、薬の量や種類を調整してもらうこともできます。
下記の記事では精神科に行った方がよい人を解説しているので、あわせてご覧ください。
精神科に行ったことが周囲にバレる可能性は低い
本人の同意なしに、精神科に通っていることが周囲にバレる可能性は低いです。
なぜなら、医師や看護師、カウンセラーは患者さんの情報を正当な理由なく漏らしてはならないと定められているからです。[2][3]
そのため、たとえ会社の同僚や家族から問い合わせがあったとしても、医師が本人の許可なく受診の事実や病状を伝えることはありません。
ただし、健康保険の被扶養者になっている人は注意が必要です。
健康保険組合から世帯主宛てに送付される「医療費のお知らせ」には、被扶養者の受診日、病院名、費用が記載されています。そのため、通院の事実が家族に知られる可能性があるのです。
家族に知られることに不安を感じるときは、事前に正直に相談するか「体調が優れなくて病院に通っているんだ」とだけ伝えておきましょう。
精神科に行ってよかった人の体験談
「精神科に行ったら終わり」という不安を抱えているとき、実際に通院して回復した人の声は参考になります。ここでは、精神科に行ってよかった人の体験談を紹介します。
大学病院の精神科に通っています。
悪いイメージばかり先行しているようですが、実際は違うと感じます。
精神科は助けてもらう場であって、終わりとかそんなことはありません。
私の主治医はいつも根気強く話を聞いてくれて、薬の相談にものってくれます。
変な薬を飲まされる、とありますが、薬が処方されるのだとしたら患者の不調を改善する為に有効なお薬が処方されたということです。
私は薬の副作用とどう付き合うかで5回ほどお薬変更がありましたが、今は合う薬に出会えています。
合う薬に出会うまで、副作用がしんどくて少し辛いかもしれませんが、主治医とその都度相談、変薬していくのです。
薬に頼るばかりでは嫌だという場合も主治医に相談して自費カウンセリングという手もあります。
つまり、辛いのであれば1度診察を受けてみる事です。
引用: Yahoo!知恵袋
最後に話しているように「つらい」と感じたときに頼れる場所があるということが、こころの支えになるでしょう。
精神科は、薬を処方するだけの場所ではなく、対話を通じてこころの回復をサポートする役割も担っているのです。
体験談からは「精神科は終わり」ではなく、つらい状況から抜け出すための「心強いスタート地点」であることが伝わってきます。
精神科を受診するときの注意点
初めて精神科を受診する際の注意点には、次の3つがあります。
事前に準備しておくことで、受診への不安をやわらげスムーズに診察を受けられます。
病院のホームページを見る
まず、受診する病院やクリニックのホームページを事前に確認しましょう。
精神科といっても、うつ病や不安障害を専門にしているところ、発達障害の診断に力を入れているところなど、それぞれに特徴があります。
ホームページには、どのような症状や病気を対象としているかが書かれているため、あなたの悩みと合っているかを確認する目安になるのです。
また、在籍している医師の資格を確認するのもひとつの方法です。
たとえば、「精神保健指定医」や「精神科専門医」などの資格は、精神科医療に関する知識と経験を持つ医師であることを示します。もちろん資格が全てではありませんが、病院を選ぶ際の参考になるでしょう。
自宅や職場からの通いやすさも考慮し、ムリなく通院を続けられそうな場所を選んでください。

ホームページを見てわからないときは電話で聞いてみましょう!
予約をしてから受診する
次に、事前に予約をしてから受診しましょう。
精神科や心療内科では、予約制を優先する病院が多いです。
とくに初診では症状を詳しく聞くため、30分から1時間程度の診察時間を確保します。
そのため、1日に診察できる初診の人数が限られており、希望の日時で予約がとれないケースもあります。予約が数週間先になる可能性も念頭に置いておきましょう。
予約方法は電話が一般的ですが、ホームページの予約フォームから受けつけているクリニックもあります。
予約の際には初診であると伝え、簡単な症状や相談したい内容を伝えると、診察がスムーズに進みます。
まずは気になるクリニックに連絡をとり、初診の予約が可能か問い合わせてみましょう。
話す内容をメモにまとめておく
診察で話したい内容はあらかじめメモにまとめておきましょう。
診察室では緊張してしまい、本当に伝えたかったことを忘れてしまうかもしれません。限られた診察時間を有効に使うためにも、事前の準備が役立ちます。
具体的には、次の3つを書き出しておくとよいでしょう。
- 今一番つらいこと(例:眠れない、やる気が出ない)
- いつから続いているか(例:2週間前から仕事のある日だけひどい)
- 生活の中で困っていること(例:仕事に集中できない、朝起きられない)
メモを担当の医師に見せながら話すことで伝え忘れを防ぎ、あなたの状態を正確に理解してもらう助けになります。
まとめ
「精神科に行ったら終わり」という言葉は誤解です。実際には、精神科はつらい状況から抜け出し、回復を目指すためのスタート地点になります。
精神科を受診する際は、事前にホームページで病院の情報を確認し予約をとってからにしましょう。
話したい内容をメモにまとめておくと、診察がスムーズに進みます。
ひとりで悩みを抱えてつらいと感じていたら、医師やカウンセラーを頼るのもひとつの選択肢です。おおかみこころのクリニックでは毎日夜22時まで診察しています。ホームページからも予約を受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。
24時間予約受付中
おおかみこころのクリニック
【参考文献】
[1]精神疾患に対するスティグマへのアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)による介入の可能性,津田菜摘,武藤 崇
https://pscenter.doshisha.ac.jp/journal/PDF/Vol6/pp65-.pdf
[2]医師法|e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
[3]精神科医師の倫理綱領細則|日本精神神経学会
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/about/ethics_detailed_regulations.pdf